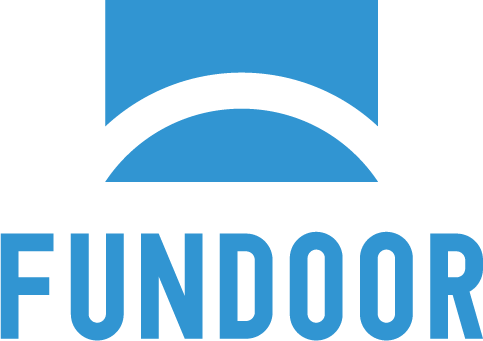気候変動対策に関するリスク管理の必要性

かつて、気候変動対策は企業の社会的責任(CSR)活動の一環として語られることが多く、コストセンターと見なされがちでした。
しかし現在、その認識は大きく変わり、気候変動への対応は企業の存続そのものを左右する最重要の経営課題として位置づけられています。気候変動に起因するリスクを適切に管理できない企業は、事業継続が困難になるだけでなく、市場や社会からの信頼を失い、企業価値を大きく損なう時代に突入したのです。
では、なぜ今、これほどまでに気候変動のリスク管理が不可欠なのでしょうか。その理由は、大きく3つの側面に集約されます。
ESG投資の潮流とステークホルダーからの要請
現代の企業経営において、投資家や金融機関の動向を無視することはできません。近年、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への配慮、すなわち「ESG」を重視して投資先を選ぶ「ESG投資」が、世界の金融市場で急速に主流となっています。
特に、世界最大級の年金基金である日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がESG投資を積極的に推進していることは、国内企業にとって大きな影響を与えています。投資家たちは、企業の長期的な成長性やリスク耐性を評価する上で、気候変動への対応状況を極めて重要な判断材料と見なしています。具体的には、温室効果ガス排出量の削減目標や再生可能エネルギーの導入状況、気候変動リスクが事業に与える財務的影響の分析といった非財務情報が厳しく評価されるのです。
気候変動リスクへの対策が不十分だと判断された企業は、投資家から「ダイベストメント(投資引き揚げ)」の対象となったり、金融機関からの融資条件が厳しくなったりするなど、資金調達の面で深刻な不利益を被る可能性があります。さらに、企業を取り巻くステークホルダーは投資家だけではありません。
| ステークホルダー | 企業への主な要請・期待 |
|---|---|
| 顧客・消費者 | 環境に配慮した製品やサービスの提供、サプライチェーン全体での人権・環境配慮 |
| 取引先 | 自社の脱炭素目標達成に向けた、サプライヤーに対するGHG排出量削減の要請 |
| 従業員 | 持続可能な社会に貢献できる企業で働くことへの誇り、安心して働ける事業環境の維持 |
| 地域社会 | 事業活動が地域の環境に与える影響の最小化、災害時におけるレジリエンスの確保 |
このように、あらゆるステークホルダーから気候変動への真摯な対応を求められており、これに応えられない企業は、製品の不買や優秀な人材の流出、社会的な信用の失墜といった多岐にわたるリスクに直面します。
サプライチェーン寸断という現実的な脅威
気候変動は、もはや遠い未来の不確実な問題ではありません。激甚化する台風や豪雨、深刻化する干ばつといった異常気象は、すでに世界各地で現実の脅威として事業活動に深刻な影響を及ぼしています。
日本国内でも、毎年のように発生する豪雨や台風によって、工場が浸水被害を受けたり、交通網が麻痺したりすることで、生産停止や物流の遅延に追い込まれる企業が後を絶ちません。例えば、河川の氾濫で主要な生産拠点が操業停止に陥れば、その影響は自社だけでなく、部品を供給している取引先の生産ラインにまで波及します。
このリスクは、国内に限りません。海外の生産拠点や原材料の調達先が、干ばつによる水不足や海面上昇による高潮被害などに見舞われる可能性も高まっています。自社の拠点が直接的な被害を受けなくとも、サプライチェーン上のどこか一か所が機能不全に陥るだけで、製品の製造や供給が不可能になるのです。グローバルに広がる複雑なサプライチェーンに依存する現代の企業にとって、気候変動がもたらす物理的なリスクは、事業継続計画(BCP)の根幹を揺るがす、極めて現実的かつ深刻な脅威と言えます。
国内外で進む規制強化と情報開示の義務化
気候変動問題への国際的な危機感の高まりを受け、各国政府や規制当局は、企業に行動変容を促すためのルール作りを加速させています。特に「規制強化」と「情報開示の義務化」という2つの流れは、企業経営に直接的な影響を与えます。
情報開示の側面では、金融安定理事会(FSB)が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言が、事実上のグローバルスタンダードとなっています。日本においても、東京証券取引所の市場再編に伴い、2022年4月からプライム市場上場企業に対して、コーポレートガバナンス・コードを通じてTCFD提言に基づく情報開示が実質的に義務化されました。さらに、2023年3月期決算からは、有価証券報告書でのサステナビリティ情報の開示が義務付けられ、気候変動への対応は投資家向けの開示情報として必須項目となっています。
一方、規制強化の動きとしては、脱炭素社会への移行を促すための政策導入が進んでいます。代表的なものが、二酸化炭素の排出量に応じて企業に金銭的な負担を求める「カーボンプライシング」です。具体的には、炭素税や排出量取引制度などが挙げられ、これらの導入や強化は、化石燃料に依存する企業のコストを直接的に押し上げます。こうした政策や規制の変更は、企業の事業戦略や収益構造に大きな変革を迫る「移行リスク」として認識しなければなりません。これらの国内外の動向に対応できなければ、法令違反による罰則や、市場からの信頼を失うといったレピュテーションリスクに直結するため、もはや気候変動対策は任意ではなく、必須の経営課題となっているのです。
知っておくべき気候変動の2大リスク「物理的リスク」と「移行リスク」

気候変動が企業経営に与えるリスクは、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言において、大きく「物理的リスク」と「移行リスク」の2つに分類されています。これら2つのリスクの性質を正しく理解することが、効果的な気候変動対策とリスク管理の第一歩となります。
自社の事業にどのような影響が及ぶ可能性があるのか、具体的に見ていきましょう。
物理的リスクとは 異常気象が事業に与える直接的な影響
物理的リスクとは、気候変動の進行によって引き起こされる異常気象や長期的な気候パターンの変化が、企業の保有資産やサプライチェーン、事業活動に直接的な損害を与えるリスクを指します。
このリスクは、発生の仕方によって「急性リスク」と「慢性リスク」の2つに分けられます。
台風や洪水による急性リスク
急性リスクは、台風の大型化や線状降水帯の発生による集中豪雨、洪水、干ばつといった、特定の気象イベントによって突発的に発生するリスクです。近年、日本でも毎年のように大規模な水害が発生しており、企業にとって極めて現実的な脅威となっています。
例えば、2019年の令和元年東日本台風(台風19号)では、多くの河川が氾濫し、広範囲にわたる浸水被害が発生しました。これにより、特定の地域の工場が被災しただけでなく、部品供給が滞ったことで全国の自動車メーカーの生産ラインが停止するなど、サプライチェーン全体を巻き込む甚大な被害に繋がりました。自社が直接被災しなくても、取引先や物流網がダメージを受けることで、事業継続が困難になるケースは少なくありません。
急性リスクへの備えとしては、ハザードマップによる拠点立地の再評価、BCP(事業継続計画)の策定・見直し、サプライヤーの多様化(マルチサプライヤー化)などが急務となります。
平均気温上昇や海面上昇による慢性リスク
慢性リスクは、平均気温の上昇や海面上昇、降雨パターンの変化といった、長期にわたる気候の変化によって徐々に進行するリスクです。突発的な被害をもたらす急性リスクとは異なり、気づかぬうちに経営基盤を蝕んでいくサイレントな脅威と言えます。
具体的には、以下のような影響が考えられます。
- 農業・水産業への影響:気温上昇による農作物の品質低下や収穫量の不安定化、海水温上昇による漁獲対象の変化や減少は、食品メーカーや飲食業界の原材料調達を困難にします。
- 労働生産性の低下:猛暑日の増加は、建設業や運輸業など屋外での作業効率を低下させ、従業員の熱中症リスクを高めます。
- インフラ・資産への影響:海面上昇は、沿岸部に位置する工場や港湾施設、倉庫の浸水リスクを高め、長期的な資産価値の低下につながります。
- コストの増加:気温上昇に伴うオフィスや工場の空調コストの増加や、渇水リスクに対応するための水資源確保コストなどが挙げられます。
これらの慢性リスクは、事業の前提条件を根本から変えてしまう可能性があり、長期的な視点での事業戦略の見直しが不可欠です。
移行リスクとは|脱炭素社会への移行期に発生する経営課題
移行リスクとは、低炭素・脱炭素社会への移行が進む過程で生じる、政策・法規制、技術、市場、評判などの変化に対応できないことによって企業が被る財務的な損失リスクです。物理的リスクが自然現象による直接的な影響であるのに対し、移行リスクは社会経済システムの変革によって間接的に発生します。
政策・法規制の変更に伴うリスク
世界各国で脱炭素化に向けた政策や法規制の導入が加速しており、これが企業にとって大きなリスク要因となっています。対応が遅れれば、ある日突然、事業の前提が覆され、大幅なコスト増や事業機会の損失につながる可能性があります。
代表的な政策・法規制リスクには、以下のようなものがあります。
- カーボンプライシングの導入:CO2排出量に応じて金銭的な負担を求める「炭素税」や「排出量取引制度」が導入・強化されると、化石燃料を多く使用する製造業や運輸業などは直接的なコスト増に直面します。日本でも「GXリーグ」における排出量取引制度の本格稼働が予定されています。
- エネルギー・環境関連規制の強化:省エネ法のように、製品や設備に対するエネルギー効率基準が厳格化されれば、基準を満たすための追加的な設備投資が必要となります。
- 情報開示の義務化:東京証券取引所のプライム市場上場企業を対象に、TCFD提言に沿った気候変動関連の情報開示が実質的に義務化されたように、開示要求は今後さらに拡大する見込みです。これに対応するための体制構築やデータ収集にもコストがかかります。
市場や顧客ニーズの変化によるリスク
脱炭素化への移行は、市場の構造や顧客の価値観にも大きな変化をもたらします。この変化を的確に捉えられなければ、企業の競争力は著しく低下してしまいます。
市場関連のリスクは多岐にわたります。
- 需要のシフト:消費者の環境意識の高まりにより、ガソリン車から電気自動車(EV)へ、従来電力から再生可能エネルギー由来の電力へと需要がシフトしています。環境価値を製品やサービスに組み込めない企業は、市場シェアを失い、淘汰されるリスクに晒されます。
- ESG投資の拡大:投資家が企業の環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への取り組みを重視するESG投資が主流となる中、気候変動対策に消極的な企業は投資対象から外され(ダイベストメント)、資金調達が困難になる可能性があります。
- サプライチェーンからの要請:Appleやトヨタ自動車といったグローバル企業が、サプライヤーに対してCO2排出量の削減を要請する動きが活発化しています。こうした要請に応えられなければ、大手企業との取引を失うことになりかねません。
- 人材獲得への影響:特に若い世代を中心に、企業のサステナビリティへの姿勢を就職先選びの重要な基準とする傾向が強まっています。魅力的な対策を打ち出せない企業は、優秀な人材の獲得競争で不利になります。
TCFD提言に沿って始める気候変動対策リスク管理の5ステップ

気候変動対策におけるリスク管理を具体的に進める上で、現在、世界的な標準となっているのが「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の提言です。これは金融安定理事会(FSB)によって設立され、投資家などが企業の気候関連リスクを適切に評価できるよう、一貫性のある情報開示の枠組みを企業に提供するものです。ここでは、TCFD提言が推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」という4つの開示項目に沿った、実践的な5つのステップを解説します。
※参照:気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)|環境省
ステップ1|推進体制の構築(ガバナンス)
気候変動対策は、特定の部署だけで完結するものではありません。経営層が主導し、全社横断で取り組むべき経営課題です。そのため、最初のステップとして、気候関連のリスクと機会を監督・管理するための強固なガバナンス体制を構築することが求められます。
具体的には、まず取締役会が気候変動問題を監督する最終的な責任を負うことを明確にします。取締役会は、気候関連のリスクと機会が事業戦略に与える影響を定期的に議論し、経営陣の取り組みを監督する役割を担います。その下で、CEOや担当役員などの経営陣が、リスク評価や管理方針の策定、具体的な戦略の実行責任者となります。
さらに、実務を推進するために、サステナビリティ委員会や部門横断的なタスクフォースを設置することも有効です。これにより、各部門の専門知識を結集し、迅速な意思決定と実行が可能になります。経営トップの強いコミットメントを明確にし、全社的な推進体制を構築することが、実効性のあるリスク管理の第一歩となります。
ステップ2|重要なリスクと機会の特定(戦略)
次に、自社の事業にとって重要性の高い気候関連のリスクと機会を特定します。これは、自社の事業活動、サプライチェーン、そして市場環境を短・中・長期の3つの時間軸で多角的に分析するプロセスです。この特定作業は「重要性評価(マテリアリティ分析)」とも呼ばれ、限られた経営資源をどこに集中させるべきかを判断する上で不可欠です。
特定すべきリスクと機会は多岐にわたります。以下の表を参考に、自社のビジネスモデルに照らし合わせて洗い出してみましょう。
| 分類 | リスク/機会の具体例 | 事業への影響例 |
|---|---|---|
| 物理的リスク(急性) | 台風の大型化、集中豪雨、洪水 | 生産拠点の操業停止、サプライチェーンの寸断、資産の損壊 |
| 物理的リスク(慢性) | 平均気温の上昇、海面上昇、水資源の枯渇 | 空調コストの増大、農作物の不作による原材料価格の高騰、生産拠点の移転コスト |
| 移行リスク(政策・規制) | 炭素税の導入、排出量取引制度の強化、省エネ基準の厳格化 | 炭素コストの増加、既存製品の販売規制、コンプライアンス対応コストの発生 |
| 移行リスク(市場) | 低炭素製品・サービスへの需要シフト、ESG投資の拡大 | 既存製品の売上減少、資金調達コストの上昇 |
| 事業機会 | 省エネ技術の導入、再生可能エネルギーへの転換、サーキュラーエコノミー型製品の開発 | 光熱費の削減、新たな収益源の創出、ブランドイメージの向上、競争優位性の確立 |
自社の事業拠点やバリューチェーン全体を俯瞰し、気候変動がもたらす直接的・間接的な影響を網羅的に洗い出すことが重要です。
ステップ3|シナリオ分析による財務的影響の評価(戦略)
ステップ2で特定したリスクと機会が、将来的にどの程度の財務的インパクトをもたらすのかを評価するために「シナリオ分析」を実施します。シナリオ分析とは、将来起こりうる複数の世界(シナリオ)を描き、それぞれの世界で自社の事業戦略がどのように影響を受けるかを検証する手法です。
TCFDでは、複数のシナリオを用いて分析することが推奨されています。代表的なものには以下のようなシナリオがあります。
- 1.5℃/2℃シナリオ:パリ協定の目標に沿って、世界が脱炭素化へ大きく舵を切る世界。移行リスクは高まるが、物理的リスクは抑制される。
- 4℃シナリオ:気候変動対策が十分に進まず、地球の平均気温が4℃上昇する世界。物理的リスクが深刻化し、事業継続に大きな脅威がもたらされる。
これらのシナリオに基づき、特定したリスク・機会が売上高、営業費用、設備投資、資産価値などに与える影響を定性的・定量的に評価します。例えば、「炭素税が導入された場合(1.5℃シナリオ)のコスト増加額」や、「大規模な洪水が発生した場合(4℃シナリオ)の生産停止による逸失利益」などを試算します。シナリオ分析は未来を正確に予測するものではなく、不確実な未来に対する自社の戦略の頑健性(レジリエンス)を評価し、経営判断の質を高めるためのツールです。
ステップ4|全社的なリスク管理プロセスへの統合(リスク管理)
気候変動リスクは、これまでの事業活動で管理してきた財務リスクやオペレーショナルリスクなどとは別の、特別なリスクとして扱うべきではありません。持続的な企業経営を実現するためには、気候変動リスクを既存の全社的リスク管理(ERM:Enterprise Risk Management)の枠組みに完全に統合することが不可欠です。
統合により、気候変動リスクを他の経営リスクと同じ基準で評価し、優先順位をつけ、経営資源を適切に配分することが可能になります。具体的なプロセスは以下の通りです。
- リスクの識別と評価:ステップ2で特定した気候関連リスクを、リスク管理規程などに基づき、発生可能性や影響度を評価し、全社的なリスクマップに位置づけます。
- リスク対応策の決定:評価結果に基づき、リスクを「低減」「移転(保険など)」「受容」「回避」するかの対応方針を決定し、具体的な対策と担当部署を明確にします。
- モニタリングと報告:リスク対策の進捗状況を定期的にモニタリングし、その結果をリスク管理委員会などを通じて経営陣や取締役会へ報告するサイクルを確立します。
気候変動リスクを日常の業務プロセスや投資判断の基準に組み込むことで、場当たり的な対応ではなく、戦略的かつ継続的なリスク管理が実現します。
ステップ5|指標と目標の設定および情報開示(指標と目標)
リスク管理の最終ステップは、取り組みの進捗を測定・管理するための「指標(Metrics)」と、達成すべき具体的な「目標(Targets)」を設定し、その内容をステークホルダーに対して透明性高く開示することです。
指標と目標を設定することで、取り組みの進捗が可視化され、組織全体のモチベーション向上につながります。また、投資家や顧客はこれらの客観的なデータに基づき、企業の気候変動への取り組み姿勢を評価します。設定すべき指標と目標の例は以下の通りです。
| 分類 | 指標の例 | 目標の例 |
|---|---|---|
| GHG排出量 | Scope1, 2, 3の温室効果ガス排出量(t-CO2e)、売上高あたり排出量原単位 | 2030年までにScope1, 2排出量を50%削減(2020年比)、SBT認定の取得 |
| エネルギー | 総エネルギー消費量、再生可能エネルギーの利用率(%) | 2040年までに事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギー化(RE100加盟) |
| 水資源 | 総取水量、水ストレスの高い地域での取水量 | 2030年までに製品あたりの水使用量を30%削減 |
| 気候関連投資 | 低炭素技術への研究開発投資額、気候変動適応策への設備投資額 | 今後5年間で気候関連技術へ100億円を投資 |
これらの指標と目標、そしてステップ1から4までの取り組み内容を、統合報告書やサステナビリティレポート、ウェブサイトなどを通じて積極的に開示します。透明性の高い情報開示は、ステークホルダーからの信頼を獲得し、資金調達の有利化や企業ブランド価値の向上に直結する重要な活動です。
リスク管理はコストではない!気候変動対策がもたらす事業機会

気候変動対策におけるリスク管理は、単なるコストや守りの経営戦略と捉えられがちです。しかし、TCFD提言がリスクと同時に「機会」の分析を重視しているように、脱炭素社会への移行は、企業にとって新たな成長の原動力となり得ます。
規制強化や市場の変化といった「移行リスク」を的確に捉え、能動的に対応することで、これからの時代に求められる企業価値を創造することが可能です。
ここでは、気候変動対策がもたらす具体的な事業機会を3つの側面から解説します。
省エネ・再エネ導入によるコスト削減と新たな収益源
気候変動対策の第一歩として多くの企業が取り組む省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入は、直接的な経済的メリットをもたらします。化石燃料価格の変動や将来的な炭素税導入のリスクを低減し、経営の安定化に大きく貢献します。
具体的には、工場の生産設備を高効率なものへ更新したり、社屋の照明をLEDに切り替えたりすることで、エネルギー消費量を削減し、光熱費を大幅に圧縮できます。また、自社の屋根や遊休地に太陽光発電設備を設置する「自家消費型太陽光発電」は、電力会社から購入する電力量を減らすだけでなく、PPA(電力販売契約)モデルを活用すれば初期投資を抑えて導入することも可能です。
さらに、発電した電力が自社の消費量を上回る場合には、余剰電力を電力市場に売却することで新たな収益源とすることもできます。このように、省エネ・再エネへの投資は、コスト削減と収益創出の両面で企業の財務基盤を強化する重要な一手となります。
| 取り組み | 主なメリット | 具体例 |
|---|---|---|
| 省エネルギー | エネルギーコストの直接的な削減、エネルギー価格変動リスクの低減 | ・生産プロセスの見直し ・高効率空調・ボイラーへの更新 ・断熱性能の向上、LED照明の導入 |
| 再生可能エネルギー | 電力コストの削減・安定化、新たな収益源の創出、エネルギー自給率の向上 | ・自家消費型太陽光発電の導入(PPAモデル含む) ・余剰電力の売電(FIP制度など) ・非化石証書など環境価値の取引 |
技術革新による競争優位性の確立
脱炭素社会への移行は、既存の産業構造を大きく変革させるインパクトを持っています。これは、裏を返せば、新しい技術やサービス、ビジネスモデルを創出する絶好の機会です。気候変動という社会課題の解決に貢献するイノベーションは、企業の競争優位性を確立するための強力な武器となります。
例えば、製造業においては、CO2排出量を劇的に削減する新たな生産プロセスや、CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)といった先進技術の開発が求められています。また、サプライチェーン全体でのCO2排出量を可視化・管理するプラットフォームや、環境配慮型の新素材開発なども、大きなビジネスチャンスを秘めています。
他社に先駆けて脱炭素化に資する技術やサービスを開発・提供できれば、市場のルールメーカーとなり、先行者利益を享受することが可能です。自社の事業領域における「移行リスク」を深く分析し、それを乗り越えるための研究開発に積極的に投資することが、持続的な成長への鍵となります。
企業ブランドイメージの向上と人材獲得
気候変動対策への取り組みは、企業のレピュテーション(評判)を大きく左右する時代になりました。ESG投資の拡大に見られるように、投資家は企業の非財務情報、特に環境(E)への対応を厳しく評価し、投資判断の重要な基準としています。気候変動リスクと機会に関する情報を積極的に開示し、具体的な対策を進める企業は、資本市場からの信頼を獲得しやすくなります。
また、消費者や取引先の意識も変化しています。環境に配慮した製品やサービスを選ぶ「エシカル消費」が広がり、サプライチェーン全体での人権・環境への配慮を求める動きも加速しています。気候変動対策に真摯に取り組む姿勢は、顧客からの共感を呼び、製品やサービスの選択において有利に働きます。
さらに、この影響は人材獲得の側面にも及びます。特にミレニアル世代やZ世代をはじめとする若い世代は、企業の社会課題への貢献意欲やパーパス(存在意義)を重視する傾向が強くあります。気候変動というグローバルな課題解決に貢献する企業は、優秀で意欲の高い人材にとって魅力的な職場と映り、採用競争において大きなアドバンテージとなるでしょう。これは従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下にも繋がり、組織全体の活力を高める効果も期待できます。
| ステークホルダー | 得られる効果 |
|---|---|
| 投資家・金融機関 | ESG評価の向上、資金調達の有利化、企業価値の向上 |
| 顧客・取引先 | 企業・製品ブランドへの信頼向上、取引関係の強化、新たな顧客層の獲得 |
| 従業員・求職者 | 採用競争力の強化、従業員エンゲージメントの向上、離職率の低下 |
まとめ
気候変動対策におけるリスク管理は、もはや単なるコストではなく、企業の持続的成長に不可欠な経営戦略です。異常気象などの物理的リスクや、脱炭素社会への移行リスクは、事業継続を脅かす現実的な脅威となっています。
TCFD提言に沿った5つのステップでリスクと機会を評価し、全社的な管理プロセスに統合することが求められます。これらの取り組みは、コスト削減や新たな事業機会の創出にも繋がり、企業価値の向上に貢献します。