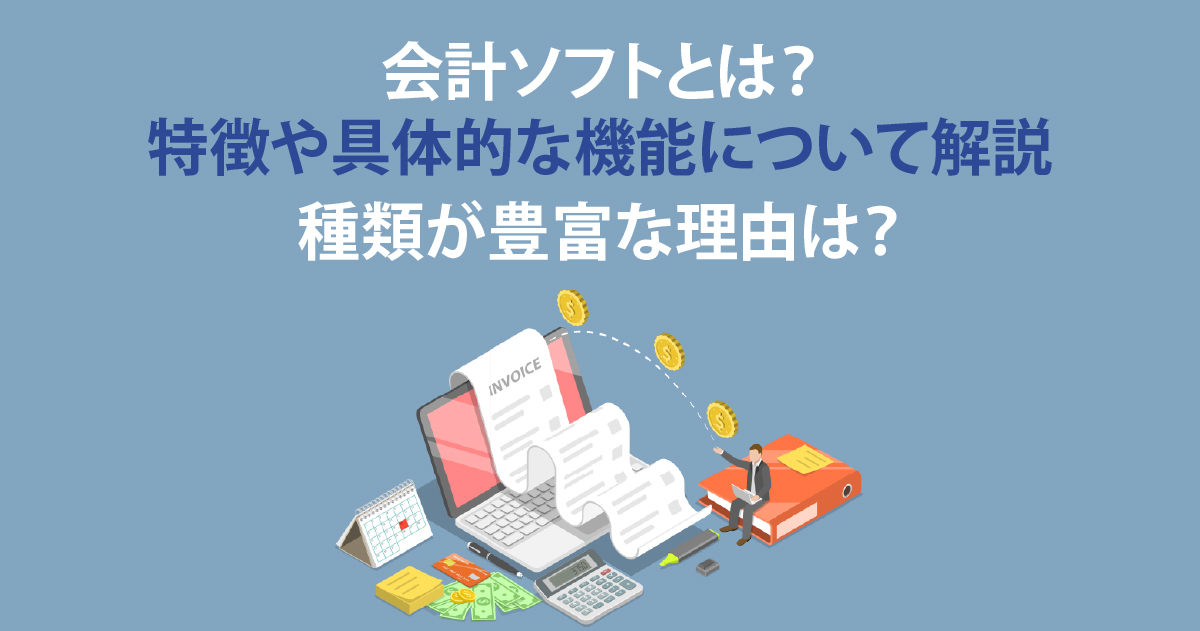クラウド会計のセキュリティ対策が重要視される背景

近年、中小企業や個人事業主を中心に、クラウド会計ソフトの導入が急速に進んでいます。場所や時間を選ばずに経理業務を行える利便性や、法改正への迅速な対応力が高く評価されているためです。
しかし、その利便性の裏側で、セキュリティ対策の重要性がかつてないほど高まっています。企業の生命線ともいえる財務情報をインターネット上で管理するということは、常に情報漏洩やサイバー攻撃のリスクと隣り合わせであることを意味します。
なぜ今、クラウド会計のセキュリティ対策がこれほどまでに重要視されるのか、その背景を3つの側面から詳しく解説します。
クラウド会計の急速な普及とDX推進の波
クラウド会計ソフトが広く受け入れられるようになった背景には、社会全体の大きな変化があります。政府が主導するDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正への対応、そしてテレワークの定着が、導入を強力に後押ししました。これらの変化に対応するため、多くの企業が従来のインストール型(オンプレミス型)ソフトからクラウド型へと移行しています。しかし、業務効率化や柔軟な働き方の実現といったメリットを享受する一方で、これまでとは異なる新たなセキュリティ上の脅威に直面しているという現実を認識しなければなりません。利便性が向上すればするほど、その裏に潜むリスクへの備えが不可欠となるのです。
扱う情報の機密性が極めて高い
クラウド会計ソフトが扱うデータは、企業の経営そのものと言っても過言ではありません。売上や利益といった財務状況はもちろん、取引先の情報、従業員の給与データなど、そのすべてが極めて機密性の高い情報です。もしこれらの情報が外部に漏洩すれば、その被害は計り知れません。直接的な金銭被害だけでなく、社会的信用の失墜、取引先からの契約打ち切り、顧客離れなど、事業の継続を揺るがす深刻な事態に発展する可能性があります。サイバー犯罪者にとって、これらの機密情報は非常に価値のある標的であり、常に狙われているという意識を持つことが重要です。
| 情報の種類 | 具体的な内容 | 漏洩した場合の主なリスク |
|---|---|---|
| 財務情報 | 売上、原価、利益、資産、負債、資金繰り | 経営戦略の漏洩、株価への影響、競合他社による悪用 |
| 取引先情報 | 企業名、担当者、連絡先、取引内容、請求情報 | 取引関係の悪化、信用の失墜、なりすまし詐欺への悪用 |
| 従業員情報 | 氏名、住所、給与・賞与額、マイナンバー | プライバシー侵害、従業員からの損害賠償請求 |
| 顧客情報 | 氏名、連絡先、購買履歴、クレジットカード情報 | ブランドイメージの低下、顧客からの損害賠償請求 |
サイバー攻撃の巧妙化と増加
企業を狙ったサイバー攻撃は年々増加しており、その手口も巧妙化・悪質化の一途をたどっています。特定の企業を狙い撃ちする「標的型攻撃」、データを人質に身代金を要求する「ランサムウェア」、偽のメールやウェブサイトで情報を盗み出す「フィッシング詐欺」など、その種類は多岐にわたります。インターネット経由でいつでもどこからでもアクセスできるクラウドサービスは、攻撃者にとって格好のターゲットとなり得ます。従来の社内ネットワークだけで完結していたオンプレミス型のセキュリティ対策だけでは、クラウド特有の脅威を防ぎきることはできません。クラウドという新しい環境に適した、より高度で多層的なセキュリティ対策を講じることが、すべての企業にとって急務となっているのです。
クラウド会計に潜む主なセキュリティリスク3つ

クラウド会計ソフトはインターネットを介して利用するため、従来のインストール型ソフトとは異なるセキュリティリスクが存在します。利便性の裏に潜む危険性を正しく理解することが、適切な対策を講じる第一歩です。ここでは、特に注意すべき3つの主要なセキュリティリスクについて詳しく解説します。これらのリスクは、企業の財務状況や信用に直接的な打撃を与える可能性があるため、決して軽視できません。
不正アクセスによる情報漏洩
クラウド会計における最も深刻なリスクの一つが、悪意のある第三者による不正アクセスです。攻撃者は盗み出したIDやパスワードを用いてシステムに侵入し、企業の機密情報を窃取しようとします。情報漏洩は、企業の信用を根底から揺るがし、顧客や取引先との関係にも深刻なダメージを与える可能性があります。
不正アクセスの主な手口としては、以下のようなものが挙げられます。
- パスワードリスト攻撃:他のサービスから流出したIDとパスワードの組み合わせを使い、ログインを試みる攻撃。複数のサービスで同じパスワードを使い回していると、被害に遭う危険性が非常に高まります。
- フィッシング詐欺:会計ソフトの提供者や金融機関を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してログイン情報を入力させる手口です。
- 推測されやすいパスワードの設定:「password」や「12345678」、会社名や担当者の誕生日など、容易に推測できるパスワードを設定していると、簡単に突破されてしまいます。
一度不正アクセスを許してしまうと、売上データ、仕入先情報、顧客情報、従業員の給与情報といった、経営の根幹に関わる機密情報が外部に流出する恐れがあります。これらの情報が悪用されれば、直接的な金銭被害だけでなく、取引先を巻き込んだ二次被害に発展するケースも少なくありません。
内部不正やヒューマンエラー
セキュリティリスクは、外部からの攻撃だけに限りません。従業員による意図的な不正行為や、悪意のない操作ミス(ヒューマンエラー)も、情報漏洩やデータ破損の大きな原因となります。外部対策と同様に、組織内部の管理体制や従業員への教育が極めて重要です。
具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
| リスクの種類 | 具体的な事例 |
|---|---|
| 内部不正 | 退職予定の従業員が、転職先で利用する目的で顧客リストや財務データをUSBメモリなどにコピーして持ち出す。あるいは、個人的な恨みから重要なデータを改ざん・削除する。 |
| ヒューマンエラー | 担当者が誤った操作で重要な取引データを削除してしまう。また、アクセス権限の設定ミスにより、本来閲覧権限のない従業員が機密情報(役員報酬や従業員の給与など)を閲覧できる状態になってしまう。 |
特に、従業員全員に管理者権限のような強い権限を与えている場合、たった一人のミスや不正行為が会社全体に甚大な被害を及ぼす可能性があります。内部からのリスクを防ぐためには、従業員の役職や業務内容に応じた適切なアクセス権限の管理が不可欠です。
データ消失やサービス停止
クラウド会計は、自社でサーバーを管理する必要がない反面、サービス提供者側のトラブルによって業務が停止するリスクを抱えています。これは、自社の努力だけではコントロールできない外部要因であり、ソフト選定時の重要な評価項目となります。
データ消失やサービス停止を引き起こす主な原因は以下の通りです。
- サーバー障害:クラウドサービスを提供しているデータセンターで、ハードウェアの故障やシステムトラブルが発生し、サービスにアクセスできなくなる。
- 自然災害:地震、火災、水害などの大規模な災害により、データセンターが物理的な損害を受け、サービスが停止する。
- サイバー攻撃:サービス提供者のシステムがDDoS攻撃などを受け、サーバーがダウンし、サービスが利用不能になる。
もしサービスが長時間停止すれば、請求書の発行や入金確認、経費精算といった日常業務が滞り、事業活動に支障をきたします。さらに、万が一、提供者側でバックアップ体制が不十分だった場合、会計データが完全に失われ、決算や税務申告が不可能になるという最悪の事態も想定されます。そのため、サービス提供者がどのような災害対策やバックアップ体制を構築しているかを確認することが非常に重要です。
クラウド会計のセキュリティは提供者と利用者の両面対策が必須

クラウド会計ソフトのセキュリティを考える上で最も重要なのは、「セキュリティ対策はソフト提供者と利用者の双方に責任がある」という認識を持つことです。どれだけ堅牢なシステムをソフト提供者が構築しても、利用者側の使い方に問題があれば、情報漏洩などのインシデントは容易に発生してしまいます。
この考え方は、クラウドサービス全般で「共同責任モデル」と呼ばれており、クラウド会計ソフトも例外ではありません。つまり、提供者が責任を持つ範囲と、利用者が責任を持つ範囲が明確に分かれているのです。安全にクラウド会計を利用するためには、まずこの責任分界点を正しく理解することが第一歩となります。
クラウドにおける「共同責任モデル」とは
共同責任モデルとは、クラウドサービスのセキュリティについて、クラウド提供事業者と利用者がそれぞれの責任範囲を分担し、協力して安全性を確保するという考え方です。具体的に、それぞれの責任範囲は以下のように分けられます。
- 提供者(ベンダー)の責任範囲:クラウドサービスを構成するインフラストラクチャ(データセンター、サーバー、ネットワーク、OSなど)のセキュリティを確保する責任。
- 利用者(ユーザー)の責任範囲:クラウドサービス上で扱うデータや、サービスへのアクセス管理(ID、パスワード、アクセス権限など)のセキュリティを確保する責任。
例えば、ソフト提供者はデータセンターへの物理的な侵入を防いだり、サーバーへのサイバー攻撃を防御したりする責任を負います。一方で、利用者は従業員が推測されやすいパスワードを使ったり、退職者のアカウントを放置したりしないよう管理する責任を負います。両者の対策が揃って初めて、クラウド会計のセキュリティは強固なものとなるのです。
責任範囲の具体例
提供者と利用者の責任範囲をより具体的に理解するために、以下の表で整理しました。自社がどこに責任を持つべきかを明確に把握しましょう。
| 対策項目 | 提供者(ベンダー)の責任範囲 | 利用者(ユーザー)の責任範囲 |
|---|---|---|
| データセンターの物理的セキュリティ | ◯(入退室管理、監視カメラ、災害対策など) | – |
| サーバー・ネットワークインフラ | ◯(不正侵入検知、DDoS攻撃対策など) | – |
| アプリケーションの脆弱性対策 | ◯(定期的な脆弱性診断、修正パッチの適用など) | – |
| データの暗号化・バックアップ | ◯(通信経路や保管データの暗号化、システムのバックアップ) | △(必要に応じて自社でもデータのバックアップを取得) |
| ID・パスワードの管理 | – | ◯(強力なパスワードの設定、定期的な変更) |
| 二段階認証の設定 | △(機能の提供) | ◯(機能の有効化と運用) |
| アクセス権限の管理 | △(機能の提供) | ◯(従業員ごとの適切な権限設定、棚卸し) |
| 利用端末・ネットワークの管理 | – | ◯(OSやソフトの最新化、ウイルス対策ソフトの導入、安全なWi-Fiの利用) |
| 社内セキュリティ教育 | – | ◯(フィッシング詐欺への注意喚起、情報リテラシー向上) |
このように、クラウド会計ソフトのセキュリティは、提供者側の対策に依存するだけでは不十分です。後の章で詳しく解説しますが、ソフトを選ぶ際には「提供者側の対策」を厳しくチェックし、導入後は「利用者側の対策」を徹底するという、両面からのアプローチが不可欠なのです。
【ソフト選びの基準】主要クラウド会計ソフト提供者側のセキュリティ対策

クラウド会計ソフトのセキュリティは、私たち利用者側の対策だけで万全になるわけではありません。大切な会社のデータを預ける以上、サービス提供者側がどのようなセキュリティ対策を講じているかを確認することは、ソフト選びにおける最も重要な基準の一つです。
ここでは、信頼できるクラウド会計ソフトを見極めるためにチェックすべき、提供者側の主要なセキュリティ対策について解説します。
データの暗号化(通信と保管)
クラウド会計ソフトでは、インターネットを介してデータの送受信が行われ、提供者のサーバーにデータが保管されます。そのため、「通信時」と「保管時」の両方でデータが暗号化されていることが必須です。
通信の暗号化には「SSL/TLS」という技術が用いられ、これにより第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎます。また、サーバーに保管されているデータ自体も暗号化することで、万が一サーバーからデータが流出しても、その内容を解読されるリスクを大幅に低減できます。ソフトを選ぶ際は、公式サイトなどで通信と保管の両方で強力な暗号化技術(例:AES256)を採用しているか必ず確認しましょう。
不正侵入検知・防御システム(IDS/IPS・WAF)
悪意のある第三者によるサイバー攻撃からデータを守るためには、サーバーを常時監視し、不正なアクセスを検知・防御する仕組みが欠かせません。その代表的なシステムが「IDS/IPS」と「WAF」です。
- IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム):ネットワークやサーバーへの不審な通信を検知し、管理者への通知や通信の遮断を行います。
- WAF(Webアプリケーションファイアウォール):Webアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃を特化して防御します。
これらのシステムが24時間365日体制で稼働していることで、外部からの脅威に対して多層的な防御が実現されます。多くの主要ソフトでは、これらのシステムの導入を明記しています。
第三者認証の取得(ISMS認証やプライバシーマーク)
提供者が「セキュリティは万全です」と主張するだけでは、その信頼性を客観的に判断するのは困難です。そこで重要になるのが、第三者機関による認証の取得状況です。
- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証:情報セキュリティに関する組織の管理体制が、国際規格「ISO/IEC 27001」に適合していることを示す認証です。特定の技術だけでなく、組織全体で情報セキュリティを適切に管理・運用している証となります。
- プライバシーマーク(Pマーク):個人情報の取り扱いが適切であることを示す認証です。日本産業規格「JIS Q 15001」に準拠した体制が整備されている企業に付与されます。
これらの認証を取得しているサービスは、客観的な基準で情報管理体制の信頼性が証明されていると言えます。ソフト選定時には、これらの認証マークの有無を確認することが安心材料の一つとなります。
【今日からできる】情報漏洩を防ぐ7つのセキュリティ対策チェックリスト

クラウド会計ソフト提供者側が高いレベルのセキュリティ対策を講じていても、それだけでは万全とは言えません。なぜなら、セキュリティインシデントの多くは、利用者側の不注意や設定ミスが原因で発生するからです。大切な会社の財務情報を守るためには、利用者自身がセキュリティ意識を高く持ち、適切な対策を実践することが不可欠です。ここでは、今日からすぐに取り組める7つの具体的なセキュリティ対策をチェックリスト形式で解説します。
強力なパスワードの設定と定期的な見直し
セキュリティ対策の基本であり、最も重要なのがパスワード管理です。推測されやすい単純なパスワードは、不正アクセスの最初の突破口となります。以下のポイントを守り、第三者に解読されにくい強力なパスワードを設定しましょう。
- 長さ: 最低でも12文字以上を推奨します。
- 複雑さ: 英大文字、英小文字、数字、記号をすべて組み合わせます。
- 独自性: 他のサービスで利用しているパスワードの使い回しは絶対に避けてください。
- 非推測性: 会社名、担当者名、生年月日など、個人情報や関連情報から推測できる文字列は使用しません。
また、設定したパスワードを長期間変更しないこともリスクを高めます。少なくとも3ヶ月に1回など、定期的にパスワードを見直すルールを社内で徹底しましょう。複数のパスワードを覚えるのが難しい場合は、パスワード管理ツールの導入も有効な手段です。
不正ログインを防ぐ二段階認証の有効化
二段階認証(2要素認証とも呼ばれます)は、IDとパスワードによる認証に加えて、スマートフォンアプリやSMSで受け取る確認コードなど、本人しか知り得ない情報を用いて二重の認証を行う仕組みです。この設定を有効にすることで、万が一パスワードが漏洩してしまった場合でも、第三者による不正ログインを極めて困難にできます。
現在、主要なクラウド会計ソフトでは、この二段階認証機能が標準で提供されています。設定は簡単で、セキュリティレベルを飛躍的に向上させることができるため、まだ設定していない場合は今すぐ有効化することを強く推奨します。
従業員ごとのアクセス権限の適切な管理
クラウド会計ソフトを複数の従業員で利用する場合、全員に同じ権限を与えるのは非常に危険です。内部不正や操作ミスのリスクを最小限に抑えるため、「必要最小限の権限(ミニマム・パーミッション)」の原則に基づき、従業員の役職や担当業務に応じてアクセスできる機能やデータを細かく設定しましょう。
例えば、以下のように権限を分けることで、情報漏洩や誤操作のリスクを低減できます。
| 役職・担当 | 権限設定の例 | 目的 |
|---|---|---|
| 経営者・管理者 | 全機能へのアクセス・設定変更 | 全体の管理・監督 |
| 経理担当者 | 仕訳入力、請求書発行、レポート閲覧 | 日常業務の遂行に必要な機能に限定 |
| 営業担当者 | 見積書・請求書の発行のみ | 全社の財務情報へのアクセスを遮断 |
また、従業員の退職や部署異動があった際には、速やかにアカウントの削除や権限の変更を行うことを忘れないでください。定期的に権限設定を見直す運用ルールを設けることが重要です。
利用端末とネットワーク環境の安全確保
クラウド会計ソフトにアクセスするパソコンやスマートフォン、タブレット端末自体のセキュリティが脆弱では、そこから情報が漏洩する可能性があります。以下の対策を徹底してください。
OSやソフトウェアのアップデート
OS(Windows, macOSなど)やブラウザ、ウイルス対策ソフトは常に最新の状態に保ちましょう。アップデートには、発見された脆弱性を修正する重要なセキュリティパッチが含まれています。
ウイルス対策ソフトの導入
業務用端末には必ず信頼できるウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを常に最新の状態に更新してください。これにより、マルウェアやスパイウェアの感染を防ぎます。
公共Wi-Fi利用時の注意
カフェやホテルなどの暗号化されていない、あるいはセキュリティレベルの低い公共Wi-Fi環境からクラウド会計ソフトにアクセスするのは非常に危険です。通信内容を盗聴されるリスクがあるため、極力利用を避け、やむを得ない場合はVPN(仮想プライベートネットワーク)を利用して通信を暗号化しましょう。
万が一に備えるデータのバックアップ
クラウド会計ソフトは提供者側でデータのバックアップを行っていますが、利用者側の操作ミスによるデータ削除や、予期せぬサービス障害に備え、自社でも定期的にデータをバックアップしておくことが賢明です。多くのソフトには、仕訳データや各種帳票をCSVやPDF形式でエクスポート(出力)する機能が備わっています。月末や決算期など、定期的にデータをエクスポートし、社内の安全な場所に保管する習慣をつけましょう。
不審な連携アプリやメールへの警戒
クラウド会計ソフトを装ったフィッシング詐欺にも注意が必要です。「パスワードを更新してください」「アカウントがロックされました」といった件名で偽のログインページへ誘導するメールが後を絶ちません。メール内のリンクは安易にクリックせず、必ず公式サイトのブックマークからアクセスするようにしてください。
また、API連携で他のサービスとデータを共有できるのはクラウド会計の利点ですが、提供元が不明なアプリや信頼性の低いサービスとの連携は避けましょう。不要になった連携は速やかに解除し、定期的に連携アプリの一覧を確認することも大切です。
社内でのセキュリティ意識の向上と共有
これまで挙げてきた対策は、従業員一人ひとりがその重要性を理解し、実践して初めて効果を発揮します。セキュリティ対策は、情報システム部門だけの仕事ではありません。組織全体で取り組むべき経営課題であるという認識を共有することが何よりも重要’mark>です。
社内でクラウド会計ソフトの利用に関するセキュリティポリシーや運用ルールを明確に定め、全従業員に周知徹底しましょう。また、定期的にセキュリティに関する研修会を開き、最新のサイバー攻撃の手口や対策について学ぶ機会を設けることで、組織全体のセキュリティリテラシーを高めていくことができます。
セキュリティ対策の観点から見たクラウド会計ソフトの選び方
これまで見てきたように、クラウド会計のセキュリティは、ソフト提供者側の堅牢なシステムと、利用者側の適切な運用の両輪で成り立っています。どちらか一方が欠けても、情報漏洩などの重大なインシデントにつながるリスクは高まります。そこで本章では、これまでの内容を踏まえ、自社にとって最も安全で最適なクラウド会計ソフトを選ぶための具体的なチェックポイントを解説します。
提供者のセキュリティ体制を客観的な指標で確認する
まず最も重要なのは、ソフト提供者がどのようなセキュリティ体制を構築しているかを、客観的な事実に基づいて評価することです。公式サイトの宣伝文句だけでなく、信頼できる第三者による評価や、具体的な技術情報の開示状況を確認しましょう。
第三者認証の取得状況
セキュリティ体制の信頼性を測る上で、最も分かりやすい指標が第三者認証の取得状況です。特に以下の認証は、厳格な審査基準をクリアした証であり、必ず確認すべき項目です。
- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証:情報セキュリティ管理体制が国際規格(ISO/IEC 27001)に適合していることを示す認証です。組織全体で情報を適切に管理する仕組みが整っている証明となります。
- プライバシーマーク:個人情報の取り扱いが適切であることを示す認証です。マイナンバーなどの重要な個人情報を取り扱う会計ソフトにおいて、この認証の有無は重要な判断材料です。
- SOC(Service Organization Control)報告書:外部の監査法人が、企業の内部統制の有効性を評価した報告書です。特に財務報告に関する内部統制を評価する「SOC1報告書」は、会計ソフトの信頼性に直結します。
セキュリティ情報の公開レベル
信頼できる提供者は、自社のセキュリティ対策について積極的に情報を公開しています。公式サイトに「セキュリティ・ホワイトペーパー」のような専門資料を用意しているか、また、データの暗号化方式(通信:TLS、保管:AES256など)、不正侵入検知・防御システム(IDS/IPS、WAF)の導入、脆弱性診断の実施状況などが具体的に明記されているかを確認しましょう。情報の透明性が高いほど、セキュリティに対する意識と自信の表れと判断できます。
利用者側で設定できるセキュリティ機能の充実度を比較する
提供者側の対策が万全でも、利用者側の設定が甘ければリスクは残ります。そのため、自社のセキュリティポリシーに合わせて柔軟な設定が可能か、機能の充実度を比較検討することが不可欠です。
- 二段階認証(多要素認証):ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリやSMSなど、別の要素での認証を必須にできる機能です。不正ログイン対策の基本であり、必ず対応しているソフトを選びましょう。
- アクセス権限の管理:従業員ごとに「閲覧のみ」「入力担当」「管理者」など、役割に応じて操作できる範囲を細かく設定できる機能です。内部不正や操作ミスのリスクを最小限に抑えるために極めて重要です。
- IPアドレス制限:社内ネットワークなど、許可されたIPアドレスからのみアクセスを許可する機能です。テレワーク環境なども考慮し、柔軟に設定できるかを確認しましょう。
- 操作ログの閲覧・監視:「いつ」「誰が」「どのデータを」「どう操作したか」を記録・確認できる機能です。不正の早期発見や原因究明に役立ちます。
万が一の事態に備えたサポート体制と実績
どれだけ対策を講じても、セキュリティリスクをゼロにすることはできません。万が一、インシデントが発生した際や、システムに障害が起きた場合に、迅速かつ適切なサポートを受けられるかは非常に重要です。データバックアップの頻度や体制、障害発生時の復旧プロセス、問い合わせ窓口の対応時間などを事前に確認しておきましょう。また、長年の運用実績や大手企業の導入事例も、サービスの安定性や信頼性を判断する上での参考になります。
【比較表】セキュリティ観点で選ぶクラウド会計ソフトのチェックポイント
最後に、これまで解説したポイントを一覧表にまとめました。ソフトを比較検討する際のチェックリストとしてご活用ください。
| 大項目 | チェックポイント | 確認事項 |
|---|---|---|
| 提供者の体制 | 第三者認証 | ISMS認証、プライバシーマーク、SOC報告書などを取得しているか |
| 技術的対策の公開 | データの暗号化方式、WAF等の導入、脆弱性診断の実施状況が明記されているか | |
| データセンター | 国内外の信頼性の高いデータセンターを利用しているか | |
| 利用者の機能 | 二段階認証 | 標準機能として利用できるか。認証方法の種類は豊富か |
| アクセス権限管理 | 役職や担当業務に応じて、機能ごとに細かく権限を設定できるか | |
| IPアドレス制限 | 特定のIPアドレスからのアクセスのみに制限できるか | |
| 操作ログ管理 | ユーザーの操作履歴を長期間保存し、いつでも確認できるか | |
| サポートと実績 | バックアップ体制 | データのバックアップは自動で行われるか。復旧手順は明確か |
| 障害・緊急時対応 | サポート窓口の対応時間や連絡手段は十分か。障害情報の公開は迅速か |
まとめ
本記事では、クラウド会計のセキュリティ対策について、ソフト提供者側と利用者側の両面から網羅的に解説しました。クラウド会計は業務効率を飛躍的に向上させる便利なツールですが、その裏には不正アクセスや内部不正による情報漏洩といった重大なリスクが潜んでいます。
安全な利用のための結論として、セキュリティ対策はソフト提供者任せにするのではなく、利用者自身も主体的に取り組むことが不可欠です。freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計 オンラインといった主要ソフトは、データの暗号化や第三者認証の取得など高水準の対策を講じていますが、最終的な情報資産を守るのは利用者自身に他なりません。
まずは、今回ご紹介した「7つのセキュリティ対策チェックリスト」を活用し、自社の運用体制を見直すことから始めましょう。強力なパスワードの設定や二段階認証の有効化、従業員のアクセス権限管理といった基本的な対策を徹底するだけでも、セキュリティレベルは格段に向上します。
提供者側の堅牢なセキュリティと、利用者側の高いセキュリティ意識。この両輪が揃って初めて、クラウド会計を安心・安全に活用できます。本記事を参考に、自社の大切な情報を守り、クラウド会計のメリットを最大限に引き出してください。