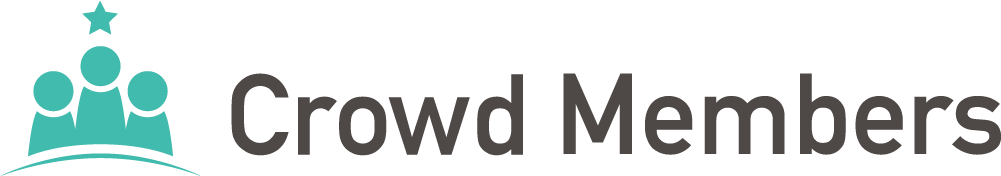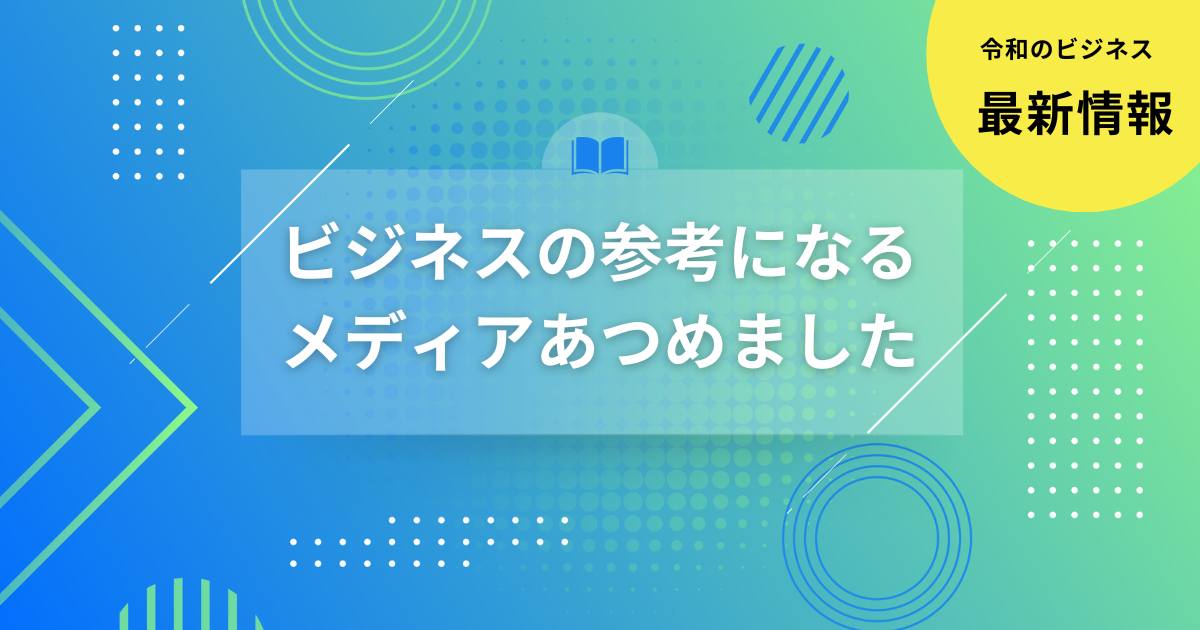新規事業育成が失敗するよくある3つの事例

多くの企業が未来の成長エンジンを求めて新規事業育成に乗り出しますが、その道のりは決して平坦ではありません。むしろ、成功するプロジェクトはほんの一握りというのが現実です。しかし、失敗は単なる無駄ではありません。失敗の裏には、組織が乗り越えるべき共通の課題が隠されています。
ここでは、多くの企業が陥りがちな3つの典型的な失敗事例を深掘りし、そこから得られる教訓を探ります。
イノベーションのジレンマ
「イノベーションのジレンマ」とは、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した理論です。これは、優良企業が既存顧客のニーズに応え、現在の主力事業を改善し続けることで、結果的に市場の構造を破壊するような新しい技術やビジネスモデル(破壊的イノベーション)に対応できなくなり、新興企業に市場を奪われてしまうという現象を指します。
巨大企業がこのジレンマに陥る背景には、成功体験に根差した強固な組織構造と価値基準があります。
- 既存顧客の声の重視:企業は主要な収益源である既存顧客の意見を最優先します。しかし、破壊的イノベーションは当初、既存市場の顧客からは評価されないニッチな市場から生まれることが多く、優良企業のアンテナにはかかりにくいのです。
- リソース配分の論理:新規事業は当初、市場規模が小さく、収益性も不透明です。そのため、確実なリターンが見込める既存事業に優先的に経営資源(ヒト・モノ・カネ)が配分され、革新的なアイデアの芽が育ちません。
- 既存の評価プロセス:確立された事業計画や投資判断のプロセスは、予測可能性の高い持続的イノベーションには適していますが、不確実性の高い破壊的イノベーションの評価には不向きです。
このジレンマは、決して経営陣が無能であるために起こるわけではありません。むしろ、合理的な経営判断を積み重ねた結果として、巨大な船がゆっくりと沈んでいくように進行するのが特徴です。持続的イノベーションと破壊的イノベーションの違いを理解することが、この罠を回避する第一歩となります。
| 比較項目 | 持続的イノベーション | 破壊的イノベーション |
|---|---|---|
| ターゲット顧客 | 既存市場の主要顧客 | 新規市場または既存市場のローエンド層 |
| 技術・性能 | 既存製品の性能向上(高機能化、高品質化) | シンプル、低価格、便利など、異なる価値基準を持つ |
| 市場への影響 | 既存市場の維持・拡大 | 新しい市場を創造、または既存市場を破壊・再定義 |
| 収益性 | 予測しやすく、利益率が高い傾向 | 当初は不透明で、利益率が低い傾向 |
| リスク | 比較的低い | 非常に高い(不確実性が高い) |
減点主義の評価制度と短期的なROIの追求
新規事業育成を阻むもう一つの大きな壁が、組織の評価制度とそれに伴う文化です。特に、日本企業に根強く残る「減点主義」は、新しい挑戦の前に立ちはだかります。
減点主義の文化では、成功して100点を取るよりも、失敗してマイナス評価を受けることを避けるインセンティブが強く働きます。新規事業は本質的に失敗の連続であり、「失敗は許されない」というプレッシャーは、担当者から大胆な挑戦への意欲を奪い、前例踏襲の無難なアイデアへと向かわせます。一度の失敗がキャリアの汚点となるような環境では、誰もリスクを取ろうとはしません。
この文化をさらに強化するのが、短期的な投資対効果(ROI)を過度に追求する経営姿勢です。既存事業の評価指標である売上や利益、ROIを、まだ顧客も定まっていない新規事業の初期フェーズから厳しく適用してしまうと、以下のような問題が生じます。
- 早期の収益化への圧力:本来、顧客課題の発見や仮説検証に時間をかけるべき段階で収益化を急がされ、中長期的に大きな可能性を持つアイデアが「儲からない」という理由で切り捨てられます。
- 小規模な成功への固執:大きなリスクを伴うが革新的なアイデアよりも、小さくても確実に成果が出そうな、既存事業の延長線上にあるテーマばかりが選ばれるようになります。
- 学習機会の損失:失敗から得られる学びこそが新規事業の資産であるにもかかわらず、それを評価する仕組みがないため、組織に知見が蓄積されません。
新規事業の初期段階で測るべきは、売上高ではなく「どれだけ顧客について学べたか」「どれだけ多くの仮説を検証できたか」といった学習の進捗です。既存事業とは異なる評価のモノサシを持たない限り、イノベーションの芽は育ちません。
縦割り組織による部門間の対立
企業の組織構造そのものが、新規事業の障壁となるケースも少なくありません。多くの大企業で見られる機能別に最適化された「縦割り組織(サイロ)」は、既存事業の効率的な運営には適していますが、部門を横断する連携が不可欠な新規事業にとっては大きな足かせとなります。
新規事業担当者が直面する部門間の壁は、主に以下の3つです。
- 既存事業部との対立:新規事業が自社の既存事業と競合する、いわゆる「カニバリゼーション」を恐れる既存事業部からの抵抗は根強いものがあります。協力が得られないばかりか、優秀な人材の異動を拒んだり、予算配分で対立したりと、社内でのリソース獲得競争が激化します。
- 管理部門との摩擦:法務、経理、人事といった管理部門は、社内規定やコンプライアンスを遵守する役割を担っています。しかし、そのルールが前例のない取り組みを前提としていないため、新規事業のスピード感を著しく阻害することがあります。「前例がない」「リスクが不明確」といった理由で承認が遅れ、市場投入のタイミングを逃してしまうのです。
- 技術・情報部門の非協力:各部門が持つ技術、データ、顧客情報などが共有されず、サイロの中に閉じ込められている状態も問題です。全社の知見を結集すれば大きなイノベーションにつながる可能性があるにもかかわらず、部門の壁がそれを阻み、結果として車輪の再発明のような非効率が発生します。
こうした部門間の対立や連携不足は、担当者のエネルギーを社内調整に消耗させ、本来向けるべき市場や顧客から目を逸らさせてしまいます。組織全体で新規事業を育成するという共通認識がなければ、どんなに優れたアイデアも組織の壁に阻まれて立ち消えになってしまうのです。
壁を乗り越える!新規事業育成を成功に導く組織の条件

前章で解説したように、多くの新規事業は「イノベーションのジレンマ」や「既存組織との軋轢」といった根深い課題によって頓挫します。これらの失敗は、担当者の能力不足というよりも、むしろ事業を育む「土壌」である組織の在り方に起因することがほとんどです。裏を返せば、新規事業が生まれ育つ組織的な条件を整備することこそが、成功への最も確実な道筋となります。
本章では、失敗の壁を乗り越え、イノベーションを継続的に生み出すための組織の条件を具体的に解説します。
心理的安全性の確保と挑戦を奨励する文化
新規事業育成において、最も重要かつ根幹となるのが「心理的安全性」です。心理的安全性とは、チームの誰もが「こんなことを言ったら馬鹿にされるかもしれない」「失敗したら責められるだろう」といった不安を感じることなく、安心して自分の意見を述べたり、リスクのある挑戦をしたりできる状態を指します。この概念は、米Google社が生産性の高いチームの共通点を探るために実施した調査「プロジェクト・アリストテレス」によって、成功の最も重要な因子であることが明らかにされました。
新規事業は、前例のない不確実な道のりを進む活動です。誰も正解を知らないからこそ、チームメンバー一人ひとりが持つ多様な視点や気づき、そして大胆なアイデアが不可欠です。心理的安全性が確保されていない組織では、メンバーは萎縮し、当たり障りのない意見しか出なくなります。その結果、致命的な問題が見過ごされたり、画期的なアイデアの芽が摘まれたりしてしまうのです。
「失敗」の再定義:学習機会としての失敗
挑戦を奨励する文化を醸成するためには、まず「失敗」に対する組織全体の認識を変える必要があります。新規事業における失敗は、単なる「間違い」や「敗北」ではありません。それは「市場や顧客を理解するための貴重なデータを得られた学習機会」なのです。重要なのは、失敗そのものを責めるのではなく、その失敗から何を学び、次にどう活かすかをチーム全体で考える文化を根付かせることです。
例えば、失敗事例を共有し、その要因と学びを称賛する「失敗共有会」のような場を設けたり、挑戦のプロセス自体をナレッジとして蓄積・共有する仕組みを構築したりすることが有効です。
評価制度の見直し:挑戦を評価する仕組み
従来の減点主義や短期的な売上・利益のみを評価する制度は、新規事業の担当者から挑戦する意欲を奪います。なぜなら、不確実性の高い新規事業では、短期的に成果が出ないことや、失敗する確率の方が高いからです。そこで、挑戦したプロセスや、そこから得られた学び、顧客課題の解決に向けた進捗などを評価する新しい仕組みが求められます。
目標設定フレームワークである「OKR(Objectives and Key Results)」の導入も有効な手段の一つです。OKRは、達成が困難な野心的な目標(Objectives)を掲げ、その進捗を測る具体的な指標(Key Results)を設定します。達成度が60〜70%でも成功と見なされることが多く、結果だけでなくプロセスにおける挑戦を評価する文化と非常に相性が良いとされています。
心理的安全性を高め、挑戦を促す具体的な施策
文化や風土といった目に見えないものを変えるには、具体的な制度や施策が必要です。以下にその一例を挙げます。
| 施策カテゴリ | 具体的な施策内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 対話の促進 | 1on1ミーティングの定例化、役職や部門を超えた対話の場の設定(タウンホールミーティングなど) | 上司・部下間の信頼関係構築、風通しの良いコミュニケーションの実現 |
| 機会の提供 | 社内ビジネスコンテスト、アイデアソンの開催、社内副業制度の導入 | 挑戦意欲の喚起、潜在的なアイデアや人材の発掘 |
| 意思決定の支援 | 失敗から学ぶ「ふりかえり(レトロスペクティブ)」の定着、撤退基準の事前設定 | サンクコスト(埋没費用)に囚われない合理的な判断の促進、失敗からの迅速な学習 |
経営トップによる強力なバックアップ
心理的安全性の高い文化づくりと並行して、絶対に欠かせないのが経営トップによる強力なバックアップです。新規事業は、既存事業から見れば「リソースを奪う厄介者」であり、時には既存事業の領域を脅かす(カニバリゼーション)存在にもなり得ます。社内のさまざまな部署から抵抗や反発を受けることは避けられません。こうした逆風から新規事業チームを守り、推進力を与える「防波堤」であり「エンジン」となるのが経営トップの役割です。
ビジョンとミッションの明確化
経営トップがまず行うべきは、「なぜ今、この新規事業に取り組む必要があるのか」を自らの言葉で、情熱を持って社内外に語り続けることです。会社の未来像(ビジョン)や社会における存在意義(ミッション)と新規事業を結びつけ、全社的な「大義」として位置づけることで、従業員の共感と協力を得やすくします。
このビジョンが明確であればあるほど、現場の担当者は日々の困難な判断に迫られた際に、「会社の目指す方向性に合っているか」という揺るぎないコンパスを持つことができます。
リソースの確保と大胆な権限移譲
「言うは易く行うは難し」で、言葉だけの応援では事業は進みません。経営トップは、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営リソースを、既存事業の論理に捉われず、聖域なく配分する覚悟が求められます。特に、優秀な人材を新規事業チームに配置することは、経営の本気度を社内に示す強力なメッセージとなります。
さらに、スピードが命である新規事業においては、意思決定のプロセスを短縮するための「権限移譲」が不可欠です。稟議書を回し、何人もの承認を得なければ何も進められないような従来のやり方では、市場の変化に対応できません。担当チームに予算執行や採用に関する一定の裁量権を与え、迅速に仮説検証サイクルを回せる環境を整えることが成功の鍵を握ります。
社内調整と「守護神」としての役割
新規事業が既存事業部門の協力なしに成功することは稀です。しかし、前述の通り、両者の間には利害の対立が生まれがちです。ここで経営トップが「守護神」としての役割を果たさなければなりません。既存事業部門からの過度な干渉や短期的な成果要求からチームを守り、部門間の対立が発生した際には、より高い視点から仲裁し、全社最適の判断を下すことが求められます。
時には、既存組織のルールや慣習から隔離された「出島」のような独立した組織を設置することも有効な手段です。これにより、新規事業チームは既存のしがらみから解放され、自由な発想とスピーディーな行動で事業開発に集中することができます。
新規事業育成を進める際の重要な思考法

既存事業の成功体験や評価基準をそのまま持ち込むと、新規事業は頓挫しがちです。不確実性が高く、前例のない挑戦である新規事業を成功に導くためには、特有の思考法(マインドセット)とフレームワークが不可欠です。
そこで、担当者が必ず押さえておくべき3つの重要な思考法を、具体的な手法とともに解説します。
顧客課題の深掘りから始める(ジョブ理論)
多くの新規事業が失敗する原因の一つに、「作り手が良いと信じるもの」と「顧客が本当に求めているもの」のズレがあります。このズレを防ぐために非常に有効なのが、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した「ジョブ理論(Jobs to be Done)」です。
ジョブ理論とは、「顧客は製品やサービスを購入しているのではなく、特定の状況で片付けたい『用事(ジョブ)』を解決するために、それらを『雇用』している」という考え方です。顧客の属性(年齢、性別など)や製品の機能に着目するのではなく、顧客がどのような状況(コンテキスト)で、何を成し遂げたいのかという根本的な動機を深く理解しようと試みます。
例えば、朝の通勤途中にミルクシェイクを買う人は、単に「甘いものが飲みたい」のではなく、「長くて退屈な車通勤の時間を紛らわし、かつ片手で手軽に空腹を満たせるもの」というジョブを片付けるためにミルクシェイクを“雇用”しているのかもしれません。この本質的なジョブを理解できれば、競合は他の飲料だけでなく、バナナやドーナツ、さらにはオーディオブックにまで広がり、全く新しい解決策のヒントが見えてきます。
新規事業のアイデアを考える際は、まず「私たちの製品・サービスによって、顧客はどんなジョブを片付けられるのか?」を徹底的に自問自答し、顧客インタビューや行動観察を通じてその解像度を高めていくことが、成功への第一歩となります。
アジャイルな開発と高速な仮説検証サイクル(リーンスタートアップ)
新規事業は、未知の要素が多く、当初の計画通りに進むことはほとんどありません。完璧な事業計画を立ててから壮大なシステムを開発する従来型の進め方(ウォーターフォール型)では、市場のニーズとズレていた場合に莫大な損失を生むリスクがあります。そこで重要になるのが、エリック・リースが提唱した「リーンスタートアップ」という手法です。
リーンスタートアップの核心は、「構築(Build)-計測(Measure)-学習(Learn)」というフィードバックループを可能な限り速く回すことにあります。まず、事業の根幹となる仮説を検証するための最小限の機能を持った製品「MVP(Minimum Viable Product)」を迅速に構築します。MVPは完成品である必要はなく、顧客の課題を解決できるか、その解決策にお金を払う価値があるかを検証できる最低限のもので十分です。
次に、そのMVPを実際の顧客に提供し、その反応や行動データを計測します。そして、得られたデータから学びを得て、次の打ち手(製品の改善、ターゲットの変更など)を決定し、再びMVPを構築する、というサイクルを繰り返します。この高速な仮説検証サイクルにより、無駄な開発を最小限に抑え、顧客が本当に求める価値を効率的に見つけ出すことが可能になります。
| 観点 | リーンスタートアップ | 従来型(ウォーターフォール)開発 |
|---|---|---|
| 開発思想 | 仮説検証と学習の繰り返し | 綿密な計画と仕様通りの実行 |
| プロダクト | MVPから始め、継続的に改善 | 最初から完成品を目指す |
| 顧客の関与 | 開発の初期段階から継続的に関与 | 主に要件定義と受け入れテストの段階で関与 |
| 失敗に対する考え方 | 学習の機会として歓迎 | 避けるべきもの、計画の不備 |
| 意思決定 | データと顧客からの学びに基づく | 当初の計画と仕様書に基づく |
ピボット(方向転換)を恐れない意思決定
リーンスタートアップの仮説検証サイクルを回す中で、当初立てた事業の根幹となる仮説が、実は間違っていたと判明することがあります。その際に必要となるのが「ピボット(Pivot)」、すなわち事業の方向転換です。
ピボットは、単なる計画変更や失敗を意味するものではありません。それまでの活動で得られた「学び」を活かし、より成功確率の高い方向へと戦略的に舵を切る意思決定です。例えば、以下のような種類があります。
- 顧客セグメントのピボット: 製品は変えずに、ターゲットとする顧客層を変更する。(例: 若者向けSNSを、ビジネスパーソン向けの情報共有ツールに転換)
- 課題のピボット: ターゲット顧客は同じまま、より深刻で解決価値の高い別の課題に取り組む。
- ソリューションのピボット: 顧客の課題は正しいと確信したが、現在の解決策(製品・技術)では不十分だと判断し、全く新しいアプローチで解決を目指す。
- 収益モデルのピボット: 価値提供の方法はそのままに、収益化の方法を変更する。(例: 製品の売り切りモデルから、月額課金のサブスクリプションモデルへ転換)
新規事業の担当者や経営層は、初期のアイデアに固執することなく、客観的なデータや顧客の声に真摯に耳を傾け、時には大胆な方向転換を決断する勇気が求められます。ピボットを恐れて間違った道を進み続けることは、貴重なリソース(時間・資金・人材)を浪費するだけです。ピボットは失敗ではなく、成功に近づくための賢明なプロセスの一部であると捉えることが重要です。
新規事業育成を加速させる外部リソースの活用法

新規事業を自社のリソースだけで完結させようとすると、スピードの低下やアイデアの枯渇を招きがちです。現代の急速に変化する市場環境において、自前主義から脱却し、外部の知識、技術、資本を積極的に活用することは、成功の確率を高める上で不可欠な戦略となっています。
ここでは、新規事業育成を加速させるための代表的な外部リソース活用法を3つ解説します。
スタートアップ企業との連携:オープンイノベーション
オープンイノベーションとは、自社の技術やアイデアに固執するのではなく、社外の組織が持つ技術、アイデア、サービス、ノウハウなどを積極的に取り入れ、革新的な価値を創造する考え方です。特に、最先端の技術や斬新なビジネスモデルを持つスタートアップ企業との連携は、大企業にとって大きなメリットをもたらします。
スタートアップ連携の主なメリットは以下の通りです。
- 開発スピードの向上:意思決定が速く、アジャイルな開発を得意とするスタートアップと組むことで、事業化までの時間を大幅に短縮できます。
- 革新的な技術・アイデアの獲得:自社にない専門技術や、既存の常識を覆すような新しい発想にアクセスできます。 –
- 新規市場へのアクセス:スタートアップが既に開拓しているニッチな市場や、新しい顧客層への足がかりを築くことができます。
- 企業文化への刺激:失敗を恐れず挑戦を続けるスタートアップの文化に触れることで、自社の組織風土に変革をもたらすきっかけとなります。
連携の具体的な手法は、目的やフェーズに応じて多岐にわたります。
| 連携手法 | 概要 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 業務提携・共同開発 | 互いの強み(技術、販売網など)を活かし、共同で製品開発やサービス提供を行う。 | 製品・サービスの高度化、開発期間の短縮 |
| アクセラレータープログラム | テーマを定めてスタートアップを公募し、出資やメンタリングを通じて短期間で事業共創を目指す。 | 幅広い技術・アイデアの探索、協業パートナーの発掘 |
| M&A(合併・買収) | スタートアップ企業を買収し、その技術や人材、事業を丸ごと取り込む。 | 事業ポートフォリオの抜本的な転換、市場投入時間の劇的な短縮 |
経済産業省も日本の産業競争力強化のためにオープンイノベーションを推進しており、多くの企業がこの動きに追随しています。参考:オープンイノベーション | 経済産業省
CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の設立
CVC(Corporate Venture Capital)とは、事業会社が自己資金でファンドを組成し、主に自社の事業領域と関連性の高いスタートアップ企業に投資を行う活動、またはその組織を指します。独立系のVC(ベンチャーキャピタル)が純粋な財務的リターン(キャピタルゲイン)を主な目的とするのに対し、CVCはそれに加えて本業との事業シナジー創出を最大の目的とする点が大きな特徴です。
CVCを設立することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 戦略的な情報収集(センシング):投資活動を通じて、業界の最新技術動向や新たなビジネスモデル、市場の変化などをいち早く察知できます。
- 将来の協業・M&A候補の探索:出資を通じてスタートアップと中長期的な関係を構築し、将来の事業提携やM&Aの可能性をじっくりと見極めることができます。
- イノベーション文化の醸成:社外の最先端で奮闘する起業家たちと接点を持つことで、社内にイノベーションの必要性やスピード感といった意識を浸透させる効果が期待できます。
CVCの運営を成功させるには、経営陣の強いコミットメントのもと、投資判断のスピードを担保するための独立した意思決定プロセスを確立し、投資先企業に対して資金提供だけでなく、自社のアセット(販路、研究施設、ブランド力など)を提供するなど、積極的な支援(ハンズオン)を行うことが重要です。これにより、単なる投資家としてではなく、事業を共に成長させるパートナーとしての信頼関係を築くことができます。
外部コンサルタントや専門家の知見を借りる
新規事業は、既存事業とは異なる知識やスキルセットが求められる場面が数多くあります。市場調査、ビジネスモデルの構築、技術検証、知財戦略、法務など、すべての分野を社内人材だけでカバーするのは困難です。このような場面で、外部のコンサルタントや専門家の知見を借りることは非常に有効な手段となります。
外部専門家を活用する最大のメリットは、社内の論理や固定観念から脱却し、客観的な視点を得られることです。長年同じ業界にいると、無意識のうちに視野が狭くなりがちですが、第三者の冷静な分析や他業界の成功事例に基づいた提言は、プロジェクトの方向性を正す上で大きな助けとなります。
活用すべき具体的な場面としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 事業計画の策定フェーズ:市場規模の算出や競合分析、収益モデルの妥当性評価など、専門的なフレームワークを用いた精度の高い計画策定を支援してもらえます。
- 技術的な壁に直面した際:特定の技術領域(例:AI、ブロックチェーン)に精通した専門家から、技術的なアドバイスや開発パートナーの紹介を受けることができます。
- 仮説検証(PoC)の設計・実行:限られたリソースの中で、最も効果的・効率的に事業の仮説を検証するためのプロセス設計や実行支援を依頼できます。
- 組織体制の構築:新規事業に適した人事評価制度やインセンティブ設計など、組織論に関する専門家の知見を借りることで、チームのモチベーションを最大化できます。
コンサルタントや専門家を選ぶ際は、単にレポートを提出するだけでなく、プロジェクトに深く入り込み、汗をかいてくれる「伴走型」のパートナーを見つけることが成功の鍵となります。
国内企業の新規事業育成の成功事例から学ぶ
理論や思考法を学んでも、具体的なイメージが湧きづらいかもしれません。ここでは、日本国内で新規事業育成に成功している企業の事例を3つ取り上げ、その成功の裏側にある仕組みや文化を深掘りします。自社の状況と照らし合わせながら、取り入れられるヒントを見つけていきましょう。
リクルートホールディングス
リクルートは「アントレプレナーシップ(起業家精神)」を組織文化の根幹に据え、数多くの新規事業を生み出してきた代表的な企業です。その原動力となっているのが、1982年から続く新規事業提案制度「Ring」です。
Ring:社員起点のボトムアップ型イノベーション
「Ring」は、リクルートグループの従業員なら誰でも、領域を問わず新規事業を提案できる制度です。単なるアイデアコンテストではなく、最終審査を通過した案件は事業化が約束され、提案者自らが責任者として事業を推進することが大きな特徴です。この制度から「ゼクシィ」や「スタディサプリ」「ホットペッパー」といった、今や社会インフラともいえる事業が誕生しました。
成功の背景には、個人の「Will(やりたいこと)」を尊重し、挑戦を称賛する企業文化があります。審査過程では、役員がメンターとして伴走し、事業計画を徹底的に磨き上げます。たとえ事業化に至らなくても、その挑戦のプロセス自体が個人の成長につながるという考え方が根付いており、失敗を恐れずに挑戦できる土壌を醸成しています。
徹底した「当事者意識」の醸成
リクルートの新規事業育成は、制度だけでなく、社員一人ひとりのマインドセットに支えられています。「お前はどうしたい?」と常に問われる文化の中で、社員は自らが事業の主役であるという「当事者意識」を強く持ちます。この当事者意識こそが、困難な事業立ち上げを乗り越えるための強力なエンジンとなっているのです。
ソニーグループ
エレクトロニクスからエンタテインメント、金融まで多岐にわたる事業を展開するソニーグループは、その多様な技術シーズと人材を活かした新規事業創出の仕組みを構築しています。その中核を担うのが「Sony Startup Acceleration Program(SSAP)」です。
Sony Startup Acceleration Program (SSAP)によるエコシステムの構築
SSAPは、2014年にスタートした新規事業創出プログラムです。特徴的なのは、ソニー社内のアイデアだけでなく、社外のスタートアップや大企業の新規事業も支援対象としている点です。オーディションで選ばれたアイデアに対し、ソニーが培ってきた製品開発やマーケティング、販売などのノウハウを提供し、事業化までを一気通貫でサポートします。このプログラムから、スマートウォッチ「wena wrist」や、エンタテインメントロボット「aibo」の復活など、ソニーらしいユニークな製品・サービスが生まれています。
SSAPは、単なる社内制度に留まらず、外部の知見やアイデアを積極的に取り込むオープンイノベーションのプラットフォームとして機能しており、ソニーグループ全体のイノベーションエコシステムを形成しています。
「技術」と「クリエイティビティ」の融合
ソニーの強みは、世界トップレベルの技術力です。しかし、技術があるだけでは新しい価値は生まれません。SSAPでは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というグループのPurpose(存在意義)に基づき、技術者が持つシーズと、クリエイターの自由な発想を掛け合わせることを重視しています。この異分野の才能の融合が、人々の心を動かす革新的な新規事業の源泉となっています。
富士フイルム
富士フイルムは、写真フィルムという主力事業の市場が急激に縮小するという存亡の危機を乗り越え、ヘルスケアや高機能材料などの分野で成長を遂げた「事業ポートフォリオ転換」の代表的な成功事例です。
「第二の創業」を支えたコア技術の水平展開
同社は、写真フィルムの製造で培った高度な独自技術を棚卸しし、それらを全く異なる市場に応用できないか徹底的に分析しました。例えば、以下のような技術の転用が挙げられます。
| 写真フィルムで培ったコア技術 | 応用された新規事業分野 | 具体的な製品・サービス |
|---|---|---|
| コラーゲン研究、抗酸化技術 | ヘルスケア(化粧品) | 「アスタリフト」シリーズ |
| 精密な薄膜塗布技術(ナノテクノロジー) | 高機能材料 | 液晶ディスプレイ用フィルム |
| 化学合成技術、品質設計技術 | 医薬品 | 医薬品の開発・製造受託(CDMO) |
既存事業の強みである「コア技術」を深く理解し、その応用可能性をゼロベースで探索するというアプローチは、多くの企業にとって参考になるはずです。これは、自社の資産を再評価し、新たな価値創造につなげる戦略的な思考法と言えます。
大胆なM&Aによる事業領域の拡大
富士フイルムは、自社の技術だけでは足りない部分を補い、事業化のスピードを加速させるために、積極的なM&A(企業の合併・買収)も活用しています。特にヘルスケア領域では、医薬品や再生医療分野の有力企業を次々と買収し、短期間で事業の柱を構築しました。自前主義に固執せず、外部リソースを戦略的に活用する意思決定が、劇的な事業転換を成功に導いた重要な要因です。
これから新規事業育成の担当者になるあなたへ

この記事をここまで読み進めてくださったあなたは、これから新規事業育成という、やりがいと困難に満ちた航海へ出発する船長、あるいは航海士なのかもしれません。大きな期待を寄せられる一方で、前例のない挑戦に対するプレッシャーや、何から手をつければよいのかという不安も感じているのではないでしょうか。
新規事業育成は、単なる新商品開発ではありません。企業の未来を創り、ときには社会に新たな価値をもたらす、極めて創造的で尊い仕事です。この章では、そんな大役を任されたあなたが、自信を持って第一歩を踏み出すための心構えと具体的なアクションプランを解説します。
担当者が持つべき3つのマインドセット
不確実性の高い新規事業を推進するには、既存事業とは異なる特別なマインドセットが求められます。困難な状況でも道を切り拓くために、以下の3つの心を常に携えてください。
失敗を恐れない「実験」のマインド
新規事業の世界では、失敗は避けて通れません。むしろ、失敗は「うまくいかない方法」を学んだ貴重なデータであり、成功に向けた学習プロセスの一部です。最初から完璧な計画を立てるのではなく、「これは壮大な実験なのだ」と捉えましょう。小さな仮説を立て、素早くプロトタイプを作り、市場に問いかける。このサイクルを高速で回すことで、致命的な失敗を避けながら、成功への確度を高めていくことができます。すべての結果は、次の一手を考えるための重要な学びなのです。
社内外を巻き込む「越境」のマインド
あなたのアイデアや情熱だけでは、事業を形にすることはできません。新規事業は、多様な知識、スキル、視点が交差する場所で生まれます。自部署の壁、さらには会社の壁を軽々と「越境」し、積極的に仲間を探しにいきましょう。他部署のキーパーソン、技術シーズを持つ研究者、外部の専門家、スタートアップの起業家など、様々な人を巻き込む力が事業の成否を分けます。日頃から社内外に人的ネットワークを築き、「この指とまれ」と声を上げたときに、力を貸してくれる仲間を増やしておくことが、あなたの強力な武器となります。
粘り強くやり抜く「執念」のマインド
新規事業の道のりは、決して平坦ではありません。予算の壁、社内の抵抗、技術的な課題、顧客の無反応など、数えきれないほどの困難が待ち受けています。心が折れそうになる瞬間も一度や二度ではないでしょう。しかし、そこで事業の未来を信じ、どんな逆風にも屈せず、粘り強くやり抜く「執念」とも呼べる強い意志が不可欠です。なぜこの事業を成し遂げたいのか、という自分自身の内なる情熱(インサイト)と、社会や顧客に対する使命感を持ち続けることが、困難を乗り越える原動力となります。
担当者に求められるスキルセット
マインドセットと同時に、具体的なスキルを磨くことも重要です。新規事業担当者は、特定の専門性だけでなく、幅広い領域をカバーする「総合力」が求められます。ここでは、特に重要となるスキルを3つのカテゴリーに分けてご紹介します。
| スキルカテゴリー | 具体的なスキル名 | スキルの概要 |
|---|---|---|
| 思考・戦略系スキル | 仮説構築力 | 限られた情報から、事業の成功確度を高めるための「問い」を立てる能力。顧客課題やソリューションに関する仮説を言語化し、検証可能な形に落とし込む力。 |
| 思考・戦略系スキル | 情報収集・分析力 | 市場トレンド、競合動向、顧客インタビューなどから必要な情報を効率的に収集し、事業機会を見出すためのインサイトを抽出する能力。 |
| 実行・推進系スキル | プロジェクトマネジメント | ゴール設定、タスク分解、進捗管理、リスク管理など、不確実なプロジェクトを計画通りに、あるいは計画を修正しながら推進していく能力。 |
| 実行・推進系スキル | ファシリテーション | 多様なバックグラウンドを持つメンバーとの会議やワークショップを円滑に進行し、創造的なアイデアを引き出し、合意形成を促す能力。 |
| 対人・組織系スキル | プレゼンテーション | 経営層や協力者に対し、事業のビジョンや計画を論理的かつ情熱的に伝え、共感と協力を得るための表現力。 |
| 対人・組織系スキル | 交渉・調整力 | 社内外のステークホルダーとの利害を調整し、予算やリソースの獲得、協力体制の構築などを実現する能力。 |
これらのスキルは、最初からすべて完璧に備わっている必要はありません。日々の業務や研修、読書などを通じて、意識的に伸ばしていくことが大切です。
最初の100日でやるべきこと
担当者に任命された直後の期間は、今後の活動の方向性を決定づける非常に重要な時期です。闇雲に動き出すのではなく、戦略的に行動しましょう。ここでは、最初の100日で取り組むべき3つのステップをご紹介します。
Step 1: 関係者へのヒアリングと期待値のすり合わせ
まずは、あなたのミッションに関わる主要なステークホルダー(経営層、事業部長、関連部署のキーパーソンなど)にヒアリングを行いましょう。彼らが新規事業に何を期待しているのか(売上規模、事業領域、スケジュール感など)を正確に把握し、認識のズレをなくすことが最初の仕事です。この期待値のすり合わせが曖昧なまま進むと、後々「こんなはずではなかった」という事態を招きかねません。同時に、誰があなたの強力なサポーターになってくれそうかを見極める良い機会にもなります。
Step 2: 社内資源(技術・人材・データ)の棚卸し
次に、自社内に眠っている「お宝」を探しに行きましょう。あなたの会社には、まだ事業化されていない優れた技術、特定の分野に深い知見を持つ人材、活用されていない顧客データなど、価値ある資源(アセット)が眠っている可能性があります。研究開発部門、知財部門、情報システム部門など、様々な部署を訪ねてヒアリングし、活用可能な社内資源のリストを作成してください。ゼロからすべてを生み出すのではなく、既存のアセットを組み合わせることで、ユニークな事業アイデアが生まれることも少なくありません。
Step 3: 小さなプロトタイプでクイックウィンを目指す
最初から完璧な事業計画や大規模な開発を目指す必要はありません。まずは、顧客課題を解決する最小限の機能を持ったプロトタイプ(MVP:Minimum Viable Product)を短期間で作成し、実際の顧客にぶつけてみましょう。たとえ小さなものでも、「顧客からポジティブな反応が得られた」「有料で使ってくれる人が現れた」といった具体的な成果(クイックウィン)を出すことが重要です。この小さな成功体験が、あなたのチームの士気を高め、経営層や周囲からの信頼を獲得し、次のステップへ進むための推進力となります。
新規事業育成は、先の見えない暗闇を進むようなものです。しかし、その先には、あなたが創り出した事業によって笑顔になる顧客や、活性化する組織、そして新しい未来が待っています。この記事で得た知識と、あなた自身の情熱を羅針盤に、ぜひこの挑戦を楽しんでください。応援しています。
まとめ
本記事では、新規事業育成の担当者が直面する課題と、成功への道筋を多角的に解説しました。多くの失敗は、既存事業の論理や短期的なROIを追求する評価制度といった「イノベーションのジレンマ」に起因します。
成功の鍵は、心理的安全性を確保し挑戦を奨励する組織文化と、経営トップの強力なコミットメントです。担当者はリーンスタートアップなどの思考法を武器に、顧客課題と真摯に向き合い続けることが求められます。