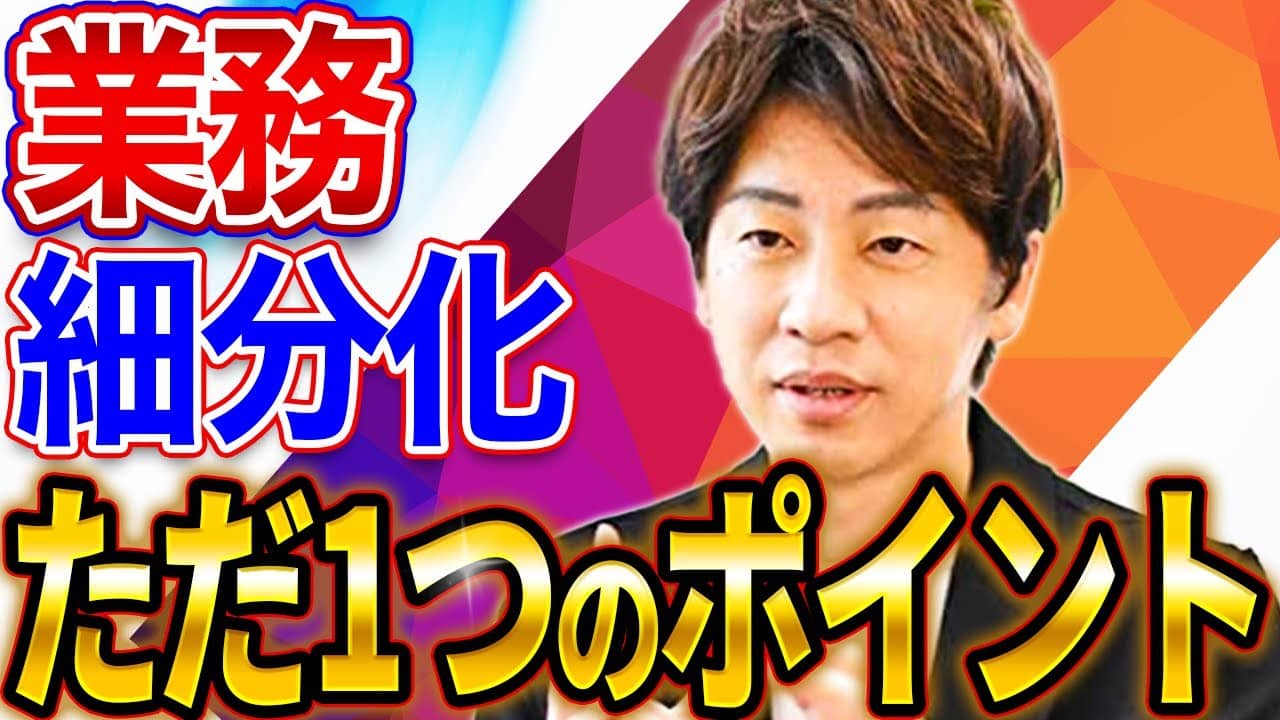SaaSチャンネル【kyozon】Vol.168
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ILIolXvuFoE
生産性を向上させるための鍵は“業務細分化”
今回は売上最小化、利益最大化の法則※を執筆されている 木下 勝寿 × 鈴木 章裕のお二人が対談した際の話をまとめています。 生産性を向上させるためにはどうすればいいのか、木下さんが詳しく解説してくれておりますので、筋肉質な経営をしたい方はぜひご覧ください。
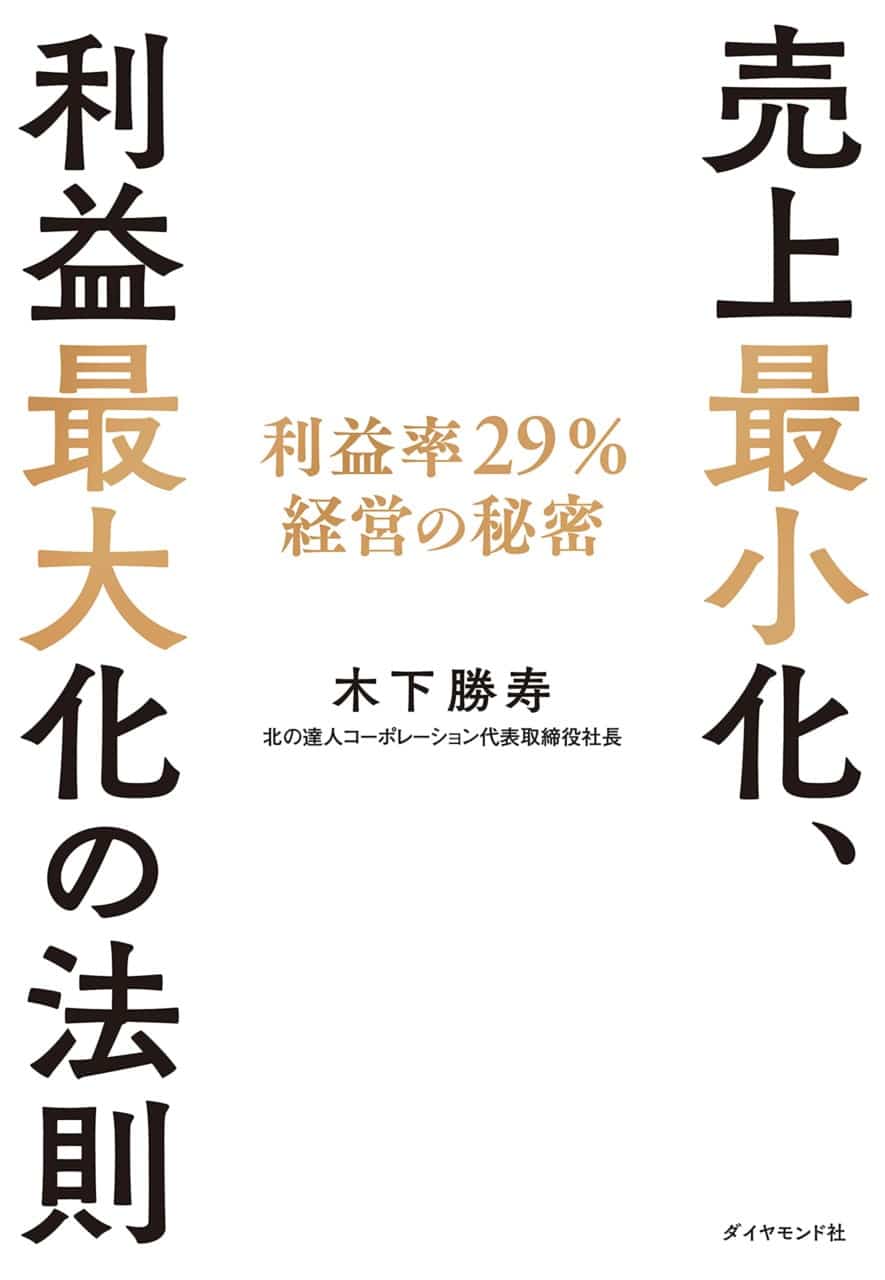
※紹介している著書:売上最小化、利益最大化の法則──利益率29%経営の秘密 – 木下 勝寿 (著)
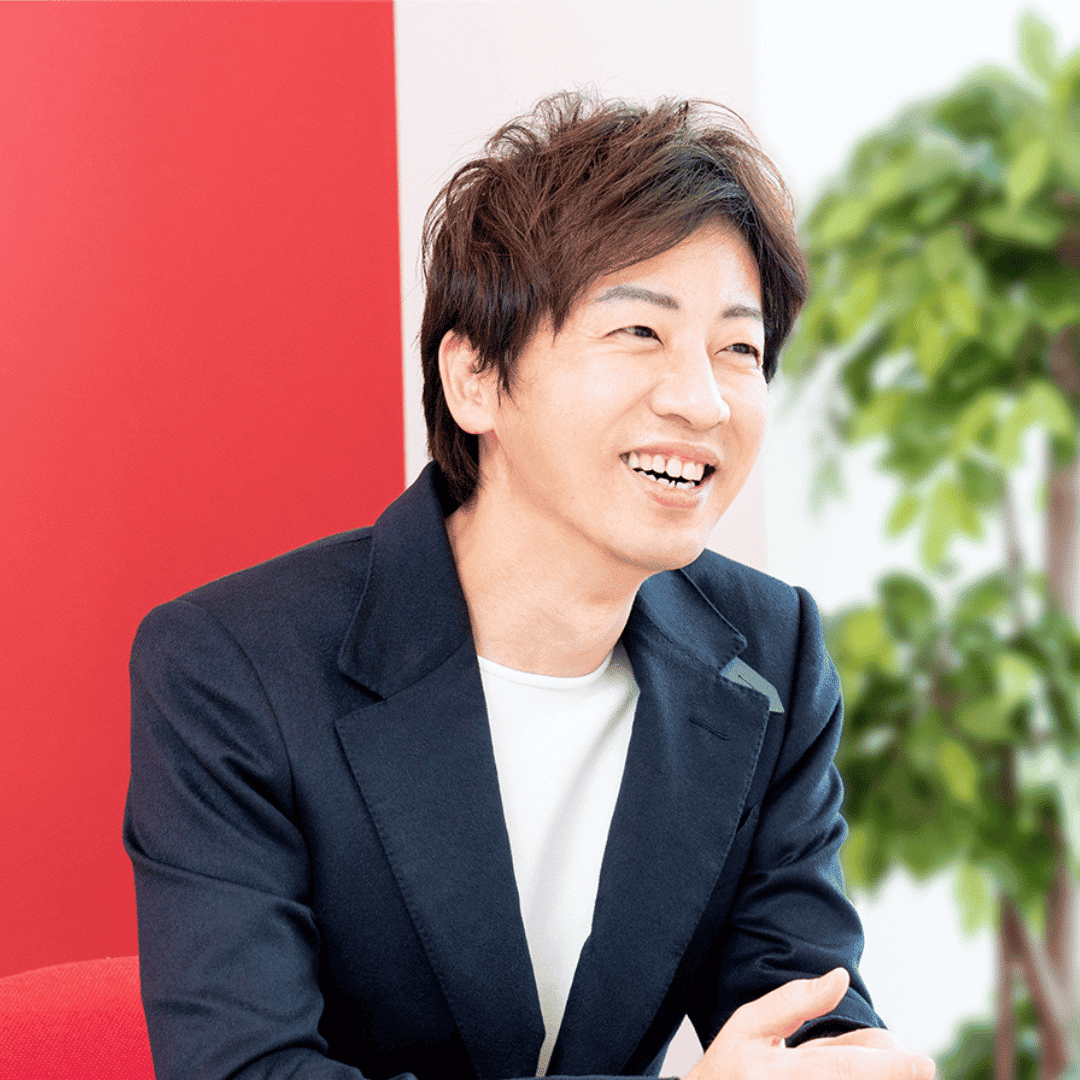
1968年、神戸生まれ。大学在学中に学生企業を経験し、卒業後は株式会社リクルートで勤務。
その後、独立するも、事業に失敗しフリーターに。無一文の中、「次は絶対に顧客満足にこだわったビジネスを行うこと」、「日本を代表する企業を創ること」を胸に再起を誓う。
コネもツテも一切無い状況から事業を起こし、たった一代にして東証プライム上場企業にまで押し上げた。

1969年、大阪府生まれ。甲南大学法学部を卒業後、広告代理店の営業部長を経て、2000年にインターネット広告を手掛けるアイブリッジ株式会社へ入社。
2007年9月、アイブリッジ株式会社、アドデジタル株式会社、アカラ株式会社、ブランド総合研究所という4つの会社を束ねるグループ会社へと成長した同社の社長を辞し、株式会社コミクスを設立し、代表取締役社長に就任。
業務細分化を図るために必要な仕組み化とは?
――株式会社北の達人コーポレーションの木下さん/株式会社COMIX代表取締役 鈴木との対談

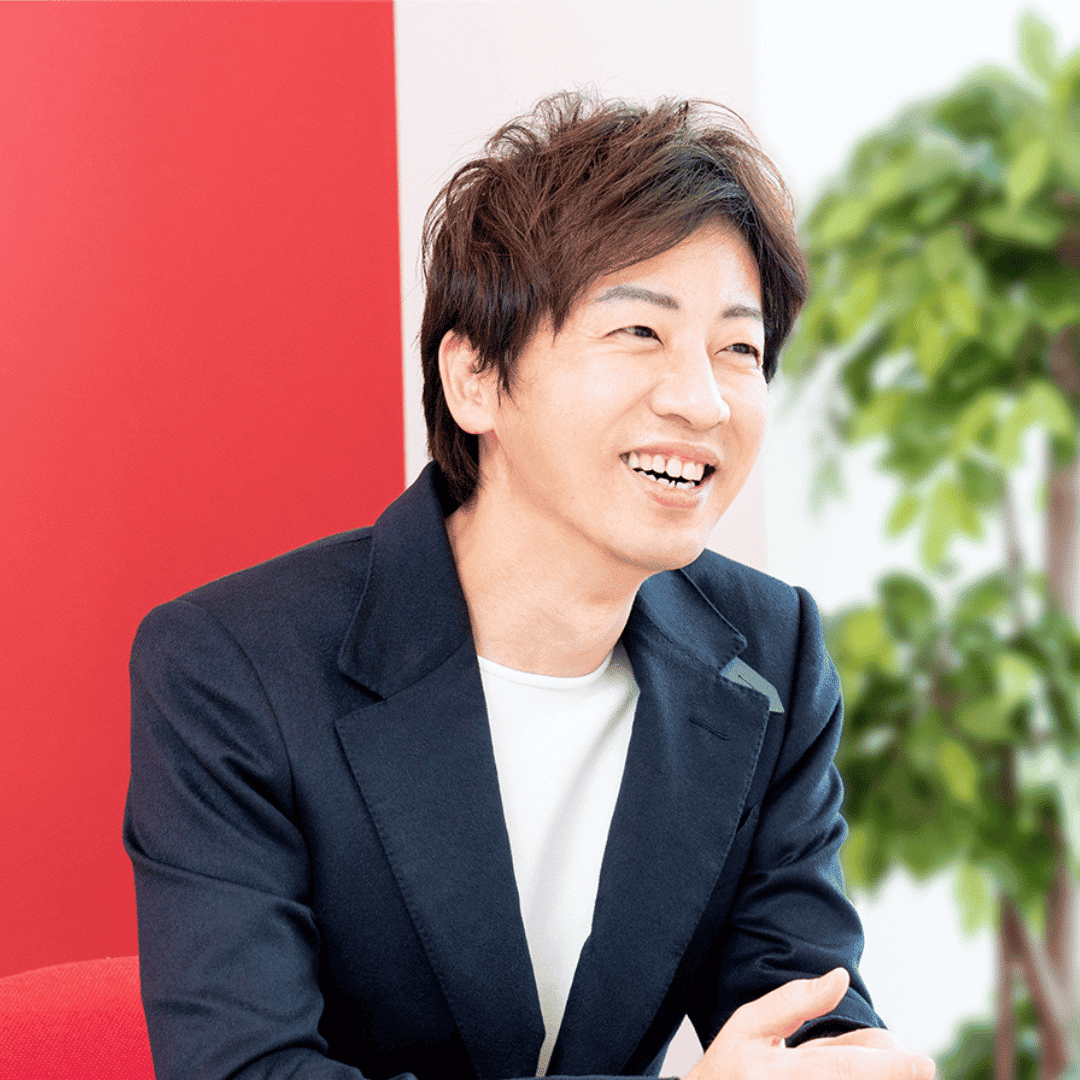
具体的にはどういうことなんですかね?
そこで、「ベテランしかできない部分」と「初心者でもできる部分」に業務を分解していくっていう仕組み化がすごく重要になります。 結局ベテランだったりとか、優秀な人ってそんなすぐにポンポン採用できないじゃないですか。 だから、「ベテランしかできないビジネスモデル」のままだと拡大できないので、ベテランしかできない業務は一部だけにすることが重要。 他は仕組み化・マニュアル化しながらアルバイトだったりとか、新人でもできるように業務を組み込んでいくっていう事が結果的に重要だと思うんですよね。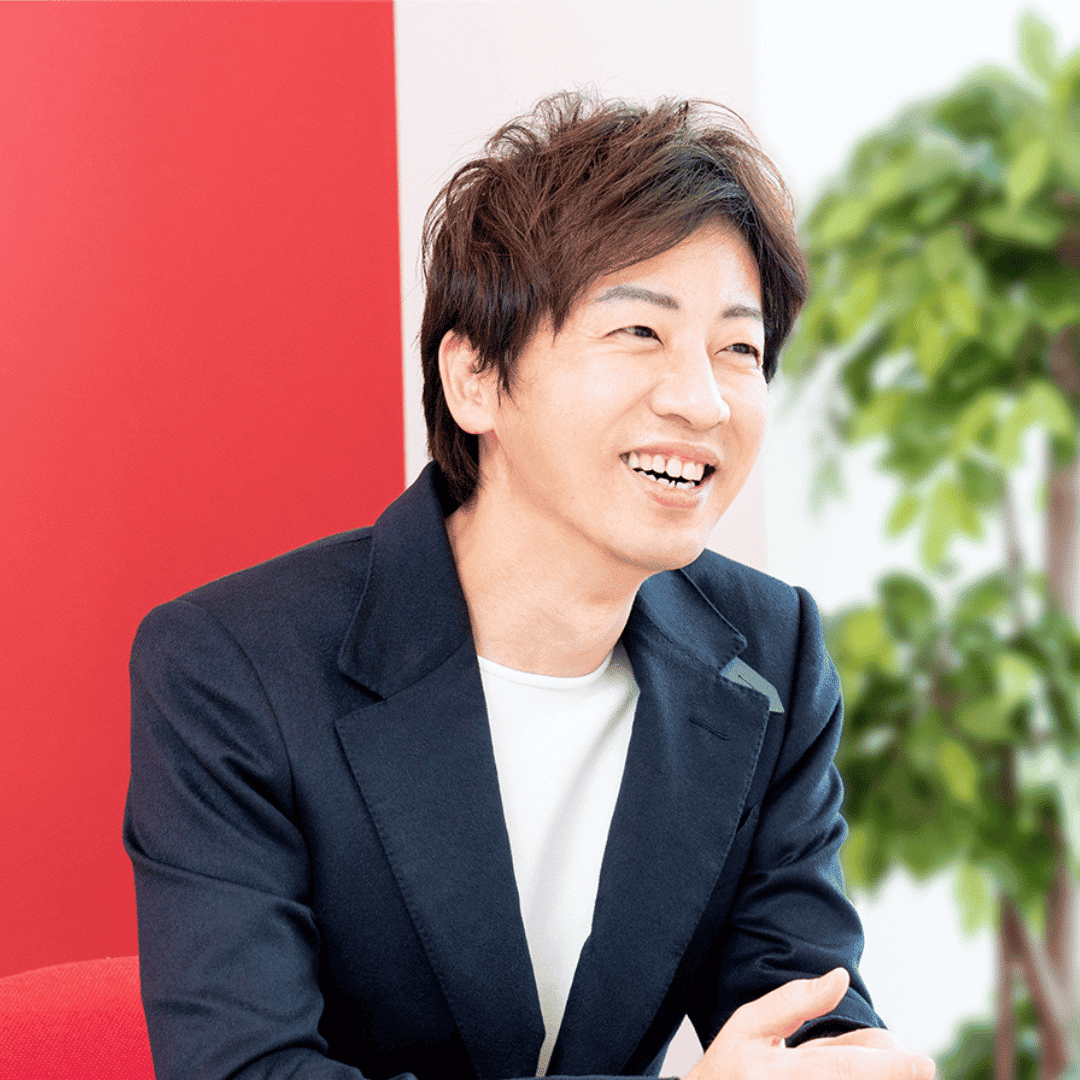
それこそ、この間出されたばっかりのこちらの本※にも書かれていましたよね。業務の内容をすごく細かく切っていました。 これは「アルバイトでもできるよな」とか、ここは「若手社員でもできるよな」ってことで、業務を分解するんですよね。 例えばトヨタは車生産における工程を細かく分けていますよね。それに近いイメージでしょうか?

※紹介している著書:ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法 – 木下 勝寿 (著)
その業務を全部分解していって、ベルトコンベア方式で素人が集まってでも作れる仕組みにしたことによって大量生産できるようになったという流れだと思うんですけども、それと考え方は完全に一緒です。 業務をもっと細分化していくことによって、ある程度ここだけだったら、入りたての人でもできるみたいな工程を組み合わせて、最終ジャッジ・全体プロデュースはベテランが担う。 このようにして、「ベテランができる業務」と「新人でもできる業務」に分けていくことによって、つまりは拡大しやすくするっていうとこですね。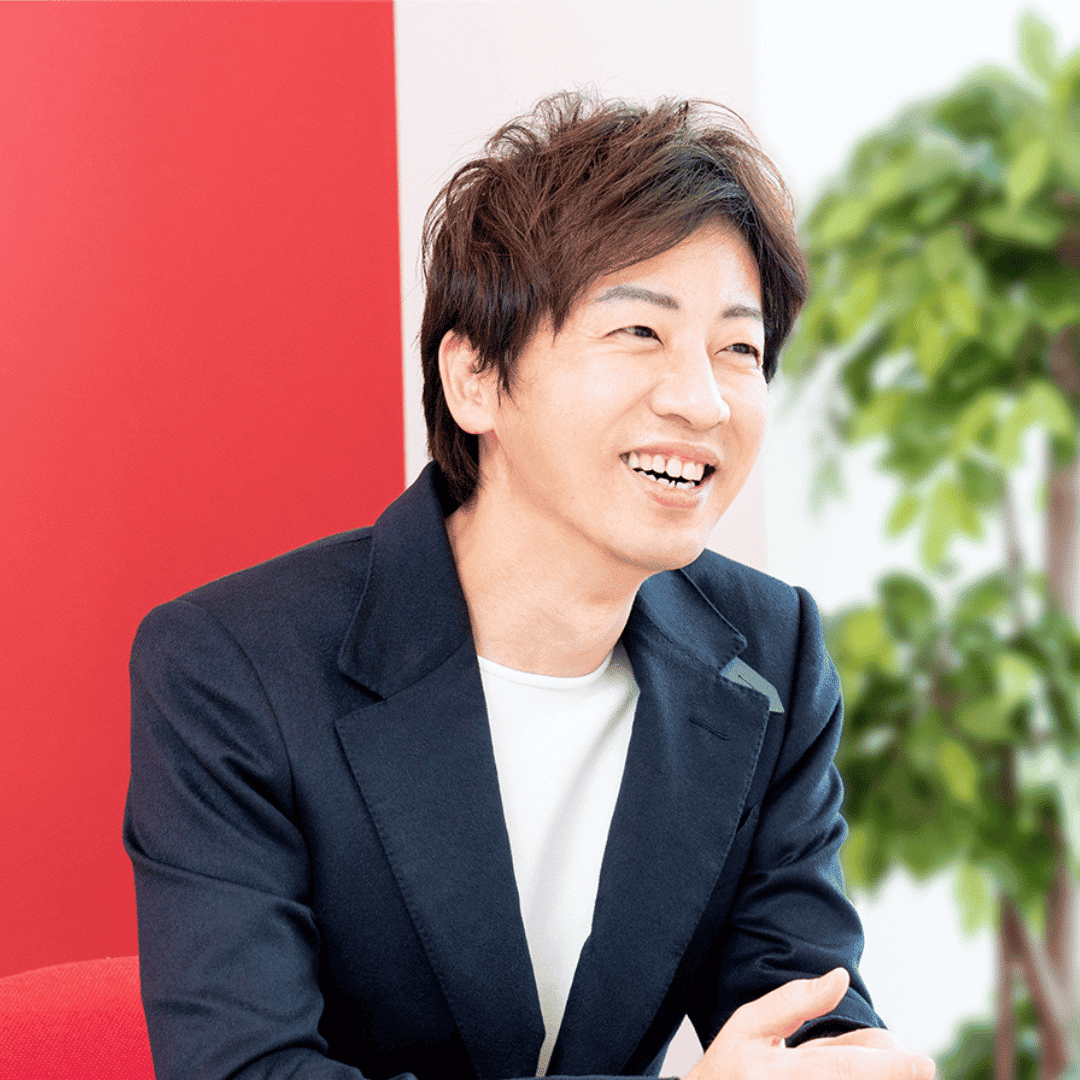
業務細分化を図るようになったキッカケ

だから、例えば職人さんが「自分のやってることを細分化」して、「素人でもできるようにできるのか」 これは結構難しいわけですよね。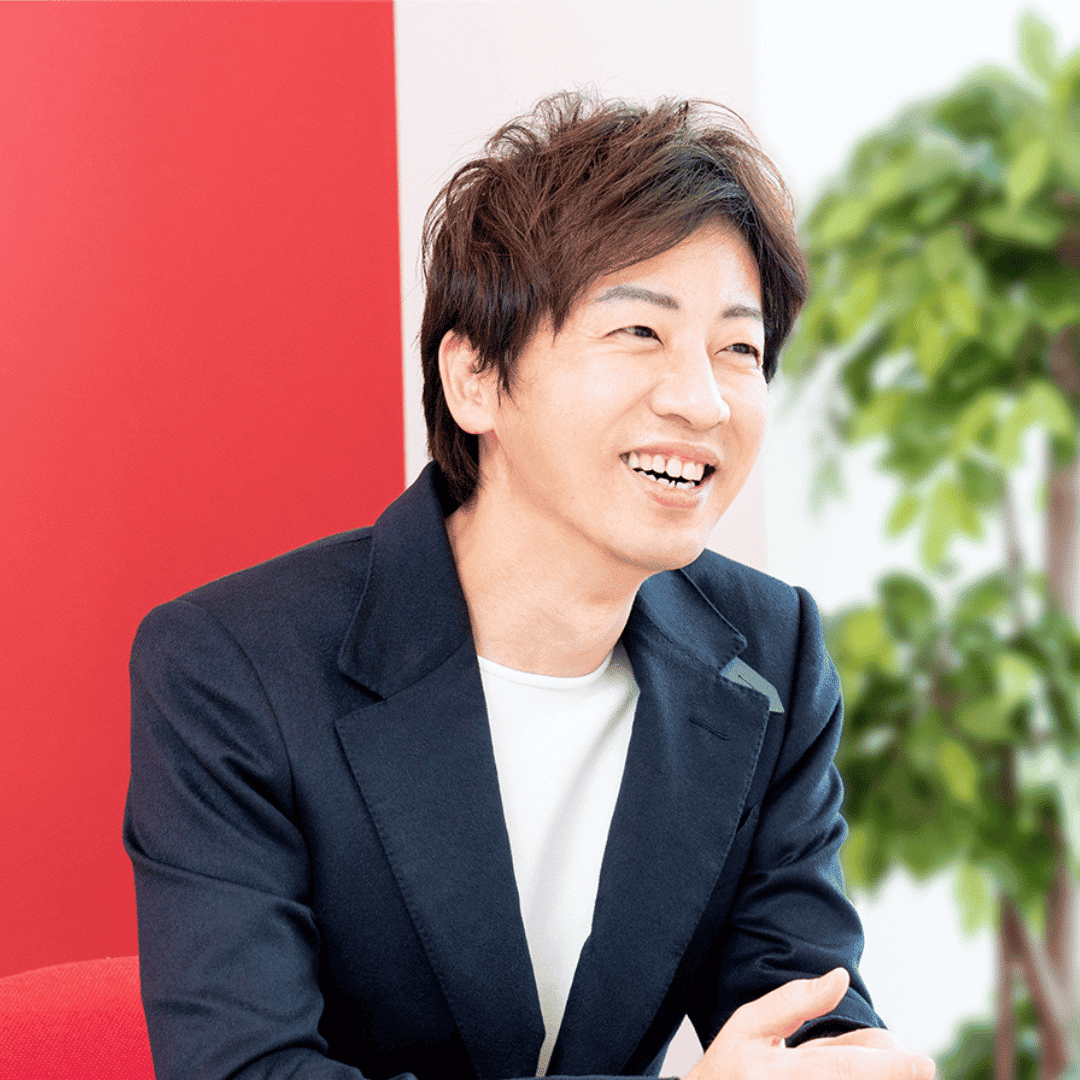

そのベテラン社員が退職するって話があって、でもベテランじゃないとこの仕事はできないからどうしよう…っていう話がありまして もう一旦、自分が引き継ぐしかないなという事がありました。 ただ全部が全部はできないから、その仕事をアルバイトでもできる部分は任せてみようって、仕事をバーっと引き継いでいったんです。 そのときに、「この場合ってどういうふうに判断してるの?」って言ったら、「ケースバイケースです」とか、そういうやりとりをずっと聞いてると、ケースバイケースって言ってるけど、実際には法則性があるって話になりまして。 その業務を全部記憶ベースでやってるだけじゃないのかっていう事があって、それらを全部エクセルに落としていったんですよ。 このときはこれ、このときはこれって業務を確認できるようにする。 最終的には全部エクセルに落とし込んで、アルバイトの人が自動的にできるようになったんですね。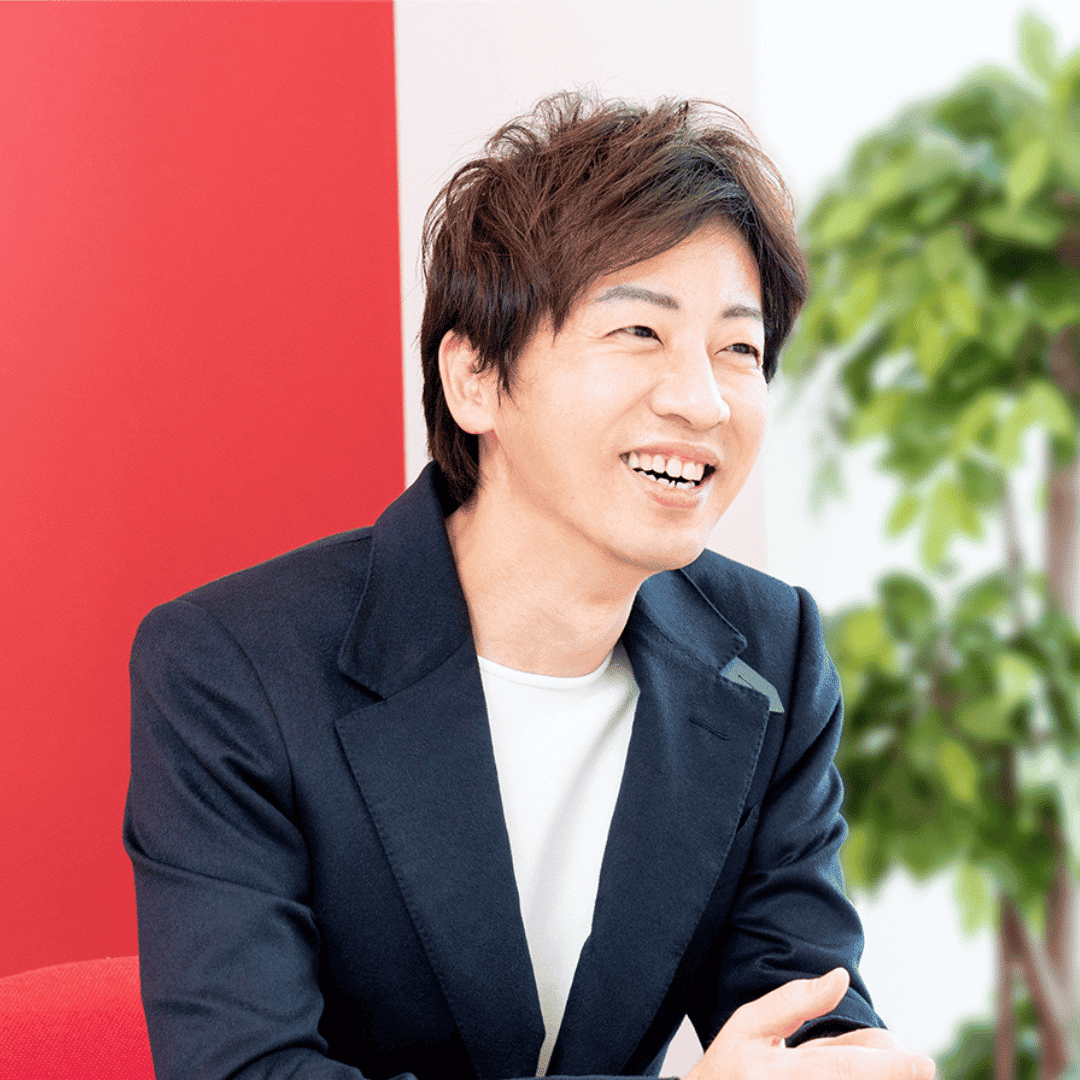

第三者目線で業務内容をヒアリングする
「これはもう難しいからやめとこうか」って言われた時に、「いやでも!そう言われても困るから教えてください!」みたいな。 何かやろうと思っても結局、「経験者がちゃんと落とし込んでくれなくて、うまくできない」があるあるなんで。 他の仕事だったらできたけども、逆に経営の仕事をできるかっていうと無理じゃないですか。 その意外と無理だと思う業務内容を、他の人にヒアリングされながらやっていくみたいなのがすごく重要です。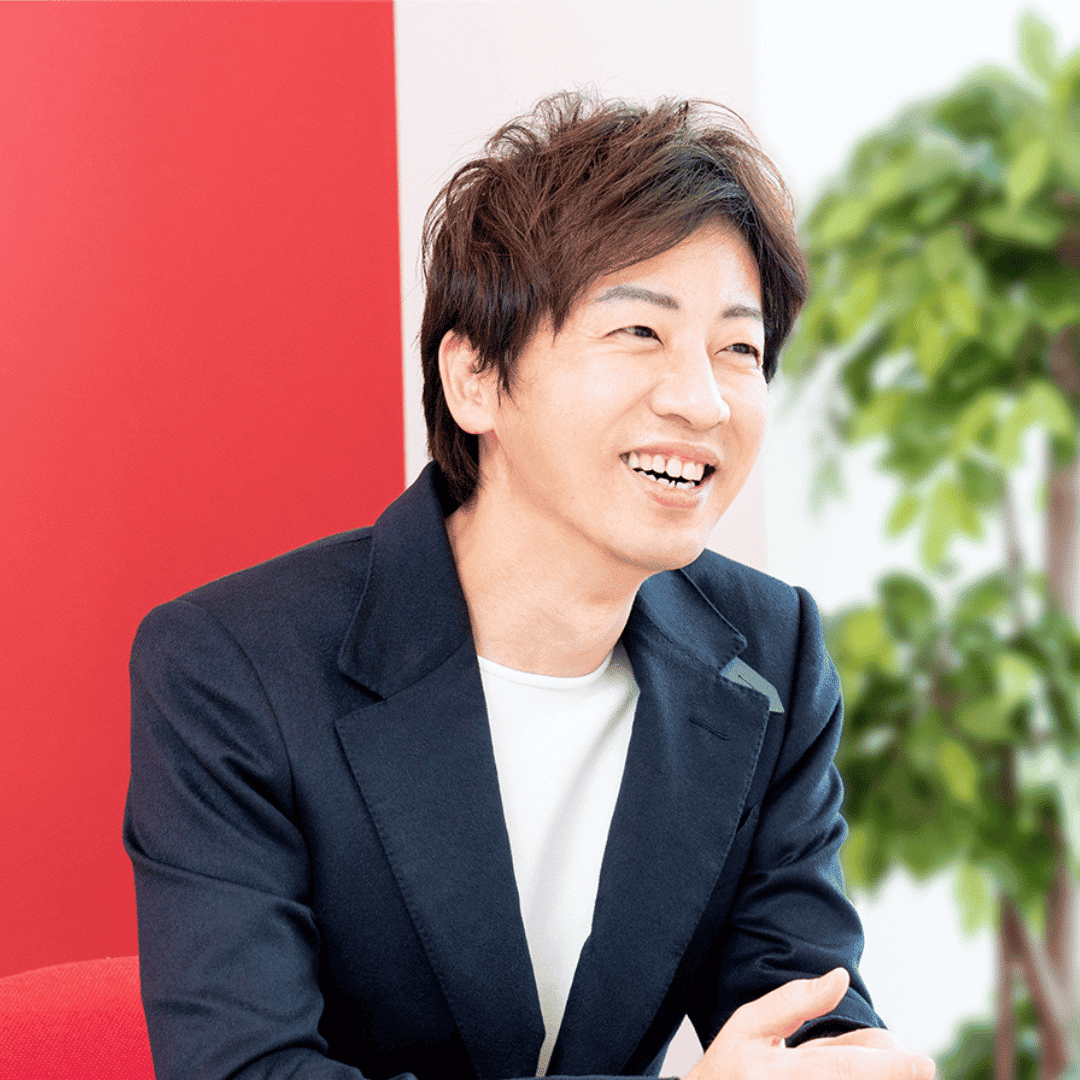

あれって職人さんのパンの作り方っていうのを確かパナソニックの開発者たちがずっとヒアリングしながら開発したんですよ。 初めは職人さんが説明した通りにやっても、全然うまくいかなかったらしいですね。 よくよく製造過程見てると、職人さんが言語化しないポイントが結構あったらしいんすよ。 「これはもうね普通に混ぜるだけなんだよね。」みたいに言ってるんだけども、その「普通に混ぜるだけ」っていう工程が実はすごいコツがあったらしいんです。 職人は「こんな事は誰でもできるだろう」と。そこで開発部が「今の手首のひねりってちょっと工夫があるかもな」みたいな目線で空気入れてるんだっていう気付きがある。 そんなこと職人は言ってないですけど、第三者目線だから分かる。 その後改良を続けていって、ほぼ職人と同じパンができたって話があったんですけど。 つまり第三者の取材が重要という事ですね。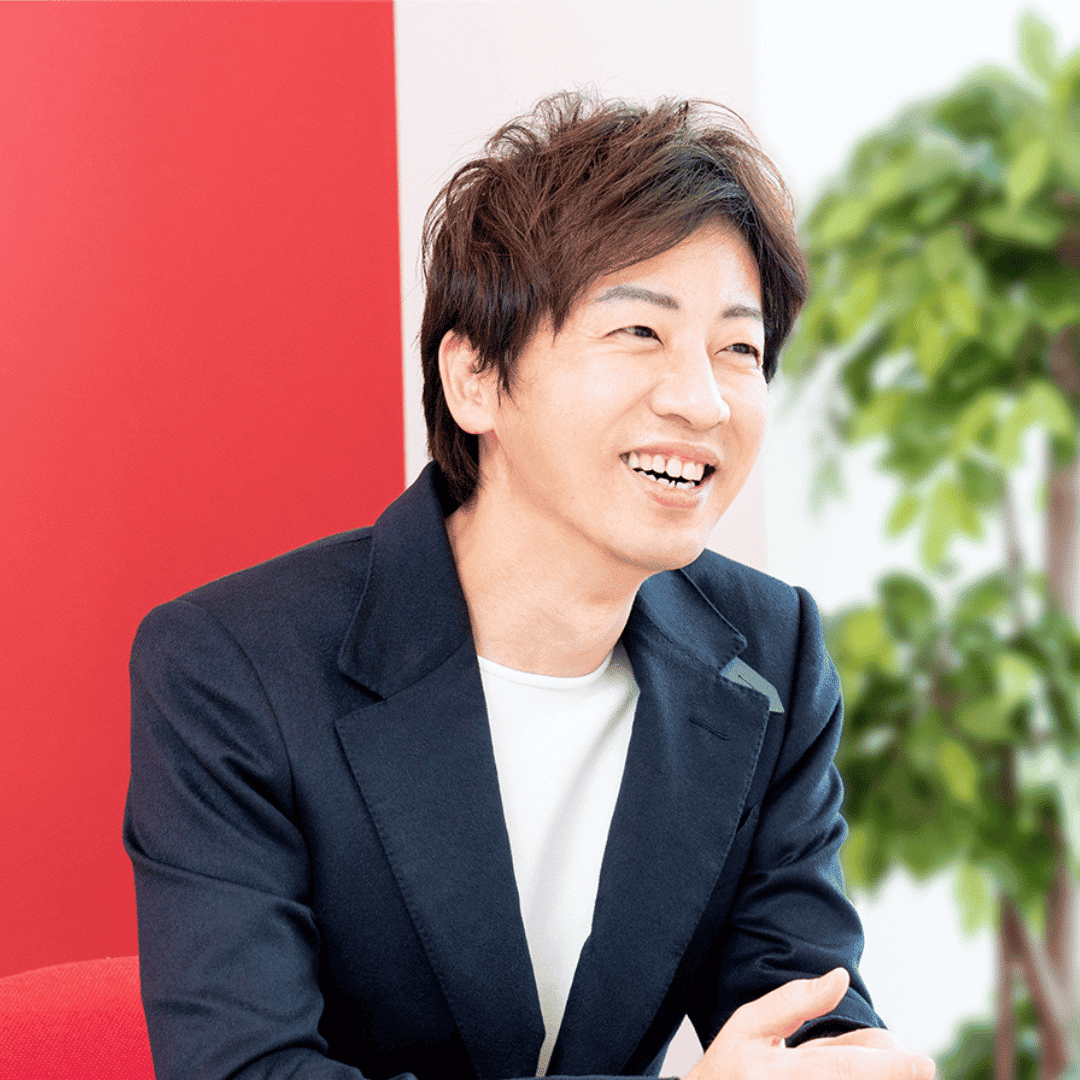

まとめ
中でも自動パン焼き器ができるまでのお話はインパクトがありました。 決済者のためのSaaSチャンネルkyozonではその他にも対談・イベント動画もたくさん上げております。今後も新しい動画を上げていきますのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。
決済者のためのSaaSチャンネルkyozon
URL:https://www.youtube.com/@SaaSBusinessSupportCH
【SNSフォローのお願い】
kyozonは日常のビジネスをスマートにする情報を毎日お届けしています。
今回の記事が「役に立った!」という方はtwitterとfacebookもフォローいただければ幸いです。
twitter:https://twitter.com/kyozon_comix