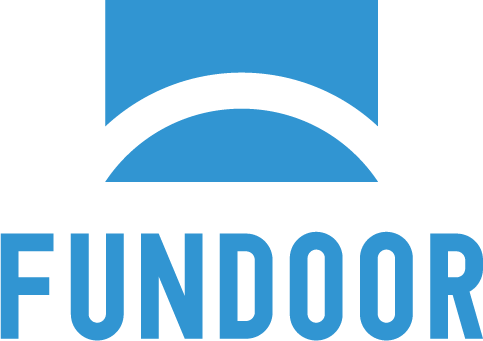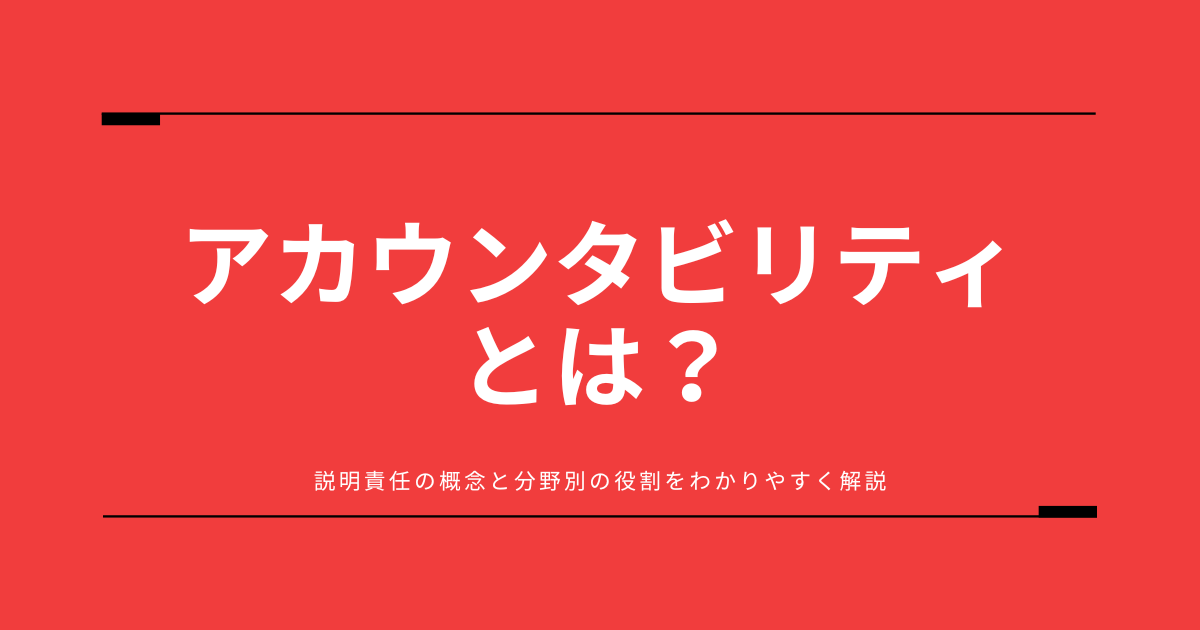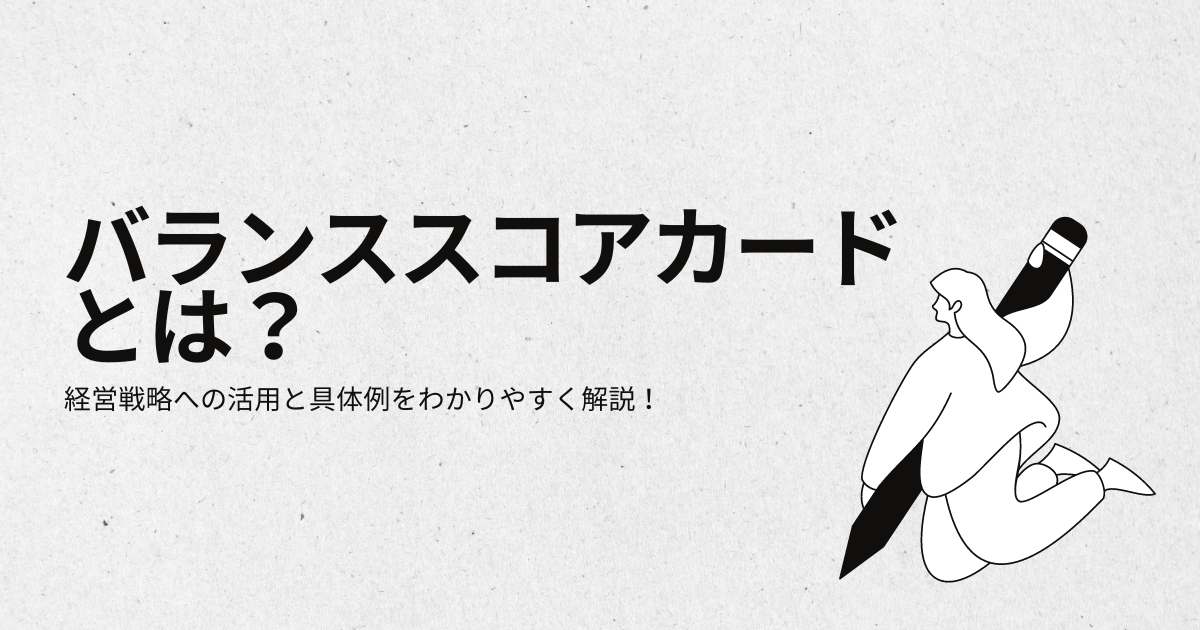なぜ今脱炭素の企業目標設定が求められるのか

近年、「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉を耳にする機会が急増しました。これは単なる環境保護のトレンドではなく、企業の存続と成長を左右する極めて重要な経営課題となっています。気候変動問題への対応は世界的な潮流となり、日本政府も2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。この大きな流れの中で、企業規模の大小を問わず、具体的な脱炭素目標の設定と実行が強く求められているのです。
もはや脱炭素への取り組みは、一部の大企業だけの話ではありません。むしろ、サプライチェーンの一員である中小企業こそが、この変化に迅速に対応する必要に迫られています。ここでは、なぜ今、すべての企業にとって脱炭素目標の設定が不可欠なのか、その背景と具体的なメリットを詳しく解説します。
サプライチェーン全体で進む脱炭素化の潮流
中小企業が脱炭素目標の設定を急ぐべき最大の理由の一つが、サプライチェーン全体での脱炭素化の要請です。Appleやトヨタ自動車といったグローバル企業は、自社の排出量(Scope1, 2)だけでなく、取引先の部品製造や物流などを含むサプライチェーン全体の排出量(Scope3)の削減目標を掲げています。
これは、自社製品のライフサイクル全体における環境負荷を低減するためであり、その達成にはサプライヤーである取引先企業の協力が不可欠です。そのため、多くの大企業は取引先に対し、CO2排出量の算定・報告や、具体的な削減目標の設定を求めるようになっています。
この動きは今後さらに加速することが確実視されており、脱炭素化に対応できない企業は、「取引の継続が困難」と判断され、サプライチェーンから排除されてしまうリスクに直面します。逆に言えば、早期に脱炭素目標を掲げ、着実に取り組みを進めることで、主要な取引先との関係を強化し、新たな取引機会を獲得するチャンスにも繋がるのです。
企業が脱炭素目標を掲げる3つのメリット
脱炭素への取り組みは、取引先からの要請に応えるという守りの側面だけではありません。むしろ、企業の未来を切り拓くための積極的な経営戦略と捉えるべきです。脱炭素目標を掲げることで、企業は主に3つの大きなメリットを享受できます。
| メリットの分類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 企業価値と競争力の向上 | ESG投資家からの評価向上、ブランドイメージの強化、光熱費などのコスト削減に繋がる。 |
| 新たなビジネス機会の創出 | 環境配慮型製品・サービスの開発や、脱炭素化を支援する新規事業への参入機会が生まれる。 |
| 資金調達や人材採用での優位性 | サステナビリティ・リンク・ローンなど有利な融資を受けやすくなり、環境意識の高い優秀な人材を惹きつける。 |
企業価値と競争力の向上
脱炭素目標を設定し、その進捗を情報開示することは、企業の価値評価に直結します。近年、投資家は企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への取り組みを重視する「ESG投資」を拡大しています。脱炭素への明確な姿勢は、気候変動リスクに対応できる持続可能な企業であることの証明となり、投資家からの評価を高めます。
また、環境意識の高い消費者や顧客からの信頼獲得にも繋がり、企業や製品のブランドイメージを大きく向上させます。さらに、目標達成の過程で実施する省エネルギー設備の導入や業務プロセスの見直しは、電気代や燃料費といった光熱費の削減に直結し、企業の収益性を高めるという直接的なメリットももたらします。
新たなビジネス機会の創出
社会全体が脱炭素へ移行する過程では、新しい市場やビジネスチャンスが数多く生まれます。例えば、自社の工場やオフィスの屋根に太陽光発電設備を設置するだけでなく、そのノウハウを活かして他社に導入支援サービスを提供する事業展開も考えられます。
他にも、省エネ性能の高い製品の開発、環境負荷の少ない素材への切り替え、使用済み製品を回収・再資源化するサーキュラーエコノミー(循環型経済)の構築など、自社の技術や強みを活かした新たな収益の柱を創出する絶好の機会となり得ます。この変革期をチャンスと捉え、積極的に行動することが、将来の成長の鍵を握ります。
資金調達や人材採用での優位性
脱炭素への取り組みは、資金調達と人材採用の面でも大きなアドバンテージとなります。金融機関は、融資先の気候変動リスクを厳しく評価するようになっており、脱炭素目標を掲げている企業を高く評価する傾向にあります。近年では、野心的なサステナビリティ目標の達成度合いに応じて金利が変動する「サステナビリティ・リンク・ローン」など、環境への取り組みを後押しする有利な融資制度も増えています。
人材採用においても、特にミレニアル世代やZ世代といった若い世代は、企業の社会貢献や環境への姿勢を就職先選びの重要な判断基準としています。企業のパーパス(存在意義)に共感し、持続可能な社会の実現に貢献したいと考える優秀な人材にとって、脱炭素を経営の中心に据える企業は非常に魅力的です。明確な目標を掲げることは、優秀な人材の獲得と定着(リテンション)に繋がり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
脱炭素の企業目標とは?国際的なイニシアチブを解説

脱炭素に向けた企業目標は、単に「CO2を削減します」といったスローガンを掲げるだけでは十分ではありません。その目標が客観的に評価され、社会的な信頼を得るためには、国際的に認められた枠組みや基準に沿って設定することが不可欠です。ここでは、企業が脱炭素目標を設定する上で指標となる、世界的に広く認知されている主要な国際イニシアチブについて詳しく解説します。
科学的根拠に基づく目標「SBT」とは
SBTとは「Science Based Targets」の略称で、日本語では「科学的根拠に基づく目標」と訳されます。これは、気候変動に関する国際的な枠組みである「パリ協定」が目指す「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃を十分に下回り、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標と整合した、企業の温室効果ガス(GHG)排出削減目標のことです。
SBTイニシアチブは、CDP(旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)、国連グローバル・コンパクト、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)という4つの国際機関が共同で運営しており、企業が設定した目標が科学的根拠に基づいているかを検証し、認定を与えています。この認定を受けることで、企業の脱炭素への取り組みが国際基準に則った信頼性の高いものであることを対外的に証明できます。
SBTが定める目標水準には、主に以下のレベルがあります。
| 目標水準 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.5℃目標 | 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑えるための科学的知見と整合した削減目標。 | 現在、SBTイニシアチブが新規に認定する目標はこの水準のみとなっています。より野心的な削減が求められます。 |
| WB2D(2℃を十分に下回る)目標 | 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃を十分に下回る水準に抑えるための削減目標。 | 過去に認定されていた水準ですが、現在は新規の認定は行われていません。 |
SBT認定を目指すことは、自社の排出削減努力をグローバルな視点で位置づけ、投資家や顧客、サプライチェーン上の取引先からの信頼を獲得する上で極めて有効な手段です。
事業活動を100%再エネで賄う「RE100」
RE100(Renewable Energy 100%)は、事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加盟する国際的なイニシアチブです。国際環境NGOであるクライメイト・グループがCDPとのパートナーシップのもとで運営しています。
SBTが温室効果ガス排出量全体の削減を目指す包括的な目標であるのに対し、RE100は「電力」に特化している点が大きな特徴です。加盟企業は、目標達成の年次を宣言し、その進捗を毎年報告することが求められます。
RE100への加盟は、年間消費電力量が100GWh以上(日本では50GWh以上)といった基準があり、主に世界的に影響力の大きい大企業が中心となっています。目標達成のための具体的な手段としては、以下のような方法が認められています。
- 自家発電:自社の敷地内に太陽光発電設備などを設置し、発電した電力を直接使用する。
- 再エネ電力メニューの契約:電力会社が提供する、再生可能エネルギー由来の電力を供給する料金プランを契約する。
- 再エネ証書の購入:J-クレジットや非化石証書、グリーン電力証書など、再生可能エネルギーの持つ「環境価値」を証書化したものを購入する。
- コーポレートPPA(電力購入契約):発電事業者と長期の電力購入契約を直接結び、再生可能エネルギーを調達する。
RE100への加盟は、クリーンなエネルギー利用を推進する企業姿勢を明確に示し、企業ブランドの向上やESG投資を呼び込む上で大きな効果が期待できます。
中小企業向けのSBT目標について
「SBTは大企業向けのもの」というイメージがあるかもしれませんが、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中、中小企業の役割はますます重要になっています。こうした背景から、SBTイニシアチブは中小企業(従業員500人未満など)を対象とした、簡素化された目標設定・申請ルートを用意しています。
この中小企業向けルートには、大企業向けの通常ルートとは異なる特徴があり、中小企業が取り組みやすいように設計されています。
| 項目 | 中小企業向けSBTの要件 |
|---|---|
| 目標の対象範囲 | 自社での燃料使用や電力使用に伴う排出(Scope1およびScope2)が対象です。サプライチェーン全体の排出量であるScope3の算定と目標設定は不要です。 |
| 目標水準 | 大企業と同様に、パリ協定の1.5℃目標に整合する水準が求められます。具体的な削減率が事前に定義されており、企業はそれに沿って目標を設定します。 |
| 申請プロセス | コンサルタントなどを介さず、オンラインの申請フォームから直接提出できる簡略化されたプロセスが提供されています。申請にかかる費用も通常ルートより低く設定されています。 |
この制度を活用することで、中小企業であっても国際的な認証を取得し、脱炭素への取り組みを客観的に示すことが可能です。これにより、大手取引先からの要請に応え、サプライヤーとしての競争力を維持・強化することにつながります。
中小企業でもできる脱炭素の企業目標策定3ステップ

脱炭素経営への第一歩は、大企業だけの話ではありません。サプライチェーンの一員である中小企業にも、具体的な目標設定と行動が求められています。しかし、「何から手をつければ良いかわからない」と感じる経営者の方も多いのではないでしょうか。ここでは、中小企業でも実践可能な、脱炭素の企業目標を策定するための具体的な3つのステップを、順を追って詳しく解説します。
ステップ1:CO2排出量の現状把握(Scope1,2,3の算定)
削減目標を立てる上で最も重要な最初のステップが、自社の現状を正確に把握することです。つまり、自社の事業活動によってどれだけの温室効果ガス(GHG)、主に二酸化炭素(CO2)が排出されているかを「見える化」します。この排出量の算定には、国際的な基準である「GHGプロトコル」で定められた「Scope(スコープ)」という考え方が用いられます。
Scope1:直接排出量とは
Scope1は、事業者自らが所有または管理する排出源から直接排出される温室効果ガスを指します。具体的には、燃料の燃焼や工業プロセスなどが該当します。
中小企業における主なScope1の例:
- 工場で稼働するボイラーや工業炉で使用する燃料(都市ガス、LPガス、重油など)の燃焼
- 社用車(営業車、トラックなど)のガソリンや軽油の燃焼
- 製造プロセスにおける化学反応による排出
これらの排出量は、燃料の使用量や走行距離などの活動量データに、定められた排出係数を掛け合わせることで算定できます。
Scope2:間接排出量とは
Scope2は、他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴って間接的に排出される温室効果ガスを指します。自社で直接排出しているわけではありませんが、自社の事業活動のために購入したエネルギーが作られる過程で排出されるものです。
中小企業における主なScope2の例:
- オフィスや工場の照明、空調、OA機器、生産設備などで使用する購入電力
- 他社から供給される熱や蒸気の使用
電力会社から毎月送られてくる「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」に記載された電力使用量に、電力会社ごとに定められた排出係数を乗じることで算定するのが一般的です。
Scope3:その他の間接排出量とは
Scope3は、Scope1、Scope2以外の、事業者の活動に関連するサプライチェーン全体からの間接排出を指します。原材料の調達から製品の製造、輸送、販売、使用、廃棄に至るまで、事業活動の全般に関わる排出が含まれるため、算定範囲が非常に広いのが特徴です。
中小企業がいきなり全てのScope3を算定するのは困難なため、まずは自社の事業と関連が深く、算定しやすいカテゴリから着手することが推奨されます。
Scope3は以下の15のカテゴリに分類されます。
| カテゴリ | 内容 | 中小企業における具体例 |
|---|---|---|
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 原材料、部品、消耗品(事務用品など)の製造段階での排出 |
| カテゴリ2 | 資本財 | 生産設備や建物などの建設・製造段階での排出 |
| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料・エネルギー活動 | 購入した燃料や電力の採掘、精製、輸送などにおける排出 |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 購入した原材料や製品の自社までの輸送 |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 廃棄物の輸送や処理(焼却・埋立)に伴う排出 |
| カテゴリ6 | 出張 | 従業員の出張における移動(電車、飛行機など)に伴う排出 |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤(電車、バス、自家用車など)に伴う排出 |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 自社が借りているリース資産(車両、コピー機など)に関する排出 |
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 販売した製品の顧客までの輸送 |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 販売した中間製品が他社で加工される際の排出 |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 販売した製品(家電、自動車など)が使用される際の排出 |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 販売した製品が廃棄・処理される際の排出 |
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | 自社が貸しているリース資産に関する排出 |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | フランチャイズ加盟店の事業活動に伴う排出 |
| カテゴリ15 | 投資 | 投資先の事業活動に伴う排出 |
特に「カテゴリ1:購入した製品・サービス」「カテゴリ4:輸送、配送(上流)」「カテゴリ6:出張」「カテゴリ7:雇用者の通勤」などは、比較的データが集めやすく、算定に着手しやすい項目です。
ステップ2:削減目標の設定(基準年と目標年)
自社のCO2排出量を把握できたら、次はその数値を基に具体的な削減目標を設定します。目標設定においては、「いつから(基準年)」「いつまでに(目標年)」「何を(対象範囲)」「どれだけ(削減率)」を明確にすることが重要です。これにより、進捗管理が容易になり、社内外への説明責任も果たしやすくなります。
自社の状況に合わせた目標レベルの決定
目標は、背伸びしすぎず、かつ挑戦しがいのあるレベルに設定することが継続の鍵です。まずは自社の経営資源や事業特性、取引先からの要請などを総合的に勘案し、現実的で達成可能な目標を立てましょう。
例えば、以下のような目標設定が考えられます。
- 「2025年度を基準年とし、2030年度までにScope1とScope2の排出量を20%削減する」
- 「エネルギー使用量の多い生産設備を更新するタイミングに合わせ、今後5年間で電力使用量を15%削減する」
最初はScope1とScope2を対象とし、Scope3については算定可能な範囲から着手して、段階的に目標設定の範囲を広げていくというアプローチも有効です。
SBT認定を目指す場合の水準
より意欲的で、国際的に認められた目標を設定したい場合は、「SBT(Science Based Targets)」の認定取得を目指すことをお勧めします。SBTは、パリ協定が求める「世界の気温上昇を産業革命前より1.5℃に抑える」という水準と整合した、科学的根拠に基づく削減目標です。
中小企業向けには、簡素化された申請プロセスが用意されています。主な要件は以下の通りです。
- 対象範囲:Scope1とScope2の排出量削減が必須です。
- 目標水準:少なくとも、世界の気温上昇を「2℃を十分に下回る水準(Well-below 2℃)」に抑える経路(年率2.5%の直線的削減)に整合した目標を設定する必要があります。より推奨されるのは「1.5℃水準」(年率4.2%の直線的削減)です。
- Scope3:Scope3の排出量が総排出量の40%以上を占める場合は、Scope3についても削減目標を設定することが求められます。
SBT認定を取得することは、企業の脱炭素への取り組みが科学的根拠に基づいていることを客観的に証明し、顧客や金融機関からの信頼を高める強力な武器となります。
ステップ3:削減計画の策定と実行
目標を設定したら、それを達成するための具体的な行動計画を策定し、実行に移します。目標が「山頂」だとすれば、削減計画は「登山ルート」です。どの施策を、いつ、どの部署が担当して行うのかを明確にし、全社的に取り組む体制を整えましょう。中小企業でも取り組みやすい主な削減策には、「省エネルギーの推進」と「再生可能エネルギーの利用」があります。
省エネによるエネルギー効率の改善
省エネは、CO2排出量削減の基本であり、光熱費などのコスト削減に直結するため、最も着手しやすい施策です。日々の地道な取り組みから、設備投資を伴うものまで、様々なアプローチがあります。
- 照明のLED化:オフィスや工場の照明を消費電力の少ないLEDに切り替える。
- 高効率設備への更新:古い空調設備、コンプレッサー、ボイラーなどをエネルギー効率の高い最新機種に入れ替える。国の補助金制度を活用できる場合もあります。
- 断熱性能の向上:窓を二重サッシにしたり、屋根や壁に断熱材を追加したりすることで、空調効率を高める。
- 運用改善:設備のこまめなオンオフ、空調の温度設定の見直し、生産プロセスの効率化など、従業員の意識改革と運用ルール徹底による削減。
再生可能エネルギーの導入と調達
Scope2排出量を抜本的に削減するためには、使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えることが極めて効果的です。近年は中小企業でも導入しやすい様々な選択肢が登場しています。
| 再エネ調達方法 | 特徴 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 自家消費型太陽光発電 | 自社の屋根や敷地に太陽光パネルを設置し、発電した電気を自社で使う。 | ・電気料金の削減効果が高い。 ・災害時の非常用電源になる。 ・企業の環境貢献をアピールしやすい。 | ・初期投資が必要。 ・設置スペースが必要。 ・天候により発電量が変動する。 |
| PPAモデル | PPA事業者が費用負担で太陽光パネルを設置・所有し、企業は発電した電気を事業者から購入する。 | ・初期投資ゼロで導入可能。 ・メンテナンスは事業者が行う。 ・長期契約が必要。 | ・契約期間が長い(15年~20年)。 ・設置場所の審査がある。 |
| 再エネ電力メニューへの切り替え | 電力会社が提供する、再生可能エネルギー由来の電力を供給する料金プランに契約を切り替える。 | ・手続きが簡単ですぐに始められる。 ・設備投資が不要。 | ・通常の電気料金より割高になる場合がある。 ・電力会社やプランの選定が必要。 |
| 非化石証書・J-クレジット等の購入 | 再エネの「環境価値」を証書として購入し、自社が使用した電力と組み合わせることで、実質的に再エネを利用したとみなす方法。 | ・物理的な制約なく再エネ利用率100%を達成可能。 ・必要な量を柔軟に購入できる。 | ・電気料金とは別に証書の購入費用がかかる。 ・直接的な省エネにはつながらない。 |
これらの削減策を組み合わせ、自社の状況に最適な計画を立てて実行していくことが、脱炭素目標の達成につながります。
まとめ
脱炭素の企業目標設定は、サプライチェーンからの要請や企業価値向上の観点から、今や中小企業にとっても避けては通れない経営課題です。本記事で解説した3ステップ(CO2排出量の把握、目標設定、削減計画の策定)に沿って進めることで、自社の状況に合った実効性のある目標を立てることが可能です。
SBTなどの国際的なイニシアチブも参考にしつつ、まずは自社の排出量算定から着手し、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出しましょう。