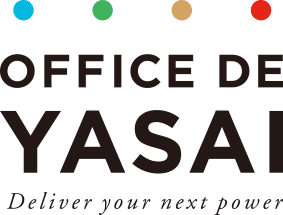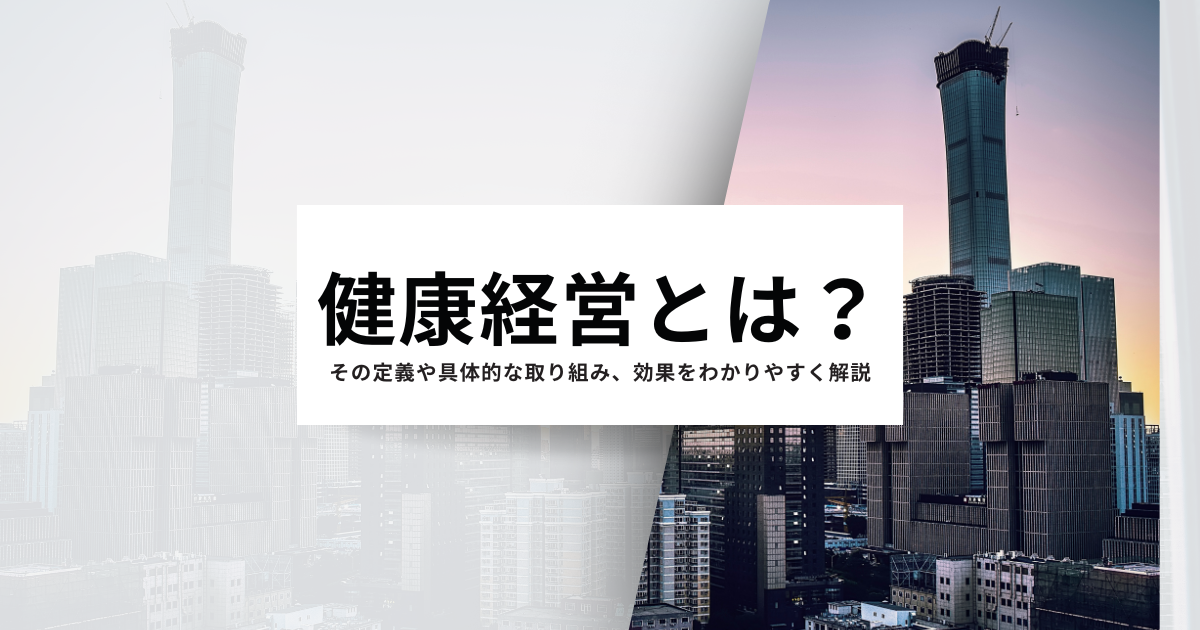あなたの生活を豊かにするヘルステックとは

「ヘルステック(HealthTech)」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?これは、「Health(健康)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、AI(人工知能)やIoT、クラウド、スマートフォンなどの最新技術を活用して、医療やヘルスケア分野の課題を解決するサービスや製品全般を指します。
難しく聞こえるかもしれませんが、実は私たちの生活をより健康的で便利にする、非常に身近な存在になりつつあります。病気の治療だけでなく、日々の健康維持や病気の予防、さらには病院での体験そのものを、より快適で質の高いものへと変革させる大きな可能性を秘めているのです。
身近なスマホアプリもヘルステックの一種
「ヘルステック」と聞くと、最先端の医療機器や専門的なシステムを想像するかもしれません。しかし、あなたが毎日使っているスマートフォンのアプリの中にも、ヘルステックはたくさん存在します。これらは、私たちの健康意識を高め、手軽にセルフケアを実践するための強力なツールです。
例えば、歩数や消費カロリーを自動で記録する健康管理アプリ、睡眠の質を分析してくれる睡眠追跡アプリ、食事の写真を撮るだけで栄養バランスを計算してくれる食事管理アプリなどが代表例です。Apple Watchなどのウェアラブルデバイスと連携すれば、心拍数や血中酸素濃度といった、より詳細な身体のデータを24時間記録し続けることも可能になります。これらのアプリは、これまで見えにくかった日々の健康状態を「見える化」し、生活習慣の改善を促すことで、病気になりにくい体づくり、いわゆる「予防医療」の領域で大きな役割を果たしています。
病院での体験を変えるヘルステック技術
ヘルステックは、私たちの日常生活だけでなく、病院での医療体験も大きく変えようとしています。多くの人が経験したことのある「病院の長い待ち時間」や「煩雑な手続き」といった課題も、ヘルステックによって解決されつつあります。
例えば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも診察予約ができる「オンライン予約システム」は、もはや当たり前になりました。さらに、来院前に症状などを詳しく入力できる「Web問診システム」を導入する医療機関も増えています。これにより、病院での問診票記入の手間が省け、医師も事前に患者の状態を把握できるため、よりスムーズで質の高い診察につながります。また、AIがチャット形式で症状を分析し、関連する病気の可能性や受診すべき診療科を提案してくれる「AI問診サービス」も登場し、受診前の不安を和らげる手助けをしています。
このように、ヘルステックは医療の質を向上させるだけでなく、患者と医療従事者双方の負担を軽減し、より快適で効率的な医療の実現に貢献しているのです。以下の表は、従来の医療体験とヘルステック導入後の体験の違いをまとめたものです。
| 場面 | 従来の医療体験 | ヘルステック導入後の医療体験 |
|---|---|---|
| 予約 | 診療時間内に電話で予約。話し中で繋がらないことも。 | スマホやPCから24時間いつでもオンラインで予約可能。 |
| 受付・問診 | 来院後に受付し、待合室で問診票に手書きで記入。 | 事前にWeb問診を済ませ、来院後はスムーズに受付完了。 |
| 診察 | 医師が口頭で症状を聞き取り、紙のカルテに記入。 | Web問診や電子カルテの情報を元に、より深く的確な診察が可能に。 |
| 会計 | 診察後に会計窓口で長時間待つことがある。 | キャッシュレス決済や後払いシステムの導入で待ち時間を短縮。 |
この表からもわかるように、ヘルステックは患者が医療サービスを受けるまでのあらゆるプロセスを最適化し、ストレスの少ない体験を提供します。これにより、私たちは病気になったときも、より安心して質の高い医療を受けられるようになります。
こんなに便利!私たちの暮らしを変えるヘルステックサービス具体例

ヘルステックは、もはや未来の技術ではありません。すでに私たちの生活の中に溶け込み、健康に関する悩みや不安を解決する身近なサービスとして利用されています。
ここでは、私たちの暮らしをより豊かに、そして便利に変えてくれる代表的なヘルステックサービスを4つの分野に分けて具体的にご紹介します。
自宅で診察が受けられる「オンライン診療」
オンライン診療は、スマートフォンやパソコンのビデオ通話機能を使って、自宅や職場にいながら医師の診察を受けられるサービスです。医療機関へ足を運ぶことなく、予約から診察、決済、さらには処方箋の受け取りまでを完結できます。
これまで「体調が悪いけれど、仕事が休めない」「病院の待ち時間が長いのが負担」「小さな子どもがいて、気軽に外出できない」といった理由で受診をためらっていた方々にとって、医療へのアクセスを劇的に改善する画期的なサービスと言えるでしょう。特に、定期的な通院が必要な生活習慣病の管理や、プライバシーが気になる心療内科などの分野で活用が広がっています。
| オンライン診療の主なメリット | 注意点・デメリット |
|---|---|
| 通院にかかる時間や交通費を削減できる | 触診や聴診、精密な検査はできない |
| 病院や薬局での待ち時間を短縮できる | すべての疾患や症状に対応できるわけではない |
| 院内での二次感染リスクを低減できる | 安定したインターネット環境が必要になる |
| 全国どこからでも専門的な医療相談が可能になる場合がある | 対面診療に比べて得られる情報が限られることがある |
もちろん、緊急性の高い症状や、詳細な検査が必要な場合には対面での診療が不可欠ですが、オンライン診療は医療の選択肢を広げ、私たちの多忙な日常に寄り添う新しい医療の形として定着しつつあります。
日々の健康を可視化する「健康管理アプリ」
スマートフォンアプリやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを活用した健康管理サービスは、最も身近なヘルステックの一つです。歩数や消費カロリー、睡眠時間といった日々の活動量を自動で記録し、健康状態を「見える化」してくれます。
これらのサービスは、単にデータを記録するだけではありません。蓄積されたデータをAIが分析し、個人の目標や状態に合わせた食事メニューや運動プランを提案してくれるなど、パーソナルトレーナーのような役割を果たします。日々の頑張りがグラフや数値で目に見えることでモチベーションの維持につながり、ゲーム感覚で楽しみながら健康習慣を身につけることができます。
食事の写真を撮るだけで栄養素を自動計算してくれるアプリ、睡眠の深さや質を分析して改善点をアドバイスしてくれるアプリなど、その種類は多岐にわたります。これらのデータを活用することで、漠然とした「健康に気をつけよう」という意識から、「具体的な目標を持って行動する」という主体的な健康づくりへとシフトすることが可能です。
自分の体質を知る「遺伝子検査サービス」
「自分はどんな病気にかかりやすいのだろう?」「自分に合ったダイエット法が知りたい」と考えたことはありませんか?遺伝子検査サービスは、自宅で唾液などの検体を採取して郵送するだけで、そうした疑問に答えるヒントを提供してくれます。
このサービスでは、生まれ持った遺伝的な傾向を分析し、特定の疾患へのかかりやすさ(リスク)や、肥満・肌質・薄毛といった体質について知ることができます。自分の体の設計図とも言える遺伝情報を知ることで、将来の健康リスクに備え、より効果的な予防策やライフスタイルの改善につなげることが期待できます。
| 遺伝子検査でわかることの例 | |
|---|---|
| 疾患リスク | がん(胃、肺、大腸など)、生活習慣病(糖尿病、高血圧など)、その他特定の疾患のかかりやすさ |
| 体質 | 肥満タイプ、肌質(シミ・シワのできやすさ)、アルコール耐性、カフェイン感受性、筋肉のつきやすさなど |
| その他 | 祖先のルーツ、能力(記憶力、計算速度など)の遺伝的傾向 |
ただし、検査結果はあくまで統計的なリスクや傾向を示すものであり、将来の健康を確定させるものではありません。結果を正しく理解し、過度に不安になることなく、前向きな健康管理に活かすことが重要です。
アプリで病気を治す「治療用アプリ」
「アプリで病気を治す」と聞くと、SFの世界のように思えるかもしれませんが、これはすでに現実のものとなっています。「治療用アプリ」または「DTx(デジタルセラピューティクス)」と呼ばれるこの分野は、ヘルステックの中でも特に注目されている新しい治療法です。
治療用アプリは、一般的な健康管理アプリとは一線を画し、医薬品や医療機器と同様に、病気の治療を目的として国の承認を受けた「医療機器」として扱われます。医師が患者に処方し、保険が適用されるケースも出てきています。
例えば、禁煙治療をサポートするアプリでは、患者の呼気中の一酸化炭素濃度を測定するデバイスと連携し、日々の状態に合わせて個別のアドバイスやビデオメッセージを送信することで、禁煙の継続を支援します。また、高血圧症の治療用アプリでは、食事や運動、服薬といった生活習慣の改善を促し、血圧の管理をサポートします。
このように、従来の医薬品だけでは介入が難しかった患者の日常生活や心理面にアプローチし、行動変容を促すことで治療効果を高めるのが治療用アプリの大きな特徴です。副作用がほとんどない点もメリットであり、既存の治療法と組み合わせることで、医療の可能性を大きく広げると期待されています。
注目のヘルステック企業とサービスをわかりやすく紹介

日本のヘルステック市場は急速に拡大しており、多くの革新的な企業が次々と新しいサービスを生み出しています。ここでは、私たちの健康や医療との関わり方を大きく変える可能性を秘めた注目のヘルステック企業を、「健康管理・予防」「診療・コミュニケーション」「治療・医薬品」の3つの分野に分けて、具体的なサービス内容とともにわかりやすく解説します。
健康管理・予防分野
病気になる前の「未病」や「予防」の段階で、日々の健康維持や増進をサポートする分野です。個人の健康データを活用し、一人ひとりに最適なソリューションを提供することで、健康寿命の延伸に貢献します。
株式会社FiNC Technologies
株式会社FiNC Technologiesは、パーソナルAIトレーナーを搭載したヘルスケアプラットフォームアプリ「FiNC」を提供する、予防ヘルスケア領域のリーディングカンパニーです。「すべての人にパーソナルコーチを」をミッションに掲げ、AIテクノロジーを駆使して個人の健康課題の解決を目指しています。
主力サービスである「FiNC」アプリは、歩数・食事・睡眠・体重などのライフログを手軽に記録できるだけでなく、そのデータに基づいてAIがパーソナライズされた健康アドバイスを毎日提供してくれます。さらに、専門家が監修するフィットネス動画や健康レシピなどのコンテンツも豊富で、楽しみながら健康習慣を身につけられる点が大きな魅力です。法人向けにも「FiNC for BUSINESS」を展開し、従業員の健康経営を支援しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的なサービス | ヘルスケアプラットフォームアプリ「FiNC」 |
| 主な特徴 | AIによるパーソナライズされた健康アドバイス、豊富なウェルネスコンテンツ、ライフログ管理機能 |
| ターゲット | 健康意識の高い個人、健康経営を目指す法人 |
診療・コミュニケーション分野
患者と医療機関をつなぎ、医療へのアクセスを向上させる分野です。オンライン診療や症状検索エンジンの登場により、時間や場所の制約なく、必要な時に適切な医療情報やサービスを受けられる環境が整いつつあります。
株式会社メドレー
株式会社メドレーは、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、多角的に事業を展開するヘルステック業界の代表格です。医療従事者と患者、双方の課題を解決するプラットフォームを構築しています。
代表的なサービスには、国内最大級のオンライン診療システム「CLINICSオンライン診療」があります。これにより、患者は自宅や職場からビデオ通話で医師の診察を受けることが可能になります。同社は他にも、医療介護分野の人材不足を解消する求人サイト「ジョブメドレー」や、クラウド型電子カルテ「CLINICSカルテ」なども提供しており、医療現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を包括的に支援している点が強みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的なサービス | オンライン診療システム「CLINICSオンライン診療」、医療介護求人サイト「ジョブメドレー」 |
| 主な特徴 | 患者向け・医療機関向け双方のサービスを提供し、医療プラットフォームを構築。オンライン診療のパイオニア。 |
| ターゲット | 患者、医療機関、クリニック、薬局、介護施設 |
Ubie株式会社
Ubie株式会社は、「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」ことを目指し、現役医師とエンジニアが創業したスタートアップです。AIをコア技術として、生活者と医療機関の双方に向けたサービスを提供しています。
生活者向けの症状検索エンジン「ユビー」は、気になる症状を入力すると、関連する病名や適切な診療科、近くの医療機関などを調べることができるサービスです。一方、医療機関向けには「ユビーAI問診」を提供。患者が来院前にスマートフォンなどで詳細な問診を済ませることで、医師は診察前に質の高い情報を得られ、診察の効率化と質の向上につながります。これにより、患者の待ち時間短縮と医療現場の負担軽減を同時に実現しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的なサービス | 症状検索エンジン「ユビー」、医療機関向けサービス「ユビーAI問診」 |
| 主な特徴 | AIを活用した精度の高い問診アルゴリズム。生活者と医療機関をつなぎ、受診行動をスムーズにする。 |
| ターゲット | 体調に不安のある生活者、業務効率化を目指す医療機関 |
治療・医薬品分野
ソフトウェアやアプリを用いて病気の治療を行う「デジタルセラピューティクス(DTx)」が注目される分野です。従来の医薬品や医療機器では介入が難しかった領域で、新たな治療選択肢を提供します。
株式会社CureApp
株式会社CureAppは、日本における「治療用アプリ®︎」のパイオニアであり、ソフトウェアを用いた新しい治療法の開発・提供を行っています。現役の医師が創業し、医学的エビデンスに基づいた開発を進めているのが特徴です。
同社が開発したニコチン依存症治療用アプリ「CureApp SC」や、高血圧症治療用アプリ「CureApp HT」は、日本で初めて製造販売承認を取得し、保険適用となった「治療用アプリ」です。これらのアプリは医師によって処方され、患者は日々の生活の中でアプリからの個別化されたガイダンスに従って行動変容に取り組みます。診察時以外の「空白期間」をアプリがサポートすることで、治療効果を最大化し、医療の質の向上に貢献しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的なサービス | ニコチン依存症治療アプリ「CureApp SC」、高血圧症治療アプリ「CureApp HT」 |
| 主な特徴 | ソフトウェアを「医薬品」として開発・提供。医師が処方し、保険適用される点が画期的。 |
| ターゲット | 特定の疾患を持つ患者、治療を行う医療機関 |
ヘルステックがなぜこれほど注目されているのか

近年、ニュースやビジネスシーンで「ヘルステック」という言葉を耳にする機会が急増しました。単なるIT技術の医療応用というだけでなく、私たちの生活や社会のあり方そのものを変える可能性を秘めているからです。では、なぜ今、これほどまでにヘルステックが大きな注目を集めているのでしょうか。その背景には、日本が抱える社会的な課題と、国を挙げた大きな変革の動きがあります。
健康寿命の延伸への期待
日本が直面している最も大きな課題の一つが「超高齢社会」です。平均寿命が延び続ける一方で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を示す「健康寿命」との間に約10年のギャップが存在することが問題視されています。
このギャップは、個人のQOL(生活の質)の低下を招くだけでなく、医療費や介護給付費といった社会保障費の増大にも直結します。この深刻な課題を解決する鍵として、ヘルステックに大きな期待が寄せられているのです。
これまでの医療は、病気になってから治療するという「治療中心」のアプローチが主流でした。しかし、ヘルステックは個人の健康データを日常的に収集・分析することで、病気になる前の「予防」や「早期発見」を可能にします。ウェアラブルデバイスで日々の活動量や睡眠の質を把握したり、健康管理アプリで食事や血圧を記録したりすることは、まさに「治療」から「予防・セルフケア」へのシフトを促す動きです。一人ひとりが自身の健康状態を正しく理解し、主体的に管理することで、健康寿命を延ばし、より豊かで活力ある人生を送る社会の実現が期待されています。
国が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)
ヘルステック市場の成長を強力に後押ししているのが、政府が主導する「医療DX」の推進です。医療DXとは、デジタル技術を活用して医療・ヘルスケア分野の仕組みを変革し、国民の健康増進とより質の高い医療の提供を目指す取り組みです。これは、内閣官房が主導する「データヘルス改革」とも連動しており、国策として進められています。
これまで日本の医療現場では、医療機関ごとに情報が分断され、紙媒体でのやり取りが多いなど、デジタル化の遅れが指摘されてきました。この状況を打破し、医療現場の業務効率化と医療の質の向上を両立させるために、国は様々な施策を打ち出しています。
具体的には、以下のような取り組みがヘルステック企業の活躍の場を広げています。
| 国の主な施策 | 概要 | ヘルステックの役割・貢献 |
|---|---|---|
| オンライン資格確認・電子処方箋の導入 | マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、患者の薬剤情報や特定健診情報を医療機関が確認できる仕組み。電子処方箋により薬局との情報連携もスムーズになる。 | オンライン診療システムや電子カルテシステムとの連携。PHR(個人の健康記録)アプリとのデータ連携による服薬管理の効率化。 |
| 電子カルテ情報の標準化 | 各医療機関でバラバラだった電子カルテの規格を標準化し、医療機関同士でのスムーズな情報共有を目指す。 | 標準化されたデータを活用した新たな診断支援AIの開発。地域医療連携ネットワークを支えるプラットフォームの提供。 |
| 診療報酬におけるデジタル活用評価 | オンライン診療や治療用アプリなど、デジタル技術を用いた医療行為に対して診療報酬(保険点数)が設定される。 | オンライン診療サービスや治療用アプリの開発・提供が事業として成立しやすくなり、企業の参入と技術開発を促進する。 |
このように、国が制度やインフラを整備することで、ヘルステックは単なる便利なツールから、日本の医療システムに不可欠な要素へと変化しつつあります。これにより、医師や看護師の負担軽減、地域による医療格差の是正、そして国民一人ひとりへの最適な医療の提供が実現されようとしているのです。
これからのヘルステックはどうなる?未来のトレンドを予測
テクノロジーの進化は、ヘルステックの可能性を飛躍的に拡大させています。これまで「病気になったら治療する」という考え方が主流でしたが、これからは「病気にならないように予防する」「一人ひとりに最適化されたケアを受ける」という時代へと大きくシフトしていくでしょう。ここでは、ヘルステックが切り拓く未来のトレンドを、2つの大きな潮流から予測します。
AIが一人ひとりに最適な健康法を提案する時代へ
今後のヘルステックの進化を語る上で、AI(人工知能)の存在は欠かせません。AIによる高度なデータ解析は、医療・ヘルスケアのあり方を「画一的なもの」から「完全にパーソナライズされたもの」へと変えていきます。
例えば、ウェアラブルデバイスから得られる日々の活動量や睡眠データ、遺伝子検査の結果、日々の食事記録、そして電子カルテの情報まで、あらゆる健康データをAIが統合的に解析。その結果、あなただけの体質やライフスタイルに合わせた最適な食事メニューや運動プログラム、必要な栄養素などを提案してくれるようになります。これは「プレシジョン・メディシン(個別化医療)」や「プレシジョン・ニュートリション(個別化栄養学)」と呼ばれる領域で、病気の予防やパフォーマンス向上に大きく貢献すると期待されています。
さらに、仮想空間上に自分自身のデジタルコピー(デジタルツイン)を構築し、新しい治療法や薬の効果を投与前にシミュレーションするといった、SF映画のような世界も現実味を帯びてきています。これにより、治療効果の最大化と副作用の最小化が期待できるのです。
データ活用で病気の早期発見がより身近に
ヘルステックのもう一つの重要なトレンドは、IoTデバイスの進化とデータ活用による病気の超早期発見です。私たちの健康状態は、常にゆるやかに変化しています。その微細な変化を捉えることが、重篤な疾患の予防に繋がります。
今後は、スマートウォッチやスマートリングだけでなく、衣服や寝具、コンタクトレンズといった、より生活に溶け込んだデバイスが私たちのバイタルデータを24時間365日、途切れることなく収集するようになります。心拍数や血圧、体温はもちろん、血糖値や血中酸素濃度といった従来は採血が必要だったデータも、非侵襲(体を傷つけない)でモニタリング可能になるでしょう。
そして、収集された膨大な時系列データ(PHR:Personal Health Record)をAIが常時解析し、本人も気づかないような体調の異常や、特定の病気につながる予兆を検知すると、即座に本人や家族、かかりつけ医にアラートを送信する。このような仕組みが一般化すれば、心筋梗塞や脳卒中といった突然死のリスクを劇的に低減できる可能性があります。
これらの未来を実現するためには、技術の進化だけでなく、個人情報を安全に管理・活用するための法整備や社会全体の理解が不可欠です。しかし、ヘルステックがもたらす未来は、私たちがより健康で豊かな人生を送るための大きな希望となることは間違いありません。
ヘルステックの未来像を、技術領域ごとに表で整理してみましょう。
| 技術領域 | 具体的な未来像 | もたらされる価値 |
|---|---|---|
| AI・データ解析 | ゲノム情報や生活習慣データに基づいた、個人最適化された食事・運動指導。デジタルツインによる治療シミュレーション。 | 究極の予防医療の実現。治療効果の最大化と副作用の最小化。 |
| IoT・ウェアラブルデバイス | 衣服型やコンタクトレンズ型デバイスによる非侵襲での常時バイタルモニタリング。健康データの自動収集と異常値の検知・通知。 | 重篤な疾患の超早期発見。突然死リスクの低減と健康寿命の延伸。 |
| VR/AR・メタバース | 仮想空間でのリアルな手術トレーニングやリハビリテーション。遠隔地にいる専門医による手術支援。 | 医療技術の向上と標準化。医療における地域格差の是正。 |
| PHR・ブロックチェーン | 個人が自身の健康・医療情報を安全に一元管理し、許可した範囲で医療機関等と共有できるプラットフォームの普及。 | スムーズな医療連携の実現。個人のデータが創薬や公衆衛生に貢献。 |
まとめ
ヘルステックは、オンライン診療や健康管理アプリなどを通じて、私たちの医療体験や日々の健康管理を大きく変革する技術です。健康寿命の延伸への期待や国の医療DX推進を背景に市場は急成長しており、株式会社メドレーや株式会社CureAppといった企業が革新的なサービスを提供しています。
今後はAIやデータを活用し、一人ひとりに最適化された予防医療や病気の早期発見がさらに身近になるでしょう。私たちの未来を豊かにするヘルステックの動向から目が離せません。