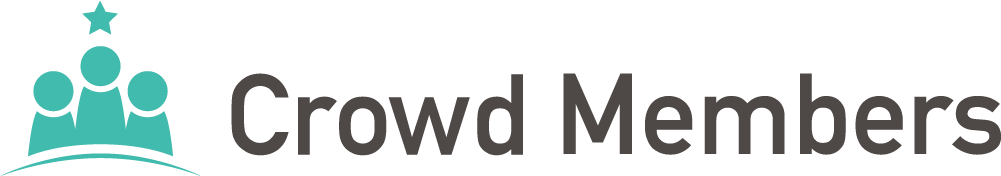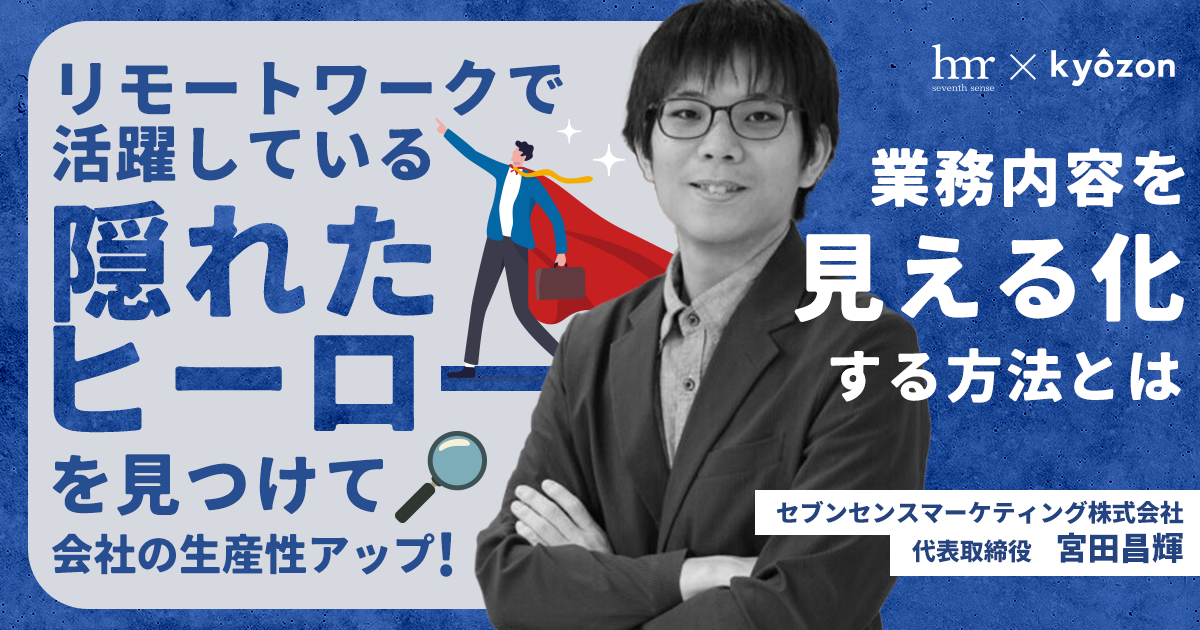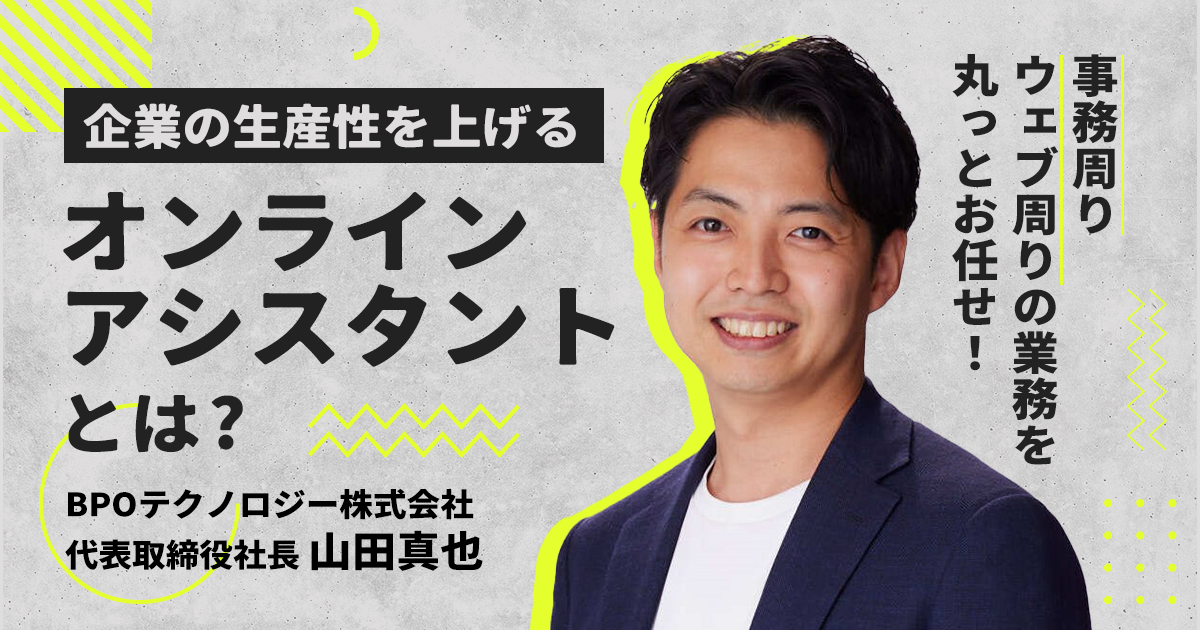HRテックとは

近年、人事領域で「HRテック」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。しかし、その具体的な意味や、なぜ今これほどまでに注目されているのかを正確に理解している方はまだ少ないかもしれません。
この章では、HRテックの基本的な定義から、現代のビジネス環境においてその重要性が増している背景までを詳しく解説します。人事部門が抱える課題を解決し、企業の成長を加速させる鍵となるHRテックの全体像を掴みましょう。
HRテック=人事領域の課題をテクノロジーで解決する手法
HRテック(HR Tech)とは、「Human Resources(人事)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。その名の通り、AI(人工知能)、クラウド、ビッグデータといった最先端のテクノロジーを活用して、採用、労務管理、人材育成、人事評価など、人事領域におけるさまざまな業務課題を解決するソリューションや手法の総称を指します。
従来、人事部門の業務は、紙の書類やExcelでの手作業に依存することが多く、非効率な面が課題とされてきました。HRテックは、これらの定型業務を自動化・効率化するだけでなく、従業員のスキルや経験、パフォーマンスといったデータを一元管理・分析することで、データに基づいた客観的で戦略的な意思決定(戦略人事)を可能にします。
HRテックがカバーする領域は非常に幅広く、企業の課題に応じて多岐にわたるサービスが存在します。主な領域と、それに対応するHRテックの役割を以下に示します。
| 人事領域 | 主な業務内容 | HRテックによる解決策(例) |
|---|---|---|
| 採用管理 | 求人情報の作成・掲載、応募者情報管理、選考進捗管理、面接日程調整 | 採用管理システム(ATS)による応募者情報の一元管理、選考プロセスの自動化 |
| 労務管理 | 勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、年末調整、入退社手続き | 勤怠管理システムや給与計算ソフトによる業務自動化、ペーパーレス化の推進 |
| 人材育成・開発 | 研修プログラムの管理、eラーニングの提供、学習進捗の把握、スキル管理 | LMS(学習管理システム)によるオンライン研修の効率的な運用、スキルマップの可視化 |
| 人事評価 | 評価シートの配布・回収、評価プロセスの管理、評価結果の集計・分析 | 人事評価システムによる評価プロセスの効率化、評価基準の統一、評価データの蓄積 |
| タレントマネジメント | 従業員のスキル・経歴・キャリア志向の把握、最適な人材配置、後継者育成 | タレントマネジメントシステムによる人材情報の可視化、データに基づく戦略的な人員配置 |
| 組織開発 | 従業員エンゲージメントの測定、組織コンディションの可視化、社内コミュニケーション活性化 | エンゲージメントサーベイツールによる組織課題の特定、社内SNSによるコミュニケーション促進 |
HRテックが今注目される背景
なぜ今、多くの企業がHRテックの導入を進めているのでしょうか。その背景には、日本企業が直面する複数の社会的な変化や経営課題が複雑に絡み合っています。ここでは、特に重要な4つの背景について解説します。
1. 少子高齢化による労働人口の減少
日本は深刻な少子高齢化に直面しており、生産年齢人口は年々減少し続けています。これにより、多くの業界で人手不足が深刻化し、優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。限られたリソースの中で企業が成長を続けるためには、一人ひとりの従業員の生産性を最大限に高めると同時に、魅力的な労働環境を整備して人材の定着(リテンション)を図ることが不可欠です。HRテックは、採用活動の効率化や、データに基づいた離職防止策の立案、従業員の能力開発支援などを通じて、この課題に対する有効な解決策を提供します。
2. 働き方の多様化への対応
リモートワーク(テレワーク)やフレックスタイム制の普及、副業・兼業の解禁など、従業員の働き方は急速に多様化しています。こうした変化は、従業員に柔軟な働き方を提供する一方で、企業の人事・労務管理を複雑化させています。例えば、オフィス外での労働時間の正確な把握や、多様な雇用形態に対応した給与計算、離れた場所で働く従業員のコンディション把握などが新たな課題となっています。HRテックは、クラウドベースの勤怠管理システムやコミュニケーションツールを提供することで、場所や時間にとらわれない新しい働き方に柔軟に対応できる基盤を構築します。
3. DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の潮流
ビジネス環境の急速な変化に対応するため、多くの企業が経営戦略の柱としてDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。DXは、単にITツールを導入することではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革し、競争上の優位性を確立することを目的とします。この流れの中で、これまでアナログな手法が根強く残っていた人事部門も、変革の対象となっています。HRテックの導入は、人事部門におけるDXの第一歩であり、バックオフィス業務の効率化を通じて、人事担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を創出します。
4. 従業員エンゲージメントと人的資本経営の重要性の高まり
企業の持続的な成長のためには、従業員が自社のビジョンに共感し、仕事に対して情熱と誇りを持って自律的に貢献しようとする意欲、すなわち「従業員エンゲージメント」が極めて重要であるという認識が広まっています。また、従業員をコストではなく「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上につなげる「人的資本経営」も注目されています。HRテックは、サーベイツールによるエンゲージメントの可視化や、個々の従業員のキャリア志向に合わせた育成プランの提案、公正な評価制度の運用などを支援し、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる組織作りを実現するための強力な武器となります。
HRテック導入のメリットと知っておくべきデメリット

HRテックの導入は、人事領域に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、メリットだけでなくデメリットや注意点も正確に理解し、自社の状況と照らし合わせて慎重に検討することが不可欠です。
ここでは、HRテック導入によって得られる多角的なメリットと、導入前に必ず確認しておくべきデメリットを詳しく解説します。
業務効率化だけではないHRテックのメリット
HRテック導入のメリットとして、まず思い浮かぶのは「業務効率化」かもしれませんが、その効果は多岐にわたります。定型業務の自動化によって生まれた時間を、より戦略的な人事施策に充てられるようになることこそ、HRテックがもたらす最大の価値と言えるでしょう。ここでは、代表的な5つのメリットを掘り下げてご紹介します。
メリット1:人事関連業務の大幅な効率化と生産性向上
給与計算、勤怠管理、入退社手続き、年末調整といった人事・労務領域の業務は、毎月・毎年発生する定型業務でありながら、多くの工数を要します。HRテックを導入することで、これらの手作業で行っていた煩雑な業務を自動化し、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。これにより、ヒューマンエラーの削減にも繋がり、業務全体の正確性が向上します。創出された時間を人材育成計画の策定や組織開発といった、企業の成長に直結するコア業務に振り分けることで、人事部門全体の生産性向上を実現します。
メリット2:データに基づいた客観的で戦略的な人事施策の立案
HRテックは、これまで個別に管理されがちだった従業員の経歴、スキル、評価、勤怠状況といった人材データを一元的に集約・可視化します。これにより、勘や経験に頼った主観的な判断ではなく、客観的なデータに基づいた戦略的な意思決定(データドリブン人事)が可能になります。例えば、ハイパフォーマーの行動特性を分析して採用や育成に活かしたり、離職者の傾向を分析してリテンション施策を講じたり、従業員のスキルデータを基に最適な人材配置を行うなど、より精度の高い人事戦略を展開できるようになります。
メリット3:従業員エンゲージメントと満足度の向上
HRテックは、人事担当者だけでなく、従業員にとっても多くのメリットをもたらします。スマートフォンから容易に休暇申請や勤怠打刻ができたり、評価プロセスがシステム上で透明化されることで、評価に対する納得感が高まったりします。また、定期的なパルスサーベイなどを通じて、企業が従業員のコンディションを把握し、迅速なケアを行うことで、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)向上’mark>に繋がります。働きやすい環境が整備されることは、従業員満足度を高め、優秀な人材の定着にも貢献します。
メリット4:コンプライアンス強化と労務リスクの低減
働き方改革関連法をはじめ、労働関連法規は頻繁に改正されます。これらの法改正に対応し、常に最新の状態で勤怠管理や給与計算を行うことは、企業にとって重要な責務です。多くのクラウド型HRテックサービスは、法改正に合わせてシステムが自動でアップデートされるため、コンプライアンスを遵守した労務管理を容易に実現できます。労働時間を正確に把握し、長時間労働を未然に防ぐアラート機能を活用することで、従業員の健康を守ると同時に、企業の労務リスクを大幅に低減させることが可能です。
メリット5:採用活動の質の向上と採用コストの最適化
採用管理システム(ATS)を導入することで、複数の求人媒体からの応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況を可視化できます。面接日程の自動調整や応募者とのコミュニケーションを効率化することで、採用担当者の負担を軽減し、選考スピードを向上させます。さらに、応募経路ごとの採用決定率などを分析することで、費用対効果の高い採用チャネルを見極め、採用戦略を最適化できます。これにより、採用のミスマッチを減らし、採用コストの削減と定着率の向上に繋げることが可能です。
導入前に確認したいデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、HRテックの導入にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前にリスクを把握し、対策を講じておくことが成功の鍵となります。
デメリット1:導入・運用コストが発生する
HRテックサービスの導入には、初期費用や月額(または年額)の利用料といったコストが発生します。特に多機能なサービスや、利用する従業員数が多い場合は、相応の費用が必要となります。導入を検討する際は、単に機能や価格だけで比較するのではなく、自社の課題解決によって得られる効果(業務削減時間、人件費削減効果など)を算出し、費用対効果(ROI)を検証することが重要です。無料トライアル期間を活用したり、まずは一部の部門からスモールスタートしたりするなど、慎重に導入を進めることも有効な手段です。
デメリット2:システムの導入と社内浸透に手間と時間がかかる
新しいシステムを導入する際には、ツールの選定から始まり、既存データの移行、初期設定、業務フローの見直し、そして従業員への説明やトレーニングなど、多くの工数と時間が必要です。特に、ITツールに不慣れな従業員が多い場合、新しいシステムへの抵抗感が生まれることも少なくありません。導入がゴールではなく、全従業員が適切に活用して初めて効果が生まれることを理解し、導入目的やメリットを丁寧に説明する場を設け、マニュアル整備や研修を行う”mark>など、社内への浸透活動を計画的に行う必要があります。
デメリット3:情報漏洩などのセキュリティリスク
HRテックは、氏名、住所、給与、評価といった極めて機密性の高い従業員の個人情報を扱います。そのため、セキュリティ対策は最も重要な選定基準の一つです。万が一、サイバー攻撃や内部不正によって情報が漏洩した場合、企業の社会的信用は大きく損なわれます。サービス選定時には、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマークの取得状況、データの暗号化、アクセス制限機能、サーバーの監視体制など、提供事業者のセキュリティ対策が万全であるかを必ず確認しましょう。
| デメリット・注意点 | 確認・対策すべきこと |
|---|---|
| コストの発生 | ・費用対効果(ROI)を事前にシミュレーションする。 ・無料トライアルやスモールスタートを検討する。 |
| 導入・定着の手間 | ・導入プロジェクトの責任者を明確にし、計画的に進める。 ・従業員への説明会や研修を十分に行う。 ・導入後のサポート体制が充実しているサービスを選ぶ。 |
| セキュリティリスク | ・ISMS認証やプライバシーマークの有無を確認する。 ・アクセス権限設定など、サービス側のセキュリティ機能を確認する。 ・社内の情報管理ルールを整備・徹底する。 |
| ツールへの過度な期待 | ・導入の目的と解決したい課題を明確にする。 ・自社の業務フローに適合するかを確認する。 ・複数のツールを連携させる場合は、連携の可否や方法を確認する。 |
HRテックで業務効率化を実現する5つの方法

HRテックは、人事領域のさまざまな業務を効率化し、より戦略的な人事活動へとシフトさせるための強力なツールです。ここでは、具体的な業務課題と、それを解決するためのHRテック活用法を5つの分野に分けて詳しく解説します。
方法1:採用管理システムで採用プロセスを自動化する
採用活動は、企業の成長を支える重要な業務ですが、そのプロセスは非常に煩雑です。応募者情報の管理、面接の日程調整、選考結果の連絡など、多くの手作業が発生し、採用担当者の大きな負担となっています。採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、これらの課題を解決し、採用活動全体を効率化します。
システムを導入することで、複数の求人媒体からの応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況をリアルタイムで可視化できます。また、面接官との情報共有や日程調整もシステム上で完結するため、コミュニケーションコストや調整にかかる時間を大幅に削減できます。
採用管理システムの導入による変化を以下にまとめました。
| 項目 | 導入前(手作業) | 導入後(システム活用) |
|---|---|---|
| 応募者管理 | Excelやスプレッドシートで個別に管理。情報の更新漏れや重複が発生しやすい。 | 各求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み、一元管理。重複応募も自動で検知。 |
| 選考進捗管理 | 担当者しか状況を把握できず、社内での情報共有に手間がかかる。 | 候補者ごとの選考ステータスが可視化され、関係者全員がリアルタイムで状況を把握可能。 |
| 面接日程調整 | 候補者と面接官の間で何度もメールのやり取りが発生し、時間がかかる。 | 候補者が空き時間を選択できるURLを発行。面接官のカレンダーと連携し、調整を自動化。 |
| 効果測定 | 求人媒体ごとの応募数や採用決定数を手動で集計する必要があり、分析が困難。 | 媒体別の費用対効果や選考フローごとの通過率などを自動で分析。データに基づいた採用戦略を立案可能。 |
このように、採用管理システムは採用業務の自動化・効率化だけでなく、蓄積されたデータを分析し、採用の質を向上させる戦略的な役割も担います。
方法2:勤怠管理システムで打刻から集計までを一元管理する
タイムカードやExcelによる勤怠管理は、毎月の集計作業に膨大な時間がかかるだけでなく、打刻漏れや計算ミスといった人為的エラーが発生しやすいという課題があります。また、テレワークやフレックスタイム制など多様化する働き方への対応も困難です。勤怠管理システムは、これらの労務管理における課題を解決します。
PC、スマートフォン、ICカードなど、さまざまな方法で打刻が可能になり、従業員の労働時間をリアルタイムで正確に把握できます。打刻データは自動で集計され、残業時間や休暇取得状況も可視化されるため、管理者の負担を劇的に軽減します。
さらに、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得義務化といった頻繁な法改正にも、システムが自動でアップデート対応するため、コンプライアンス違反のリスクを低減できる点も大きなメリットです。申請・承認のワークフロー機能を使えば、休暇や残業の申請から承認までをペーパーレスで完結させることも可能です。
方法3:給与計算ソフトで面倒な計算業務から解放される
給与計算は、従業員の生活に直結するため1円のミスも許されない、非常にプレッシャーのかかる業務です。所得税や住民税、社会保険料などの複雑な計算に加え、毎年のように行われる法改正や保険料率の変更にも正確に対応しなければなりません。
給与計算ソフトを導入することで、これらの複雑な業務を自動化できます。勤怠管理システムと連携すれば、労働時間や残業代の計算を自動で行い、手入力によるミスを根本からなくすことができます。社会保険料や税金の計算も、最新の法令や料率に基づいて自動で行われるため、担当者は専門的な知識を常にアップデートし続ける負担から解放されます。
また、多くのソフトにはWeb給与明細機能が搭載されており、明細書の印刷・封入・配布といった物理的な作業も不要になります。従業員はいつでもスマートフォンやPCから自身の給与明細を確認できるようになり、利便性も向上します。年末調整機能を使えば、煩雑な書類の回収や計算作業も大幅に効率化が可能です。
方法4:人事評価システムで評価業務の公平性と透明性を高める
人事評価は、従業員のモチベーションや成長に大きく影響する重要な制度ですが、「評価基準が曖昧」「評価者によって判断がブレる」といった課題を抱える企業は少なくありません。Excelなどのアナログな方法では、評価シートの配布・回収・集計に手間がかかる上、過去の評価データが分散してしまい、人材育成に活かしきれないという問題もあります。
人事評価システムは、評価制度の運用を円滑にし、公平性と透明性を高めるための機能を提供します。目標設定(MBOやOKRなど)から評価の実施、フィードバック、承認までの一連のプロセスをシステム上で完結させることができます。評価基準や進捗状況が可視化されることで、評価者と被評価者の間での認識のズレを防ぎ、従業員の納得感を高める効果が期待できます。
さらに、評価データが一元的に蓄積されるため、個人の成長記録として活用できるだけでなく、全社的な視点で評価の甘辛調整や傾向分析を行うことも可能です。これにより、勘や経験に頼らない、客観的なデータに基づいた評価制度の改善や人材育成計画の策定が実現します。1on1ミーティングの記録を残す機能などを活用すれば、日々のコミュニケーションの質を高め、エンゲージメント向上にも繋がります。
方法5:タレントマネジメントで戦略的な人材配置を実現する
企業の持続的な成長には、従業員一人ひとりの能力やスキルを最大限に活かす「戦略的人事」が不可欠です。しかし、「誰がどのようなスキルを持っているのか把握できていない」「優秀な人材が離職してしまう」「後継者育成が進まない」といった課題を抱えているケースが多く見られます。
タレントマネジメントシステムは、従業員のスキル、経歴、資格、研修履歴、評価といった人材情報を一元管理し、可視化するためのプラットフォームです。社内に埋もれていた優秀な人材を発掘し、適材適所の人材配置や、次世代リーダー候補の育成(サクセッションプラン)をデータに基づいて計画的に進めることが可能になります。
例えば、新規プロジェクトを立ち上げる際に、システムで必要なスキルを検索すれば、部署を横断して最適なメンバーを迅速にアサインできます。また、従業員のエンゲージメントやコンディションを定期的にモニタリングし、離職の兆候を早期に察知して対策を講じる「リテンションマネジメント」にも活用できます。タレントマネジメントシステムは、単なる業務効率化ツールではなく、人材という経営資源を最大化し、企業の競争力を高めるための戦略的な基盤となるのです。
【分野別】注目のおすすめHRテックサービス

HRテックサービスは多岐にわたりますが、ここでは特に多くの企業が課題を抱える「採用管理」「労務管理」「タレントマネジメント」の3つの分野に分けて、注目度の高いおすすめのサービスをご紹介します。各サービスの特徴を比較し、自社の課題解決に最も貢献するツールを見つけるための参考にしてください。
採用管理領域のHRテックサービス
採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、候補者の応募から採用決定までのプロセスを一元管理し、採用活動の効率化と質向上を支援するツールです。煩雑な情報管理やコミュニケーションコストの削減に大きく貢献します。
HRMOS採用
HRMOS(ハーモス)採用は、株式会社ビズリーチが提供する採用管理クラウドです。採用活動におけるデータを可視化・分析することで、勘や経験に頼らないデータドリブンな採用戦略の実現をサポートします。求人票の作成から候補者管理、選考進捗の可視化、採用実績の分析まで、採用業務全体を一気通貫で管理できる点が大きな強みです。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| 候補者管理 | 各求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み、一元管理。候補者とのやり取りもシステム内で完結。 |
| 進捗管理 | 選考ステータスをリアルタイムで可視化。面接官とのスムーズな連携や日程調整を支援。 |
| データ分析 | 応募経路別の効果測定や選考フェーズごとの通過率などを分析し、採用活動の改善点を特定。 |
| 求人媒体連携 | 主要な求人媒体やダイレクトリクルーティングサービスと連携し、応募者情報を自動で登録。 |
データに基づいた採用改善を行いたい企業や、複数の採用チャネルを効率的に管理したい企業に特におすすめのサービスです。
HERP Hire
HERP Hireは、株式会社HERPが提供する採用管理プラットフォームです。最大の特徴は、社員紹介(リファラル採用)を含む全社一丸となった「スクラム採用」を推進する設計にあります。SlackやChatworkといったビジネスチャットツールとの強力な連携により、現場社員が日常的に使うツール上で候補者情報を共有し、採用活動へスムーズに参加できる環境を構築します。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| チャットツール連携 | Slack等に候補者情報が通知され、チャット上で選考評価やフィードバックが可能。 |
| 候補者情報の一元管理 | 20以上の求人媒体と連携し、あらゆる経路からの応募者を自動で集約。 |
| タスク管理機能 | 書類選考や面接調整など、各候補者に対する次のアクションをタスクとして管理し、対応漏れを防止。 |
| レポート機能 | 採用ファネル分析やチャネル別効果測定など、採用活動全体の状況を可視化。 |
エンジニア採用などでリファラル採用を強化したいIT企業や、採用活動に現場を巻き込み、全社で採用力を高めたいと考えている企業に最適なツールです。
労務管理領域のHRテックサービス
労務管理システムは、入退社手続き、勤怠管理、給与計算、年末調整といった定型業務を自動化・効率化するツールです。ペーパーレス化を促進し、法改正にも迅速に対応できるため、人事担当者の負担を大幅に軽減します。
SmartHR
SmartHRは、株式会社SmartHRが提供する労務管理クラウドで、この分野で圧倒的なシェアを誇ります。入社手続きや雇用契約、年末調整といった煩雑な書類作成をオンラインで完結させられる点が最大の特徴です。従業員自身がスマートフォンやPCから直接情報を入力するため、人事担当者のデータ入力作業や書類の配布・回収の手間がなくなります。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| 入退社手続き | 社会保険・雇用保険の資格取得・喪失届などの書類を自動作成し、電子申請に対応。 |
| 年末調整 | アンケート形式で従業員が情報を入力するだけで、面倒な申告書作成が完了。 |
| Web給与明細 | 給与明細や源泉徴収票をオンラインで配布。印刷・封入・郵送コストを削減。 |
| 従業員データベース | 収集した従業員情報を一元管理し、組織図の作成や各種分析に活用可能。 |
紙ベースの労務手続きに課題を感じている企業や、従業員情報の管理を効率化し、ペーパーレス化を推進したいあらゆる規模の企業におすすめです。
freee人事労務
freee人事労務は、「会計freee」で知られるfreee株式会社が提供するクラウド型人事労務ソフトです。その強みは、勤怠管理から給与計算、年末調整、労務手続きまでをシームレスに連携できる点にあります。さらに、会計freeeと連携させることで、給与計算の結果を自動で仕訳に反映でき、バックオフィス業務全体の大幅な効率化を実現します。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| 勤怠管理 | ICカード打刻やGPS打刻など多様な打刻方法に対応。労働時間を自動で集計。 |
| 給与計算 | 勤怠データや従業員情報をもとに給与を自動計算。社会保険料や税金の計算にも対応。 |
| 年末調整 | 従業員がスマホで質問に答えるだけで申告が完了。計算から書類作成までを自動化。 |
| 会計ソフト連携 | 給与支払いや社会保険料の支払いデータを会計freeeに連携し、仕訳を自動で作成。 |
既に「会計freee」を利用している企業はもちろん、経理と人事労務のデータを一元化し、バックオフィス全体の生産性を向上させたい中小企業に特に適しています。
タレントマネジメント領域のHRテックサービス
タレントマネジメントシステムは、従業員のスキル、経歴、評価、キャリア志向といった人材情報を一元管理・可視化し、戦略的な人材配置や育成、離職防止に活用するためのツールです。「戦略人事」を実現するための基盤となります。
カオナビ
カオナビは、株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステムです。その名の通り、社員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースで、人材情報を一元化・可視化できることが最大の特徴です。スキルや評価、経歴などの情報を組み合わせ、優秀な人材の発掘や最適な人材配置のシミュレーションを簡単に行うことができます。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| プロファイルブック | 顔写真付きで社員のスキルや経歴、個性などの情報を一元管理するデータベース。 |
| 評価ワークフロー | MBOや360度評価など、様々な評価制度の運用をシステム上で効率化。甘辛調整も可能。 |
| 配置シミュレーション | ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、異動や組織改編後の人員構成をシミュレーション。 |
| アンケート機能 | 従業員サーベイやパルスサーベイを実施し、エンゲージメントや満足度を定点観測。 |
従業員一人ひとりの顔と名前を一致させ、個性や能力を把握した上で適材適所を実現したい企業や、Excelや紙での人事評価管理から脱却し、評価プロセスの効率化と納得性の向上を図りたい企業に最適です。
タレントパレット
タレントパレットは、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する科学的人事の実践を支援するタレントマネジメントシステムです。人材データの分析機能に非常に長けており、蓄積された人事データやスキル、適性検査の結果などを多角的に分析し、離職予兆の検知やハイパフォーマー分析、最適配置のシミュレーションなどが可能です。マーケティングで培われた分析技術を人事に活用している点がユニークです。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 |
|---|---|
| 人材データ分析 | 離職予兆分析、エンゲージメント分析、ハイパフォーマー分析など、多彩な分析機能を提供。 |
| 人事評価 | 評価シートの設計から甘辛調整、評価者モニタリングまで、評価運用をトータルでサポート。 |
| スキル管理 | 社員の保有スキルを可視化し、スキルマップを作成。育成計画や人員配置に活用。 |
| 研修管理 | eラーニング機能や研修の出欠管理、アンケート実施など、人材育成プロセスを支援。 |
客観的なデータに基づいて人事戦略を立案・実行したい企業や、離職率の改善、従業員エンゲージメントの向上といった経営課題に本格的に取り組みたい企業にとって、強力な武器となるでしょう。
自社に最適なHRテックサービスの選び方
数多くのHRテックサービスの中から、自社の課題を解決し、組織の成長に貢献する最適なツールを選ぶことは、導入成功の鍵を握ります。価格や知名度だけで安易に選んでしまうと、現場で活用されず形骸化してしまったり、かえって業務が煩雑になったりする恐れがあります。ここでは、後悔しないためのHRテックサービスの選び方について、5つの重要なポイントを解説します。
解決したい人事課題を明確にする
HRテック導入を検討する最初のステップは、「何のために導入するのか」という目的、つまり解決したい人事課題を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、どのサービスが自社に合っているのか判断する基準が持てません。「業務効率化」という漠然とした目的だけでなく、より具体的に課題を洗い出すことが重要です。まずは、人事領域ごとに現状の課題を整理し、優先順位をつけましょう。
| 人事領域 | 課題の例 | 対応するHRテックの分野 |
|---|---|---|
| 採用 | 応募者情報の管理が煩雑でExcelの限界を感じる。選考プロセスに時間がかかり、候補者を逃してしまう。 | 採用管理システム(ATS) |
| 労務 | 毎月の勤怠締めや給与計算に多くの工数がかかっている。紙ベースの申請・承認フローを電子化したい。 | 勤怠管理システム、給与計算ソフト、労務管理システム |
| 評価・育成 | 評価基準が曖昧で、評価者によってばらつきがある。社員のスキルや経験を可視化し、戦略的な配置に活かしたい。 | 人事評価システム、タレントマネジメントシステム |
| 組織改善 | 従業員のエンゲージメントが低い。離職率の高さが課題になっている。ハラスメントなどの問題を早期に発見したい。 | エンゲージメントサーベイツール、組織診断ツール |
すべての課題を一度に解決しようとせず、最も緊急性が高く、解決した際のインパクトが大きい課題から着手することが、導入を成功させるためのポイントです。
操作性とサポート体制を確認する
HRテックサービスは、人事担当者だけでなく、多くの一般社員や管理職も利用するものです。そのため、誰にとっても使いやすいこと、そして困ったときにすぐに助けが得られる体制が整っていることが、定着の鍵となります。
直感的に使えるUI/UXか
多機能であっても、操作が複雑で分かりにくいシステムは敬遠されがちです。マニュアルを熟読しなくても直感的に操作できるような、シンプルで分かりやすい画面デザイン(UI/UX)であることが重要です。無料トライアルやデモ画面を積極的に活用し、実際にシステムを利用する複数の立場の従業員(人事担当者、管理職、一般社員)で操作感を試すことを強く推奨します。その際、PCだけでなくスマートフォンやタブレットからの見やすさや操作性も確認しておくと良いでしょう。
- マニュアルを見なくても、基本的な操作ができるか
- 画面の表示速度やページの切り替えはスムーズか
- 入力フォームは分かりやすく、ストレスなく入力できるか
- モバイル端末でも快適に利用できるか
導入時・導入後のサポートは手厚いか
新しいシステムの導入には、初期設定やデータ移行、社内への周知など、多くのハードルが伴います。また、運用開始後も不明点やトラブルが発生することは避けられません。そのため、ベンダーのサポート体制が充実しているかは非常に重要な選定基準です。導入前の相談から導入時の設定支援、運用開始後のフォローまで、一貫したサポートを提供してくれるベンダーを選びましょう。
- サポート窓口:電話、メール、チャットなど、問い合わせ方法が複数用意されているか。
- 対応時間:自社の業務時間内に対応してもらえるか(平日日中のみ、24時間365日など)。
- サポート内容:導入時の初期設定代行や、操作説明会の実施といったオンボーディング支援はあるか。
- ナレッジベース:FAQやオンラインマニュアル、活用方法のコラムなどが充実しているか。
特に、頻繁な法改正が伴う労務管理や給与計算の領域では、迅速かつ正確なアップデートと、それに関するサポート体制の質がサービスの価値を大きく左右します。
セキュリティ対策は万全かチェックする
HRテックサービスは、氏名、住所、給与、評価といった従業員の極めて機密性の高い個人情報を扱います。万が一、情報漏洩が発生すれば、従業員からの信頼を失うだけでなく、企業の社会的信用も大きく損なわれ、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。そのため、セキュリティ対策は最も優先すべきチェック項目です。
サービス選定時には、以下の点を確認し、自社のセキュリティポリシーを満たしているかを慎重に判断してください。
- 通信の暗号化:すべての通信がSSL/TLSによって暗号化されているか。
- アクセス制限:IPアドレスによるアクセス制限や、役職に応じた権限設定が柔軟に行えるか。
- 不正ログイン対策:二段階認証やログインアラートなどの機能が備わっているか。
- データ管理体制:データのバックアップは適切に行われているか。国内の堅牢なデータセンターで管理されているか。
- 第三者認証の取得:客観的な信頼性の指標となる「プライバシーマーク」や「ISMS(ISO/IEC 27001)」認証などを取得しているか。
サービス提供企業のウェブサイトでセキュリティポリシーを公開しているか、また過去に重大なセキュリティインシデントが発生していないかも併せて確認しましょう。
既存システムとの連携性は十分か
HRテックを導入する際、すでに社内で利用している他のシステム(勤怠管理、給与計算、会計ソフトなど)と連携できるかは、業務効率を大きく左右するポイントです。システム間でデータが分断されていると、データの二重入力や転記作業が発生し、かえって業務が非効率になるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
例えば、「勤怠管理システムで集計した勤務データを、ボタン一つで給与計算ソフトに取り込める」「採用管理システムで内定承諾となった候補者の情報を、人事労務ソフトに自動で登録できる」といった連携が可能であれば、業務は劇的に効率化します。CSVファイルによるデータのインポート・エクスポート機能はもちろんのこと、よりシームレスな連携を実現するAPI連携に対応しているかを確認しましょう。将来的なシステムの拡張も見据え、連携の柔軟性が高いサービスを選ぶことが賢明です。
費用対効果(コスト)は見合っているか
サービスの導入・運用にかかるコストも重要な選定基準です。ただし、単純に価格の安さだけで選ぶのは危険です。重要なのは、支払うコストに対して、どれだけの効果(業務工数の削減、生産性の向上、離職率の低下など)が得られるかという「費用対効果」の視点です。
HRテックの料金体系は、主に以下のパターンがあります。
- 月額固定制:従業員数に関わらず、月々の料金が一定のプラン。
- 従量課金制:利用する従業員数(ID数)やデータの量に応じて料金が変動するプラン。
- 初期費用+月額費用:導入時に初期設定費用などが発生し、それに加えて月額利用料がかかるプラン。
自社の従業員規模や利用頻度に合わせて最適な料金体系を選びましょう。また、基本料金に含まれる機能の範囲と、追加料金が必要なオプション機能を事前にしっかり確認することが大切です。「安価だと思ったら、必要な機能がほとんどオプションだった」という事態を避けるため、複数のサービスから見積もりを取り、機能と価格を詳細に比較検討することをおすすめします。
まとめ
本記事では、HRテックの概要から具体的な活用方法、サービスの選び方までを解説しました。少子高齢化による人材不足が深刻化する中、HRテックは単なる業務効率化ツールにとどまりません。定型業務を自動化することで、人事担当者が従業員エンゲージメントの向上や戦略的な人材配置といった、より付加価値の高い業務に注力できる環境を実現します。
まずは自社の人事課題を明確にし、最適なサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。