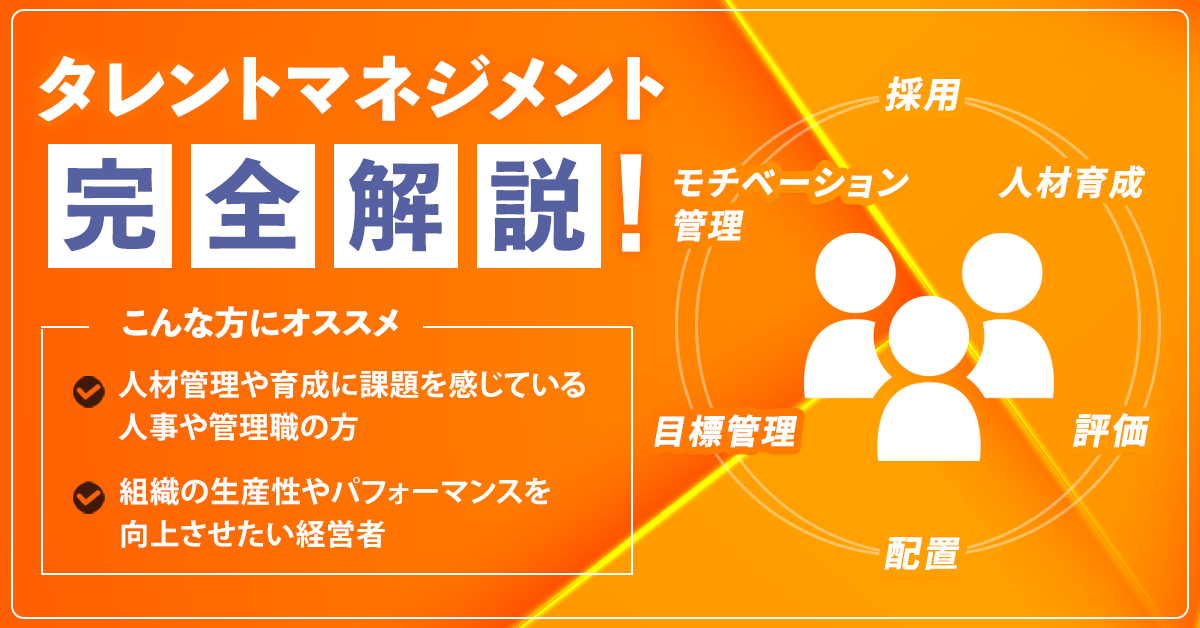近接性バイアスとは

近年、働き方の多様化が進む中で「近接性バイアス(Proximity Bias)」という言葉が注目を集めています。これは、無意識のうちに職場での不公平感を生み出し、チームの生産性や従業員のエンゲージメントを低下させる可能性がある、非常に重要な課題です。特に、オフィス勤務者とリモートワーカーが混在するハイブリッドワーク環境では、このバイアスが顕在化しやすくなります。
この章では、まず近接性バイアスの基本的な意味と、なぜ今これほどまでに注目されているのか、その背景をわかりやすく解説します。
近接性バイアスの基本的な意味
近接性バイアスとは、物理的に距離が近い人や、頻繁に顔を合わせる人を、無意識のうちに高く評価したり、好意的に扱ったりしてしまう心理的な偏りのことです。英語では「Proximity Bias」と呼ばれます。
これは、人間の脳が情報を処理する際の癖である「認知バイアス」の一種です。私たちは日々、膨大な情報を処理するために、無意識に物事を単純化したり、特定のパターンに当てはめたりする傾向があります。近接性バイアスもその一つで、決して悪意があって生まれるものではありません。しかし、この無意識の偏りが、職場において特に人事評価や業務の割り振り、コミュニケーションの質に大きな影響を与え、意図しない不公平を生む原因となります。
例えば、「すぐ近くの席にいる部下の方が、リモートで働く部下よりも頑張っているように見える」「オフィスで雑談する機会が多いメンバーの意見を、つい重視してしまう」といった状況は、まさに近接性バイアスが働いている典型例です。このバイアスは、他の心理効果とも密接に関連しています。
| 関連する心理効果・バイアス | 概要 |
|---|---|
| 単純接触効果(ザイオンス効果) | 特定の対象と繰り返し接することで、その対象に対する好感度や評価が高まる心理効果。近くにいる人と頻繁に会うことで、自然と親近感が湧きやすくなります。 |
| イングループ・アウトグループバイアス | 自分が所属する集団(イングループ)のメンバーを、それ以外の集団(アウトグループ)のメンバーよりもひいき目で見てしまう心理的な偏り。「オフィス出社組」と「リモートワーク組」という無意識のグループ分けが、このバイアスを助長することがあります。 |
これらの心理的な働きが複合的に作用することで、近接性バイアスはより強固なものとなり、組織内に根深い問題を引き起こす可能性があるのです。
ハイブリッドワークの普及で注目される背景
近接性バイアスという概念自体は以前から存在していましたが、なぜ今、これほどまでに多くの企業で問題視されるようになったのでしょうか。その最大の理由は、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、ハイブリッドワークという働き方が急速に普及・定着したことにあります。
かつて多くの企業では、従業員のほとんどが毎日同じオフィスに出社して働くのが当たり前でした。この環境下でも、マネージャーの席に近い従業員が優遇されるといった形の近接性バイアスは存在していました。しかし、全員が同じ空間にいたため、その差は比較的小さなものにとどまっていました。
しかし、リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークが主流となったことで、状況は一変します。従業員が「オフィスで働く人」と「自宅や遠隔地で働く人」に物理的に分断されるようになったのです。この分断こそが、近接性バイアスが深刻な問題として顕在化する大きな要因です。
具体的には、マネージャーやリーダーは、目の前にいるオフィス勤務者の働きぶりや努力、困っている様子を直接見ることができます。一方で、リモートワーカーの状況は、チャットの文字やウェブ会議の画面といった限られた情報から推測するしかありません。この情報量の圧倒的な差が、無意識のうちに「近くにいる部下は信頼できる」「リモートの部下は何をしているかわからない」といった評価の偏りを生み出します。結果として、リモートワーカーが正当な評価を受けられなかったり、重要なプロジェクトから外されたり、キャリア形成の機会を失ったりするリスクが高まります。
このような不公平感は、従業員のモチベーションやエンゲージメントを著しく低下させるだけでなく、優秀な人材の離職にもつながりかねません。そのため、近接性バイアスへの対策は、多様な働き方を推進する現代の組織にとって、公平性を担保し、持続的に成長していくための重要な経営課題として認識されるようになっているのです。
近接性バイアスが起こる主な3つの原因

近接性バイアスは、特定の誰かが悪いわけではなく、人間の心理的な特性や環境が組み合わさることで自然に発生してしまいます。なぜこのバイアスが生まれてしまうのか、その背景にある主な3つの原因を詳しく見ていきましょう。
単純接触効果(ザイオンス効果)による親近感
私たちの脳は、繰り返し接触するものに対して、無意識に好意や親近感を抱きやすい性質を持っています。これは心理学で「単純接触効果(ザイオンス効果)」と呼ばれる現象です。
職場の環境に置き換えて考えてみましょう。オフィスに出社しているメンバーは、上司や同僚と毎日顔を合わせます。朝の挨拶、エレベーターでの短い会話、ランチタイムの雑談、休憩中のやり取りなど、業務とは直接関係のない偶発的なコミュニケーションが頻繁に発生します。この接触回数の多さが、知らず知らずのうちに「よく知っている身近な存在」という認識を強め、信頼感や安心感につながっていくのです。
一方で、リモートワーク中心のメンバーは、意図的に設定された会議やチャット以外で接触する機会がほとんどありません。そのため、単純接触効果が働きにくく、オフィス勤務のメンバーに比べて心理的な距離が生まれやすくなります。能力や成果が同じであっても、マネージャーは「いつも顔を合わせる部下」の方を、無意識に「親しみやすく、連携しやすい」と感じてしまう傾向があるのです。
無意識に生まれる思い込みや先入観
近接性バイアスは、「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」の一種でもあります。私たちは、自分でも気づかないうちに「目の前にいる人は頑張っている」「見えない場所にいる人は何をしているかわからない」といった思い込みや先入観を持ってしまうことがあります。
例えば、マネージャーがオフィスで遅くまで残業している部下の姿を見れば、「熱心に仕事に取り組んでいるな」とポジティブに評価しがちです。しかし、リモートワーカーが同じように家庭で遅くまで働いていたとしても、その努力は可視化されにくいため、評価に結びつかない可能性があります。むしろ、「ちゃんと集中できているだろうか」といったネガティブな憶測を呼んでしまうことさえあります。
このように、「見える努力」と「見えない努力」の間に評価のギャップが生まれてしまうのが、この原因の大きな問題点です。以下の表は、勤務形態によってマネージャーが抱きがちな思い込みの例をまとめたものです。
| 勤務形態 | マネージャーが抱きがちな無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の例 |
|---|---|
| オフィス勤務者 |
|
| リモートワーカー |
|
コミュニケーション量の差がもたらす情報格差
物理的な距離は、コミュニケーションの質と量に直接的な影響を及ぼし、深刻な情報格差を生む原因となります。
オフィス環境では、会議室で行われるフォーマルな情報共有だけでなく、廊下での立ち話や給湯室での雑談といったインフォーマル(非公式)なコミュニケーションが頻繁に発生します。こうした偶発的な会話の中から、プロジェクトの重要なヒントや背景情報、他部署の動向、新しいアイデアの種などが共有されることは少なくありません。
オフィスに出社しているメンバーは、こうした情報のシャワーを自然に浴びることができます。しかし、リモートワーカーは、チャットやWeb会議といった決められた場以外で情報を得る機会が極端に少なくなります。その結果、重要な意思決定の背景にある文脈やニュアンスが伝わらなかったり、プロジェクトに関する最新の状況を知らないまま業務を進めてしまったりする事態が起こり得ます。この情報格差が、リモートワーカーの疎外感を深め、キャリアアップの機会損失につながることもあるため、組織にとって非常に大きなリスクとなります。
職場で見られる近接性バイアスの具体例とデメリット

近接性バイアスは、単なる心理的な傾向にとどまらず、職場のさまざまな場面で具体的な問題として現れます。特にハイブリッドワークが浸透した現代の組織では、その影響は深刻です。ここでは、オフィスで起こりがちな具体例を挙げながら、それらがもたらす重大なデメリットについて詳しく解説します。
人事評価における不公平感の増大
近接性バイアスが最も深刻な影響を及ぼすのが人事評価です。評価者であるマネージャーが、無意識のうちに身近な部下を高く評価してしまうことで、従業員間に大きな不公平感を生み出します。これは従業員のキャリアに直接的なダメージを与え、組織全体の士気を低下させる要因となり得ます。
昇進や重要なプロジェクトへの抜擢機会の偏り
マネージャーの目に触れる機会が多いオフィス出社者は、日々の頑張りや人柄が伝わりやすいものです。廊下での立ち話や雑談の中から「そういえば、新しいプロジェクトのリーダーを探しているんだ」といった重要な情報が共有され、その場で「彼に任せてみよう」と抜擢されるケースは少なくありません。
一方で、リモートワーカーは質の高い成果を上げていても、そのプロセスや努力が可視化されにくいため、存在感が薄れがちです。結果として、能力や実績とは無関係に、オフィスにいるというだけで昇進やキャリアアップの機会が偏ってしまうのです。これは優秀なリモートワーカーのモチベーションを著しく削ぎ、キャリアの停滞を招くだけでなく、最終的には貴重な人材の流出につながる大きなリスクをはらんでいます。
フィードバックの質と量の低下
部下の成長を促す上で不可欠なフィードバックにも、近接性バイアスは影を落とします。オフィスにいれば、マネージャーは部下の様子を見て「少し悩んでいるな」と察し、「あの件、ちょっといい?」と気軽に声をかけて、タイムリーなアドバイスを送ることができます。このような日常的なやり取りの中で行われる質の高いフィードバックは、部下の成長に大きく貢献します。
しかし、相手がリモートワーカーの場合、わざわざチャットで連絡を取り、オンライン会議を設定するといった手間がかかります。そのため、フィードバックはどうしても形式的になり、頻度も減少しがちです。結果としてリモートワーカーは成長の機会を奪われ、スキルアップが遅れてしまう可能性があります。また、ポジティブなフィードバックが減ることで承認欲求が満たされず、仕事へのエンゲージメントが低下する一因にもなります。
リモートワーカーの孤立とエンゲージメント低下
物理的な距離は、心理的な距離を生み出します。オフィスでは、業務の合間の雑談やランチ、コーヒーブレイクといったインフォーマルなコミュニケーションが自然に発生し、これが人間関係の潤滑油となり、チームの一体感を育みます。
リモートワーカーは、こうした偶発的なコミュニケーションから疎外されがちです。オンライン会議が終わればすぐに一人になり、同僚たちがオフィスで盛り上がっている様子を想像して、孤独感を深めることもあります。また、重要な情報がオフィスでの口頭ベースで共有され、後からチャットで断片的に知らされるといった情報格差も、疎外感を助長します。このような孤独感や疎外感は、従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、会社への帰属意識や仕事への熱意(エンゲージメント)を著しく低下させる危険なサインです。
チームの一体感喪失と生産性の悪化
近接性バイアスは、個人間の問題にとどまらず、チーム全体を蝕んでいきます。無意識のうちに「オフィス組」と「リモート組」という見えない分断が生まれ、チーム内に心理的な壁ができてしまうのです。
例えば、重要な意思決定がオフィスにいるメンバーだけで行われ、リモートワーカーは決定事項を知らされるだけ、といった状況が頻発するとどうなるでしょうか。リモートワーカーは「自分はチームの一員として尊重されていない」と感じ、次第に会議で発言しなくなったり、主体的な提案を控えたりするようになります。こうした状況の違いを以下の表にまとめました。
| オフィスワーカー(出社者) | リモートワーカー | |
|---|---|---|
| 情報アクセス | 偶発的な会話から最新情報を得やすい | 意図的に共有されない限り情報から取り残されやすい |
| 意思決定への関与 | 非公式な場で意見を求められ、議論に参加しやすい | 議論のプロセスから外れ、結果のみを知らされがち |
| 心理的状態 | チームの一員であるという連帯感を持ちやすい | 疎外感や孤独感を感じやすく、帰属意識が低下しやすい |
このように、チーム内に生まれた亀裂は、円滑な情報共有や率直な意見交換を妨げ、イノベーションの芽を摘んでしまいます。多様な視点が失われ、同質的な意見ばかりが採用されるようになると、組織は硬直化します。結果として、チーム全体のパフォーマンスは低下し、生産性の悪化という深刻な事態を招くことになるのです。
近接性バイアスを解消するマネジメント術5選

近接性バイアスは無意識のうちに生じるため、完全に排除することは困難です。しかし、マネージャーが意識的に対策を講じることで、その影響を最小限に抑え、チーム内の不公平感をなくすことは可能です。ここでは、ハイブリッドワーク環境でも公平で生産性の高いチームを作るための具体的なマネジメント術を5つご紹介します。
評価基準を明確化しプロセスを透明にする
近接性バイアスによる評価の歪みをなくすためには、主観的な印象ではなく、客観的な事実とデータに基づいて評価する仕組みを構築することが最も重要です。誰が、いつ、何を基準に評価されるのかを明確にし、全員が納得できる環境を整えましょう。
具体的な方法としては、OKR(Objectives and Key Results)やMBO(Management by Objectives)といった目標管理制度を活用することが有効です。評価項目を「チームへの貢献度」のような曖昧なものではなく、「新規契約獲得数◯件」「プロジェクトの納期遵守率◯%」といった、誰が見ても判断できる定量的・定性的な指標に落とし込みます。そして、その評価プロセス自体を全メンバーに公開し、透明性を確保することで、オフィス勤務かリモートワークかに関わらず、公平な評価が実現します。
コミュニケーションの機会を意図的に設計する
オフィスでの「ちょっとした雑談」や「廊下での立ち話」から生まれる偶発的なコミュニケーションは、リモートワーカーにはありません。この差を埋めるためには、偶然に頼るのではなく、マネージャーが意図的にコミュニケーションの機会を創出することが鍵となります。物理的な距離を感じさせないための工夫が求められます。
定期的な1on1ミーティングの実施
オフィス勤務者、リモートワーカーを問わず、すべてのチームメンバーと「同じ頻度」「同じ時間」で定期的な1on1ミーティングを実施しましょう。業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みやプライベートな雑談など、心理的安全性を確保しながら対話できる場とすることが重要です。ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsなどのオンライン会議ツールを活用すれば、場所に関係なく質の高いコミュニケーションが可能です。
オンラインでの雑談や交流の場を設ける
業務外のコミュニケーションを活性化させることも、チームの一体感を醸成する上で欠かせません。SlackやTeamsに雑談専用のチャンネル(例:「#zatsudan」「#hobby」など)を作成したり、oViceやGatherのようなバーチャルオフィスツールを導入して、気軽に話しかけられる仮想空間を作るのも一つの手です。また、定期的にオンラインランチ会やバーチャルコーヒーブレイクの時間を設けるなど、意識的にインフォーマルな交流の場を設計しましょう。
情報共有のルールを徹底し格差をなくす
「オフィスにいる人だけが重要な情報を知っている」という状況は、リモートワーカーの孤立感や不公平感を増大させる最大の原因です。「その場にいた人だけが知っている」という状況を徹底的に排除し、情報の非対称性をなくすことが不可欠です。
そのためには、情報共有のルールを明確に定め、チーム全体で徹底する必要があります。例えば、会議の議事録は必ず作成し、NotionやConfluenceといった情報共有ツールに保管して誰もが閲覧できるようにします。口頭での決定事項やオフィスでの立ち話で決まった重要な内容も、必ずチャットツールなどでテキスト化して共有する文化を根付かせましょう。
| 項目 | 悪い例(バイアスを助長) | 良い例(バイアスを解消) |
|---|---|---|
| 意思決定 | オフィスでの立ち話や、その場にいたメンバーだけで物事を決めてしまう。 | 決定事項は必ずチャットツールや共有ドキュメントに記録し、全メンバーに共有する。 |
| 会議の議事録 | 作成しない、もしくは一部のメンバーにしか共有されない。 | 担当者を決め、必ず議事録を作成。全員がアクセスできる場所に保管する。 |
| ちょっとした相談 | 近くの席のメンバーにだけ口頭で相談し、その場で解決する。 | オープンなチャットチャンネルで相談し、他のメンバーの意見も聞けるようにする。 |
成果物(アウトプット)で判断する文化を醸成する
「夜遅くまでオフィスで働いているから熱心だ」「すぐに応答してくれるから仕事が速い」といった、働く場所や時間、プロセスに基づいた評価は、近接性バイアスや、それに類似したプレゼンス・バイアス(姿が見えることを高く評価する傾向)を助長します。これを防ぐためには、「どこで、どれだけ働いたか」ではなく、「何を生み出したか」で評価する文化への転換が求められます。
各メンバーの役割と責任、そして期待される成果物(アウトプット)を明確に定義しましょう。評価は、その成果物の質や量、設定した目標の達成度に基づいて行います。これにより、リモートワーカーもオフィスワーカーも、純粋な貢献度によって公平に評価されるようになり、各自が最も生産性の高い働き方を選択しやすくなります。
マネージャー自身がバイアスを自覚し意識を変える
これまで挙げてきた4つの対策は、すべてマネージャー自身の意識が土台となって初めて機能します。すべての施策の成功の鍵を握るのが、マネージャー自身のバイアスへの気づきと意識改革です。
人間は誰しも、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を持っています。まずは、自分自身にも近接性バイアスが存在する可能性を認識することが第一歩です。その上で、定期的に自分の行動を振り返ってみましょう。「最近、特定のメンバーとばかり話していないか?」「重要な仕事をついオフィスにいるメンバーに任せていないか?」など、セルフチェックする習慣が大切です。また、リモートワーカーの働きぶりや貢献は目に見えにくいからこそ、積極的に状況をヒアリングし、見えない部分を想像する努力がマネージャーには求められます。「デフォルトをリモート」に考え、会議は原則オンラインで設定するなど、リモートワーカーが不利にならない環境を意識的に作る姿勢が、チーム全体の信頼関係を築きます。
まとめ
本記事では、物理的な距離が近い人を高く評価してしまう「近接性バイアス」について解説しました。ハイブリッドワークが普及する現代において、このバイアスは人事評価の不公平感やリモートワーカーの孤立を招き、チーム全体の生産性を低下させる原因となります。
この問題を解消するには、マネージャー自身がバイアスを自覚することが第一歩です。その上で、評価基準の明確化や意図的なコミュニケーション設計、成果で判断する文化を醸成し、全従業員が公平に活躍できる環境を構築することが不可欠です。