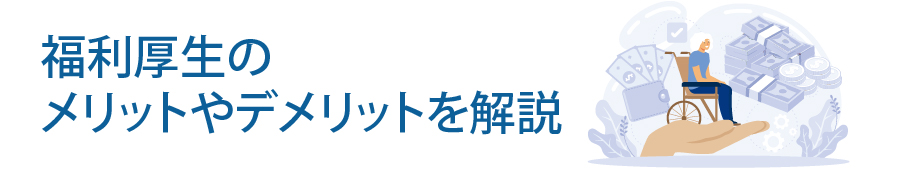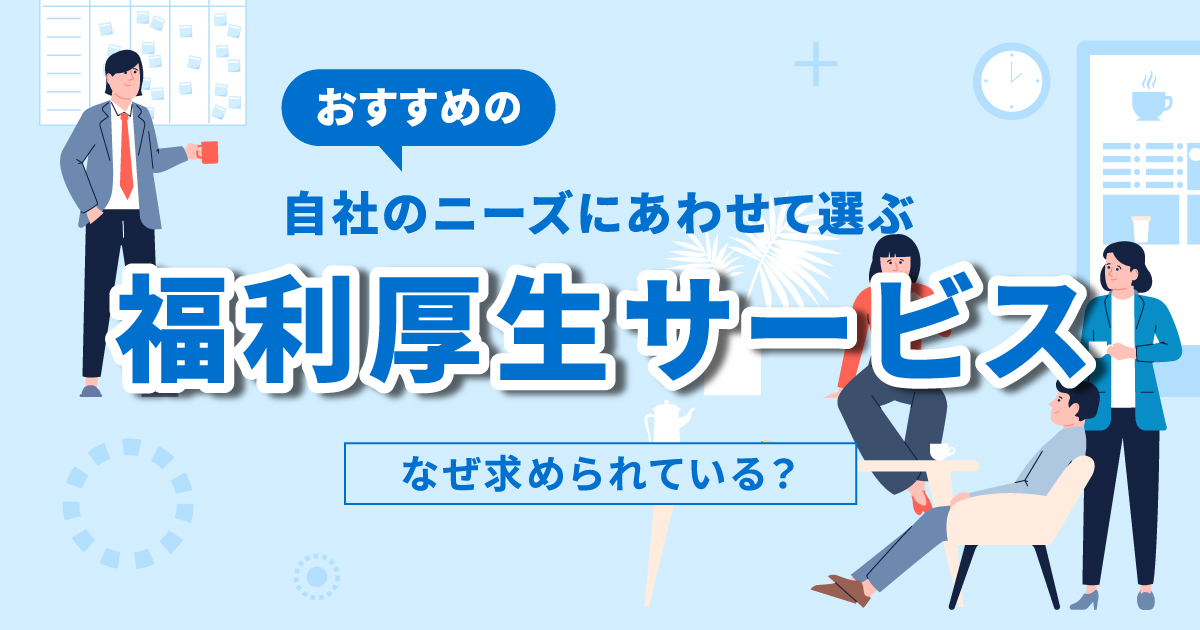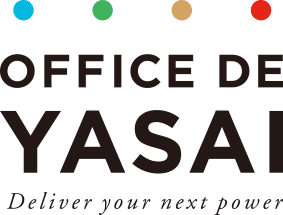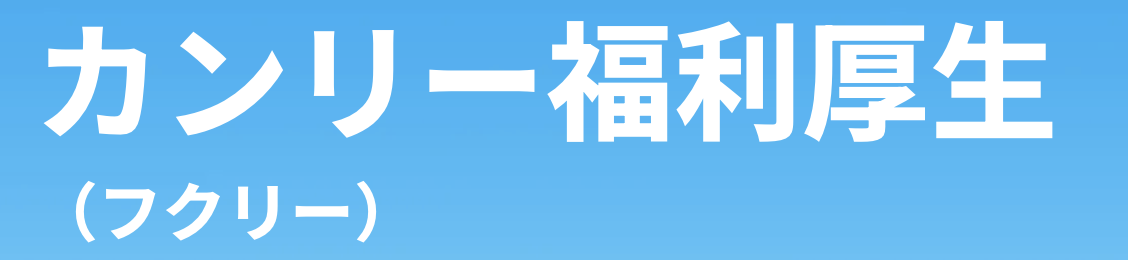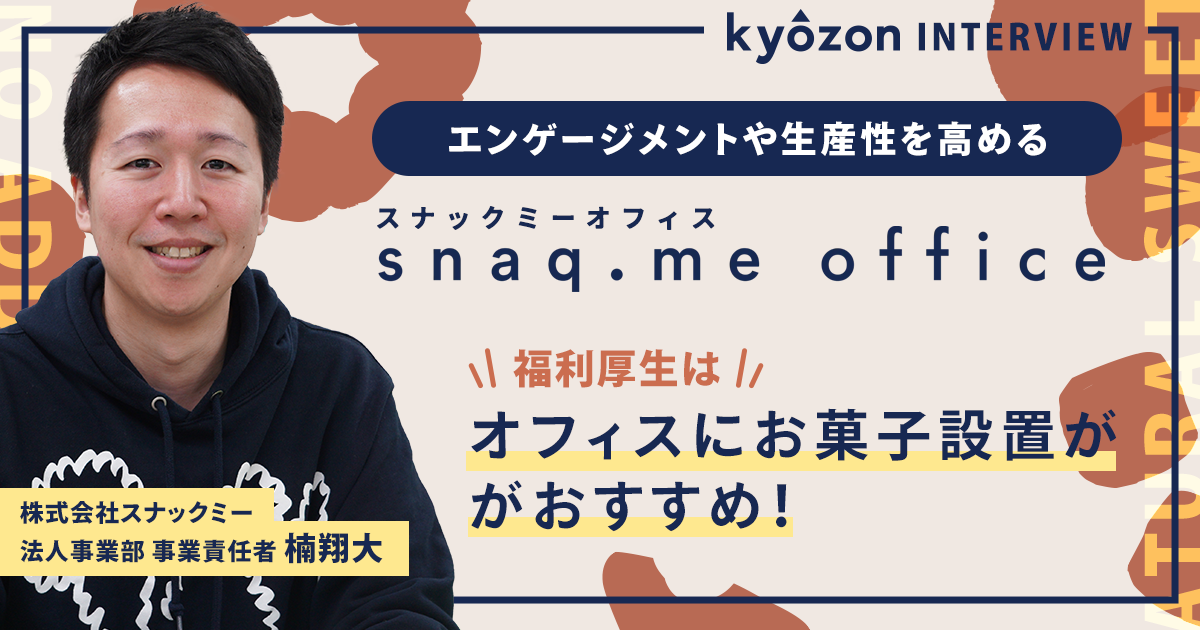福利厚生を導入する目的
福利厚生を導入する最大の目的は、従業員がより働きやすい環境を整えることです。
福利厚生とは、従業員が受け取れる賃金以外の報酬・サービスのことです。基本的に福利厚生は全従業員を対象にしていますが、全員が平等に利用できるもの(社会保険、社員食堂、クラブ活動など)と特定の条件を満たさないと利用できないもの(育児手当、住居手当など)に分けられます。
会社が従業員やその家族を経済面や健康面、精神面などから支えることで、より働きやすくなり、人材を確保しやすくなったり生産性を高めたりできます。
福利厚生を導入する6つのメリット
福利厚生を導入することで得られるメリットには以下の6つがあります。
- 採用活動に効果をもたらす可能性がある
- 従業員の健康維持・促進につながる
- 従業員の満足度や定着率などのエンゲージメントが上がる
- 生産性が高まる
- 社会における信頼性が高くなる
- 法人税を節税できる
採用活動に効果をもたらす可能性がある
福利厚生は、今や会社を選ぶ際の基準の1つになっています。福利厚生の充実している企業で働きたいと考える人が少なくありません。そのため、福利厚生を充実させることで優秀な人材が集まりやすくなる可能性があります。
ただし、選考回数を増やしたり基準を見直したりして、自社に合った人材を見極めて採用するようにしなければいけませんので注意しましょう。
従業員の健康維持・促進につながる
保険の加入や定期健診の案内など、従業員の健康にかかわる福利厚生もあり、こういった制度は従業員の健康維持・促進に役立ちます。
福利厚生には法律で導入が義務付けられている「法定福利厚生」と、取り決めのない「法定外福利厚生」があり、社会保険への加入や健康診断の実施は法定福利厚生に含まれています。
この制度があるため、自分で健康を管理するのが苦手な従業員も安心して働けるのです。
従業員の満足度や定着率などのエンゲージメントが上がる
福利厚生が充実していると、採用活動が行いやすくなるだけではなく、すでに勤務している従業員の満足度や定着率も高まります。
これは、研修や教育にかかるコストが減ったり、職場の人間関係が良くなったりすることにもつながります。
生産性が高まる
福利厚生を含む複数の要素で測られる従業員満足度(ES)と業績の間には、比例関係があります。厚生労働省が出している資料によると、以下の傾向があるそうです。
「従業員と顧客満足度の両方を重視する」という経営方針を持つ企業は、 「顧客満足度のみを重視する」という企業と比べ、売上高営業利益率、売上高 ともに「増加傾向にある」とする割合が高くなっています。
引用:厚生労働省
すなわち、福利厚生を充実させ、従業員の労働環境を整えることで営業利益や売上が上がる可能性がある、ということです。
社会における信頼性が高くなる
福利厚生が充実していることを公表すると、社会における信頼性が高くなり、営業活動が進めやすくなる、という利点もあります。逆に、全く導入していない状態では「従業員を大切にしていない会社」というレッテルを貼られてしまう可能性もあります。
福利厚生の導入を検討しているのであれば、早期に導入することをおすすめします。
法人税を節税できる
法人税は売上にかかるわけではなく、売上から原価や経費を差し引いた所得にかかります。そのため、同じ売上であっても、経費が増えれば払う税金は少なくなります。
福利厚生には費用が掛かりますが、その費用は経費として扱えます。つまり、福利厚生を充実させると、法人税を節税できるのです。
福利厚生の4つのデメリット
残念ながら、福利厚生はメリットばかりではありません。次は、福利厚生を導入するデメリットについて解説します。
- 費用がかかる
- 導入や管理に手間がかかる
- 全員を満足させることはできない
- 一度導入すると廃止しづらい
費用がかかる
福利厚生をどんなものにするにしても、内容の決定や周知、利用促進などのためには少なからずお金がかかってしまいます。特に、お金にあまり余裕のない企業は、社員食堂やレジャー施設の設置、住宅手当など、直接お金のかかる福利厚生は導入しにくいでしょう。
導入したくても、できるものが限られてしまうというのも現実もあります。そのため、できるだけお金のかからない施策を考えるなどの工夫が必要です。
導入や管理に手間がかかる
どのような内容の福利厚生であっても、導入や管理には手間がかかります。ほとんどの場合、導入して終わりではなく長期間にわたって運用していくことが必要になります。
誰が運用を担当するのか、その費用の予算はどこから、いくら捻出するのかなどをあらかじめ決めておきましょう。導入して赤字になってから慌てて考えることのないよう注意しなくてはなりません。
全員を満足させることはできない
どんなに福利厚生を充実させても、残念ながら全ての従業員を満足させることはできません。育児手当制度を作っても子どものいない従業員には関係がなく、社員食堂を作ってもさまざまな事情で利用しにくい従業員も出てくるでしょう。
どの制度も利用しない人から不満が出ることが想定されます。利用者には満足してもらいながら、利用しない人から不満が出ないようなバランスを考慮して制度を作る必要があります。
一度導入すると廃止しづらい
導入はしてみたものの、利用者が少なかったりコストがかかりすぎてしまったりして、制度を廃止したい状況になることも想定できます。しかし、一度導入し、周知してしまった制度は簡単には廃止しにくいです。
特に利用者がいる制度の場合、利用者にとってはその制度は必要なものであり、急に廃止するといわれても他の解決策がなければ困ってしまう可能性もあります。
内容の変更やそのための一時的な停止であれば、良いかもしれませんが、完全な廃止となると、利用者から不満が出てしまうかもしれません。廃止を検討する場合は、あらかじめ利用者と相談して、他の解決策などを提示したうえで決めた方が良いでしょう。
独自・ユニークな福利厚生の事例5選
福利厚生は法律で決まっているものだけではなく、各企業が独自に作り出せるものです。
そのため、ユニークなものや意義のあるものなど、企業の特色が出ます。それぞれの企業が独自の福利厚生を出していますが、ここではその中から参考にしやすそうなものを5つ厳選しました。
ドキュサイン・ジャパン株式会社
ドキュサイン・ジャパンは、シェア率世界ナンバーワンの電子署名のクラウドサービス『DocuSign(ドキュサイン)』を提供するドキュサイン社の日本法人。外資系企業ということで、アメリカ本社ではオーガニックスナックやフルーツなどが豊富に提供されています。
日本でも米国と同じような福利厚生を提供したいという想いで、ドキュサイン・ジャパンでは『snaq.me office (スナックミーオフィス)』の置き菓子を長年利用しています。無添加&ユニークなヘルシーおやつが社内休憩スペースに設置され、従業員はそれを小腹が減った時などに自由に食べていいという仕組み。健康促進と聞くと運動や厳しい食事制限などを想起しますが、日々食べるお菓子から少しずつヘルシーなものにしていくというのは、従業員にとってもポジティブに取り組みやすいヘルスケア施策ですね。
健康経営につながるヘルシーお菓子の福利厚生 snaq.me office (スナックミーオフィス)
株式会社中西製作所
学校や病院などの厨房で使う機器を製造・販売している中西製作所は、特に出産や育児に関する福利厚生が充実しています。
例えば、従業員の子どもが小・中学校に入学したときに、子ども1人につき1万円の祝い金を支給する制度や、給食費の補助を出す制度などがあります。同社の、給食費を支給する福利厚生は、日本企業で初めての試みでした。
このように、育児にかかるお金を企業がサポートするというのは従業員にとってわかりやすいメリットであるため、ある程度の利用率も見込めるでしょう。
Chatwork株式会社
Chatwork株式会社では、ゴールデンウィークや年末年始など、従業員が実家に帰省する際に費用を支給する「ゴーホーム制度」があります。1人につき14,000円、配偶者がいる場合にはさらに14,000円が支給されます。
またゴーホーム制度以外にも、海外旅行を支援する「ゴーグローバル制度」や誕生日に食事代を支給するバースデー制度などがあります。いずれの制度も、従業員やその家族を大切にし、従業員の成長を信じているからこそ実施されているといえるでしょう。
株式会社Eyes, JAPAN
株式会社Eyes, JAPANはシステム開発やセキュリティなど、ITに関する仕事をしている企業です。
休憩時に昼寝を認めるシエスタ制度や、本格的なコーヒーを自由に飲めるフリーカフェイン制度など、効率や生産性にこだわるIT企業ならではの福利厚生が充実しています。
このように、自社の業界やジャンルに合わせた福利厚生も探してみると良いでしょう。
株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
多くの企業が社員の”遊びや楽しみ”に福利厚生予算の多くをかけているが、利用率はどこも20%程度。
その一部をマネソル+に振り分けたところ、生産性とエンゲージメントが向上する結果に。
マネソル+は、AIと独立系FPの支援により従業員のライフプランの可視化や金融教育をサポートするため、
従業員がお金の不安から解消され、安心して仕事に従事するようになり、経済に対する関心度が高まり、仕事に活かすようになります。
エンゲージメントと生産性が上がる福利厚生サービスマネソル+(プラス)
まとめ
福利厚生は従業員の生活をサポートする、従業員のためのものです。そのため、役員や人事部だけで考えるのではなく、全従業員の意見を聞くことが大切です。全てを取り入れることはできませんが「こういう考え方の人もいる」「こんなニーズもある」ということを把握しておくだけでも違います。
また、せっかく導入するのであれば、多くの人に利用してもらいたいものです。導入後はぜひ、周知・利用促進することも忘れないようにしましょう。