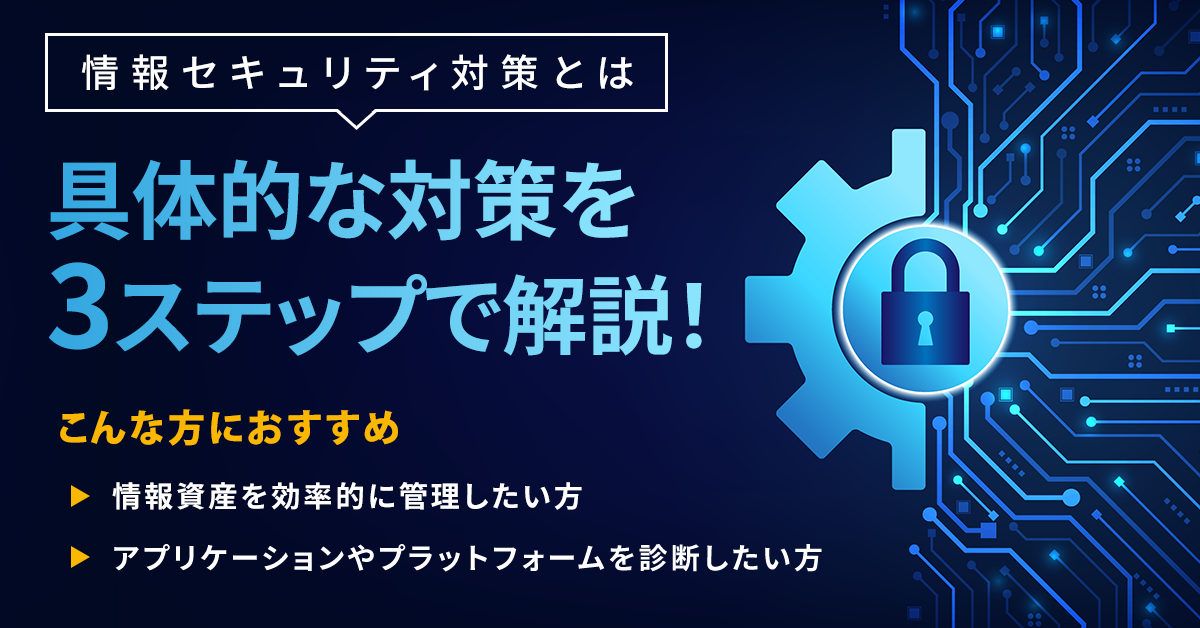サイバー保険に入らない場合の3つの経営リスク

サイバー攻撃はもはや大企業だけの問題ではありません。むしろ、セキュリティ対策が手薄になりがちな中小企業こそ、攻撃者の格好の標的となっています。万が一サイバーインシデントが発生した場合、サイバー保険に未加入であることは、企業の存続を揺るがしかねない深刻な経営リスクに直結します。
ここでは、保険に入らないことで直面する具体的な3つのリスクを解説します。
莫大な損害賠償と事故対応費用
サイバー攻撃の被害に遭った場合、企業の負担は攻撃による直接的なダメージだけにとどまりません。情報漏洩などが発生すれば、顧客や取引先に対する損害賠償責任に加え、事故の収束に向けた様々な対応費用が発生し、その総額は数千万円から数億円に上ることも珍しくありません。
特に2022年4月に施行された改正個人情報保護法では、法人に対する罰金が最大1億円に引き上げられるなど、企業の法的責任はますます重くなっています。保険未加入の場合、これらの費用をすべて自己資金で賄う必要があり、企業の財務状況に壊滅的な打撃を与える可能性があります。
具体的にどのような費用が発生するのか、以下の表で確認してみましょう。
| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 損害賠償金 | 情報漏洩の被害者(顧客・取引先)への慰謝料や、取引先が被った事業中断損失などに対する賠償金。 | 漏洩した情報の種類や件数により、数千万円~数十億円規模になるケースも。 |
| 事故原因調査費用 | 外部の専門家(フォレンジック調査会社など)に依頼し、攻撃の侵入経路や被害範囲を特定するための費用。 | 数百万円~数千万円 |
| 復旧費用 | 破損したシステムやデータの復旧、セキュリティ強化、代替機器の購入などにかかる費用。 | 数百万円~数千万円以上 |
| コールセンター設置費用 | 被害者からの問い合わせに対応するための専用窓口の設置・運営費用。 | 数百万円~ |
| 見舞金・見舞品購入費用 | 被害者へのお詫びとして支払う見舞金や、商品券などの見舞品を購入する費用。 | 漏洩件数 × 単価(例: 500円~) |
| 弁護士・コンサルタント費用 | 法的な助言を求める弁護士費用や、広報対応などを依頼するPRコンサルタントへの費用。 | 数百万円~ |
事業停止による売上減少と機会損失
ランサムウェア攻撃などにより、基幹システムや生産管理システム、ECサイトなどが停止してしまうと、企業は事業活動そのものを中断せざるを得なくなります。事業が停止すれば、その間の売上はゼロになり、顧客からの注文も受けられず、深刻な機会損失が発生します。
特に、製造業で工場の生産ラインが停止した場合や、小売業でPOSシステムがダウンした場合には、1日あたりの損失額は莫大なものになります。復旧までの期間が長引けば長引くほど、損失は雪だるま式に膨れ上がり、資金繰りを圧迫します。
さらに、見過ごせないのが「サプライチェーン攻撃」のリスクです。自社が攻撃の踏み台にされ、取引先へ被害が拡大した場合、自社の事業停止だけでなく、取引先全体のサプライチェーンを麻痺させてしまう可能性があります。このような事態に陥れば、損害賠償問題に発展するだけでなく、重要な取引関係を失うことにもつながりかねません。
取引先や顧客からの信用失墜
サイバーインシデントがもたらす損害の中で、最も回復が難しいのが「信用の失墜」です。情報漏洩や事業停止といった事態はニュースやSNSを通じて瞬く間に拡散し、「セキュリティ管理が甘い企業」「顧客情報を守れない会社」というネガティブな評判(レピュテーションリスク)が定着してしまいます。
一度失った信用を取り戻すことは極めて困難であり、企業の存続そのものを脅かす無形の損害となります。顧客は個人情報の漏洩を恐れてサービスから離れ、長年付き合いのあった取引先からも契約を打ち切られる可能性があります。特に、セキュリティ基準の厳しい大手企業と取引している場合、インシデントをきっかけにサプライヤーから外されるケースは少なくありません。
このように、金銭的な損失は時間とともに回復できるかもしれませんが、ブランドイメージの毀損や顧客離れは、長期にわたって業績に暗い影を落とし続けるのです。
サイバー保険とは?補償内容をわかりやすく解説

サイバー保険とは、サイバー攻撃を受けた際に発生するさまざまな損害を補償するための専門的な保険です。不正アクセスやマルウェア感染、ランサムウェアによる被害、内部関係者による情報漏えいなど、企業を取り巻くサイバーリスクは年々深刻化しています。万が一、こうしたセキュリティインシデントが発生した場合、企業は損害賠償だけでなく、原因調査やシステムの復旧、事業停止による利益の損失など、多岐にわたる経済的負担を強いられます。サイバー保険は、これらの費用を包括的にカバーし、企業の経営を守るための重要なセーフティネットです。
特に、セキュリティ対策に十分なリソースを割くことが難しい中小企業にとって、サイバー攻撃は事業継続を揺るがす致命的な脅威となり得ます。サイバー保険に加入することで、金銭的な補償はもちろん、インシデント発生時の専門家によるサポートなどを受けられ、被害を最小限に抑えることが可能になります。
サイバー保険でカバーできる主な損害範囲
サイバー保険の補償内容は多岐にわたりますが、大きく分けると「第三者への損害賠償」「自社が負担する事故対応費用」「事業停止による自社の損失」の3つに分類できます。ここでは、それぞれの補償内容について具体的に見ていきましょう。
| 補償の分類 | 具体的な補償内容の例 |
|---|---|
| 損害賠償責任の補償 | 個人情報・法人情報の漏えいに対する損害賠償金、訴訟費用、人格権侵害(名誉毀損など)による賠償金など |
| 事故対応費用の補償 | 原因調査費用(フォレンジック調査)、システム復旧費用、コールセンター設置費用、見舞金・見舞品購入費用、コンサルティング費用など |
| 利益損失の補償 | サイバー攻撃により事業が停止した場合の逸失利益、事業を継続するために必要となった追加費用(営業継続費用)など |
損害賠償責任の補償
サイバー攻撃によって顧客情報や取引先の機密情報が漏えいした場合、企業は被害者に対して法的な賠償責任を負うことになります。この補償は、そうした第三者への損害賠償にかかる費用をカバーするものです。
例えば、ECサイトから顧客のクレジットカード情報が流出して不正利用された場合、顧客一人ひとりへの慰謝料や賠償金が発生します。また、取引先のシステムにマルウェアを感染させてしまい、相手の事業を停止させてしまった場合には、莫大な賠償請求を受ける可能性があります。こうした損害賠償は、企業の財務状況に深刻なダメージを与えるため、サイバー保険の中核となる補償の一つです。
その他、ウェブサイトの改ざんによる名誉毀損や、著作権侵害といった「人格権侵害」によって発生した賠償責任も補償の対象となる場合があります。
事故原因調査や復旧にかかる費用の補償
サイバー攻撃の被害に遭った場合、まず「何が起きたのか」「どこまで被害が及んでいるのか」を正確に把握する必要があります。この補償は、インシデント発生後の初動対応から完全復旧までにかかる、自社が直接負担する費用をカバーします。
主な費用には以下のようなものがあります。
- 原因調査費用:専門家(フォレンジック調査会社など)に依頼し、不正アクセスの経路や被害範囲を特定するための費用。
- 復旧費用:破損したデータやシステムを元に戻したり、再構築したりするための費用。
- 通知・対応費用:情報漏えいの被害者への通知にかかる郵送費や、問い合わせに対応するためのコールセンター設置・運営費用。
- コンサルティング費用:弁護士への法律相談費用や、PR会社への広報支援依頼など、専門家に対応を依頼するための費用。
- 見舞金・見舞品購入費用:被害者へのお詫びとして支払う見舞金や、代替品(商品券など)の購入費用。
近年被害が急増しているランサムウェア攻撃においては、暗号化されたデータを復旧するために支払う身代金(BTCなどの暗号資産)を補償の対象とする保険もあります。これらの事故対応費用は、迅速かつ適切な対応のために不可欠であり、合計すると数百万~数千万円に上ることも少なくありません。
事業中断による利益損失の補償
サイバー攻撃により、工場の生産ラインや基幹システム、ECサイトなどが停止し、正常な事業活動ができなくなるケースがあります。この補償は、事業が中断したことによって得られなかった利益(逸失利益)や、事業を継続するために臨時で発生した費用(営業継続費用)をカバーするものです。
例えば、製造業の企業がランサムウェアの被害に遭い、生産管理システムが停止して工場が稼働できなくなった場合、その期間中に本来得られるはずだった利益が補償されます。また、店舗のPOSシステムがダウンし、代替のレジをレンタルして営業を続けた場合のレンタル費用なども営業継続費用として補償の対象となります。
特に中小企業にとって、長期間の事業停止はキャッシュフローの悪化に直結し、倒産のリスクさえはらんでいます。この補償は、事業の早期復旧と再建を支える上で非常に重要な役割を果たします。
補償の対象外となるケースにも注意が必要
非常に頼りになるサイバー保険ですが、どのような損害でも無条件に補償されるわけではありません。契約内容によっては補償の対象外となる「免責事由」が定められており、加入前に必ず確認しておく必要があります。
一般的に、以下のようなケースは補償の対象外となる可能性が高いです。
- 経営者や従業員の故意・重過失による損害:意図的に情報を漏えいさせた場合など。
- 戦争、テロ、暴動などの非常事態に起因する損害:大規模な社会混乱によるサイバー攻撃など。
- 電力・通信インフラの障害による損害:電力会社や通信事業者側のトラブルが原因の場合。
- 保険契約前に発生していたインシデント:契約時点で既に認識していたサイバー攻撃被害など。
- 基本的なセキュリティ対策の懈怠:OSを長期間アップデートしていない、ウイルス対策ソフトを導入していないなど、保険加入の条件として定められた対策を怠っていたことに起因する損害。
- ハードウェアの物理的な損害:サーバーやPC本体の故障や破損など、物理的なモノの損害。
自社にどのようなリスクがあり、どの範囲まで補償が必要かを明確にした上で、契約内容や免責事項を十分に理解することが、いざという時に保険を最大限活用するための鍵となります。
中小企業向けサイバー保険の失敗しない選び方

サイバー保険は、今や多くの保険会社が提供しており、補償内容や保険料も多種多様です。選択肢が多いからこそ、「どの保険を選べば良いのかわからない」と悩む経営者の方も少なくありません。ここでは、数ある商品の中から自社の状況に本当にマッチしたサイバー保険を見極めるための5つの重要な選定ポイントを、具体的に解説します。
自社の事業リスクに合った補償内容か
サイバー保険を選ぶ上で最も重要なのは、自社が抱えるサイバーリスクの実態と、保険の補償内容が合致しているかという点です。業種や事業形態によって、想定されるリスクは大きく異なります。まずは自社のビジネス環境を分析し、どのようなサイバー攻撃の脅威に晒されており、万が一インシデントが発生した場合にどのような損害が生じるかを洗い出すことから始めましょう。
例えば、以下のように事業内容によって優先すべき補償は変わってきます。
- ECサイト運営や顧客の個人情報を多く預かる企業:情報漏洩が発生した場合、顧客への見舞金や損害賠償請求への備えが不可欠です。損害賠償責任の補償が手厚いプランを重視すべきでしょう。
- 製造業や工場を稼働させている企業:ランサムウェア攻撃により工場の生産管理システムが停止すると、莫大な利益損失につながります。事業中断による利益損失や営業継続費用を補償する特約の必要性が高くなります。
- 特定の取引先への部品供給などサプライチェーンを担う企業:自社のシステム停止が原因で取引先に損害を与えてしまった場合、賠償責任を問われる可能性があります。他社への影響も考慮した補償範囲を確認する必要があります。
自社にとってどのリスクが最も深刻かを判断し、そのリスクを的確にカバーできる補償内容となっているか、パンフレットや約款を注意深く確認することが失敗しないための第一歩です。
保険料と補償額のバランスは適切か
保険を選ぶ際、どうしても月々や年間の保険料に目が行きがちです。しかし、保険料の安さだけで選んでしまうと、いざという時に「補償額が全く足りなかった」という事態に陥りかねません。支払う保険料と、有事の際に受け取れる保険金額(支払限度額)のバランスを慎重に見極めることが肝心です。
適切な補償額を設定するためには、サイバー攻撃を受けた際の最大損害額を試算してみることが有効です。例えば、システムの復旧費用、専門家への調査依頼費用、顧客への見舞金、事業停止期間中の逸失利益などを合計し、その金額をカバーできる補償額を設定するのが理想です。もちろん、補償額を高くすれば保険料も上がります。企業の財務状況や許容できるコストを考慮し、どこまでのリスクを保険でカバーし、どこからは自社で負担するのか、コストパフォーマンスを意識して最適なバランス点を見つけましょう。
緊急時対応など付帯サービスは充実しているか
サイバー保険の価値は、金銭的な補償だけではありません。特にIT専門の担当者がいない、または少ない中小企業にとって、サイバー攻撃発生時の緊急対応をサポートしてくれる付帯サービスの有無と質は、保険選びの極めて重要な判断基準となります。
サイバーインシデントは、発生直後の初動対応が被害の拡大を抑える鍵を握ります。しかし、パニック状態で何から手をつければ良いのかわからないケースがほとんどです。そんな時に、専門家による的確なアドバイスや実務支援を受けられるかどうかで、その後の復旧スピードや事業への影響は大きく変わります。
保険商品によって付帯サービスの内容は異なりますが、主に以下のようなサポートが提供されています。
| サービス項目 | サービス内容と重要性 |
|---|---|
| 24時間365日対応ヘルプデスク | 夜間や休日を問わず、インシデント発生時にいつでも専門家に相談できる窓口。迅速な初動対応の起点となります。 |
| 原因調査・復旧支援 | 被害状況の特定、原因究明(フォレンジック調査)、システムの復旧作業などを支援する専門家を派遣・紹介してくれます。 |
| 法的アドバイス | 顧客への通知義務や監督官庁への報告、損害賠償請求への対応など、法律の専門家による助言を提供します。 |
| 広報・PRコンサルティング | 記者会見の実施やプレスリリースの作成など、顧客や取引先からの信用失墜を防ぐための広報活動をサポートします。 |
これらのサービスがパッケージに含まれているか、オプション(特約)なのか、また利用回数に制限はないかなどを事前に確認しておきましょう。
免責金額(自己負担額)を確認する
免責金額とは、保険金を請求する際に、保険会社が支払う保険金から差し引かれる自己負担額のことです。例えば、免責金額が50万円で損害額が300万円だった場合、保険会社から支払われるのは250万円となり、残りの50万円は自社で負担する必要があります。
一般的に、この免責金額を高く設定すればするほど保険料は安くなり、低く設定すれば保険料は高くなるという関係にあります。保険料を抑えたいからといって免責金額を高く設定しすぎると、いざインシデントが発生した際に自己負担額をすぐに用意できず、迅速な対応が取れないという本末転倒な事態になりかねません。
自社の財務体力やキャッシュフローを考慮し、万が一の際に無理なく支払える範囲で免責金額を設定することが重要です。複数のプランを比較検討する際には、保険料と補償額だけでなく、免責金額の条件もしっかりと確認しましょう。
加入条件と手続きのしやすさ
サイバー保険は、申し込めばどの企業でも無条件で加入できるわけではありません。保険会社は、加入希望企業のセキュリティ対策状況を評価し、加入の可否や保険料を決定します。これを「加入審査」と呼びます。
審査では、多くの場合、以下のような基本的なセキュリティ対策が実施されているかが問われます。
- アンチウイルスソフトの導入と定義ファイルの常時更新
- ファイアウォールの設置と適切な設定
- OSやソフトウェアの脆弱性を解消するための定期的なアップデート
- 重要なデータの定期的なバックアップ
- ID・パスワードの適切な管理
保険会社によっては、加入前に専門家によるセキュリティ診断を必須としている場合や、より高度な対策を要求される場合もあります。まずは自社のセキュリティ対策の現状を把握し、加入条件を満たしているかを確認することが必要です。もし条件を満たしていない場合は、保険加入を機にセキュリティ体制を見直す良い機会と捉えることもできるでしょう。
また、見積もりの取得や申し込み手続きがオンラインで完結するか、書類のやり取りが煩雑でないかなど、手続きのしやすさも、日々の業務に追われる中小企業の担当者にとっては見逃せないポイントです。
サイバー保険の費用相場はどれくらい?

サイバー保険への加入を検討する際、最も気になるのが「保険料は一体いくらかかるのか」という点でしょう。結論から言うと、サイバー保険の費用は企業の状況によって大きく異なり、年間数万円から数百万円以上と非常に幅広いのが実情です。
保険料は、企業が抱えるサイバーリスクの大きさに比例して算出されます。そのため、自社の事業規模や業態、セキュリティ対策のレベルなどを正しく把握し、適切な保険料の相場観を持つことが重要になります。ここでは、保険料がどのように決まるのか、そして中小企業の具体的なモデルケースについて詳しく解説します。
企業の売上高や業種で保険料は変動する
サイバー保険の保険料を決定する主な要因は、以下の通りです。これらの要素を保険会社が総合的に評価し、個別の保険料を算出します。
- 売上高
企業の売上高は、保険料を算出する上で最も基本的な指標となります。売上高が大きいほど、サイバー攻撃による事業停止時の逸失利益や、顧客への損害賠償額が大きくなる傾向があるため、保険料も高くなります。 - 業種
取り扱う情報の種類や事業形態によってサイバーリスクは大きく異なります。例えば、個人情報やクレジットカード情報を大量に扱うECサイト運営、医療機関、金融機関などはリスクが高いと判断され、保険料が高くなる傾向にあります。一方、特定の企業間取引(BtoB)が中心で、機密情報の取り扱いが少ない業種であれば、保険料は比較的安価になる可能性があります。 - セキュリティ対策の状況
保険会社が最も重視するポイントの一つが、企業のセキュリティ対策レベルです。ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入はもちろんのこと、従業員へのセキュリティ教育の実施、EDR(Endpoint Detection and Response)の導入、脆弱性診断の実施状況、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得などは、保険料の割引要素となったり、加入の必須条件となったりする場合があります。セキュリティ対策が強固であればあるほど、リスクが低いと評価され、保険料を抑えることができます。 - 補償内容と保険金額(支払限度額)
当然ながら、補償範囲が広く、インシデント発生時に支払われる保険金の上限額(支払限度額)を高く設定するほど、保険料は上がります。損害賠償だけでなく、事業中断による損失やブランドイメージ回復のためのコンサルティング費用まで手厚くカバーするプランは、その分保険料も高額になります。 - 免責金額(自己負担額)
免責金額とは、損害が発生した際に自己負担する金額のことです。この免責金額を高く設定すれば、保険会社の負担が減るため、月々の保険料を安く抑えることができます。ただし、いざという時の自己負担は大きくなるため、企業の財務状況に合わせて慎重に設定する必要があります。
中小企業の保険料モデルケースを紹介
ここでは、中小企業におけるサイバー保険の費用感をより具体的にイメージしていただくために、いくつかのモデルケースをご紹介します。ただし、下記はあくまで一般的な目安であり、実際の保険料は各保険会社による詳細な見積もりが必要です。
| モデルケース(業種・売上規模) | 想定される保険金額(支払限度額) | 年間保険料の目安 |
|---|---|---|
| 【ケース1】 ITサービス業 (売上高:1億円未満) | 3,000万円~5,000万円 | 年間 5万円~30万円程度 |
| 【ケース2】 卸売・小売業(ECサイト運営) (売上高:5億円程度) | 5,000万円~1億円 | 年間 20万円~80万円程度 |
| 【ケース3】 製造業 (売上高:10億円程度) | 1億円~3億円 | 年間 50万円~150万円程度 |
上記のように、同じ中小企業であっても、事業内容や規模によって保険料には大きな差が出ます。特に、顧客の個人情報を多く保持する小売業や、サプライチェーンへの影響が懸念される製造業では、リスクの大きさに比例して保険料も高くなる傾向があります。
自社にとって最適な保険を見つけるためには、複数の保険会社から見積もりを取り、補償内容と保険料のバランスを比較検討することが不可欠です。保険代理店などに相談し、自社のリスクを客観的に評価してもらうのも良いでしょう。
まとめ
サイバー攻撃は他人事ではなく、特に中小企業にとってその被害は経営を揺るがす深刻なリスクとなります。サイバー保険は、莫大な損害賠償や事業停止による損失をカバーし、企業の存続を守るための重要な備えです。
本記事で解説した選び方のポイント、すなわち自社のリスクに合った補償内容、保険料と補償額のバランス、付帯サービスなどを参考に、万が一の事態に備えて最適な保険を選びましょう。