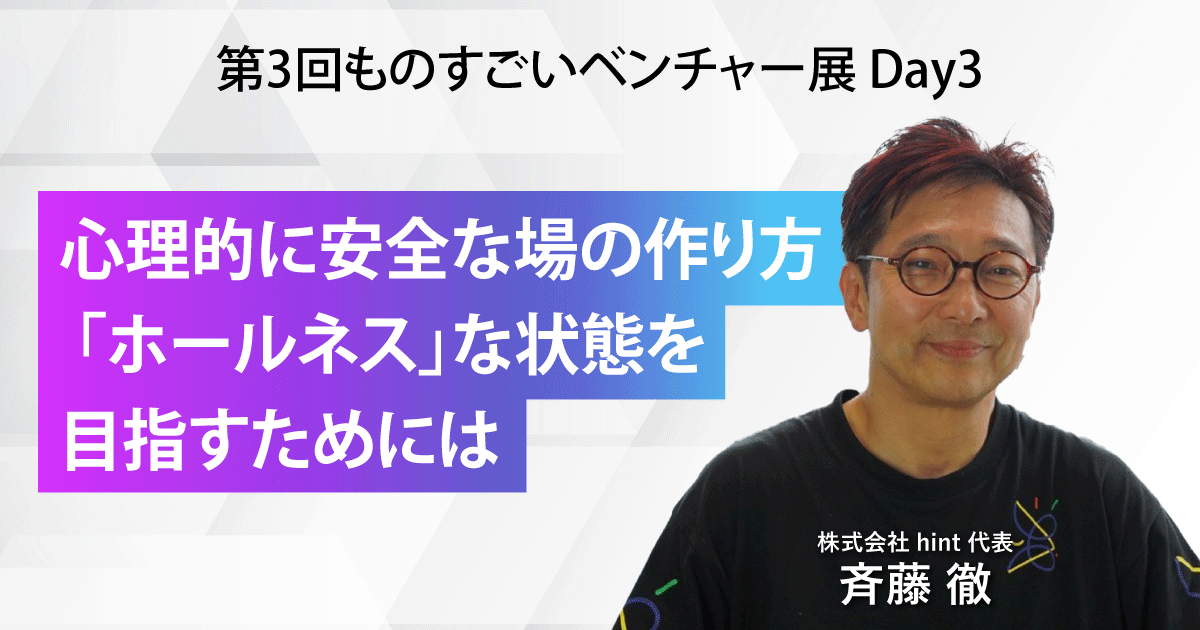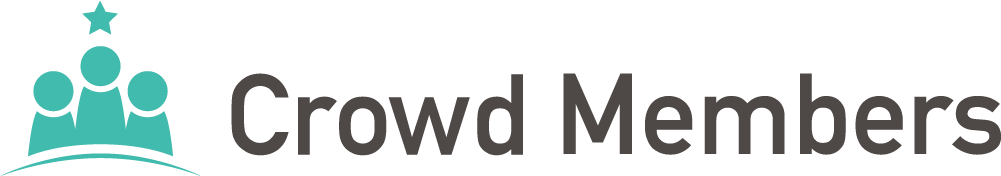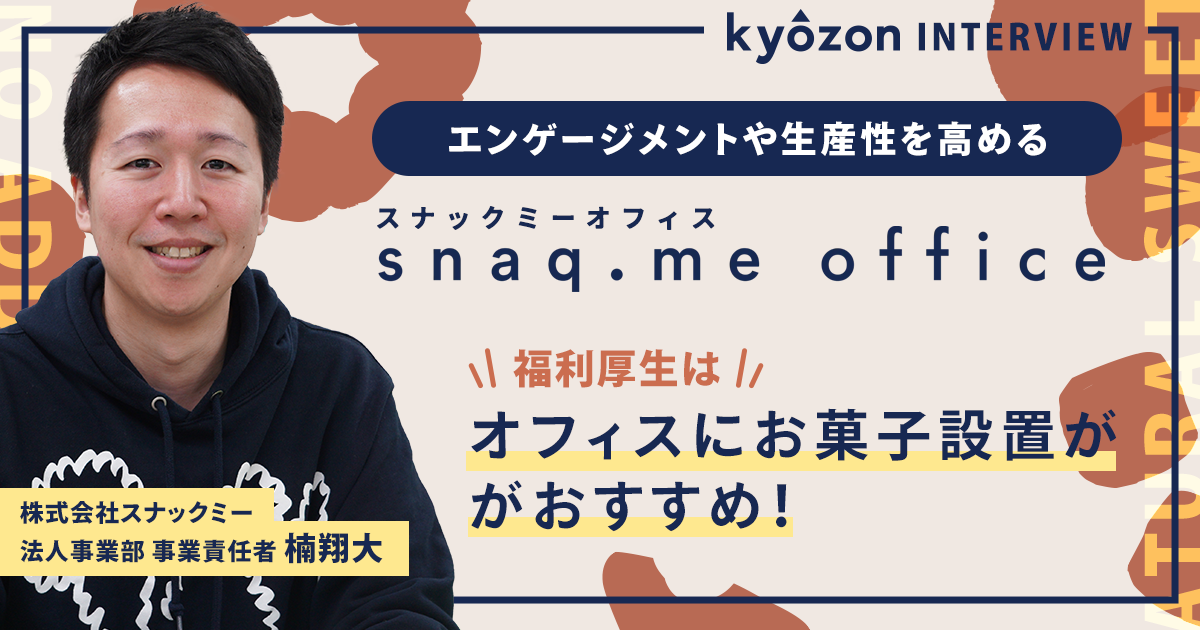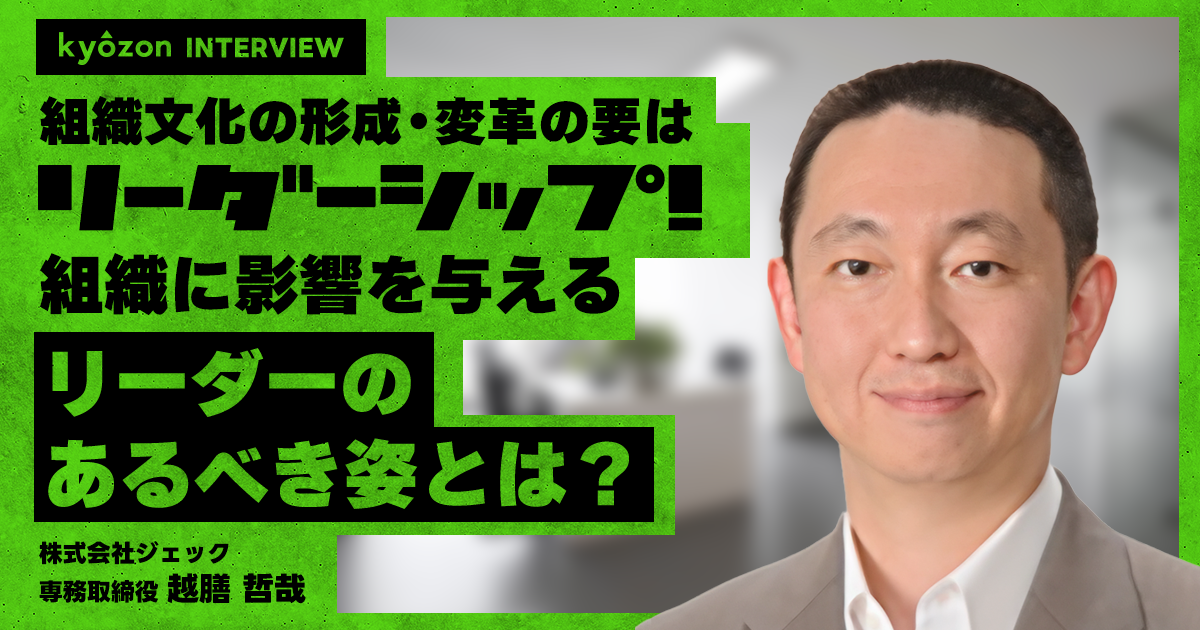登壇者プロフィール

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 / 株式会社hint代表 / 株式会社ループス・コミュニケーションズ代表
1961年、川崎生まれ。駒場東邦中学校・高等学校、慶應義塾大学理工学部を経て、1985年、日本IBM株式会社入社。29歳で日本IBMを退職。1991年2月、株式会社フレックスファームを創業し、ベンチャーの世界に飛び込む。その後、激しいアップダウンの後に、2005年、株式会社ループス・コミュニケーションズを創業。
著書「だから僕たちは、組織を変えていける」


僕は斎藤徹といいます。29歳まではコンピューターの技術者で、それから起業して31年間ずっと起業家やってます。でまぁ本もいろいろ書いたりして、6年前から学習院大学の客員教授になって、今ビジネスブレークスルー大学の教授になっています。去年の11月に「だから僕たちは、組織を変えていける」という本を出しました。
僕は2つ専門性があって、ひとつは組織論です。いい組織を作るってやつですね。それからもうひとつは、いい事業を作る企業論ですね。特に僕はですね、もう組織も事業も色々な大失敗をいっぱい繰り返して今まで生きてきました。
創業者として追放されたり、資金ショートがずっとあったり、銀行から裁判を起こされて自宅競売にかけられたり、色々なことがありました。
そういう実体験で学んできたこと、それに最新の経営理論を組み合わせて明日から実践できるような組織論として体系化したのが「だから僕たちは、組織を変えていける」という本です。
組織論って難しい言葉をいってますけど、本当に一人の社員からでも自分や自分のチームを変えていける、そのような願いを込めてこの本を作りました。この本の最初にこんなことを書きました。
「社会は指数関数的に変わっている」
じゃあ組織では変わっているかというと、変わってないですね。
この本の目的は、組織を変えることです。それはどういうふうに変えるかということ、「やる気に満ちた優しい組織を作る」っていうことです。
チームに対する自らの影響範囲を考える

反応的に生きるんじゃなくて、自ら、周囲の環境はどう変化しようと自分で判断して思考選択する能力。それで一番大切なのは「関心の輪、影響の輪」ということを彼は言いました。
皆さんも自分自身が所属してる会社には、すごい関心がありますよね、会社が関心の輪ですよね。
でも大切なのは、その中に影響の輪があるよねっていうことです。自分、会社全体に対してはもちろん関心があるけれども、自分が直接コントロールできる、あるいは影響できる範囲っていうのは、すごく小さいのが一般的ですよね。
この自分自身が影響できる範囲というのを明確に意識すること、これが大切だということです。主体的な人というのは、変えられないことに関心は持つけれども、積極的に関与はしない。
なぜかというと、自分の時間とか心理的なエネルギーは限られているわけなので、変えられないところにすごく関心を持って「それはこうじゃなくちゃいけない」みたいなことを思うと、どんどんイライラしてくるわけですね。
それで、本当に変えられるところに力を投入できなくなります。だから、大切なことはまず、自分の影響度合いを見極めて、そこにエネルギーを集中すること。だから自分自身、それから半径5メートル、これを心理的に安全なものにしていくというお話をしたいと思います。
心理的安全性を高める人物の存在

いろんなチームに難しい人っていますよね。例えば性格の悪い人、攻撃的になっちゃう人、ちょっと怠け者で一生懸命やらない人とか、すぐ愚痴言っちゃう人とか、こういう人がまあなかなか活気のあるチームにひとり入ると、どのくらい生産性は落ちると思いますか?これがオーストラリアで、実験されました。
これは生産性がだいたい3~4割は落ちちゃうんですよね、1人入るだけで。
こういう人は雇えないから、ニックっていう演技力のある学生がいるので、そのニックがこの役目をしたんですね 。みんなやる気のあるチームにニックが入っていって、ひとりだけずっと下を向いてたんですね。それでどうなったかというと、やっぱり最初はやる気があるけど、ニックがずっと下向いてると影響されてしまって、最後には3人が下向いちゃったという。で、下向いちゃったという。
まあわかりますよね。ひとつだけこの実験、ほとんどのチームがそうなっちゃったんだけど、ひとつだけ例外があったんですね。ジョンナサンがいるチームだけは、ニックが どんなに毒を注入しても、なんかジョナサンが中和してすぐにやる気を取り戻して目標に向かっていっちゃうそうなんですね。「ジョナサンは一体なにをやってるんだ」っていうことで、先生も注目し始めたんですね。
それで分かってきたことは、どうやらニックが暴言を吐いたりすると、ジョナサンは身を乗り出して笑顔を振りまいてたんですね。
つまり、ニックに「ダメだぞ」って言っちゃうみたいなあからさまな対抗はしないものの、微妙なボディーランゲージで場を和らげていると。
「なるほど、ジョナサンはわかりにくいぞ」ということで、何回も繰り返し見て、ようやくひとつのパターンを発見したんですね。それはまず、ニックがなんらかの毒を発すると、ジョナサンはすぐにそれを中和するような行動をするようです。
例えば笑顔で場にいる人を安心させる、でもそこで留まらないんです。
そのあと簡単な質問をすると、最初の人が「それはこう思う、これはこうじゃないかなーって思う」と言うと「あ、なるほどね」。
そうするとその人の心がパッと開く。また次の人が「それってこうだよね、こうじゃないかな」って答える。
そうすると「なるほど、そういう考え方もあるね」って言うと、その人も心を開く、そうやってみんながだんだん心を開いて、また元のいいチームになっていったっていう話なんですね。ジョナサンは、場に安全を提供しているんだなとわかったのだといいます。
このケースでは、ニックが場の安全性をガーッっと低くしたわけですが、ジョナサンは指示や鼓舞こそしないものの、小さなメッセージで「ここは完全な場所なんだよ」「だからみんな怖がらないで自分の意見を言っていいんだよ」「みんなの意見を聞きたいと思ってるんだ」っていうことを言っているんだと分かったんですね。ジョナサンは、場の心理的安全性を高めていたんです。
この「心理的安全性」は、経営学でいま最も注目されるキーワードのひとつですね。エドモンドソンという女性の教授が1999年に作った言葉ですが、Google の「プロジェクトアリストテレス」の中でも、チームで一番重要なものはこれだ、生産性に一番重要なのはこれだという発表もあって、非常に注目されるキーワードとなっております。
対人関係のリスクが心理的安全性を妨げる

心理的安全性を妨げるのはなにかというと、対人関係のリスクなんです。それも4つあると、エドモンドソンは言ってます。
1つ目は「無知の不安」
つまり「え、こんなことも知らないの?」て言われちゃいそうとか。
あとは「無能の不安」
「え、こんなこともできないの?」って言われちゃいそうとか。
それから「邪魔の不安」
「あっこれやったら邪魔になっちゃうよな~」とか。
最後に「否定の不安」
「この人の言うことは否定できないよな……」みたいなやつですね。
さらに、2つのタイプがあるんです。1つは、持論を戦わせるような場。
こういう徹底的に議論するみたいな感じの場は、どうしても無知とか無能の不安が出てきて、みんな強がりの仮面をつけちゃうんですね。これだとやっぱり本音が出ない。
もう1つは、空気を読み合う場。空気を読み合ってしまうと、ぱっと見たらいいチームなんだけども、やっぱり「これやっていいのかな、悪いのかな」とか「この人のいうことはちょっと逆らえないな」みたいな感じで、いい人の仮面をつけちゃうんですよ。
この強がりの仮面をつけちゃダメというのは分かりやすいんだけど、いい人の仮面もつけちゃダメなんです。自然体でみんながいろんなことを言って、そのアイディアを掛けあわせられるような場というのが大切です。
心理的安全性を横軸、縦軸が使命感の四象限で考えると、僕たちがいきたいのはですね、使命感も心理的安全性も高い、本音で競争できる場ですね。
先ほどの例でいうと、ニックは無気力とか暴言で場を無気力な場にしたり、不安ゾーンに入れたりしてたんですね。でもジョナサンは何をしたかというと、まず笑顔で空気をやわらげてから、対話の力で皆のやる気を引き出したんですね。
心理的安全性を高める人物になるためには?

これはどういうことかというと、主体性に目覚めて、常に状況がどうであっても自然体の自分でいるっていうことですね。それを「ホールネス」と言っています。
子供のころは僕たちみんなホールネスだったんですね。でも「お母さんの笑顔が見たい」とか「良い成績を取らなくちゃ」とか「数字を達成しなくちゃ」とか「リーダーになったらなめられちゃいけない」とかで、どんどん社会人になるにつれてホールネスじゃなくなってくるんですよね。偽りの自分がどんどん大きくなっていってしまって、もうこれが当たり前になっちゃうんですね。
でも心の中は「したい」っていうのよりも「しなくちゃ」みたいな感じになってくる。これは辛いし、しかも心理的に安全な場を作れなくなっちゃうんですね。
例えば、「強くて頼れるリーダーにならなきゃいけない」と思っている自分がいますよね。それはどうしてかっていうと、やっぱり「有能な人に思われたい」っていう無知の不安とか無能の不安があって、強がりの仮面をつけているんです。
でもよく考えてみたら、強がってても、長い目で見ると信頼されなくなっちゃうんですね。
それよりも背伸びをせず、自分のままでチームに貢献することを考える感じです。
あともうひとつ、「この人の言うことに従わなきゃ」「やっぱりいい人に思われたい」など、邪魔の不安や、否定の不安があるといい人の仮面を被っちゃいます。でも「自分の保身ばかり考えているのはちょっと私らしくないな」「組織のためにはやっぱり自分の意見も伝えた方がいいよね」と考えることですね。伝え方っていうのはありますが、異なる意見も場に出す、そういったことがホールネスで、自然体の自分に戻るということです。
みんなが強がりの仮面もいい人の仮面も外す、外しやすいような場にするというのが心理的安全性を高めるということですが、参加している一人ひとりは、これはそもそも外せないっていうことも結構あるんですね。だから自分も、それぞれの人が自然体に戻るっていうことが大切です。
「ホールネス」な状態を目指す

この他者の尊重において、例えば「管理職の仕事は部下をやる気にさせて予算を達成すること」「どうやって人員を適切に配置するか」こういう言葉は、人を物として見てますよね。ビジネスではむしろ、私情を抜きにして人に対して役割や機能を求めるというのが正しいやり方だというのが、従来の考え方でした。
一方でこの考え方は、統制する組織の中では非常に人を統制しやすいし統制されやすいため重要でしたが、こういう感覚で場を心理的に安全にしようとしても、上辺のことだけであって、場は完全になりません。
だからこういう感覚は良くないですね。みんな人間なんですよ、当たり前なんだけど、物じゃないんです。みんなそうなんだということを、忘れちゃうんですよね。
だから意見が異なる、それはとても良いこと、多様性があるのはとてもいいことなんだけど、一人一人は自分の言ってること、やってることが正しいと思って生きている、独自の価値感を持っている。この、人の見方の基本ができて初めてホールネスになっていきます。そのためにはやはり他者の視点に立って、自らのことのように他者の経験や感情を想像するということですね。そうすれば初めて、真の共感を制御する神経が働いてきます。
それには想像力が鍵になります。これは全然会社のためではありません。心理的に安全な場をつくるためというよりも、自分自身のためですね。他者に寛大な人ほど家庭や職場で安定した協力体制を築く機会に恵まれる、まあ想像してみれば当たり前の事ですね。自分のためにも他者をコントロールしようとするところから、尊重するというところになります。
それから相互の理解もあります。自己開示してお互いが分かり本音が話せる、コミュニケーションをとるということ、この3つが揃うとコンフォートゾーンに入るんですね。コンフォートゾーンには、ここで留まりがちという罠があります。なんていってもコンフォートだから、でもここに留まっちゃうとどうなるかというと、井の中の蛙になってしまいます。
ある人がもう他の人がいろいろ言うのも面倒くさくなってきちゃって、他に行くのも面倒くさくなってきちゃうし、ある人が不幸だよねって言うとみんなそれに同調するようになってきてしまうんですね。
だから、コンフォートゾーンに入って関係性を良くすることはとても大切ですが、そこに留まっちゃうと共鳴室現象とか同調圧力の高まりで、空気を読み合う場所になってしまいます。それで、組織の成果が落ちてきてしまう。
だから、組織の関係性が良くなったら、すかさずラーニングゾーンに歩を進めることが大切なんですね。
組織の関係性が上向いたらパーパスを共有する

例えば組織もパーパスがあるけれども、会議もパーパスありますね。例えば、お客さんのためのアイディアをみんなで出す会議の際、社長とが部長とかがポンと「ちょっとこれこうだと思うよ」ってポンと言うと、みんなはどうなるかっていうと、ばっと権威者の方を向いて「うん、これはちょっと難しい、ちょっと自分と意見が違うから調整しないといけないぞ」っていう感覚になります。
これが関係性重視のチームで、価値創造に向かなくなるんですね。だからずーっとエコーチェンバーに入っちゃうんですよ。これをやってはいけません。
もう関係性が良くなったら常にパーパスをみんなで共有して、お客さんの方を向くことで価値を生み出します。そもそもチームっていうのは、特に株式会社って価値を追うために集まってきてるわけだから、内じゃなくて外を見るという感覚を持つことが大切ですね。そのためにはね、権威者もちょっと発言やコミュニケーションの技術が必要になったり、メンバーも常にパーパスを考えたりすることが大切になります。
第三案を共創することの重要性

なぜかというと、営業部っていうのはお客さんの要望とかクレームをいつも受けてるけど、開発部っていうのはお客さんからちょっと遠いから、お客さんの声に鈍いこともあるんですね。それで、営業部の人がいつもイライラするんです。
例えばある会議で、お客さんから強いクレームを受けた営業部がそれをシェアしたものの、開発部の反応が鈍いと。そうなると営業部は「あの人は、どうしていつもお客さんの声を無視するんですか」と口にしてしまうこともあります。
こうなると、売り言葉に買い言葉になってしまいます。立場をかけた戦いになってしまうので、もう第三案の共創というのは絶対できないです。
これを防ぐためには、反応が薄かった際に「あれ、反応が薄いのは何か理由があるはずだな」ってワンクッション置く必要があります。
それで「お客さんを軽視しているのかな?それとも忙しすぎるのかな?それとも視点が違うのかな」と、ちょっと分からないから丁寧に話し合ってみようと。そうすることで、話し合えばきっと理解できるんだな、第三案を共創できるんだなという形になるんですね。
意見がいっぱい出て対立するのではなく、建設的に第三案を共創することが大切です。
まとめ

第3回ものすごいベンチャー展 Day3 『組織課題解決』
YouTube:https://youtu.be/umT-IjFPEeE?t=248
【SNSフォローのお願い】
kyozonは日常のビジネスをスマートにする情報を毎日お届けしています。
今回の記事が「役に立った!」という方はtwitterとfacebookもフォローいただければ幸いです。
twitter:https://twitter.com/kyozon_comix