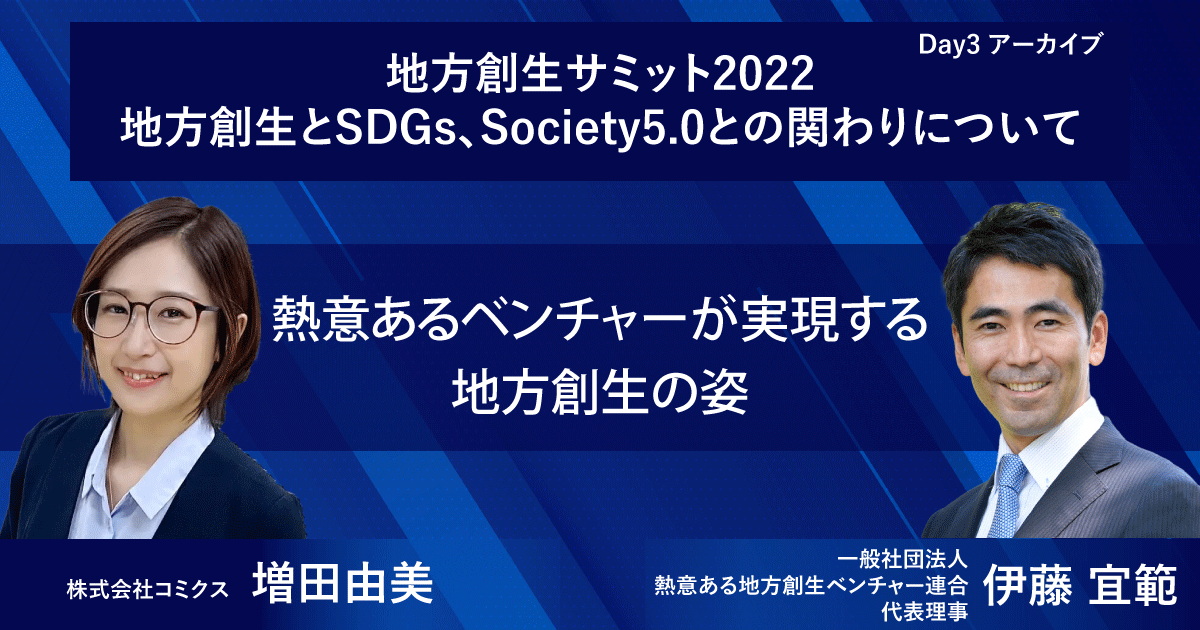登壇者プロフィール

1975年生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、アクセンチュアにて3年弱勤務。退職後、早稲田大学大学院(政治学修士)に通いながら、2003年の横須賀市議会議員選挙に立候補し、初当選。2009年の横須賀市長選挙で初当選し、2013年に再選。2017年7月に退任するまで、完全無所属を貫いた。現在、地域課題解決のための良質で戦略的な官民連携手法GR:ガバメント・リレーションズを軸に仕事している。
熱意ある地方創生ベンチャー連合の2018年に事務局長に就任。2021年からは代表理事に就任。

事業開発本部
SaaS事業者支援室
DX推進室
行政の経験を活かして地方創生に挑戦


「熱意ある地方創生ベンチャー連合」の考えと取り組み

ミッション:「ベンチャー企業のもつイノベーティブなサービスにより、地域課題解決や地域事業の生産性を上げ、持続的な地域の経済発展に貢献すること」
ビジョン:「地方創生は自治体だけではなしえない。ベンチャー企業によるイノベーションで前進する。そのベンチャー企業へ、熱意ある地方創生ベンチャー連合は地方創生のノウハウ・ドゥハウを提供する。」
ベンチャーのもっているイノベーティブなサービスを、地域の課題解決・活性化にきちんと繋げていこう、ベンチャーと一緒に地方創生を実現していこうという内容です。大きなポイントとしては、ノウハウだけではなく「Do・how」も一緒に提供していこうという部分。
こちらを説明しますと、ひとつは「公的制度」。国の交付金や地方創生の取り組み、自治体がどんな補助金を出しているか、どんな課題感をもっているか、どんな予算の仕組みで動いているかといったような、具体的課題への対処方法です。
例えば人口が減っているために地域のお祭りの担い手がいなくなっていってます。そこに対して、行政ができること、できないことといった構造も含めて、解決の方法を地方創生系ベンチャー企業様へご提供すると。もうひとつは、「フィールド」です。いろいろな地方自治体と我々は繋がっていますので、よいソリューションがあればマッチできる場をご提供できます。
「市長という行政側」から「団体理事」へ至った経緯と団体の強み


団体の強みについて、2016年設立という実績と、私は市長から、今の事務局長は楽天社からビズリーチ社を経て独立して、今、鹿児島県長島町で地方創生統括官という非常勤特別職を受けています。この点からも、地方のことをよく把握しており、ベンチャー企業や自治体との強いネットワークもある。そして2022年5月時点で、多くの分野にまたがって厚みある64社もの企業様群が会員所属、中にはKDDI社のようにベンチャー企業支援のための「地方創生ファンド」を運営されている会員企業様もいらっしゃいます。
さらにスタートアップを応援する自治体連合とも、とてもよいパートナーシップを結んでいます。実際、昨年まで福岡市から毎年職員を派遣していただくといった関係もありました。また、シェアリングエコノミー協会と共同で勉強会をしたり、内閣府の地方創生推進室と情報共有をしたりと、団体連携、情報共有も活発です。
「地方創生ベンチャーサミット」を実施

以前はリアルで実施して繋がりを作れていましたが、コロナ禍でオンライン開催、そして今年は「リアルとオンラインのハイブリット」で実施しました。思いがけない相乗効果として、自治体と特化したソリューションを持つベンチャー企業とが交わることで、このサミット自体が事業創出に繋がることもありました。
具体的には、昨年青森市の小野寺市長とcreemaにご登壇いただいたセッションで、「これを地方創生に繋げられないか」と打診してみたところ、青森市のガラス工芸やねぶたのデザイン事務所などを直接訪問することに。そこから、「クリエイターのワーケーション事業」を創出することができました。


自治体課題に関しての「勉強会」を実施

アーバンイノベーションジャパン社が岡崎市から委託を受けてスキームを作ってるんですが、岡崎市様は良き内容であれば50万円程度で発注したいとご要望くださり、ベンチャー企業から具体的な提案等ありました。自治体の課題を投げてみると、解決方法が見つかるかもしれないというのは、我々にとっても新しい発見でした。
また、新しい商品であれば「トライアル発注」もできるという制度がある自治体もあります。
イノベーティブなものであれば、単独で発注しますという自治体が生まれていることも、多くの方に知っていただきたいと考えております。なお、当勉強会は自治体と連携するにはどうすればいいかといった初級編から、スタディツアー前の準備企画まで、段階に応じて幅広くカバーしております。
変わっていく地方自治体

また、他にも「予算は用意できないですが、実証実験フィールドはご提供できます」といった自治体様だったり、連携協定であればトライアルで結べますといった自治体様も出てきています。変わってきていることを地方創生に関係するみなさんに知っていただいて、見極める目を身につけていただきたいと思います。
「スタディツアー」で裸の付き合いを

また、国の事業を受注して、ワーケーションとスキルアップをセットにした事業、熊本県多良木町のツアーでは、狩猟免許、船舶免許を取得できるといったものがセットになったツアーを実施しています。資格取得のための座学だけでなく、実際の仕掛けを見たり、お肉をいただいてリフレッシュしたりするといった体験も含めました。また、多良木の市長や地域商社との繋がりもできました。このような形で、自治体と関わっていくというやり方が増えています。


一度は現地へ足を運んで話を聞いたうえで、リモートミーティングを行うことも大切ではないでしょうか。
情報発信と双方向でのリアル相談にも対応

情報発信と双方向でのリアル相談にも対応


最後に、「シンクタンク=考えるタンク」という、実行が伴わない考えるだけの団体がいくつあっても、地方創生はうまくいかないと思います。実行する人、自治体職員や企業が「Do意識」をもって、「シンク」だけではない「Doタンク」を目指す必要があると思っています。
まとめ

地方創生サミット2022 地方創生とSDGs、Society5.0との関わりについて Day3 アーカイブ
YouTube:https://youtu.be/OM1Qqnvlvcs?t=1771
【SNSフォローのお願い】
kyozonは日常のビジネスをスマートにする情報を毎日お届けしています。
今回の記事が「役に立った!」という方はtwitterとfacebookもフォローいただければ幸いです。
twitter:https://twitter.com/kyozon_comix