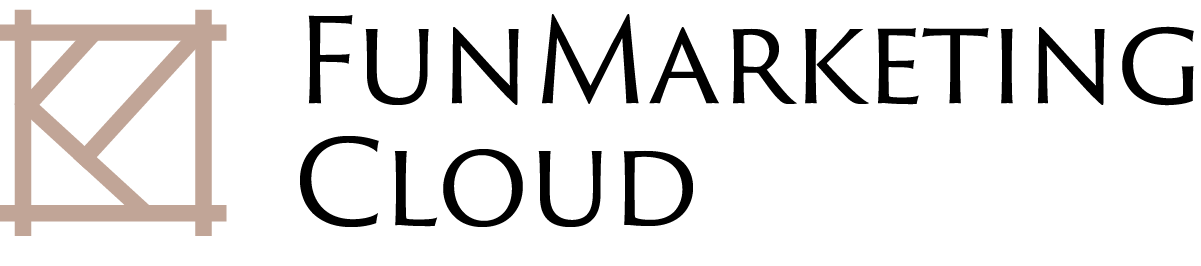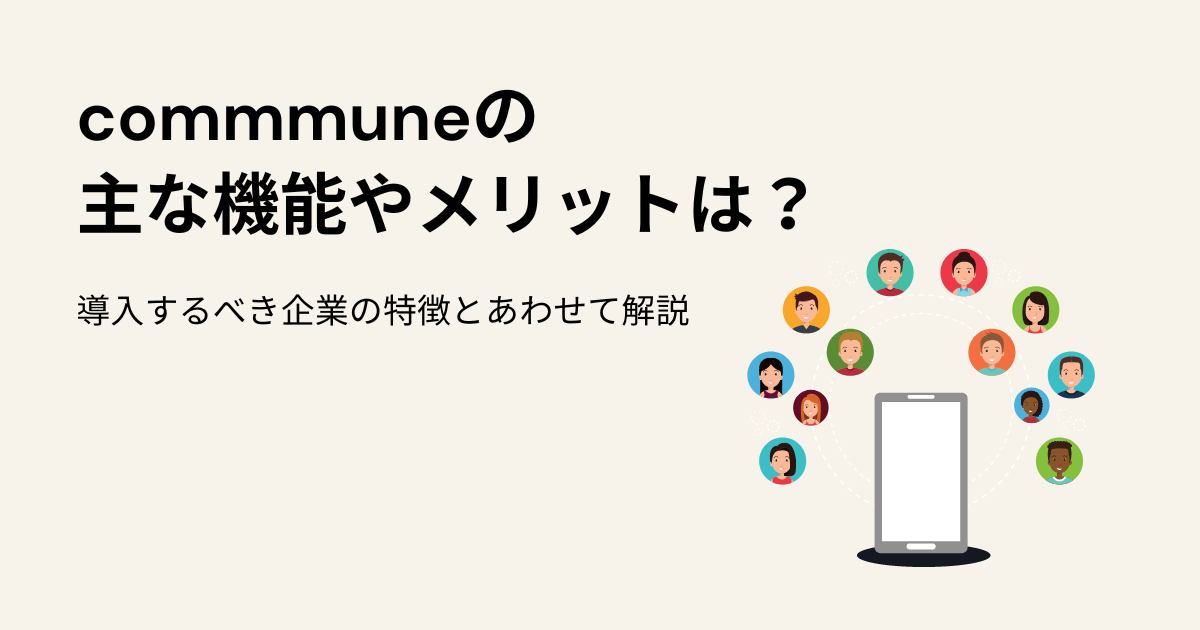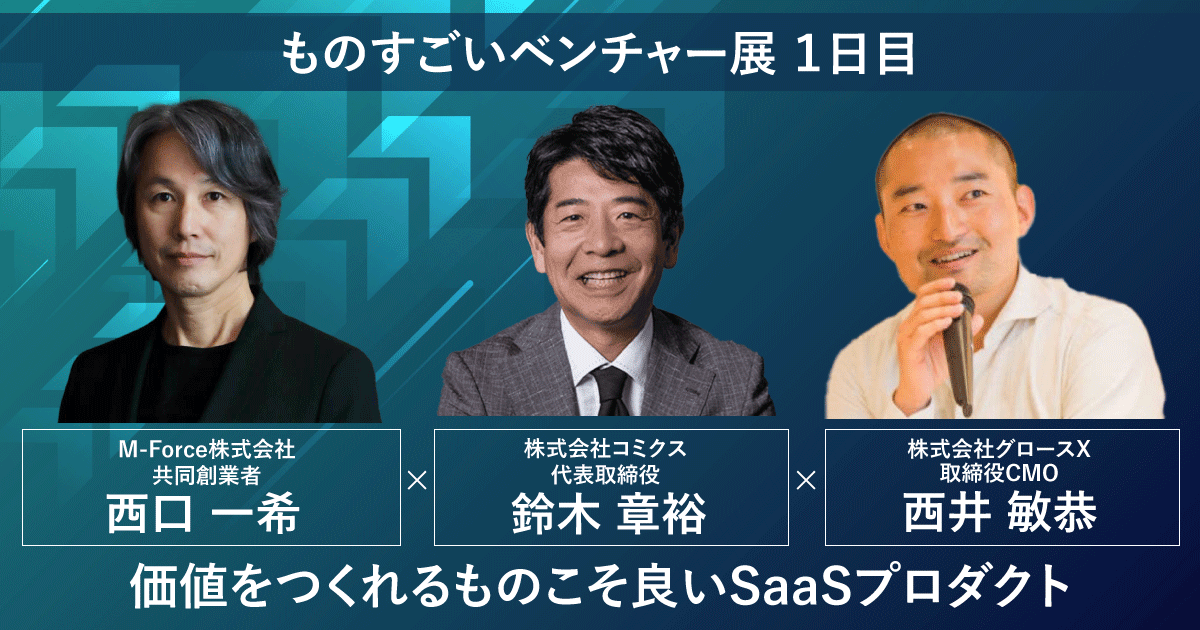ソニックブランディングとは|音で企業価値を高める新常識

ソニックブランディングとは、企業や商品のブランドイメージを象徴する「音」を戦略的に活用し、顧客とのコミュニケーションを深めるブランディング手法のことです。「サウンドブランディング」や「音響ブランディング」とも呼ばれます。スマートフォンの起動音、CMで流れる特徴的なメロディ、アプリの通知音など、私たちは日常の様々な場面で企業の「音」に触れています。
視覚的なロゴやコーポレートカラーと同様に、聴覚に訴えかける「音のアイデンティティ」を構築することで、ブランドの世界観を伝え、顧客の記憶に深く刻み込むことができます。これは単にBGMを流したり、効果音を付けたりするだけでなく、ブランドの理念や価値観を音に変換し、すべての顧客接点(タッチポイント)で一貫性のある音の体験を提供する、包括的なマーケティング戦略なのです。
サウンドロゴやジングルとの違い
ソニックブランディングを理解する上で、よく混同されがちな「サウンドロゴ」や「ジングル」との違いを明確にしておくことが重要です。これらはソニックブランディングを構成する要素の一部ではありますが、その役割と範囲は異なります。
ソニックブランディングは、これら個別の音響要素を包括し、ブランド全体で一貫した音の体験を設計・管理する上位の戦略的概念です。サウンドロゴやジングルは、その戦略に基づいて作られる具体的なアウトプットの一つと捉えると分かりやすいでしょう。
| 要素 | 定義 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| ソニックブランディング | ブランドの音に関する包括的な戦略。音を通じてブランドアイデンティティを構築し、管理する活動全体を指す。 | ・ブランドイメージの統一 ・顧客体験の向上 ・長期的なブランド価値の構築 | 企業全体の音響戦略(Webサイト、アプリ、店舗、広告など全てに適用される音のガイドライン) |
| サウンドロゴ | 企業やブランドを象徴する短いメロディや効果音。「音のロゴマーク」。 | ・ブランドの識別と想起 ・記憶への定着 | インテルの「インテル、入ってる」、マクドナルドの「I’m lovin’ it」のサウンド |
| ジングル | CMなどで使用される、商品名やキャッチコピーを含んだ短い楽曲。 | ・商品やサービスの宣伝 ・キャッチーさによる認知度向上 | 積水ハウスの「積水ハウスの歌」、大幸薬品の「正露丸」のラッパのメロディ |
なぜ今ソニックブランディングが重要視されるのか

近年、多くの先進企業がソニックブランディングに注目し、投資を始めています。その背景には、私たちの生活を取り巻く環境の大きな変化があります。
デジタルデバイスと音声コンテンツの爆発的普及
スマートスピーカーの登場、ポッドキャストや音楽ストリーミングサービスの普及、そしてTikTokやYouTube ショートといった動画コンテンツの流行により、人々が「耳」で情報やコンテンツに触れる時間(=耳の可処分時間)が急激に増加しています。画面を見ていない状況でもブランドのメッセージを届けるためには、視覚に頼らない「音」によるコミュニケーションが不可欠です。音声検索や音声アシスタントが日常に浸透する中で、音のアイデンティティを持つことは、未来の顧客接点における重要な競争優位性となります。
情報過多の時代におけるブランド差別化の必要性
現代は、WebサイトやSNS上に視覚情報が溢れかえっており、ビジュアルだけで他社と差別化を図ることが困難になっています。一方で、聴覚に訴えかけるブランディングはまだ未開拓な領域が多く、独自の「音」を持つことで、競合の中から際立った存在になることが可能です。音は人間の感情や記憶に直接働きかける力が非常に強いため、ロジックを超えて直感的にブランドへの好意や親近感を抱かせ、深いエンゲージメントを築くきっかけとなります。
一貫したブランド体験の提供による顧客ロイヤルティの向上
顧客は、オンライン広告、実店舗、製品の使用時、カスタマーサポートへの電話など、様々な場面でブランドと接触します。これらの多様なタッチポイントで一貫した「ブランドの音」が聞こえてくれば、顧客は無意識のうちに安心感や信頼感を抱きます。断片的な情報の接触が、一貫したブランド体験へと昇華されることで、ブランドの世界観が強化され、顧客のロイヤルティ向上に大きく貢献するのです。
ソニックブランディングがもたらす3つの効果

ソニックブランディングは、単に「耳に残る音」を作るだけの施策ではありません。適切に設計・運用された音は、企業のブランド価値を飛躍的に高める強力な経営資源となり得ます。視覚情報が飽和状態にある現代市場において、聴覚に訴えかけるアプローチは、顧客の深層心理に働きかけ、ビジネスに多大な好影響をもたらします。
ここでは、ソニックブランディングがもたらす代表的な3つの効果を具体的に解説します。
ブランド認知度の向上と記憶への定着
人間の五感の中でも、聴覚は特に記憶と感情に強く結びついています。特定の音楽を聴くと昔の記憶が鮮明に蘇る「プルースト効果」のように、音は無意識の領域に働きかけ、ブランドの存在を深く刻み込む力を持っています。
例えば、テレビCMで繰り返し流れるサウンドロゴを、いつの間にか口ずさんでいた経験はないでしょうか。大幸薬品の「正露丸」のラッパのメロディや、Intelの「インテル、入ってる」というサウンドロゴは、製品名や企業名を直接見聞きしなくても、音だけでブランドを即座に想起させる「サウンドトリガー」として機能しています。これは、視覚的なロゴマークと同じ、あるいはそれ以上に強力なブランド認知の手段です。
音は、視覚と違って意図的に目を逸らすことができず、受動的に情報を受け取ってしまう特性があります。この特性を活かし、様々な顧客接点でブランドサウンドに触れる機会を増やすことで、消費者の記憶にブランドを自然と刷り込み、認知度を飛躍的に向上させることが可能です。
| 聴覚情報の特性 | 記憶への影響と具体例 |
|---|---|
| 受動性と没入性 | 視線を向けなくても耳に入ってくるため、無意識に情報を刷り込める。店舗のBGMやアプリの効果音などが該当する。 |
| 感情喚起力 | 音楽や効果音は、喜びや安心感、興奮といった感情を直接的に引き起こしやすい。感情と結びついた記憶は忘れにくい。 |
| 反復性と記憶保持 | 短いメロディは口ずさみやすく、頭の中で繰り返される「イヤーワーム現象」を引き起こす。これにより、長期的な記憶定着が期待できる。 |
| 即時性 | 音は瞬時に脳に到達し、ブランドイメージを即座に伝えることができる。決済完了音などは、安心感を瞬時に提供する好例。 |
顧客ロイヤルティと信頼感の醸成
ソニックブランディングは、顧客との長期的な関係構築においても重要な役割を果たします。一貫性のあるブランドサウンドは、顧客がどのタッチポイントでブランドに接触しても「いつもの安心感」を提供し、信頼感を醸成します。
例えば、ある企業のウェブサイト、実店舗、コールセンターの保留音、製品の起動音などがすべてバラバラの印象だったらどうでしょうか。顧客は無意識のうちにブランドイメージの不一致を感じ、漠然とした不安を抱くかもしれません。逆に、すべての顧客接点で一貫したサウンドスケープ(音風景)が設計されていれば、顧客はブランドの世界観に安心して浸ることができます。
スターバックスが店舗で流す洗練されたBGMは、コーヒーの味だけでなく、「居心地の良いサードプレイス」というブランド体験そのものを演出し、多くのファンを惹きつけています。また、金融機関や航空会社のコールセンターで流れる落ち着いた保留音は、企業の信頼性や誠実さを音で表現し、顧客の待機中のストレスを和らげる効果があります。
このように、心地よい音の体験は顧客のポジティブな感情を喚起し、ブランドへの愛着(エンゲージメント)を深めます。細部にまでこだわった音の設計は、企業が顧客を大切にしている姿勢の表れと受け取られ、結果として強固な顧客ロイヤルティと信頼感の構築につながるのです。
他社との差別化と独自のブランド体験創出
製品やサービスのコモディティ化が進み、機能や価格だけでの差別化が困難な時代において、ソニックブランディングは競合との間に明確な差を生み出す有効な手段です。多くの企業が視覚的なブランディング(ロゴ、コーポレートカラーなど)に注力する一方で、聴覚へのアプローチはまだ未開拓な領域も多く、独自のポジションを築くチャンスが眠っています。
音は、ブランドが持つ世界観やパーソナリティを雄弁に物語ります。例えば、電気自動車(EV)はエンジン音がないため、各メーカーは人工的な走行音(車両接近通報音)の開発に力を入れています。中でもBMWは、映画音楽の巨匠ハンス・ジマー氏を起用し、ブランドスローガンである「駆けぬける歓び」を体現する先進的でエモーショナルなサウンドを開発しました。これは、単なる安全のための音に留まらず、BMWならではの運転体験という付加価値を創出し、他社EVとの強力な差別化を実現した事例です。
また、Mastercardが導入した決済音は、キャッシュレス決済が完了した際の「安心感」と「満足感」を顧客に提供します。この短いサウンドは、決済体験の質を高めると同時に、数ある決済ブランドの中でMastercardを際立たせる象徴的な音となっています。
視覚、触覚、嗅覚といった他の感覚と聴覚を組み合わせることで、ブランド体験はより立体的で没入感のあるものになります。他社には真似のできない「そのブランドだけの音」は、顧客の心に深く刻まれる無形の資産となり、市場における独自のブランド価値を確立するための強力な武器となるのです。
ソニックブランディングの作り方|5つの導入ステップを完全ガイド

ソニックブランディングは、単に耳心地の良い音楽を作るプロジェクトではありません。企業の根幹にあるブランド戦略と深く結びつき、顧客とのあらゆる接点で一貫した体験を創出するための戦略的プロセスです。
ここでは、成功するソニックブランディングを実現するための5つの導入ステップを、具体的なアクションとともに詳しく解説します。このステップを順に踏むことで、効果的かつ持続可能な「音の資産」を構築できるでしょう。
ステップ1|ブランド戦略の定義と音の方向性決定
ソニックブランディングの成否は、この最初のステップにかかっていると言っても過言ではありません。すべての音の土台となる、ブランドの「あるべき姿」を明確に定義することが最も重要です。感覚的に「かっこいい音」を目指すのではなく、論理的な裏付けを持って音の方向性を決定します。
ブランドアイデンティティの再確認
まず、自社のブランドアイデンティティを言語化し、関係者全員で共有します。以下の項目について、改めて深く掘り下げてみましょう。
- 企業理念・ビジョン・ミッション: 会社が何を目指し、社会にどのような価値を提供しようとしているのか。
- ブランドパーソナリティ: ブランドを「一人の人間」に例えた場合、どのような性格や個性を持っているか。(例:革新的、誠実、親しみやすい、洗練されている、情熱的など)
- ターゲット顧客像: どのような顧客に、どのような感情を抱いてもらいたいか。
- 提供価値: 製品やサービスを通じて顧客に提供している独自の価値は何か。
競合のサウンド分析
次に、競合他社がどのようなサウンドを使用しているかを調査・分析します。テレビCMのサウンドロゴ、WebサイトのBGM、アプリの通知音などをリサーチし、各社の音のポジショニングを把握します。これにより、自社が目指すべき独自のサウンドポジション、つまり他社との差別化ポイントが明確になります。
音の方向性の決定
ブランドアイデンティティと競合分析の結果を踏まえ、自社が目指す音の世界観(サウンドスケープ)を決定します。例えば、「先進的でクリーンなイメージ」を目指すなら電子音を基調としたミニマルなサウンド、「温かみと信頼感」を伝えたいならアコースティック楽器を中心としたオーガニックなサウンド、といった具体的な方向性を定めます。
ステップ2|サウンドコンセプトの策定
ステップ1で定めた抽象的な「方向性」を、より具体的な「音の設計図」へと落とし込むのがこのステップです。クリエイターが実際に音を制作するための指針となる、サウンドコンセプトを策定します。
サウンドDNAの定義
ブランドを象徴する核となる音の要素、すなわち「サウンドDNA」を定義します。これは、今後のあらゆるサウンド展開の基盤となる重要な要素です。
- メロディ: ブランドを象徴する短い旋律。
- リズム: ブランドの持つ躍動感や安定感を表現するリズムパターン。
- ハーモニー: ブランドの持つ雰囲気(明るい、重厚など)を決定づける和音。
- 音色(インストゥルメンテーション): 使用する楽器の種類(ピアノ、ギター、シンセサイザーなど)。
- テンポ: 曲の速さ。ブランドの持つスピード感を表現。
ムードボードの作成
音のイメージを関係者間で共有し、認識のズレを防ぐために「ムードボード」を作成します。目指す世界観に合った音楽、写真、映像、色、キーワードなどを集めたボードを作成することで、抽象的になりがちな音のイメージを視覚的・感覚的に共有し、具体的なクリエイティブへの橋渡しを行います。
ステップ3|サウンドロゴやブランドミュージックの制作
策定したサウンドコンセプトに基づき、いよいよ音を具現化していくクリエイティブなフェーズです。ここでは、ソニックブランディングの核となる代表的なサウンドアセットを制作します。
サウンドロゴ(サウンドアイコン)の制作
企業の顔となる最も重要な音です。テレビCMの最後やアプリの起動時などに使用される、1~3秒程度の短いメロディを制作します。NTTドコモの「♪NTTドコモ」や、インテルの「インテル、入ってる」のサウンドのように、一瞬でブランドを想起させ、記憶に強く残るキャッチーさが求められます。
ブランドミュージック(ブランドアンセム)の制作
サウンドロゴのメロディや世界観を数分程度の楽曲に展開したものです。WebサイトのBGM、コンセプトムービー、イベント会場など、より長い時間ブランドの世界観に浸ってもらいたい場面で使用されます。様々な用途に対応できるよう、ボーカル版、インスト版、ピアノソロ版など、複数のアレンジバージョンを制作することも有効です。これにより、シーンに応じた最適なブランド体験を提供できます。
UIサウンドの制作
アプリの通知音、ボタンのタップ音、決済完了音など、ユーザーインターフェース(UI)上で使用される効果音も、ブランド体験を構成する重要な要素です。サウンドロゴやブランドミュージックと一貫性のある音色やメロディを用いることで、デジタル上のあらゆる操作がブランド体験の一部となり、顧客との結びつきを強化します。
ステップ4|各タッチポイントへの展開とガイドライン作成
制作したサウンドアセットを、実際に顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)で効果的に活用していくフェーズです。一貫したブランドイメージを保つために、戦略的な展開とルール作りが不可欠です。
タッチポイントの洗い出しと実装
まず、自社と顧客との接点をすべて洗い出し、どのタッチポイントで、どのサウンドを、どのように使用するかを計画します。考えられるタッチポイントは多岐にわたります。
| カテゴリ | 具体的なタッチポイントの例 |
|---|---|
| 広告・マーケティング | テレビCM、ラジオCM、Web動画広告、YouTube、TikTok |
| デジタル | 公式Webサイト、スマートフォンアプリ(起動音、通知音)、製品(起動音、操作音) |
| リアル空間 | 店舗BGM、イベント・展示会、オフィスやショールームの環境音 |
| コミュニケーション | 電話の保留音、コールセンターのガイダンス、プレゼンテーション |
サウンドガイドラインの作成
制作したサウンドが、社内外で正しく、一貫性を持って使用されるためのルールブック「サウンドガイドライン」を作成します。これは、ブランドの音響資産価値を長期的に維持・向上させるための生命線となります。ガイドラインには、以下のような内容を明記します。
- サウンドコンセプトとサウンドDNAの定義
- 各サウンドアセット(サウンドロゴ、ブランドミュージック等)の正しい使用方法
- 各タッチポイントにおける具体的な使用規定
- 音量や再生タイミングの基準
- 改変や編集を禁止するなどの禁止事項(Don’ts)
- サウンドデータの管理方法と問い合わせ先
このガイドラインを関係部署や外部パートナーに共有・徹底することで、ブランドイメージの毀損を防ぎ、一貫した音の体験を創出できます。
ステップ5|効果測定と改善
ソニックブランディングは「作って終わり」ではありません。導入後、その効果を定期的に測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回していくことが重要です。これにより、投資対効果を可視化し、ブランド戦略の変化に合わせてサウンドを最適化していくことができます。
定量的評価
数値データに基づいて効果を客観的に評価します。
- ブランド認知度調査: サウンドロゴを再生し、ブランド名を正しく回答できる人の割合を導入前後で比較調査します。
- 広告効果測定: サウンドを使用した広告と使用しない広告で、視聴完了率やクリック率、ブランドリフト効果などを比較するA/Bテストを実施します。
- Web/アプリ分析: サウンドを実装したページの滞在時間やコンバージョン率の変化をトラッキングします。
定性的評価
顧客の感情や印象といった、数値では測れない質的な変化を評価します。
- アンケート・グループインタビュー: 顧客にサウンドを聞いてもらい、「先進的」「信頼できる」「親しみやすい」といったブランドパーソナリティが意図通りに伝わっているかをヒアリングします。
- ソーシャルリスニング: SNS上でブランドの音に関する消費者の声を収集・分析し、ポジティブ/ネガティブな反応を把握します。
これらの測定結果を基に、サウンドの活用方法を見直したり、新たなタッチポイントへの展開を検討したりと、継続的な改善活動を行います。市場や顧客の変化に対応しながらサウンドを育てていくことで、ソニックブランディングは真に価値のある経営資産となります。
ソニックブランディング制作の費用相場と依頼先の選び方
ソニックブランディングを自社に導入しようと検討する際、最も気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」「どこに依頼すれば良いのか」という点ではないでしょうか。費用は制作内容や依頼先によって大きく変動し、安易な依頼先選びはブランドイメージを損なうリスクも伴います。
ここでは、具体的な費用相場と、自社のブランド価値を最大化してくれるパートナー選びのポイントを詳しく解説します。
制作内容別の費用感
ソニックブランディングの制作費用は、サウンドロゴ単体の制作から、ブランドミュージック、サウンドスケープ(空間音響)の設計まで、その制作範囲とクオリティによって数十万円から数千万円以上と大きな幅があります。まずは、制作内容ごとの一般的な費用相場を把握しましょう。
| 制作内容 | 費用相場 | 主な内容と備考 |
|---|---|---|
| サウンドロゴ / ジングル | 30万円~300万円 | 企業の顔となる数秒の短い音。テレビCMやアプリ起動音などで使用。作曲家の知名度や修正回数、納品形式によって変動します。 |
| ブランドミュージック / ブランドアンセム | 100万円~1,000万円以上 | ブランドの世界観を表現する楽曲。Webサイト、イベント、動画コンテンツなど幅広く活用。生楽器のレコーディングや著名なアーティストを起用する場合は高額になります。 |
| Webサイト・アプリ用BGM/UIサウンド | 20万円~150万円 | Webサイトの背景音楽や、アプリの操作音(ボタンタップ音、通知音など)。ユーザー体験を向上させるための重要な要素です。 |
| 電話保留音 / ガイダンス音声 | 10万円~80万円 | ブランドミュージックをアレンジしたものや、ブランドイメージに合わせたオリジナルの音声。ナレーターのキャスティング費用も含まれます。 |
| 総合的なサウンドブランディング戦略策定 | 500万円~数千万円以上 | ブランド分析、サウンドコンセプト策定、各種サウンド制作、活用ガイドライン作成までを包括的にコンサルティング・制作するプランです。 |
上記の費用はあくまで目安です。最終的な見積もりは、プロジェクトの規模、音源の著作権の取り扱い(買取かライセンスか)、修正回数の上限、納品形式など、詳細な要件によって変動します。複数の制作会社から相見積もりを取り、内訳をしっかりと比較検討することが重要です。
制作会社選びで失敗しない3つのポイント
費用だけで依頼先を決めると、「イメージと違うものができた」「応用が利かない音源だった」といった失敗につながりかねません。長期的な視点でブランド価値を高めるためには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。ここでは、制作会社を選ぶ際に必ずチェックしたい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1|ブランド戦略への理解度と実績の確認
ソニックブランディングは、単に「かっこいい音楽」を作るプロジェクトではありません。最も重要なのは、企業の理念やビジョン、ターゲット顧客といったブランド戦略を深く理解し、それを音で表現できるかという点です。依頼を検討している会社の公式サイトで、過去の制作実績やポートフォリオを必ず確認しましょう。
その際、単に音源を聴くだけでなく、「どのような課題に対し、どのようなコンセプトでこの音を制作したのか」という背景やストーリーまで見ていくことが大切です。自社の業界や目指しているブランドイメージに近い実績があるか、多様なジャンルの音を制作できる表現力があるか、といった視点で評価しましょう。
ポイント2|透明性の高い制作プロセスとコミュニケーション体制
ブランドの根幹に関わる音作りは、制作会社と密な連携を取りながら進める必要があります。そのため、円滑なコミュニケーションが成功の鍵を握ります。初回のヒアリングからコンセプト提案、デモ制作、修正、納品までのプロセスが明確に提示されているかを確認してください。
特に、「誰が担当者になるのか」「定例会議の頻度はどれくらいか」「フィードバックの反映はどのように行われるのか」といった具体的なコミュニケーション体制は事前に確認しておくと安心です。また、見積もりの内訳が詳細で、追加料金が発生する条件などが契約前にクリアになっている、透明性の高い会社を選びましょう。
ポイント3|著作権や使用範囲など権利関係の明確化
制作した音源を様々な場面で安心して活用するためには、権利関係の整理が非常に重要です。後々のトラブルを避けるためにも、契約前に必ず確認すべき項目です。
具体的には、制作された音源の著作権(著作財産権)が自社に譲渡されるのか(買取)、それとも制作会社が保持したまま使用許諾(ライセンス)を受ける形なのかを明確にする必要があります。また、ライセンス契約の場合は、使用可能な媒体(テレビ、Web、イベントなど)、期間、地域などの範囲が定められています。将来的な事業展開も見据え、自社の利用目的に合った契約内容になっているか、著作権の取り扱いや二次利用の条件を必ず書面で確認してください。
まとめ
本記事では、ソニックブランディングの重要性から具体的な作り方までを解説しました。動画や音声コンテンツが多様化する現代において、音によるブランディングは顧客の記憶に深く刻まれ、信頼感を醸成する上で不可欠です。計画的な導入は、ブランド認知度の向上や他社との明確な差別化に繋がります。
ご紹介した5つのステップを参考に、戦略的にサウンドを設計・活用し、企業価値を飛躍的に高める独自のブランド体験を創出しましょう。