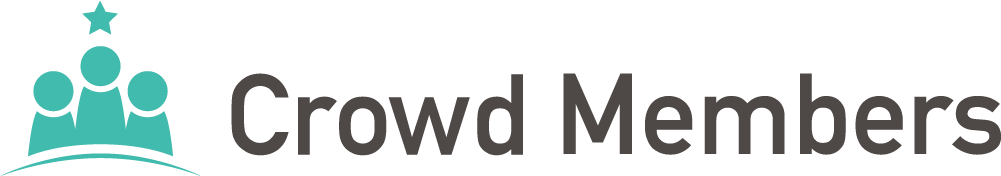まず知っておきたいカスハラの基礎知識

近年、顧客や取引先からの度を越したクレーム、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な社会問題となっています。従業員が安心して働ける環境を整備し、企業の持続的な成長を守るためにも、まずはカスハラの正しい知識を身につけることが不可欠です。
この章では、カスハラの定義から法的義務、そして放置した場合の甚大なリスクまで、対策を講じる上で必ず押さえておくべき基礎知識を解説します。
カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義とは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからのクレームや言動のうち、その要求内容が妥当性を欠いていたり、要求を実現するための手段や態度が社会通念上、不相当であったりして、従業員の就業環境を害する行為を指します。厚生労働省は、この定義を明確に示しており、企業はこれに基づいた対策が求められます。
重要なのは、正当なクレームと悪質なカスハラを明確に線引きすることです。商品やサービスに対する正当な意見や改善要求は、企業にとって貴重なフィードバックです。しかし、それが従業員の人格を否定する暴言や、理不尽な要求に変わったとき、それは断固として対応すべきハラスメント行為となります。
具体的にどのような行為がカスハラに該当するのか、また正当なクレームとはどう違うのかを以下の表で確認しましょう。
| 比較項目 | 正当なクレーム | カスタマーハラスメント(カスハラ) |
|---|---|---|
| 目的 | 商品・サービスの不具合や接客態度の改善、正当な交換・返金など、問題の解決を目的とする。 | 従業員を困らせること、精神的苦痛を与えること、過剰な金銭やサービスを不当に得ることなどが目的。 |
| 要求内容 | 事実に基づいた、社会通念上妥当な範囲での要求。 | 事実に基づかない、または過剰で理不尽な金銭要求、土下座の強要、解雇の要求など。 |
| 手段・態様 | 冷静かつ論理的な話し合い。 | 暴言、暴力、脅迫、威嚇、大声での罵倒、長時間の拘束、執拗な電話やメール、SNSでの誹謗中傷など。 |
| 結果 | 問題が解決し、企業のサービス向上に繋がる可能性がある。 | 従業員の心身に深刻なダメージを与え、企業の生産性を著しく低下させる。 |
法律で定められた企業のカスハラ対策義務
カスハラ対策は、単なる努力目標や福利厚生の一環ではありません。企業が果たすべき法的な義務として明確に位置づけられています。この法的背景を理解することは、対策の重要性を認識する上で極めて重要です。
主な法的根拠は以下の2つです。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく措置義務
2020年6月(中小企業は2022年4月)に改正・施行された労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」では、事業主に対してパワーハラスメント対策を義務付けています。この指針の中で、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関しても、事業主が従業員を守るために相談体制の整備や被害者への配慮など「講ずることが望ましい取組」が示されました。具体的には、以下のような体制整備が求められています。
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応など)
- カスハラ防止のための研修など、再発防止に向けた取組
労働契約法に基づく安全配慮義務
労働契約法第5条では、企業(使用者)は従業員(労働者)がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負うと定められています。カスハラによって従業員の心身の健康が脅かされる状況を放置することは、この安全配慮義務違反に問われる可能性があります。万が一、従業員が精神疾患を発症したり、退職に追い込まれたりした場合、企業が損害賠償責任を負うリスクもあるのです。
カスハラがもたらす企業と従業員への悪影響
カスハラを「一部の悪質な顧客の問題」として軽視し、対策を怠ると、従業員個人だけでなく企業全体に深刻な悪影響が及びます。そのリスクは多岐にわたり、放置すればするほど企業の経営基盤を揺るがしかねません。
従業員への悪影響
カスハラの直接的な被害者となる従業員には、心身ともに甚大なダメージがもたらされます。
- メンタルヘルス不調:暴言や威圧的な態度に晒され続けることで、ストレスが増大し、うつ病、適応障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症するリスクが高まります。
- モチベーションの低下:理不尽な要求や人格否定に疲弊し、仕事への意欲や誇りを失います。これにより、接客サービスの質が低下するという悪循環に陥ることもあります。
- 離職率の増加:「会社が守ってくれない」という不信感から、優秀な人材が次々と離職してしまいます。特に顧客対応の最前線に立つ従業員の離職は、組織にとって大きな損失です。
企業への悪影響
従業員が受けるダメージは、巡り巡って企業経営に大きな打撃を与えます。
- 生産性の低下:従業員のパフォーマンス低下や休職・離職は、組織全体の生産性を著しく下げます。カスハラ対応に時間を取られることで、本来の業務が滞ることも少なくありません。
- ブランドイメージの毀損:SNSの普及により、カスハラの様子が録音・録画され、瞬く間に拡散されるリスクがあります。「従業員を守れない企業」「トラブルの多い店」といったネガティブな評判は、企業のブランド価値を大きく傷つけます。
- 採用コストの増大:離職率の高さは、新たな人材を採用・育成するためのコストを増大させます。また、悪い評判が広がると、人材採用そのものが困難になる可能性もあります。
- 法的リスクの発生:前述の通り、安全配慮義務違反として従業員から損害賠償請求訴訟を起こされるリスクがあります。
このように、カスハラは従業員個人の問題ではなく、組織の存続に関わる重大な経営課題です。見て見ぬふりをせず、組織全体で毅然と立ち向かう体制を構築することが、今まさに求められています。
カスハラ発生前に企業が準備すべき対策ガイド

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、発生してから対応するのでは手遅れになるケースが少なくありません。従業員の心身の健康を守り、企業のブランドイメージや健全な経営を維持するためには、問題が発生する前の「予防」と「準備」が極めて重要です。ここでは、すべての企業が取り組むべき、カスハラ発生前の具体的な対策を3つのステップで詳しく解説します。
対策の第一歩:基本方針の策定と社内周知
カスハラ対策の基盤となるのが、企業としての明確な「基本方針」です。これは、組織としてカスハラを許さず、従業員を断固として守るという姿勢を内外に示すためのものです。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」でも、この方針の策定と周知が最初のステップとして推奨されています。
基本方針には、主に以下の要素を盛り込むことが効果的です。
- トップメッセージの発信:代表取締役など経営トップの名前で、「当社はカスタマーハラスメントを容認しません」という強いメッセージを発信します。これにより、全社的な取り組みであるという本気度が伝わります。
- カスハラに対する企業の姿勢:顧客と従業員の双方の人権を尊重し、安全で健全な労働環境の維持に努めることを明記します。
- カスハラの定義と具体例:どのような行為が自社におけるカスハラに該当するのかを具体的に示し、社内での認識を統一します。
- 従業員への約束:「一人で抱え込まずに相談してください」「会社があなたを守ります」といったメッセージを伝え、従業員が安心して働ける心理的安全性を提供します。
- お客様へのお願いと注意喚起:公式サイトや店舗内での掲示を想定し、従業員への配慮を求めるとともに、迷惑行為に対してはサービス提供の中止や警察への通報等の措置を取る可能性があることを伝えます。
そして最も重要なのは、策定した方針を全従業員に徹底的に周知することです。社内イントラネットへの掲載、ポスターでの掲示、朝礼での読み上げ、入社時研修での説明など、あらゆる機会を通じて繰り返し伝え、方針を「絵に描いた餅」で終わらせないようにしましょう。
実践的な対応マニュアルの作成方法
基本方針で企業の姿勢を示した後は、現場の従業員が実際に行動するための具体的な指針となる「対応マニュアル」を作成します。マニュアルの目的は、対応の属人化を防ぎ、組織として一貫した毅然とした対応を取ることにあります。また、従業員にとっては、不測の事態に陥った際に冷静に行動するための「お守り」のような存在にもなります。
マニュアルには、以下の項目を網羅的に盛り込むことが望ましいです。誰が読んでも理解できるよう、抽象的な表現は避け、具体的な行動レベルまで落とし込んで記述することが成功の鍵です。
| 項目 | 記載すべき内容のポイント |
|---|---|
| 1. 基本的な心構え | まずは冷静に、お客様の話をさえぎらずに聴く「傾聴」の姿勢を基本とすることを明記します。ただし、相手の言いなりになることではないと伝えます。 |
| 2. カスハラの判断基準 | どのような言動が「正当なクレーム」の範囲を超え、「カスハラ」に該当するかの具体的な基準(例:暴言、威嚇、長時間の拘束など)を定義します。 |
| 3. 対応フロー | 「初期対応(一次対応)」→「上長への報告・相談」→「責任者による対応(二次対応)」→「組織としての最終対応」といった、段階的な対応の流れを明確にします。 |
| 4. 状況別の具体的対応 | 「対面」「電話」「メール・SNS」など、発生チャネルごとの具体的な対応手順や注意点を記載します。特に電話対応では、効果的な切り上げ方も示します。 |
| 5. 記録の徹底 | 「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」の5W1Hに沿って、客観的な事実を時系列で記録する方法を定めます。録音・録画の案内方法なども含めます。 |
| 6. 社内の相談・報告ルート | トラブル発生時に誰に、どのように報告・相談すればよいのか、具体的な部署名や担当者名、連絡先を明記したフローチャートを用意します。 |
| 7. 外部機関との連携 | 警察、弁護士、産業医など、必要に応じて相談・連携すべき外部機関の連絡先と、連携する際の判断基準を記載します。 |
マニュアルは一度作成して終わりではありません。実際に発生した事例をもとに内容を定期的に見直し、より実践的なものへとアップデートしていくプロセスが不可欠です。
従業員を守るための研修と教育体制
基本方針を定め、マニュアルを作成しても、それだけで従業員が適切に対応できるわけではありません。知識をスキルとして定着させ、いざという時に自信を持って行動できるようにするためには、継続的な研修と教育が不可欠です。
研修は、知識をインプットする「座学」と、実践的なスキルを身につける「演習」を組み合わせて行うのが効果的です。
知識研修(座学)
全従業員を対象に、カスハラに関する基本的な知識を共有します。自社の方針やマニュアルの内容を改めて解説し、カスハラが対応した従業員の心身にどのような影響を与えるかといったメンタルヘルスの観点も盛り込むことで、他人事ではなく自分事として捉えてもらうきっかけになります。
スキル研修(実践演習)
カスハラ対策において最も効果が高いとされるのが、実際の場面を想定したロールプレイング形式の研修です。研修担当者が「大声で怒鳴る顧客」「理不尽な要求を繰り返す顧客」などの役を演じ、参加者はマニュアルに沿って対応する訓練を行います。この訓練を通じて、以下のスキルを体感的に習得できます。
- 冷静さを保ちながら相手の話を聴く「傾聴スキル」
- 威圧的な相手に対し、敬意を払いながらも毅然と断る「アサーティブコミュニケーション」
- 一人で抱え込まず、適切なタイミングで上長に助けを求める「エスカレーションの判断力」
また、研修は役職や立場に応じて内容を最適化することも重要です。一般従業員には初期対応を中心とした内容を、管理者層には部下からの報告を受けた後の対応、従業員のメンタルケア、組織としての意思決定といった、より高度な内容を盛り込みます。
研修の最終的なゴールは、完璧な対応ができる従業員を育てることではなく、組織全体で従業員を守るという共通認識を醸成し、その体制を強固にすることにあります。一度きりで終わらせず、定期的に実施することで、カスハラに強い組織文化を構築していきましょう。
【現場向け】状況別カスハラ対応マニュアル

この章では、従業員が現場で実際にカスタマーハラスメント(カスハラ)に遭遇した際の具体的な対応方法を、状況別に詳しく解説します。いかなる状況でも、従業員自身の安全と心の健康を守ることが最優先です。一人で抱え込まず、組織全体で対応するための実践的な手順を身につけましょう。
初期対応:冷静な状況把握と傾聴
カスハラ対応の成否は、最初の対応(初期対応)で大きく左右されます。相手の感情的な言動に引きずられず、冷静に対応することが極めて重要です。まずは落ち着いて、以下のステップを実践してください。
ステップ1:安全な場所への誘導と複数名での対応
お客様が興奮している場合、まず周囲の他のお客様への影響と、従業員の安全を確保します。「恐れ入ります、他のお客様もいらっしゃいますので、あちらで詳しくお話を伺ってもよろしいでしょうか」と伝え、会議室や応接スペースなど、少し離れた場所に移動していただきます。この際、密室は避け、必ず上司や他の従業員と共に複数名で対応することを徹底してください。一人で対応することは、身の危険や精神的負担を増大させる原因となります。
ステップ2:傾聴と事実確認
相手の話を遮らず、まずは真摯に耳を傾ける「傾聴」の姿勢が基本です。ただし、これは相手の言い分をすべて受け入れることではありません。目的は、感情的な部分と事実関係を切り分け、何が問題となっているのかを正確に把握することです。
- 相槌を打つ:「はい」「さようでございますか」といった相槌で、話を聞いている姿勢を示します。
- 共感を示す:「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」など、相手の感情に対して共感の意を示します。ただし、非がない点について安易に謝罪しないよう注意が必要です。
- 事実を整理する:5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、具体的な事実関係をメモを取りながら確認します。
ステップ3:安易な約束や即答を避ける
その場で解決できない要求や、判断に迷う内容については、「確認して、後ほど改めてご連絡いたします」「社内で検討させていただきます」などと伝え、安易な約束や即答は絶対に避けてください。不用意な言質は、さらなるトラブルの原因となります。
対応をエスカレーションする判断基準
一担当者の裁量を超える、または対応が困難だと判断した場合は、速やかに上司や専門部署に対応を引き継ぐ「エスカレーション」が必要です。迅速かつ的確なエスカレーションは、従業員を守り、問題を深刻化させないために不可欠です。以下の基準に一つでも該当する場合は、ためらわずにエスカレーションを行ってください。
| 判断カテゴリ | 具体的な状況 |
|---|---|
| 顧客の言動 | 暴言、人格を否定する言葉、脅迫、威嚇、大声で怒鳴り続けるなど、従業員が恐怖を感じる言動。 |
| 要求の内容 | 金銭の不当要求、土下座の強要、解雇要求、会社のルールを逸脱した特別扱いの要求など、社会通念上相当性を欠く要求。 |
| 拘束時間 | 1時間を超えるなど、長時間にわたり従業員を拘束する行為。何度も執拗に電話をかけてくる行為。 |
| 暴力・破壊行為 | 物を叩く、蹴る、投げつけるなどの器物損壊行為。従業員に掴みかかる、殴るなどの暴力行為、またはそれを示唆する言動。 |
| 担当者の心身状態 | 担当者が強い恐怖や精神的苦痛を感じ、正常な判断ができない状態に陥った場合。 |
エスカレーションする際は、「少々お待ちください。責任者と代わります」と相手に伝え、冷静に状況を上司に報告しましょう。引き継ぎ時には、これまでの経緯や顧客の要求内容を正確に伝えることが重要です。決して一人で問題を抱え込まないでください。
対面でのカスハラ対策と具体的な対応フロー
店舗や窓口など、顧客と直接顔を合わせる場面での対応は、特に慎重さが求められます。身の安全を確保しつつ、組織として毅然と対応するためのフローを解説します。
対応フロー
- 初期対応と場所の移動:まずは前述の初期対応を行い、周囲から隔離された応接スペースなどに誘導します。
- 複数名での対応開始:必ず上司や同僚に同席してもらい、2名以上で対応します。役割(主に対応する人、記録を取る人など)を分担すると効果的です。
- 事実確認と要求内容のヒアリング:冷静に相手の主張を聞き、事実関係と要求内容を明確にします。録音の許可を得られる場合は、ICレコーダーなどで記録を残すことも有効です。
- 会社としての方針を提示:ヒアリングした内容に基づき、会社として「できること」と「できないこと」を明確に伝えます。「規定により、そのご要望にはお応えいたしかねます」’mark>のように、個人ではなく組織としての方針であることを強調します。
- 退去勧告と警察への通報:不当な要求を繰り返し、退去に応じない場合は、「これ以上の対応は致しかねます。お引き取りいただけない場合は、やむを得ず警察に通報いたします」と最終警告を行います。それでも居座る場合は、ためらわずに110番通報してください。従業員の安全確保が最優先です。
電話でのカスハラ対策と効果的な切り上げ方
コールセンターなどでの電話対応は、相手の顔が見えない分、暴言などがエスカレートしやすい傾向にあります。通話録音の活用と、毅然とした態度での切り上げ方が重要になります。
事前準備:通話録音の実施と事前アナウンス
電話対応では、通話録音システムの導入が非常に有効です。「この通話は、応対品質の向上と内容の正確な把握のため、録音させていただいております」というアナウンスを流すことで、悪質なクレームの抑止力となります。また、録音データは後のトラブル解決において重要な証拠となります。
効果的な切り上げまでのステップ
- 傾聴と事実確認:対面時と同様に、まずは相手の言い分を冷静に聞きます。
- 保留の活用:相手が興奮している場合や、即答が難しい場合は、「確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」と伝え、一度保留にします。この時間で自分自身の気持ちを落ち着かせ、上司に相談することができます。
- 終了の事前通告(警告):話が平行線をたどる、同じ内容の繰り返しになる、暴言が続くといった場合は、「誠に恐縮ですが、これ以上お話が続きますようでしたら、お電話を切らせていただく場合がございます」と、明確に終了の可能性を伝えます。
- 最終通告と電話の終了:それでも状況が改善しない場合は、「大変申し訳ございませんが、先ほどお伝えしました通り、これ以上の対応はいたしかねますので、お電話を切らせていただきます。失礼いたします」と最終通告し、静かに受話器を置きます。相手が話し続けていても、引き延ばす必要はありません。
メールやSNSでのカスハラ対策と証拠保全
メールやSNSを通じたテキストベースのカスハラは、24時間いつでも届く可能性があり、また、インターネット上で拡散されるリスクもはらんでいます。冷静な対応と、証拠を確実に保全することが極めて重要です。
対応の基本原則
- 即時返信は避ける:感情的なメールを受け取っても、すぐに返信してはいけません。一晩置くなど、時間をおいて冷静に内容を分析し、複数名で対応を協議してから返信を作成します。
- 組織として対応する:担当者個人の名前やメールアドレスで返信するのではなく、「〇〇株式会社 お客様相談室」のように、必ず組織として公式に対応します。これにより、個人的な攻撃の対象になることを防ぎます。
- 事実に基づき簡潔に返信する:相手の感情的な表現には触れず、事実関係と会社の見解のみを、丁寧かつ簡潔に記載します。不要な謝罪や反論は新たな火種になるため避けてください。
最も重要な証拠保全の方法
メールやSNS上でのやり取りは、それ自体が法的な証拠となり得ます。悪質なケースでは、弁護士や警察に相談する必要が出てくるため、以下の方法で確実に証拠を保全してください。
- メール:受信したメールのヘッダー情報(送信元IPアドレスなどが含まれる)を含めて、全文を印刷またはPDF形式で保存します。
- SNS(X(旧Twitter)、Instagramなど):誹謗中傷の投稿やダイレクトメッセージは、必ずスクリーンショットで保存します。その際、投稿内容だけでなく、相手のアカウント名、URL、投稿日時がすべて写るように撮影することが重要です。
- ウェブサイト・ブログ:悪質な書き込みがされたページ全体をPDFで保存するか、ページ全体のスクリーンショットを撮影します。URLと日時がわかるように記録してください。
これらの証拠は、発信者情報開示請求や損害賠償請求、警察への被害届提出の際に不可欠なものとなります。少しでも悪質だと感じたら、すぐに保全する習慣をつけましょう。
【例文テンプレート集】そのまま使えるカスハラ対策フレーズ

現場でカスタマーハラスメント(カスハラ)に直面した際、冷静かつ毅然とした態度で対応するためには、事前に「何を言うか」を決めておくことが極めて重要です。
この章では、様々な状況でそのまま使える具体的なフレーズをテンプレートとしてご紹介します。クッション言葉を効果的に使い、相手を不必要に刺激せず、かつ企業の意思を明確に伝えるための会話術を身につけましょう。
不当な要求を丁寧に断るための例文
金銭の過剰要求、規定外のサービス強要、土下座の要求など、企業のルールや社会的相当性を逸脱した要求には、毅然と「できない」と伝える必要があります。その際、感情的にならず、会社の「規定」や「他のお客様との公平性」を理由にすることで、担当者個人の判断ではないことを示し、相手の矛先が個人に向かうのを防ぎます。
| 状況 | 対応のポイントと例文 |
|---|---|
| 過剰な値引きや金銭の要求 | ポイント:規定を理由に、特別扱いはできないことを明確に伝えます。公平性の観点から断ることが有効です。 例文: |
| 理不尽な返品・交換の要求 | ポイント:返品・交換ポリシーを根拠に、客観的な事実として対応できないことを説明します。 例文: |
| 土下座などの謝罪強要 | ポイント:謝罪の意は示しつつも、社会通念上、相当性を欠く行為には応じられないことをはっきりと伝えます。 例文: |
| 規定外のサービス提供の強要 | ポイント:サービス範囲を明確に線引きし、代替案が提示できる場合はそちらを案内します。 例文: |
威圧的な言動を制止するための警告フレーズ
大声、暴言、脅迫、人格否定といった威圧的な言動に対しては、段階的に警告を発し、エスカレートを防ぐことが重要です。まずは冷静になるよう促し、それでも収まらない場合は、その行為が「ハラスメント」にあたることを指摘し、最終的には警察への通報も辞さないという強い姿勢を示す必要があります。
| 警告レベル | 目的と具体的なフレーズ |
|---|---|
| ステップ1:冷静になるよう促す | 目的:相手の興奮を鎮め、話し合いが可能な状態にすることを目指します。 フレーズ例: |
| ステップ2:行為の中止を明確に要求する | 目的:相手の言動が許容できないものであることを明確に伝え、中止を求めます。 フレーズ例: |
| ステップ3:対応の打ち切りと外部機関への通報を予告する | 目的:最終警告として、これ以上の迷惑行為は受け入れず、組織として然るべき対応を取ることを通告します。 フレーズ例: |
電話を終了させたいときの切り上げトーク例
同じ内容の繰り返しや、長時間にわたる電話での拘束は、従業員の心身を疲弊させ、業務を著しく妨げます。相手の感情を逆なでしないよう配慮しつつも、明確な理由を添えて電話を終了させるためのフレーズを用意しておくことが肝心です。
| 状況 | 対応のポイントと切り上げトーク例 |
|---|---|
| 同じ主張の繰り返しで進展がない | ポイント:これ以上話しても結論は変わらないことを伝え、区切りをつけます。 トーク例: |
| 長時間にわたり電話が終わらない | ポイント:社内ルールや物理的な時間の制約を理由に、終了を予告し、実行します。 トーク例: |
| 無関係な話や世間話が続く | ポイント:本題に戻るよう促し、それでも続く場合は対応範囲外であることを伝えます。 トーク例: |
| 最終手段としての強制終了 | ポイント:何度注意しても暴言や長電話が終わらない場合の最終手段です。終了を明確に宣言してから電話を切ります。 トーク例: |
カスハラ発生後の重要なアフターケアと再発防止策

カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応は、顧客とのやり取りが終了した時点で終わりではありません。むしろ、その後の対応こそが、従業員を守り、企業のリスクを管理し、より安全な職場環境を構築するための鍵となります。対応した従業員への精神的なケアと、組織全体で取り組む再発防止策は、いわば車の両輪です。
この章では、カスハラ発生後に企業が取り組むべき具体的なアフターケアと、未来の被害を防ぐための仕組みづくりについて詳しく解説します。
対応した従業員のメンタルヘルスケア
カスハラは、対応した従業員の心に深刻なダメージを与える可能性があります。理不尽な要求や暴言に長時間さらされることで、強いストレスや恐怖を感じ、自信を喪失したり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したりするケースも少なくありません。企業には、従業員が安心して働き続けられるよう、心身の健康を守るためのケア体制を整備する責任があります。
直後のケア:一次対応者の役割
まず重要なのは、カスハラ対応直後の迅速なケアです。対応を終えた従業員を一人にせず、上司や管理職がすぐに声をかけ、安全な場所で話を聞く時間を取りましょう。
このとき、対応の是非を問うのではなく、まずは従業員の心に寄り添い、「大変だったね」「つらかったね」と共感を示すことが大切です。何があったのかを冷静にヒアリングし、従業員が「自分の対応が悪かったのではないか」と自責の念に駆られないよう、「あなたは一人ではない」「会社がしっかり守る」というメッセージを明確に伝えてください。従業員の功績を認め、肯定的なフィードバックを行うことで、精神的な孤立を防ぎます。
継続的なサポート体制の構築
一度きりの面談だけでなく、継続的なサポート体制を構築することが不可欠です。以下のような多角的なアプローチで、従業員のメンタルヘルスを支えましょう。
- 定期的な面談の実施:カスハラ対応後、1週間後、1ヶ月後など、定期的に上司が面談を行い、心身の状態に変化がないかを確認します。
- 専門家との連携:産業医や保健師、社内にいる場合はカウンセラーとの面談を設定し、専門的な視点からケアを行います。従業員が直接相談しにくい場合でも、企業側から連携を促すことが重要です。
- ストレスチェック制度の活用:定期的なストレスチェックを通じて、高ストレス状態にある従業員を早期に発見し、医師による面接指導などの適切な措置につなげます。
- 外部相談窓口(EAP)の案内:社内の人間には話しにくいと感じる従業員のために、外部の専門機関が提供するEAP(従業員支援プログラム)を導入・案内することも非常に有効です。匿名で相談できるため、従業員は安心して利用できます。
万が一、不眠や食欲不振、気分の落ち込みなどが続く場合は、専門の医療機関への受診を促すことも必要です。その際は、プライバシーに最大限配慮し、本人の意思を尊重した上でサポートしてください。
組織で情報を共有し再発を防ぐ仕組みづくり
発生したカスハラ事案を個別の問題として終わらせてしまうと、同様のケースが何度も繰り返されることになります。一件一件の事例を組織全体の教訓として蓄積し、再発防止策に繋げる仕組みづくりが、企業の危機管理能力を高めます。
対応記録の作成と一元管理
カスハラが発生したら、必ず詳細な記録を残しましょう。客観的な事実を記録することは、後の対応や法的措置を検討する上で極めて重要な証拠となります。記録すべき項目は以下の通りです。
| 記録項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 発生日時 | 年月日、曜日、時間(例:2023年10月26日(木) 14:30頃) |
| 発生場所 | 店舗名、部署名、電話、メールなど(例:〇〇支店 窓口カウンター) |
| 顧客情報 | 氏名、連絡先など、把握できている範囲の情報 |
| ハラスメントの内容 | 暴言、威圧、脅迫、不当な要求などの具体的な言動を時系列で記述。「バカヤロー」などの発言はそのまま記載する。 |
| 対応者 | 初期対応者、二次対応者など、関わった従業員の氏名 |
| 対応の経緯 | どのような説明をし、どのような対応を行ったかを具体的に記録する。 |
| 結果・解決状況 | 要求に応じたか、断ったか、警察に通報したかなど、最終的な顛末を記載。 |
| 従業員の心身への影響 | 対応した従業員の精神的・身体的な状態について記録する。 |
これらの記録は、コンプライアンス部門や人事部などで一元管理し、個人情報保護に配慮しながら、必要な範囲で共有できる体制を整えることが望ましいです。顧客管理システム(CRM)などを活用し、特定の顧客情報にフラグを立てるなどの対策も有効です。
事例分析と対応マニュアルの見直し
蓄積された事例は、定期的に分析し、対策に活かす必要があります。関係部署の担当者を集めて事例検討会などを開催し、「今回の対応の良かった点・改善点」「マニュアル通りに対応できたか」「マニュアルに不足はなかったか」などを議論します。このプロセスを通じて、現場の実情に即した、より実践的な対応マニュアルへと継続的にアップデートしていくことが可能です。改訂したマニュアルは、全従業員に周知し、ロールプレイングなどの研修を通じて浸透させるサイクルを確立しましょう。
警察や弁護士など外部機関への相談
従業員の安全確保や企業の利益保護のためには、社内での対応に固執せず、ためらわずに外部の専門機関を頼ることが重要です。特に、事態が悪質・深刻な場合には、迅速な相談が被害の拡大を防ぎます。
相談を検討すべきケースの具体例
どのような場合に警察や弁護士に相談すべきか、判断に迷うこともあるでしょう。以下の表を参考に、状況に応じた適切な相談先を選択してください。
| 相談先 | 相談を検討すべきケースの具体例 |
|---|---|
| 警察 |
これらの行為は明確な犯罪であり、緊急性が高い場合は迷わず110番通報してください。緊急性がない場合でも、証拠を持って最寄りの警察署に相談したり、警察相談専用電話「#9110」に電話したりすることで、今後の対応について助言を得られます。 |
| 弁護士 |
平時から顧問弁護士と契約しておくことで、有事の際に迅速かつ的確なアドバイスを受けることができます。顧問弁護士がいない場合は、法テラス(日本司法支援センター)や各地域の弁護士会に相談することも可能です。 |
外部機関との連携は、従業員に「会社が本気で守ってくれる」という安心感を与え、企業としての社会的責任を果たす上でも不可欠な対応と言えるでしょう。
まとめ
カスハラ対策は、今や企業の社会的責任であり、従業員を守るための必須事項です。厚生労働省が示す指針の通り、企業には対策を講じる義務があります。
本記事で解説したように、対策の鍵は「事前準備」「現場対応」「事後ケア」の3つの柱を組織的に実行することです。明確な方針とマニュアルを整備し、従業員が安心して対応できる体制を構築することが、企業と従業員双方を守ることに繋がります。
本ガイドを参考に、カスハラに毅然と対応して健全な職場環境を築きましょう。