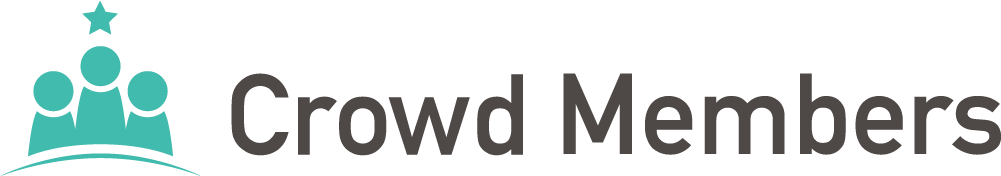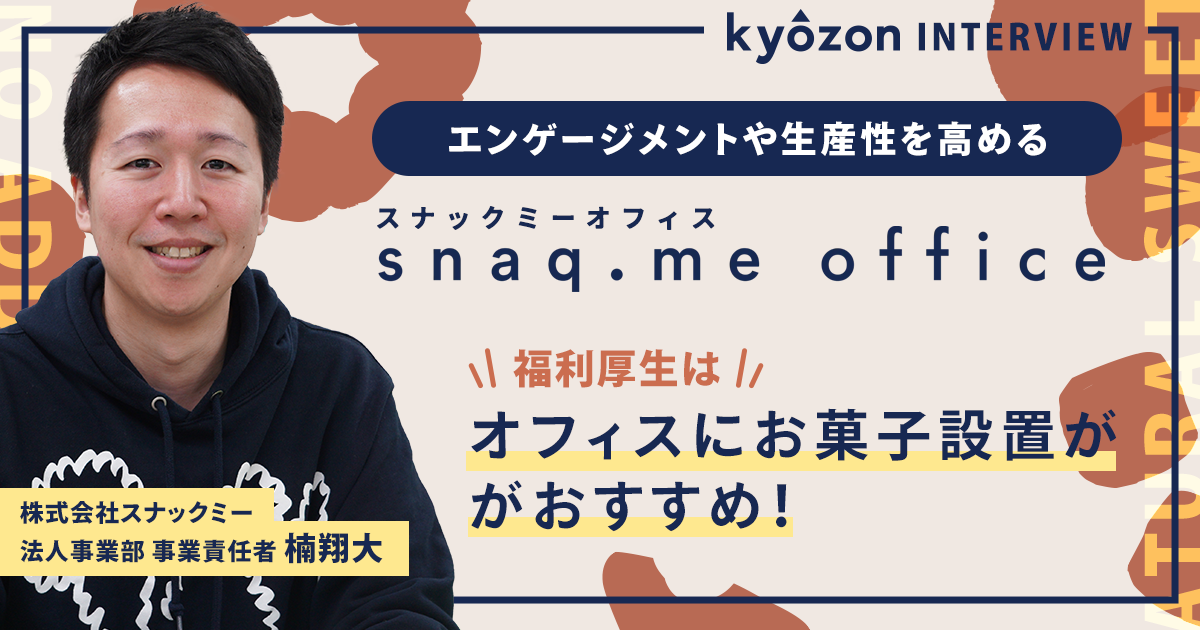内定後のキャリア相談会の必要性

近年、多くの企業が内定者フォローの一環として「キャリア相談会」に注目しています。かつての内定者懇親会のような形式的なイベントとは一線を画し、内定者一人ひとりのキャリア観に寄り添うこの取り組みは、なぜ今、これほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、深刻化する内定辞退の問題と、現代の若者、特にZ世代の特有の価値観が存在します。
高まる内定辞退率とZ世代のキャリア観
まず、企業が直面している喫緊の課題が、高止まりする内定辞退率です。売り手市場が続く昨今の採用活動において、複数の内定を保持する学生は珍しくありません。株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表した「就職プロセス調査」によると、近年、内定辞退率は高い水準で推移しており、多くの企業が内定者の確保に苦心している実態が浮き彫りになっています。
この背景には、Z世代と呼ばれる若者たちのキャリアに対する価値観の変化が大きく影響しています。終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、彼らは会社にキャリアを委ねるのではなく、自らの手でキャリアを築いていく「キャリア自律」の意識を強く持っています。企業選びにおいても、安定性や知名度だけでなく、「その会社で何ができるか」「どう成長できるか」を非常に重視する傾向があります。
| 価値観 | 具体的な内容 |
|---|---|
| キャリア自律 | 会社に依存せず、自身の市場価値を高め、主体的にキャリアを形成したいという意識。転職や副業もキャリアの選択肢として捉える。 |
| 成長実感の重視 | 日々の業務を通じて、スキルアップや自己成長を実感できる環境を求める。挑戦の機会やフィードバックの文化を重視する。 |
| 働きがいの追求 | 単に給与を得るためだけでなく、企業のパーパス(存在意義)や社会貢献性に共感し、自らの仕事に意義を見出したいと考える。 |
| 透明性と納得感 | 口コミサイトやSNSでリアルな情報を収集し、入社後のギャップを極端に嫌う。配属や業務内容について、透明性の高い説明と納得感を求める。 |
このような価値観を持つZ世代にとって、内定はゴールではなく、あくまでキャリア形成のための一つの選択肢です。そのため、内定後も自身のキャリアプランと照らし合わせ、「本当にこの会社で良いのか」と自問自答を続けます。この期間に生じる不安や疑問を解消できなければ、より魅力的に映る他社へ心が傾き、最終的に内定辞退という決断に至ってしまうのです。
内定者フォローとしてのキャリア相談会の役割
こうした状況下で、内定後のキャリア相談会は、従来の画一的な内定者フォローとは異なる重要な役割を担います。それは、内定者一人ひとりが抱える「キャリアへの不安」に寄り添い、企業と内定者の相互理解を深める対話の場を提供するという役割です。
内定者は、内定を得た喜びと同時期に、「内定ブルー」とも呼ばれる様々な不安を抱えています。
- 「この会社で自分の理想のキャリアパスを歩めるだろうか?」
- 「入社後、具体的にどのようなスキルが身につき、成長できるのだろうか?」
- 「希望する部署に配属されなかったらどうしよう…」
- 「職場の人間関係に馴染めるだろうか?」
キャリア相談会は、こうした内定者の漠然とした不安に対し、先輩社員との対話を通じて、入社後の働き方やキャリアステップを具体的にイメージさせる絶好の機会となります。選考過程では伝えきれなかった企業の魅力や、現場で働く社員のリアルな声を届けることで、内定者の企業理解を深め、働くことへの納得感を醸成します。
単なる情報提供の場に留まらず、内定者のキャリア観や価値観に真摯に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを図ること。それこそが、希薄になりがちな内定期間中の関係性を強化し、内定者のエンゲージメントを高める鍵となります。結果として、キャリア相談会は内定辞退を防ぐだけでなく、入社後のミスマッチを低減させ、早期離職の防止にも繋がる極めて戦略的な人事施策と言えるのです。
内定者キャリア相談会を実施する3つのメリット

内定者フォローの施策は数多くありますが、その中でもキャリア相談会はなぜ重要なのでしょうか。ここでは、企業が内定者向けのキャリア相談会を実施することで得られる3つの大きなメリットを、具体的な理由とともに詳しく解説します。
内定辞退の防止に繋がる
最大のメリットは、内定辞退の防止に直接的な効果が期待できることです。内定承諾後も、学生は「本当にこの会社で良いのだろうか」「もっと自分に合う企業があるのではないか」といった不安、いわゆる「内定ブルー」に陥りがちです。特に、複数の内定を保持している学生は、入社を決断する最後の最後まで迷っています。
キャリア相談会は、こうした内定者の揺れ動く心に寄り添い、不安を解消する絶好の機会です。先輩社員が自身の経験を交えながら、入社後のキャリアパスや成長できる環境について具体的に語ることで、内定者は自社で働く未来をより鮮明にイメージできるようになります。一方的な説明会とは異なり、対話を通じて個々の疑問や懸念を払拭することで、「この会社は自分のキャリアを真剣に考えてくれている」という信頼感が生まれ、入社への意思を固める強力な後押しとなるのです。
入社後のミスマッチを防ぐ
第二のメリットは、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを未然に防げる点です。採用選考の段階では、どうしても企業の魅力的な側面が強調されがちです。しかし、内定者にとっては、仕事の厳しさや乗り越えるべき壁、リアルな働き方といった情報こそが、入社後のギャップをなくすために不可欠です。
キャリア相談会では、現場で働く社員から直接、仕事のやりがいだけでなく大変さも聞くことができます。これにより、内定者は入社後の働き方に対して過度な期待を抱くことなく、現実的な視点を持つことができます。企業側にとっても、入社前に内定者の価値観やキャリア観を深く理解することで、配属先の検討やオンボーディングの計画に活かすことが可能です。結果として、ミスマッチによる早期離職を防ぎ、採用・育成コストの損失を回避することに繋がります。
| ミスマッチが引き起こす問題 | キャリア相談会による解決策 |
|---|---|
| 早期離職による採用・教育コストの増大 | 入社前にリアルな情報を伝え、期待値を健全に調整する |
| 配属後のモチベーション低下 | 具体的な業務内容やキャリアパスを示し、働くイメージを明確化する |
| 組織全体の生産性ダウン | 内定者自身の自己分析を促し、納得感のある意思決定を支援する |
内定者のエンゲージメント向上
三つ目のメリットは、入社前から内定者のエンゲージメント(企業への愛着や貢献意欲)を高められることです。内定承諾から入社までの期間は、企業との接点が途絶えがちで、内定者の帰属意識が低下しやすい「空白期間」とも言えます。
キャリア相談会という定期的な接点を設けることで、内定者は「自分は忘れられていない」「会社の一員として迎え入れられている」という安心感を得ることができます。また、先輩社員や人事担当者、さらには同期となる他の内定者と交流する中で、企業の文化や価値観への理解が深まり、人間関係の不安も解消されます。企業が自身のキャリア形成を親身に支援してくれる姿勢を感じることで、内定者のロイヤリティは格段に向上します。こうして育まれた高いエンゲージメントは、入社後の主体的な活躍や定着率の向上に大きく貢献するのです。
【完全ガイド】内定後キャリア相談会の始め方6ステップ

内定者向けのキャリア相談会を成功させるためには、事前の準備と計画が不可欠です。ここでは、企画から実施後のフォローまで、具体的な6つのステップに分けて、誰でも実践できる「始め方」を徹底解説します。このガイドに沿って進めることで、効果的なキャリア相談会を実現し、内定辞退の防止に繋げましょう。
ステップ1|目的とゴールを明確にする
何のためにキャリア相談会を実施するのか、その目的を最初に明確化することが最も重要です。目的が曖昧なままでは、プログラムの内容がぶれてしまい、期待した効果が得られません。まずは、自社の採用課題と照らし合わせ、相談会の目的を具体的に設定しましょう。
目的の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 内定者の入社に対する不安や疑問を解消する
- 内定者同士の横の繋がりを構築し、帰属意識を高める
- 入社後のキャリアパスを具体的に示し、働くイメージを持たせる
- 企業のビジョンや文化への理解を深め、エンゲージメントを向上させる
目的が定まったら、その達成度を測るためのゴール(KPI)も設定します。具体的な数値を設定することで、施策の効果測定が可能になり、次回の改善に繋げることができます。
ゴールの設定例:
- キャリア相談会参加者の内定辞退率を〇%未満に抑える
- 実施後アンケートの満足度で「大変満足」「満足」の合計を90%以上にする
- 相談会後の個別面談希望者数を〇名以上にする
ステップ2|開催形式と時期を決定する
目的とゴールが明確になったら、次に開催形式と時期を決定します。内定者の属性(居住地、学業のスケジュールなど)や、相談会で達成したい目的に合わせて最適な形式を選びましょう。
オンラインかオフラインか
オンラインとオフラインには、それぞれメリット・デメリットがあります。自社の状況や内定者の分布を考慮して選択することが重要です。近年では、両方の利点を活かしたハイブリッド形式も人気です。
| 形式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| オンライン | ・遠方に住む内定者も参加しやすい ・会場費や交通費などのコストを削減できる ・日程調整が比較的容易 | ・通信環境に左右される ・一体感の醸成や非言語的なコミュニケーションが難しい ・企業の雰囲気や社風が伝わりにくい |
| オフライン | ・社員や内定者同士の深い関係構築に繋がる ・オフィスの雰囲気や働く環境を直接伝えられる ・偶発的なコミュニケーションが生まれやすい | ・会場費や交通費、宿泊費などのコストがかかる ・遠方の内定者にとって参加の負担が大きい ・会場の確保や設営に手間がかかる |
個別形式かグループ形式か
相談会の形式も、目的に応じて使い分ける必要があります。内定者一人ひとりの深い悩みに寄り添いたいのか、それとも内定者同士の交流を促進したいのかによって、最適な形式は異なります。
| 形式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 個別形式 | ・個人的で深い悩みを相談しやすい ・一人ひとりに合わせた丁寧なフォローが可能 ・高い心理的安全性を確保できる | ・人事やメンター社員の工数が多くかかる ・一度に対応できる人数が限られる |
| グループ形式 | ・他の内定者の考えや質問を知ることができる ・内定者同士の交流が生まれ、連帯感が醸成される ・効率的に多くの内定者とコミュニケーションが取れる | ・内気な内定者が発言しにくい場合がある ・個人的な悩みを打ち明けにくい雰囲気になりがち |
おすすめは、全体会(グループ形式)と個別相談(個別形式)を組み合わせる方法です。全体で会社の情報やキャリアパスを共有した後、ブレイクアウトルームや別室で個別の相談時間を設けることで、両方のメリットを享受できます。
開催時期については、内定者の心理状態に合わせて複数回設定するのが理想的です。例えば、内定ブルーに陥りやすい内定式直後の10月〜11月、そして他社の採用活動が落ち着き入社準備を始める1月〜2月に開催すると効果的です。
ステップ3|当日のプログラム内容を企画する
開催形式が決まったら、当日のプログラムを具体的に企画します。ステップ1で設定した目的に立ち返り、「その目的を達成するためにはどのようなコンテンツが必要か」を軸に考えましょう。内定者が「参加してよかった」と思えるような、魅力的で有益なコンテンツを設計することが成功のカギです。
プログラムの構成例:
- オープニング(10分)
- 本日の目的とゴールの共有
- アイスブレイク(自己紹介、簡単なゲームなど)
- 会社・事業の最新情報共有(20分)
- 内定時からのアップデート情報(新規事業、組織変更など)
- 改めて会社のビジョンやミッションを伝える
- 先輩社員によるキャリアセッション(40分)
- 多様なキャリアを歩む若手〜中堅社員によるパネルディスカッション
- テーマ例:「入社1年目のリアルな働き方」「私のキャリアプランと実現方法」
- 質疑応答
- グループワーク(30分)
- 内定者同士で特定のテーマについてディスカッション
- テーマ例:「入社後に挑戦したいこと」「同期と協力して成し遂げたいこと」
- 個別キャリア相談会 or 座談会(40分)
- 人事担当者や先輩社員がメンターとなり、少人数のグループや1対1で相談に乗る
- 内定者が本音で話せるよう、評価とは一切関係ないことを明確に伝えることが重要です。
- クロージング(10分)
- 役員からのメッセージ
- 今後のスケジュール案内、アンケート協力依頼
ステップ4|内定者への告知と参加を促す方法
どれだけ素晴らしいプログラムを企画しても、内定者に参加してもらえなければ意味がありません。単なる事務的な案内ではなく、「ぜひ参加したい」と思わせるような工夫を凝らした告知を行いましょう。
告知メールや案内に含めるべき項目:
- 開催日時、場所(またはURL)、服装
- キャリア相談会を開催する目的・想い(例:「皆さんの入社後の活躍を心から願っており、そのための不安を解消する場です」)
- 当日の具体的なプログラム内容
- 登壇する先輩社員の簡単なプロフィール(部署、経歴、趣味など)
- 参加することで得られるメリット(例:同期と繋がれる、キャリアの不安が解消できる、会社のリアルがわかる)
- 参加申し込み方法と締め切り
参加率を高めるための工夫として、事前にアンケートを実施し、「今、何に不安を感じていますか?」「どんな先輩社員の話を聞きたいですか?」といった質問を投げかけ、その回答を当日のプログラムに反映させることを伝えると、内定者の当事者意識が高まり、参加意欲の向上に繋がります。
ステップ5|当日の運営とファシリテーションのコツ
当日の運営のスムーズさは、参加者の満足度に直結します。入念な準備と、参加者に寄り添うファシリテーションを心がけましょう。
事前準備
- 役割分担の明確化:司会進行、ファシリテーター、タイムキーパー、機材担当、オンラインのチャット監視役など、担当者を事前に決めておきます。
- 運営マニュアルの作成:タイムスケジュール、進行台本、担当者ごとの動き、トラブル発生時の対応フローなどをまとめた資料を作成し、運営メンバー全員で共有します。
- リハーサルの実施:特にオンライン開催の場合は、音声や映像のチェック、画面共有やブレイクアウトルームの操作確認など、本番同様のリハーサルを必ず行いましょう。
当日のファシリテーションのコツ
- 心理的安全性の確保:冒頭で「ここは評価の場ではありません。どんな些細なことでも安心して質問・相談してください」と明確に伝え、話しやすい雰囲気を作ります。
- 双方向のコミュニケーション:一方的な説明に終始せず、問いかけを増やしたり、オンラインの場合はチャットやリアクション機能を活用したりして、内定者が参加しやすい環境を整えます。
- 時間管理の徹底:プログラムが時間通りに進むよう、タイムキーパーを中心に運営メンバーが連携します。ただし、議論が盛り上がっている場合は、柔軟に時間を調整することも大切です。
- 傾聴の姿勢:内定者の発言を遮らず、最後まで真摯に耳を傾ける姿勢が信頼関係を築きます。質問の意図を汲み取り、的確に回答することを心がけます。
ステップ6|実施後のアンケートとフォローアップ
キャリア相談会は、実施して終わりではありません。効果を最大化し、次回の改善に繋げるために、実施後のアンケートと丁寧なフォローアップが不可欠です。
アンケートの実施
相談会終了後、当日か翌日のできるだけ早いタイミングで、Webアンケート(Googleフォームなど)を送付します。記憶が新しいうちに回答してもらうことで、より具体的で率直なフィードバックを得られます。
アンケート項目例:
- 相談会全体の満足度(5段階評価など)
- 最も有益だったプログラムとその理由
- 運営や進行に関する改善点
- 入社に対する不安は解消されたか
- 今後、会社に期待すること(自由記述)
丁寧なフォローアップ
アンケート結果を分析し、次回の企画に活かすのはもちろんのこと、参加してくれた内定者一人ひとりへのフォローも重要です。
- 御礼メールの送付:参加への感謝を伝えるとともに、相談会の要点やアンケートで出た質問への回答などを共有します。
- 個別フォロー:アンケートや相談会当日に、個別の悩みを打ち明けてくれた内定者には、後日改めて人事担当者や適切な先輩社員との面談を設定します。この一手間が、内定者の安心感とエンゲージメントを大きく高めます。
- 情報共有:相談会の様子を簡単なレポートにまとめ、参加できなかった内定者も含めて共有することで、会社全体の歓迎ムードを伝えることができます。
これらのステップを着実に実行することで、内定者の不安を解消し、入社意欲を高めるキャリア相談会を実現できるでしょう。
内定辞退を防ぐキャリア相談会を成功させる5つのポイント

内定後のキャリア相談会を成功させ、内定辞退の防止という目的を達成するためには、計画と準備に加えていくつかの重要なポイントがあります。ここでは、内定者の満足度を最大化し、エンゲージメントを高めるための5つの成功のポイントを具体的に解説します。
内定者の不安に寄り添うコンテンツを設計する
内定者は、入社を心待ちにしている一方で、多くの不安や疑問を抱えています。キャリア相談会が「企業側が伝えたいことを伝える場」になってしまうと、内定者の心は離れてしまいます。大切なのは、内定者一人ひとりが抱える不安に徹底的に寄り添うコンテンツを設計することです。
内定者が抱えがちな不安には、以下のようなものが挙げられます。
- 本当にこの会社で成長できるのだろうか?(キャリアパスへの不安)
- 希望する部署に配属されるのか?(配属への不安)
- 同期や先輩社員とうまくやっていけるだろうか?(人間関係への不安)
- 仕事とプライベートの両立は可能なのか?(働き方への不安)
- 入社までに何を勉強しておけば良いのか?(スキルへの不安)
これらの不安を解消するため、事前に匿名アンケートを実施し、「今、一番聞きたいこと・不安なこと」をヒアリングしましょう。その結果をもとに、当日のコンテンツを組み立てることで、内定者の満足度は飛躍的に向上します。例えば、「キャリアパス」に関する不安が多ければ、複数の部署で活躍する若手・中堅社員に登壇してもらい、具体的なキャリアステップや仕事のやりがいを語ってもらうセッションを設けるといった対応が考えられます。
「何でも話せる」心理的安全性の高い場を作る
内定者は「こんな質問をしたら、評価が下がるのではないか」「意識が低いと思われないか」といった懸念から、本音を言い出せないケースが少なくありません。キャリア相談会を真に価値あるものにするためには、内定者が安心して本音を打ち明けられる「心理的安全性」の高い場作りが不可欠です。
心理的安全性を確保するための具体的な施策は以下の通りです。
- 冒頭での明確な宣言:相談会の最初に「ここでの発言は選考や評価には一切関係ありません。皆さんの不安を解消するための場なので、どんな些細なことでも質問してください」と明確に伝えます。 –
社員の自己開示:
- メンター役の社員が、自らの失敗談や入社当初の不安を語ることで、内定者も自己開示しやすくなります。
- 少人数での対話:グループ形式の場合、5〜6人程度の少人数グループに分けることで、一人ひとりの発言機会を増やし、双方向のコミュニケーションを活性化させます。オンラインの場合は、ブレイクアウトルーム機能を活用しましょう。
- 匿名質問ツールの活用:「Slido」や「Mentimeter」といったツールを導入し、匿名で質問できるようにするのも効果的です。直接は聞きにくい給与や残業、福利厚生といったデリケートな質問も集めやすくなります。
人事担当者やメンターは「評価者」ではなく、内定者のキャリアを共に考える「対等なパートナー」であるという姿勢を示すことが、信頼関係を築く第一歩となります。
担当者(メンター)の人選と事前研修
キャリア相談会の成否は、当日対応する社員(メンター)の質に大きく左右されます。誰をアサインし、どのような準備をしてもらうかが極めて重要です。単に仕事ができるエース社員ではなく、内定者の気持ちに寄り添える共感性の高い社員を選ぶ必要があります。
人選と研修においては、以下の点を重視しましょう。
| 項目 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 人選のポイント |
|
| 事前研修の内容 |
|
担当社員への丁寧な事前研修が、キャリア相談会全体の質を担保し、内定者の信頼獲得に繋がります。
オンライン開催で満足度を高める工夫
近年、キャリア相談会をオンラインで実施する企業が増えています。オンラインは手軽に参加できるメリットがある一方、コミュニケーションが一方通行になりがちで、一体感が生まれにくいという課題もあります。オンラインの特性を理解し、参加者の満足度を高めるための工夫を凝らすことが成功の鍵です。
オンライン開催で満足度を高める工夫には、以下のようなものが考えられます。
- 双方向性を高めるツールの活用:Zoomのチャット、リアクションボタン、投票機能などを積極的に活用し、内定者が受け身にならずに参加できる仕掛けを作ります。「今の話、参考になった人は『いいね』ボタンを押してください!」など、こまめに働きかけることが有効です。
- ブレイクアウトルームの有効活用:少人数に分かれるブレイクアウトルームは、オンラインでの心理的安全性を高めるのに非常に効果的です。社員1名に対して内定者3〜4名程度の比率で、雑談も交えながらじっくり話せる時間を確保しましょう。
- 一体感を醸成する演出:可能であれば、事前に会社ロゴの入ったノベルティグッズや、お菓子・ドリンクなどを内定者の自宅に送付し、当日は全員で同じものを片手に参加するといった演出も、一体感の醸成に繋がります。
- 運営面の配慮:長時間のオンラインイベントは集中力が切れやすいため、1時間に1回は必ず休憩を挟むようにしましょう。また、カメラONを強制せず、参加しやすい環境を整える配慮も大切です。
他社の成功事例から学ぶ
自社だけで企画を考えると、どうしても視野が狭くなりがちです。内定者フォローに先進的に取り組む企業の成功事例から学ぶことで、自社のキャリア相談会をより良いものにするヒントが得られます。
例えば、以下のような企業の取り組みが参考になります。
- 株式会社サイバーエージェント:内定者時代から事業や組織創りに参画する機会を提供しています。例えば、内定者が役員に対して新規事業などを提案する「内定者版あした会議」は有名です。キャリアを「与えられるもの」ではなく「自ら創るもの」という当事者意識を醸成し、エンゲージメントを高める好事例です。
- ソフトバンク株式会社:内定者一人ひとりに対して、配属予定先の先輩社員との面談を複数回設定するなど、手厚い個別フォローで知られています。入社前に現場のリアルな情報を深く知ることで、入社後のギャップを最小限に抑え、納得感の高い配属を実現しています。
これらの事例をそのまま真似る必要はありません。大切なのは、各社の取り組みの裏にある「内定者にどうなってほしいか」という思想を読み解き、自社の文化や規模、内定者の特性に合わせて応用することです。「同期との繋がりを重視する」「個人のキャリアプランを深く考える機会にする」など、自社が最も大切にしたい軸を定め、他社のエッセンスを取り入れていきましょう。
まとめ
本記事では、高まる内定辞退率への対策として、内定者向けキャリア相談会の始め方から成功のポイントまでを網羅的に解説しました。Z世代のキャリア観の変化を背景に、内定期間中のコミュニケーションは以前にも増して重要になっています。キャリア相談会は、内定者の入社に対する不安を解消し、キャリアパスを具体的にイメージさせることで、内定辞退や入社後のミスマッチを防ぐ極めて有効な施策です。
相談会を成功に導く結論として、計画的な準備と「内定者に寄り添う姿勢」が最も重要です。本記事で紹介した6つのステップに沿って目的を明確にし、内定者が本音で話せる心理的安全性の高い場を設計することが、満足度を高める鍵となります。オンライン・オフライン問わず、適切な担当者をアサインし、内定者一人ひとりと真摯に向き合うことが、結果的に企業へのエンゲージメント向上に繋がります。
優秀な人材を確保し、入社後の早期活躍を促進するために、ぜひこの記事を参考に、自社に最適化されたキャリア相談会の企画・実施をご検討ください。