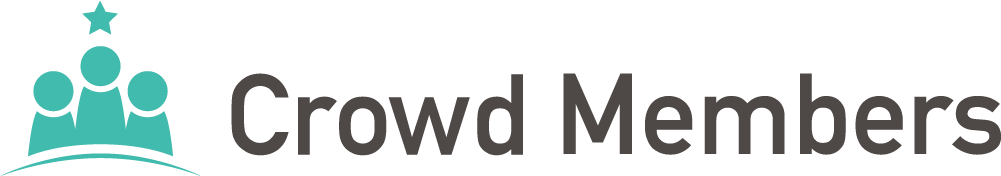なぜ組織の要である中堅社員は辞めてしまうのか

入社から数年が経過し、実務経験と専門知識を兼ね備えた中堅社員は、まさに組織の「要」となる存在です。プレイヤーとして高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、後輩の指導やチームの潤滑油としての役割も担い、現場を支えています。しかし、多くの企業でこの重要な中堅層の離職が深刻な課題となっています。
なぜ、将来を期待される彼らは、慣れ親しんだ職場を去るという決断を下すのでしょうか。その背景には、中堅社員特有の複合的な要因が隠されています。
キャリアアップが見込めない閉塞感
中堅社員が離職を考える最も大きな理由の一つが、自身のキャリアに対する将来的な不安です。日々の業務をそつなくこなせるようになった一方で、「この会社にいても、これ以上の成長は望めないのではないか」という閉塞感に苛まれることがあります。
具体的には、以下のような状況が挙げられます。
- 管理職ポストの不足: 組織の構造上、昇進できるポストには限りがあります。特に年功序列の風土が根強い企業では、上が詰まっているために優秀な中堅社員であっても昇進の機会が巡ってこないケースが少なくありません。
- ロールモデルの不在: 目標とすべき魅力的な上司や先輩社員がいない場合、自身の数年後の姿をポジティブに想像することが難しくなります。「あの人のようにはなりたくない」と感じてしまうと、社内でのキャリア形成意欲は大きく削がれてしまいます。
- 業務のマンネリ化: いつまでも同じような業務の繰り返しで、新しいスキルや知識を習得する機会が与えられないと、自身の市場価値が停滞しているのではないかと焦りを感じ始めます。挑戦的な仕事を通じて成長したいという意欲が満たされない環境は、優秀な人材ほど外部に活躍の場を求める動機となります。
自身の成長が会社の成長に繋がるという実感を得られないままでは、エンゲージメントを維持することは困難です。結果として、より挑戦的で成長機会の豊富な他社へと目が向いてしまうのです。
正当に評価されていないという給与や待遇への不満
自身の貢献度と、会社から与えられる評価や報酬との間にギャップを感じることも、離職の引き金となります。中堅社員は、自身の業務の難易度や責任の重さ、そして社外における自身の市場価値を客観的に把握し始める年代です。そのため、評価や待遇に対する目はシビアになります。
この不満は、単に「給与が低い」という金銭的な問題だけではありません。「自分の働きや成果が、会社から正当に認められていない」という承認欲求が満たされないことへの不満が根底にあります。貢献度と報酬の間に存在する不透明さや不公平感は、社員の忠誠心を著しく低下させる直接的な原因となります。
| 不満の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 評価制度 | 評価基準が曖昧で、上司の主観に大きく左右される。目標達成しても評価に結びつかない。フィードバックが不十分で、何を改善すれば評価が上がるのかが不明確。 |
| 給与・賞与 | 大きな成果を上げても昇給幅が小さい。同業他社や同年代の給与水準と比較して見劣りする。業績が良くても賞与への反映が少ない。 |
| 役職・手当 | 責任や業務量だけが増え、役職や役職手当が見合っていない。「名ばかり管理職」のような状態に置かれている。 |
このような状況が続けば、「もっと自分を高く評価してくれる会社があるはずだ」と考え、転職活動を始めるのは自然な流れと言えるでしょう。
増え続ける業務負担と責任の重さ
中堅社員は、実務能力の高さを買われ、多くの業務を任される傾向にあります。プレイヤーとしての役割に加え、後輩の育成やプロジェクトのリーダーなど、マネジメントに近い役割も期待されるようになり、業務量と責任が一気に増大します。
しかし、その責任の重さに見合うだけの権限が与えられていなかったり、十分なサポート体制がなかったりする場合、心身ともに疲弊してしまいます。特に、自身の業務とマネジメント業務の板挟みになる「プレイングマネージャー」の状態は、過重労働に繋がりやすく、燃え尽き症候群(バーンアウト)のリスクを高めます。
「会社は自分に期待してくれている」というポジティブな感情が、「都合よく使われているだけではないか」というネガティブな感情に変わったとき、ワークライフバランスの崩壊と相まって、離職という選択肢が現実味を帯びてくるのです。
会社の将来性や経営方針への疑問
会社に対する理解が深まる中堅層だからこそ、経営方針や事業の将来性に疑問を抱くことがあります。若手時代には見えなかった組織の課題や業界の動向が客観的に見えるようになり、「この船に乗り続けていて大丈夫だろうか」という不安を感じるのです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 経営層が打ち出すビジョンに共感できない、または具体性がなく現場に浸透していない。
- 市場の変化に対応できず、旧態依然としたビジネスモデルに固執している。
- 意思決定が遅く、非効率な社内プロセスが改善されない。
- コンプライアンス意識が低く、企業の社会的責任に対する姿勢に疑問を感じる。
自身のキャリアを長期的な視点で考えたとき、会社の成長戦略や組織文化に明るい未来を描けないと感じれば、より成長性や安定性の高い企業への移籍を検討するのは当然のことです。
上司と部下の板挟みによる人間関係のストレス
中堅社員は、組織の中間層として、上司と部下の間に挟まれることで特有の人間関係のストレスを抱えがちです。この「調整役」としての精神的な負担が、仕事へのモチベーションを奪い、離職へと繋がることが少なくありません。
| 相手 | 求められる役割・期待 | 中堅社員が感じるストレス |
|---|---|---|
| 上司 | 経営方針の伝達と実行、チームの業績目標達成、問題発生時の報告 | 納得できない指示でも部下に伝えなければならない。上からの過度なプレッシャー。 |
| 部下・後輩 | 的確な業務指示、キャリア相談、メンタルケア、価値観の尊重 | 世代間の価値観のギャップ。指導とハラスメントの境界線への悩み。育成の難しさ。 |
上司からは「もっとチームをまとめろ」とプレッシャーをかけられ、部下からは「現場の気持ちを分かってくれない」と突き上げられる。双方の意見を調整し、円滑なコミュニケーションを図ろうと奮闘するものの、誰からも理解されずに孤立感を深めてしまうケースもあります。このような精神的な消耗が限界に達したとき、人間関係をリセットしたいという思いから離職を決意するのです。
中堅社員の離職が組織に与える深刻なダメージ

経験とスキルの両方を備え、組織の中核を担う中堅社員。その離職は、単に「社員が一人辞める」という事実以上の、深刻で多岐にわたるダメージを組織に与えます。目に見えるコストの発生はもちろん、目に見えない組織力の低下は、企業の持続的な成長を阻害する大きな要因となり得ます。
ここでは、中堅社員の離職がもたらす具体的なダメージについて、3つの側面に分けて詳しく解説します。
チームの生産性低下と重要ノウハウの流出
中堅社員は、多くの場合、自身の業務をこなしながら後輩の指導やチームのマネジメントを担うプレイングマネージャーとしての役割を担っています。このようなキーパーソンが一人抜けるだけで、チーム全体の業務遂行能力は著しく低下します。
残されたメンバーは、退職者の業務を分担せざるを得なくなり、一人ひとりの業務負荷が増大します。引き継ぎが不十分な場合、業務の停滞やミスの頻発、顧客対応の質の低下などを招き、チーム全体の生産性が大きく損なわれるでしょう。特に、専門的な知識や複雑な判断が求められる業務を担っていた場合、その穴を埋めるには相当な時間と労力が必要となります。
さらに深刻なのは、形式知化されていない「暗黙知」や「重要ノウハウ」の流出です。長年の経験で培われた顧客との信頼関係、トラブル発生時の勘所、円滑な社内調整のコツといった、マニュアルには決して落とし込めない貴重な資産が、社員の退職と同時に社外へ失われてしまうのです。これは、企業の競争力を直接的に削ぐ、計り知れない損失と言えます。
他の社員のモチベーション低下と連鎖退職のリスク
組織の要として周囲から頼られていた中堅社員の離職は、他の社員、特に若手や同僚の心に大きな動揺を与えます。将来のキャリアモデルとして見ていた先輩が会社を去る姿は、「この会社にいても成長できないのではないか」「自分の将来も危ういのではないか」といった漠然とした不安を掻き立て、エンゲージメントを著しく低下させます。
チームの雰囲気が悪化し、コミュニケーションが停滞することも少なくありません。活発な意見交換が失われ、指示待ちの姿勢が蔓延するなど、組織全体の活力が失われていく可能性があります。
最も警戒すべきは、一人の離職が引き金となって起こる「連鎖退職」です。同じように会社に対して不満や疑問を抱えていた社員が、退職した中堅社員の姿を見て「自分も辞めていいんだ」と決断しやすくなります。特に優秀な人材ほど、外の世界に目を向けるきっかけとなりやすく、一人、また一人と人材が流出する「退職ドミノ」に陥る危険性をはらんでいるのです。
採用コストと育成コストの増大
中堅社員が一人離職すると、その欠員を補充するために新たな採用活動が必要となり、直接的・間接的に多大なコストが発生します。さらに、これまでその社員に投じてきた育成コストもすべて無駄になってしまいます。
具体的にどのようなコストが発生するのか、下の表で確認してみましょう。
| コストの種類 | 具体的な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 採用コスト(直接) | 求人広告掲載費、人材紹介会社への成功報酬(年収の30~35%が相場)、採用イベント出展費など | 即戦力となる中堅層の採用は難易度が高く、コストも高騰しがちです。 |
| 採用コスト(間接) | 書類選考や面接に関わる人事担当者・現場管理職の人件費、リファラル採用のインセンティブ費用など | 採用活動が長期化すればするほど、これらの見えないコストは膨らんでいきます。 |
| 育成コスト(機会損失) | 新しく採用した人材が退職者と同等のパフォーマンスを発揮するまでの教育期間(OJT担当者の人件費、研修費用)と、その間の生産性の低い期間に得られたはずの利益 | 組織文化への適応や人間関係の構築にも時間がかかり、本来のパフォーマンスを発揮するまでには数ヶ月~1年程度を要します。 |
このように、一人の中堅社員の離職は、過去に投じた育成コストを水泡に帰させ、さらに高額な採用コストと再育成コストを発生させる二重の損失をもたらします。これは企業の財務状況に直接的な打撃を与える、非常に深刻な問題です。
明日から実践できる中堅社員の離職防止策7選

中堅社員の離職という深刻な問題に対し、企業は傍観しているわけにはいきません。彼らが抱える不満や不安を解消し、エンゲージメントを高めるためには、具体的な打ち手が必要です。ここでは、企業が明日からでも実践できる7つの具体的な離職防止策を、多角的な視点から詳しく解説します。
キャリアパスの明確化と学び直しの機会提供
中堅社員が抱く「この会社にいても成長できないのではないか」というキャリアの閉塞感は、離職の大きな引き金となります。企業は、社員一人ひとりが自社で働く未来を描けるような道筋を示すことが重要です。個人の成長が会社の成長に直結するという好循環を生み出しましょう。
具体的な施策例
- 複線型キャリアパスの導入: マネジメント職を目指すコースだけでなく、特定の分野を極める専門職(エキスパート)コースや、プロジェクトを牽引するプロジェクトマネージャーコースなど、多様なキャリアの選択肢を用意します。これにより、個々の適性や志向に合ったキャリア形成を支援できます。
- 社内公募制度・FA制度の活性化: 社員が自らの意思で希望する部署やポジションに応募できる制度です。キャリアの自律性を促し、新たな挑戦への意欲を引き出します。
- リスキリング・学び直しの機会提供: 時代の変化に対応するためのスキルアップは不可欠です。DX人材育成研修やリーダーシップ研修、資格取得支援制度、外部セミナー参加費用の補助などを通じて、社員の市場価値を高める投資を惜しまない姿勢が求められます。
- キャリアデザイン研修と定期的な面談: 自身のキャリアについて考える研修を実施し、上司や人事部との定期的なキャリア面談を通じて、会社としてその実現をサポートする体制を構築します。
納得感を高める人事評価制度への見直し
「頑張りが正当に評価されていない」という不満は、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。評価の基準が曖昧であったり、評価プロセスが不透明であったりすると、社員は会社への不信感を募らせます。透明性・公平性・納得性の高い人事評価制度を構築することが、エンゲージメント向上の鍵となります。
評価制度を見直す際は、以下のポイントを参考にしてください。
| 評価項目 | 具体的な見直し施策 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 評価基準の明確化 | OKR(目標と主要な成果)やコンピテンシー評価を導入し、評価基準を全社員に公開する。 | 社員が何をすれば評価されるのかを理解し、目標達成に向けた行動が促進される。 |
| 評価プロセスの透明化 | 360度評価(多面評価)を導入し、上司だけでなく同僚や部下からのフィードバックも参考にする。 | 評価の客観性が高まり、一方的な評価による不満を軽減できる。 |
| フィードバックの質向上 | 評価者(管理職)向けのトレーニングを実施し、評価結果を伝えるだけでなく、今後の成長に繋がる具体的なフィードバックを行うスキルを向上させる。 | 評価が育成の機会となり、社員の成長意欲を高めることができる。 |
1on1ミーティングによる定期的なコミュニケーション
業務上の指示や報告だけでは、社員が抱える悩みやキャリアへの不安を汲み取ることは困難です。上司と部下が1対1で対話する「1on1ミーティング」を定期的に実施することで、個々のコンディションを把握し、心理的安全性を確保することができます。これは、問題が深刻化する前に早期発見・早期解決に繋がる重要な取り組みです。
効果的な1on1ミーティングのポイント
- 目的の共有: 1on1は評価面談や業務進捗会議ではありません。「部下の成長支援」や「キャリアに関する悩み相談」など、部下のための時間であることを明確に伝えます。
- 話すより聴く: 上司が一方的に話すのではなく、部下の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」の姿勢が最も重要です。部下が安心して本音を話せる雰囲気を作りましょう。
- 継続的な実施: 1回きりではなく、週に1回30分、あるいは隔週で1回など、頻度を決めて継続的に行うことで、信頼関係が深まります。
- プライベートな話題も尊重: 仕事の話だけでなく、プライベートの状況や興味関心事など、差し支えない範囲で対話することで、相互理解が深まり、より強固な信頼関係を築けます。
ワークライフバランスを重視した柔軟な働き方の推進
責任が重くなる中堅社員にとって、仕事とプライベートの両立は切実な課題です。特に育児や介護といったライフイベントと仕事の両立支援は、優秀な人材の定着に不可欠です。時間や場所に捉われない柔軟な働き方を推進することで、社員の満足度を高め、生産性の向上も期待できます。
柔軟な働き方の制度例
- リモートワーク・ハイブリッドワーク: 通勤時間の削減や、育児・介護との両立を支援します。
- フレックスタイム制度: コアタイムを設けつつ、始業・終業時間を社員が自由に決められる制度です。
- 時短勤務制度: 育児や介護などを理由に、所定労働時間を短縮できる制度です。
- 時間単位の有給休暇: 通院や子供の送り迎えなど、短時間の私用に対応しやすくなります。
これらの制度を導入するだけでなく、実際に制度を利用しやすい雰囲気や文化を醸成することも同時に重要です。管理職が率先して利用するなどの取り組みが効果的です。
挑戦を促す機会の提供と適切な権限委譲
ルーティンワークばかりでは、成長意欲の高い中堅社員は仕事への情熱を失ってしまいます。彼らの経験と能力を信頼し、新たな挑戦の機会を提供するとともに、責任ある仕事を任せる「権限委譲」’mark>を進めることが、マンネリ化を防ぎ、オーナーシップを育む上で極めて重要です。
権限委譲は、単なる「丸投げ」とは異なります。目的や期待する成果を明確に伝えた上で、プロセスについては本人の裁量に任せ、上司は必要なサポートに徹するという姿勢が求められます。挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから何を学んだかを共に振り返り、次の成功に繋げる文化を創り上げることが、社員の挑戦意欲を掻き立てます。
成果とプロセスを称賛する文化の醸成
人は誰でも「認められたい」「役に立ちたい」という承認欲求を持っています。給与や役職といった金銭的・地位的報酬だけでなく、日々の頑張りや貢献を認め、称賛するという「心理的報酬」が、社員のモチベーションを大きく左右します。特に、チームのために見えないところで努力している中堅社員の貢献に光を当てることが大切です。
称賛文化を醸成する仕組み
- ピアボーナス制度の導入: 社員同士が感謝の気持ちと共にポイントなどを送り合えるツール(例: Unipos)を活用し、称賛を可視化します。
- サンクスカード: 手書きのカードで感謝を伝え合う、アナログながらも温かみのある施策です。
- 社内報や朝礼でのグッドプラクティス共有: 素晴らしい成果やチームへの貢献を全社で共有し、称賛の輪を広げます。
- 上司からの具体的なフィードバック: 「いつもありがとう」という言葉に加えて、「先日の〇〇という対応が、お客様から非常に喜ばれていたよ」のように、具体的に伝えることで、称賛の価値は何倍にも高まります。
経営層からのビジョン共有と対話の場
「この会社はどこへ向かっているのか」「自分の仕事が会社の成長にどう繋がっているのか」という疑問は、エンゲージメントを低下させる要因となります。経営層が自らの言葉で会社のビジョンや将来の方向性を情熱をもって語り、社員と直接対話する場を設けることが、会社への帰属意識と貢献意欲を高めます。
全社総会のような形式的な場だけでなく、より少人数で双方向のコミュニケーションが取れる機会を設けることが効果的です。
対話の場の具体例
- タウンホールミーティング: 経営層が事業戦略などを説明し、社員からの質疑応答に直接答える場です。
- 経営層との座談会・ランチ会: 少人数で、よりフランクな雰囲気で意見交換を行います。
- 社内SNSやブログでの情報発信: 経営層が日々の考えや会社の状況をこまめに発信することで、社員との心理的な距離を縮めます。
これらの施策を通じて、中堅社員は自分が会社の重要な一員であると再認識し、会社の未来を自分事として捉えるようになります。
まとめ
本記事では、組織の要である中堅社員が離職してしまう原因を深掘りし、その深刻な影響と具体的な防止策について解説しました。中堅社員の離職は、単なる人材の損失に留まらず、チームの生産性低下や重要ノウハウの流出、ひいては他の社員の連鎖退職を引き起こすなど、企業の根幹を揺るがしかねない重大な問題です。
中堅社員が抱える「キャリアの閉塞感」「正当に評価されない不満」「過大な業務負担と責任」「会社の将来性への疑問」といった悩みは、彼らのエンゲージメントを著しく低下させる直接的な原因となります。これらの課題は、もはや個人の問題として片付けることはできません。
この状況を打開する鍵は、企業が主体的に働きかけ、社員一人ひとりと向き合う姿勢を示すことです。本記事で提案した「キャリアパスの明確化」「納得感のある人事評価制度への見直し」「1on1ミーティングによる対話」といった施策は、そのための具体的な第一歩となります。社員に挑戦の機会と適切な権限を与え、その成果とプロセスを正しく称賛する文化を醸成することが不可欠です。
中堅社員の離職防止は、企業の持続的な成長に直結する経営課題です。彼らが自らの未来を会社とともに描き、やりがいを持って働き続けられる環境を構築することこそが、優秀な人材を確保し、組織全体の活力を高めるための最も確実な道筋と言えるでしょう。