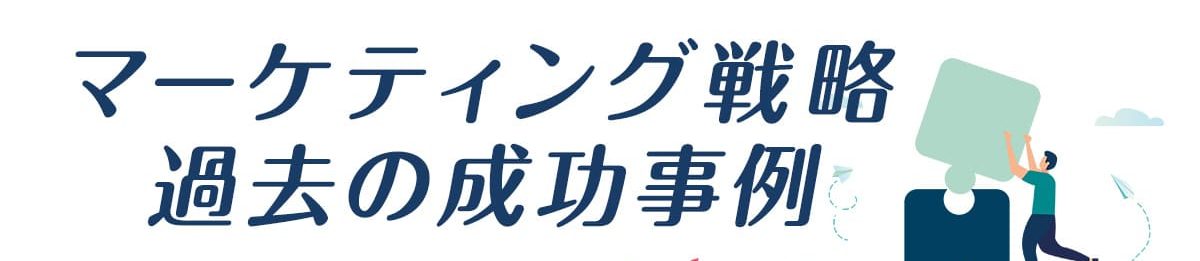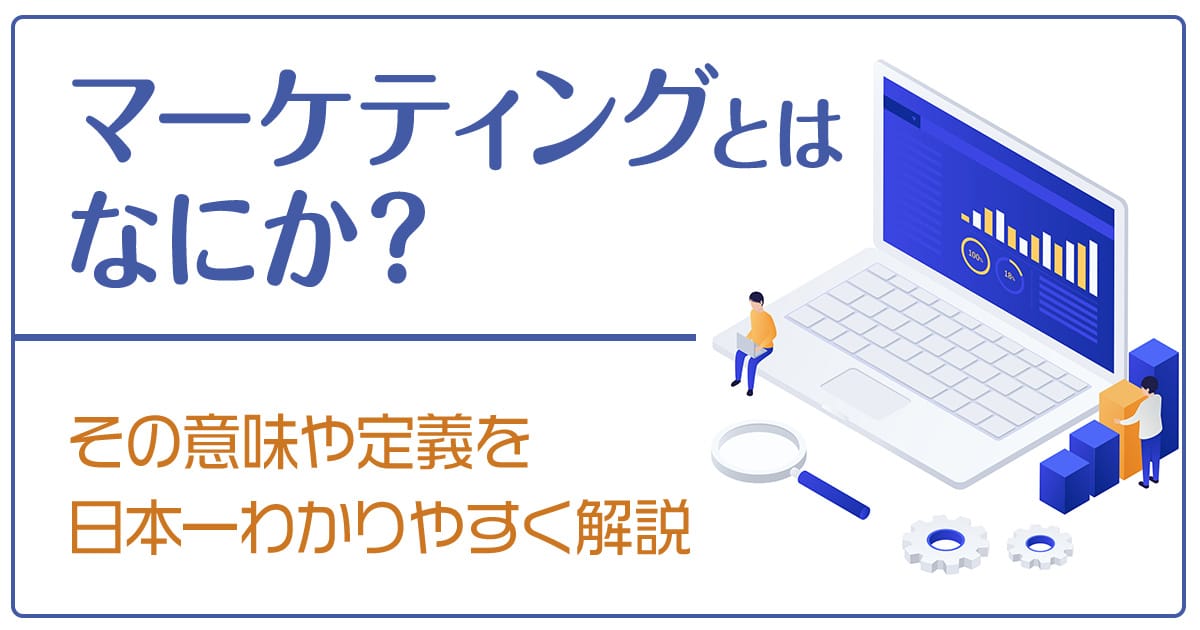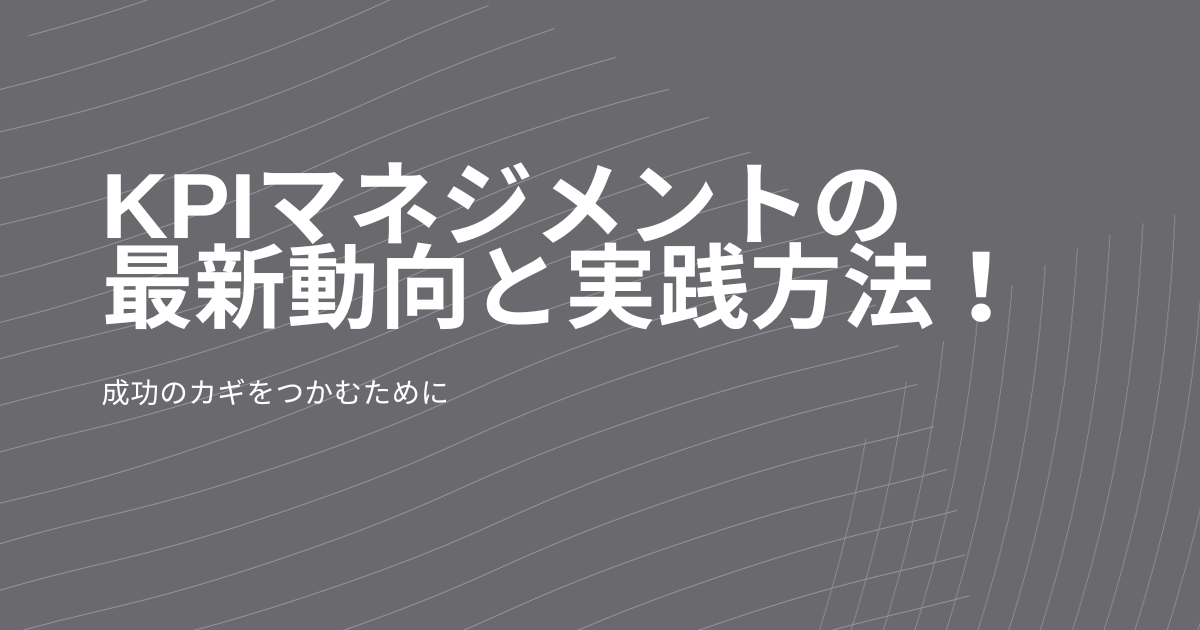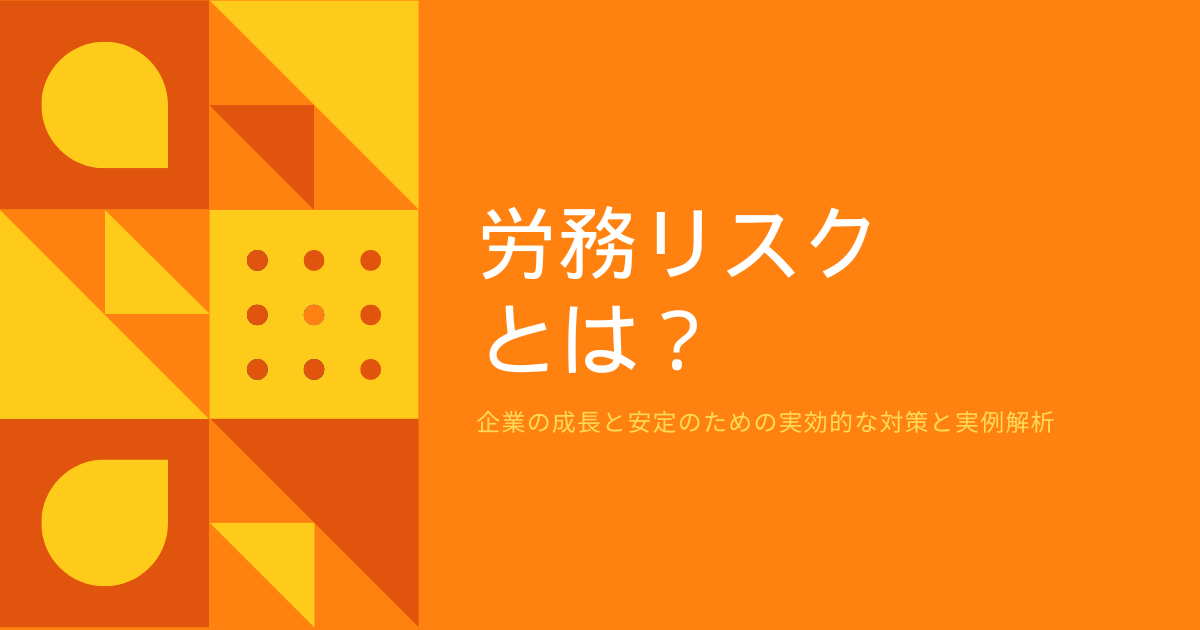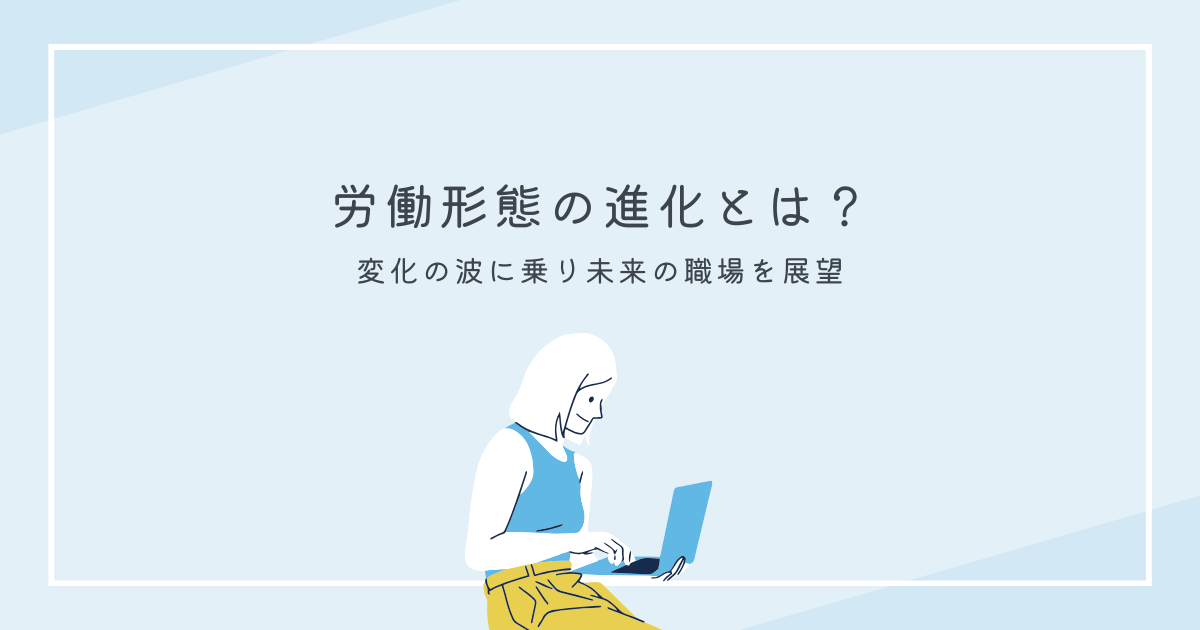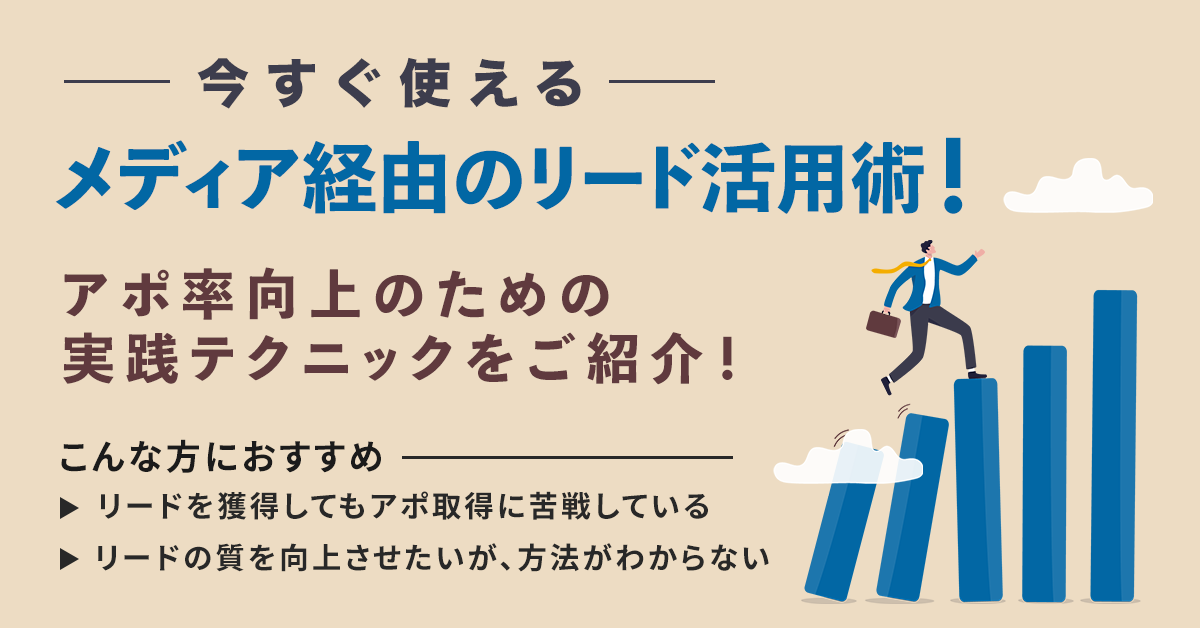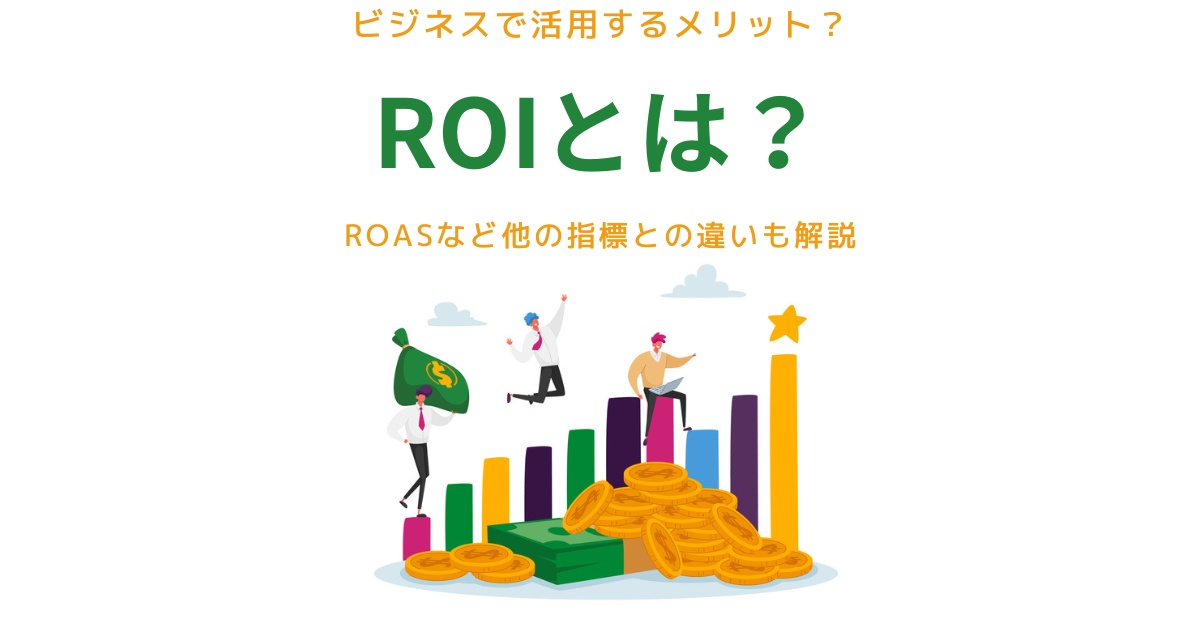マーケティング戦略とは?

マーケティング戦略とは、自社が利潤を獲得するために、どういう顧客(ターゲット)に、どのような商材(製品・サービス)を、どういう価格帯で、どのような方法・手段で提供していくのが最も経済合理性が高いかを追求することです。
なお、高度な情報化社会となった今日では、企業と顧客との関係性が昔のように一方通行では成立しません。商材が顧客に渡るまでのプロセスにおいて、双方向(インタラクティブ)の良好な関係の構築も、重要なファクターとなっています。
なお、「マーケティングとは何か」について、総合的に解説している以下の特集記事も、ぜひ参考にご一読ください。
マーケティング戦略と経営戦略の違い
「経営戦略」はマーケティング戦略と似たニュアンスを持つ言葉です。しかしながら、両者には決定的な違いがあります。
続きを読むには会員登録(無料、所要時間1分)またはログインが必要です。
続きを読むkyozon会員には以下の特典があります。
- kyozon主催イベントおよび名刺交換会に優先ご招待
- SaaS製品情報や活用ノウハウをメルマガでお届け
- 気になったSaaSサービスはマイページで比較することが可能
- 会員向けのSaaSに関するプレゼントやキャンペーンのご案内